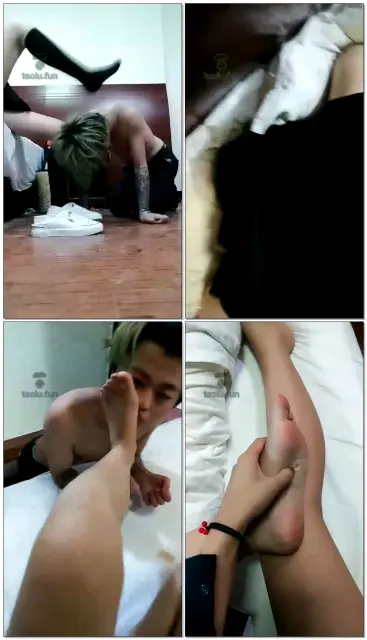日文868
1,219
以下为收费内容(by http://www.prretyfoot.com)“殺し合いゲーム”が始まる8年前―――。 これは、壺に入れられる毒蟲が、いかに毒を得るに至ったのかを語る物語。 *** 父は元々俳優だった。 映画にも何本か出たらしいが、すぐに事務所の関心は若い俳優に移り、ポジションを奪われた事で落ちぶれてしまったらしい。 事務所に入ったばかりの女優の卵を孕ませるなど素行も問題視され、事務所を退所して結婚。 生まれたのが私だった。 女優になるという夢を諦めた母は、フリーで俳優を続ける父をマネージャーとして支えながら、スーパーのレジ係をして懸命に働いた。 最初の内は父も懸命に仕事を探していたらしい。 セリフもない、ほとんど学生のアルバイトのようなエキストラでも文句一つ言わずに。 だが、芸能界は何の後ろ盾もないフリー俳優に簡単に仕事を回してくれるほど甘い世界ではなく、父は徐々に体調を崩し、酒やパチンコに溺れ、母や私に対しても暴言や暴力を振るうようになった。 学校が終わった後、私は近所の公園で暗くなるまで暇を潰すのが日課となっていた。 いつも家で飲んだくれている父と二人だけで過ごすのが耐えられず、母が帰ってくる時間に帰宅を合わせるためだ。 その日もいつも通り、公園のベンチで独り、ぼーっと夕焼け空を見上げていた。 「お嬢ちゃん、何やってるんだい?」 声にちらり、と視線を向ければ、スーツを着崩した中年のサラリーマン。 脂ぎった顔に気味の悪い笑みを浮かべ、血走った眼を向けてくる。 優しい声音を装ってはいても、腕や太もも、僅かに膨らみかけてきたばかりの胸を這い回るねっとりとした視線が本心を雄弁に物語っていた。 (気持ち悪い………) 生理的な嫌悪感が込み上げてくる。 「お嬢ちゃんみたいな可愛らしい子が一人でこんな時間に。危ないよ?……おじさんが家まで送っていってあげるよ」 気味の悪い猫撫で声に、ふーっふーっと荒い呼気が混じる。 「………」 無視を決め込んでいると、 「無視はいけないな。目上の人の話はちゃんと聞かないと」 しゃがんで目線を合わせ、にたりと笑う。 鼻腔を膨らませ、深く息を吸っているのも、気持ちが悪い。 生臭い吐息が鼻先を掠め、無性にムカムカしてくる。 思い切りビンタしてやったら、どんな顔をするだろうか。 そうは思うものの、体は動かなかった。 怒らせてしまったら、この男も父の様に暴力を振るうかもしれない。 そう思うと、体が竦んでしまう。 大人の男には、どう抗ったって勝てやしない。 「じゃあ、おじさんの家に行こうか?」 無視を決め込む私の反応をどう解釈したのかわからないが、男は舌なめずりをしながら、私の太ももを擦ってくる。 「っ―――」 全身の毛穴から嫌な汗が噴き出してくるような嫌悪感。 だが、声も出せなかった。 「くふぅ。きっと、楽しいよぉ………」 白い肌を厭らしく撫でまわす武骨な手が、そのまま半ズボンの中へと――― 「お兄さん」 「っ………」 いきなり背後から声を掛けられて、弾かれたように男が身を放す。 「い、いやっ、私は何も疚しい事はっ……ただ、迷子かな?と…」 言い訳をしながら振り向いて、目を剥く。 そこにいたのは、二人の女性。 しかも、いずれも目が覚めるような美人だった。 一人は高級そうな赤いスーツに身を包んでいた。艶やかな黒髪が上品な雰囲気を醸し出している。年齢は二十代半ばぐらいか。 もう一人はリクルートスーツのような黒いスーツ姿。栗色の髪が明るい雰囲気を醸し出しており、赤いスーツの美女よりも少し若そうだった。 「栗園さん。よろしくね」 「畏まりました、副総帥」 黒髪の美女の言葉に、栗色の髪の美女が答え、さっと男に身を寄せ、その右腕に両腕を絡ませる。 「えっ?」 戸惑う男の耳元に顔を寄せ、 「そぉんな子供より、私とイ・イ・コ・ト、しませんかぁ?あそこで♥」 蕩けるような甘い声音で囁きながら指差したのは、公衆トイレ。 「お、あ、え………?」 押し付けられる女体の柔らかさに表情を蕩けさせる男の股間を、女が撫でる。 「あふっ………」 それだけで、男の身体から力が抜けていくのが分かった。 「ね?さ、行きましょ♥」 そう言ってぐいっと腕を引っ張られると、男は抵抗する素振りも見せず、ふらふらと公衆トイレへと連れ込まれてしまう。 「お隣、いいかしら?」 一部始終を呆気に取られながら見つめていた私は、黒髪の女性に声を掛けられて漸く我に返った。 こくりと小さく頷きを返すと、女性がベンチに腰掛ける。 微かな風に乗って、女性からは、とてもいい匂いがした。 「私は佐伯真央。ヴェイングループという会社で副総帥をしているの。さっきの子は栗園穂乃果さん。今は私の下で秘書をしてもらっているわ。それで、貴女は?」 「佐倉井………君華です」 「そう。ちょっと失礼」 そう言って、女性―――佐伯さんはいきなり私をふわりと抱き締めた。 「え………」 戸惑う私を、包容力の塊のような柔らかな感触と良い香りが包み込む。 「大変だったわね」 「いえ、でも、助けてもらったので………」 「今だけじゃなく。あの男は気付かなかったのかもしれないけど、君華ちゃん。服の下が痣だらけでしょう?」 「っ………」 隠していた事を簡単に言い当てられて、思わず動揺してしまう。 「お父さん?」 「お、お父さんはっ……悪くないんです。私がもっといい子だったら………」 「そんな事はないわ。貴女は十分にいい子よ。こんな目に遭っているのに、お父さんの事を庇おうとしてる。それだけ、お父さんの事が好きなんでしょう?」 少し低めの、落ち着いた声音。 佐伯さんの言葉は、自然と体に染み込んでいくようだった。 この人にだったら、何も隠す必要はない。 初対面なのに、何故かそう確信した。 「………。はい。お酒に酔ってない時のお父さんは優しいから………」 「そう。お父さんも悪くはないわ。きっと、お父さんも苦しんでいるの。親であれば誰だって、自分の子を殴る事を楽しいだなんて思えないもの」 「じゃあ………どうすればいいんですか?」 自然と、涙が溢れてきた。 身体が震え、嗚咽が止まらなくなる。 「どうしたら、お父さんを助けられるんですか?昔みたいに、優しいお父さんに戻ってもらうためには……。私に何ができるんですか?」 抱き締められたまま、髪を優しく撫でられる。 佐伯さんから伝わってくる温もりに、涙が流れる勢いが増していく。 わんわんと声を上げて泣く私を、佐伯さんはじっと抱き締め、髪を撫で続けてくれた。 やがて、私が泣き止むと、佐伯さんは私の肩に手を置き、じっと瞳を見つめて微笑む。 「お父さんが暴力を振るってしまう原因はストレスよ。体の中にあるストレスがどうしようもなく膨れ上がってしまって。誰かにぶつけずには居られないの。賢い貴女なら、どうすればいいかわかるでしょう?」 「………別の方法で、ストレスを発散させる………?」 懸命に考えを巡らせて、私は自分の人生を変える事になる気づきに到達した。 「そう。その通り。体の中にある悪いものをぜぇんぶ吐き出させてしまえばいいの。そうすれば、男はみんなとても、“良い子”になってくれるから」 佐伯さんはにこり、と笑う。 そして―――。 「貴女が望むなら。その方法、私たちが教えてあげる」 ちらり、と佐伯さんの視線の動きを追うと、ちょうど公衆トイレから栗園と呼ばれていた女性が帰ってくる処だった。 何故か、その黒いスーツのあちこちには、白い何かがべったりとついていた。 *** それから二週間。 私は、佐伯さんと栗園さんから、男のストレスを発散させる方法を徹底的に学んだ。 最初は座学で。 次いで、実技で。 最終試験では、課題として連れてこられた男を公園の公衆トイレで徹底的に犯した。 男とは、あの日、私に声を掛けてきた名も知らぬ中年サラリーマンだった。 「幸せですか?」 手や足に付着した精液をトイレットペーパーで拭いながら尋ねると、 「し、幸せでひゅぅっ♥」 便器の上に頽れながら、男が答えた。 金玉がカラカラになるまで10回以上も搾り取られ、白目を剥き、泡を吹きながら、それでも幸せそうな表情を浮かべて痙攣している哀れな男の姿。 そんな姿を見ると、もはや恐怖感も湧いてこない。 男など、欲情に流されるだけのどうしようもない生き物だと実感する。 恐れる必要などないのだ。 「おめでとう、君華ちゃん。これできっとお父さんを助けてあげられるわ」 「ありがとうございます」 佐伯さんに頭を撫でられると、無性に嬉しかった。 「いい?できるだけ全部、搾り取るのがコツよ。泣いても叫んでも、金玉が空っぽになっても犯して犯して犯し尽くして。心を貴女一色に染めるの。貴女なしでは生きていけない。貴女の言う事だけに従う。貴女に全てを捧げる。そういう風に作り変えてしまうの。まぁ、たまにやりすぎて廃人にしてしまう事もあるかもしれないけど、お酒の飲み方と同じで、失敗しながら適量を学んでいくしかないわ……って、君華ちゃんはまだお酒も飲めないわね」 佐伯さんはくすくすと笑みを零した後、スーツのポケットから香水の小瓶を取り出し、私の掌に載せてくれた。 「これは?」 「合格祝い。私と同じ香水よ。これをつけて、頑張って」 「はい。必ず………」 ぎゅっ、と香水を握り締めて、決意を新たにする。 絶対に、お父さんを助けるんだと。 「ねぇ、お父さん」 娘―――君華に話しかけられて、思わずぴくんと震えてから、競馬新聞に落としていた視線をあげる。 キャミソールにホットパンツという露出の多い娘の、輝くような白肌を見てごくりと生唾を飲み込む。 (何やってるんだ、俺は……。娘だぞ……) 飲み込んでから、自己嫌悪が込み上げてきた。 いつからだろう。 娘から濃く“女”を感じるようになったのは。 その眼差しに、その声に、或いは香りに緊張を覚えるようになったのは。 それほど昔からではない。 精々、ここ2週間ほどの事だ。 時折見せる表情が、かつての娘と重ならない。 別人になってしまったのかと思う程だ。 まるで、娼婦のような妖艶さに、ペニスが疼いてしまう事が最近どんどん増えていた。 (ば、馬鹿馬鹿しい………) 自分を叱咤し、ごほんと咳払いを一つ。 「なんだ?」 「催眠術を掛けて欲しいの」 「………。は?」 突拍子もない話に、ちゃぶ台の上の缶ビールに伸ばしかけていた手を止め、思わず小首を傾げる。 まじまじと君華の顔を見つめても、その顔にふざけている様子はなかった。 「学校のお友達のお父さんが、催眠術を掛けられるんだって。だからお父さんもできるんじゃない?」 そう言って、糸の先に五円玉を括りつけたものを手渡してくる。 「催眠術って………」 「その子が言うには、催眠術を掛けられている間の事は“何も覚えてない”らしいんだけど、ふわふわして気持ちいいんだって。どんな感じなのか私も試してみたいの。だから、お願い♪」 「ははは。子供らしいな」 (やっぱ、ただの子供じゃないか……こんな単純な仕掛けで…) 上目遣いで懇願してくる年相応の可愛らしい様子に微かな安堵を抱く。 と、同時に、 (もうずいぶんと一緒に遊んでやってないしな………) という罪悪感も覚えた。 普段、酒を飲んでいる時の自分が、妻や娘に怖がられているという自覚はある。 だが、どうしても止められないのだ。 地を這いつくばうように仕事にしがみつく俺を、同情や侮蔑の眼差しで見つめてくるプロデューサーや監督、スタッフたちの目線。 そして、自分よりも後輩なのにちやほやされている若手俳優たちの眩さ。 そのような事を思い出す度に、自分のみじめさを突き付けられるようで、酒やパチンコに逃げてきた。 文句も言わずに懸命に働いて自分を支えてくれている妻さえ、本心では俺の事を馬鹿にしているのではないかと疑ってしまう。 そんな疑心暗鬼に陥る自分にまた自己嫌悪が込み上げてきて。 酒を飲んでは暴言や暴力を振るう、負の循環。 今もまた、競馬新聞を読みながら無意識にビールに手を伸ばしていた。 だけど、たまには君華と遊んであげるのもいいかもしれない。 「ダメ?」 「分かった分かった」 不安そうにこちらの顔色を窺う君華に、わざと渋面を作りつつ頷いてやる。 本当は、遊んで欲しいとせがんでくれることが堪らなく嬉しかったのに。 (こんな俺を……まだ、父親だと思ってくれてるんだな………) ぐっ、と込み上げてくる熱い感情を咳払いで誤魔化し、 「ほんと?やった!」 満面の笑顔を浮かべる君華の前に、糸の着いた五円玉を垂らす。 「えっと…じゃあ行くぞ」 「うん!」 「君華はだんだん眠くな~る、眠くな~る……こんな感じか?……君華はだんだん眠くな~る、眠くな~る」 それっぽく聞こえるようにとわざと声を低めにし、ゆっくりと糸を左右に振る。 君華はワクワクが止まらないと言った感じで瞳を輝かせながら、前のめりになって五円玉の動きを追う。 キャミソールの緩い胸元から覗く柔肌に視線を奪われそうになるのを何とか堪えながら、糸を振り続ける。 「君華はだんだん眠くな~る、眠くな~る………君華はだんだん眠くな~る、眠くな~る」 すると、次第に君華の瞼が重たそうに震え、瞳が眠そうになっていくではないか。 「ふわぁ………」 欠伸まで漏らし始める。 (おいおい。まじか………) 驚きつつも、 「君華はだんだん眠くな~る、眠くな~る………」 とさらに続けていくうちに、ゆらゆらと船を漕ぎ始める君華。 その肩から、キャミソールのひもがずり落ち、 「っ………」 膨らみかけの乳房、その上半分が覗く。 「君華はだんだん眠くな~る、眠くな~る………」 呪文を唱えながら、君華の様子を窺うも、その眼差しに光はなく、虚ろそのもの。 思わず、ごくり、と生唾を飲み込んでしまう。 (ば、馬鹿な………そんな………) 動揺する脳内に、君華の言葉が再生される。 ―――催眠術を掛けられている間の事は“何も覚えてない”らしいんだけど、ふわふわして気持ちいいんだって。 (な、何も覚えてない………) いつの間にか、はぁはぁ、と呼吸が荒くなっていた。 鼓動が早鐘を打ち、ズボンの下でペニスに熱い血が流れ込んでいく。 (娘に。そんな、娘なのに………) 懸命に踏み留まれと叫ぶ理性に対し、手は欲情に突き動かされるまま、もう一方の肩紐を外していた。 キャミソールがずり落ち、膨らみかけの、だが十分に“女”を感じさせる双乳が露になる。 顔を近づけると、いつも君華から漂う良い香りが強くなった気がした。 深く息を吸い込むと、頭がふわふわしてくる。 恐る恐る、右の乳房を掌中に収める。 未成熟な果実を思わせる、まだ奥に芯を感じる柔らかさ。 君華は何の反応も示さない。 (本当に、催眠術に掛かってる………のか?) まだ半信半疑だったが、高鳴る鼓動に促されるまま、今度はより大胆に、左の乳房に舌を這わせる。 舌先に感じる、瑞々しい肌の感触。 次の瞬間には我を忘れ、君華を畳の上に押し倒していた。 荒い呼吸を繰り返し、目を血走らせながら、胸に無遠慮にべろべろと舌を這わせ、揉みまくる。 (君華、君華、君華………!) 脳内で何度も何度も、娘の名を叫びながら、まだ幼さが残る肢体を無我夢中で舐め回し、唾液塗れにしていく。 ここ2週間ほど、君華の色気に当てられ、煮え滾ってきた情欲に完全に火がついてしまった。 舐めれば舐めるほど、頭の奥が痺れ、甘く蕩けていく。 ズボンの中でペニスが震え、我慢汁が滲みだしていくのが分かった。 (俺は、俺は何をやってるんだ。こんな事、すぐにやめないと……) そう考える思考とは全く反対に、舌を肌に這わせるのを止める事ができない。 乳房を舐め、乳首を吸い、お腹に舌を這わせ、太ももにちゅぱちゅぱとキスマークを付けていく。 そして再び、乳房へ。 まだまだ浅い谷間に鼻先を突っ込み、ふがふがと深呼吸を繰り返す。 すると唐突に、ふわり、と頭を抱き締められた。 「っっ………」 胸元に顔を埋めたまま恐る恐る見上げると、君華の目と目が合った。合ってしまった。 先程まで虚ろだった目には、理性の光がしっかりと宿っていて。 「き、君華っ………催眠術が解けて………」 言い訳のしようもない。 膨れ上がる絶望感に、何もかもが黒く塗り潰されていく。 だが、君華は悲鳴を上げるでもなく、非難するでもなく、ただただ優しく、俺の頭を撫でてくれた。 そして、穏やかに微笑む。 「解けてないよ、催眠術」 「………え?」 「催眠術を掛けられている間の事は“何も覚えてない”………だから、お父さんが何をしても、私は覚えてないの」 「お、覚えてないって………」 幾ら馬鹿な俺にでも、君華が言わんとしている事はわかった。 免罪符を与えようとしているのだ、と。 今、自分は実の娘に誘惑されている。 「だから、お父さんは催眠術で何でもできるの、手でも口でも、いつでもどこでも♥」 「だ、ダメだっ、親子でそんな事………」 「こ・こ♥」 「うっ………」 君華の足が、ズボン越しに痛いほどに勃起したペニスをつぅっと撫でる。 「こんなに大きくしておいて、何の説得力もないよ♥」 君華が、見ただけで男を欲情させるような妖艶な笑みを浮かべた。 そんな、蕩けるような笑みを浮かべたまま、器用に足指でジッパーを掴んで引き下げ、硬く怒張したペニスを取り出す。 「知ってるよ。男の人は、エッチな気分になるとここが大きくなるんでしょ?お・ち・ん・ち・ん♥」 一音一音を切りながら、親指の腹で亀頭をタップされる。 「お父さん、エッチな気分になってるんだね」 「あふっ♥そ、んなことは……♥♥」 「えー?違うの?」 「あぁっ……♥♥」 冷たく、柔らかな足裏にペニスを挟まれて思わず甘い声が漏れてしまう。 「違くないよね?だって、すっごいぬるぬるしてるもの♥これも知ってる。我慢汁って言うんでしょ?気持ちいい時に出るんだよね?」 瞬く間に溢れだした我慢汁が君華の足裏を汚し、ぬちゃぬちゃと卑猥な音を立てる。 「自分の娘にエッチな気分になって♥おちんちん大きくして♥我慢汁までい~っぱい出して♥お父さんは、へ・ん・た・い・さんなのかなぁ?♥♥」 詰られて、背徳感と共に快美感が込み上げてくる。 「あひんっ♥あああっ……し、扱かないでっ……♥♥」 「どうして?気持ちいいから?おちんちん、凄く熱くて。びくんびくんってしてるよ?気持ちよさそう♥」 「だ、ダメだっ、こんな事………っっ」 ゾクゾクと背筋を震わせる快楽に慄きながら、何とか君華から離れようとする。 だけども。 「逃げないで、お父さん」 優しく囁かれ、頭を撫でられ、乳房に頬を押し付けさせられて。 「ダメじゃないよ。変態でも、いいんだよ♥エッチな気分になっても。気持ちよくなっちゃっても、いいんだよ♥」 大人と子供。 跳ね除けようと思えば、簡単に跳ね除けられるはずなのに。 身体に力が入らない。 「だって、今、私は催眠術を掛けられてるんだもん。なぁんにもわからない。ただのお人形さん♥」 「き、みか………」 緩んだ口元から流れ落ちた唾液が、その胸を汚していく。 「だからいいんだよ。もっと、好きなだけおっぱい舐めて♥」 「で、でも………」 「大丈夫。後で、催眠術を解けばいいんだから。そうすれば私は全部忘れて、元通り。だから………」 「あぁっ♥」 足の甲で金玉をたぷたぷと揺すられ、さざ波のような快感に甘い声が漏れてしまう。 「ここに溜まってるもの、我慢せずにぜぇんぶ吐き出して。スッキリしよ♥」 (こんなの間違ってる。娘に欲情して、快楽に流されるなんて………) 理性は懸命に叫ぶ。 やめさせるべきだ、と。 しかし、まるで別の生き物のように動く足が齎す快感があまりに気持ちよすぎる。 たぷたぷと転がされる睾丸も。 つぅっと裏筋を撫でられるのも。 まるで、手のように器用に亀頭を握ってもぎゅもぎゅと揉まれるのも。 巧みな技巧によって齎される悦楽の前に、理性は劣勢を余儀なくされる。 「あぁっ♥な、なんで、上手すぎるっ……♥」 「あは♥褒められちゃった♪嬉しい」 「だ、だめ、君華っ、気持ちよすぎてっ………♥♥」 耐えようとする思いが、ぐりぐりと亀頭を踏みつぶされるだけで、どんどん崩れていく。 いつしか、俺は再び、君華の乳房にむしゃぶりついていた。 そうやって気を逸らさなければ、あっという間に絶頂に押し上げられてしまいそうで。 口中に次から次に溢れ出す唾液を塗りたくり、吸い、しゃぶり尽くす。 呼吸をする度に甘い香りが肺を満たす。 そんな俺の頭を、君華はずっと慈愛の籠った手つきで優しく撫でてくれる。 頭の中がどんどん真っ白になっていく。 ぷちんと音を立てて、ずーっと長い事張りつめていた糸が切れ、自然と目尻から涙が零れた。 同時に、とうとう我慢の堤防も決壊してしまった。 「イくっ♥イっちゃう♥き、君華っ♥ダメっ♥ダメなのにっ♥」 「いいよ、お父さん♥どびゅどびゅって、一杯出して♥」 両足でペニスを挟み、じゅこじゅこと激しく扱かれて。 「あああああっ♥♥イ、イぐぅぅぅぅっ♥♥」 叫び声をあげながら、俺は爆発した。 どびゅっ♥びゅくびゅくびゅくっ♥びゅるるるるっ♥♥びゅるるるるっ♥♥ 大量に噴き出した白濁液が、君華の身体を白く汚していく。 びくんびくんと震える俺の胸に頬を当て、君華が優しく抱き締めてくれる。 細い両足が腰に巻き付き、ぐっと体を沈み込まされると、 「君華っ………」 射精して尚、硬さを失わないペニスの先端が濡れた感触に当たった。 シャツを捲り、硬くしこる乳首をカリカリと爪で刺激しながら、君華が上目遣いに俺を見る。 「良いよ。お父さん♥」 何が“良い”のかを察し、俺は蒼ざめた。 「くっ♥あっ♥さ、さすがにそれはっ………」 「いいんだよ。催眠術を掛けられている間の事は“何も覚えてない”んだから………」 乳首を刺激されて体から力が抜け、重力に従って亀頭がくちゅりと沈み込んでいく。 「あぁぁっ………」 まだ入り口に僅かに潜っただけだというのに。 君華の秘所は熱く蕩け、淫らな唇のような襞が奥へ奥へと誘うように蠢いていた。 「お父さん、来て♥君華のおまんこ、一杯ズボズボして♥」 「っ………」 実の娘の口から飛び出す淫猥な言葉に、思わず脳髄が痺れてしまう。 だが、震える腰は、主の意思に反して更なる奥へと、快楽の高みへとペニスを突き入れようと動く。 「くっ、狭いっ………」 底なし沼に沈むようにペニスが進むにつれて、君華の表情も苦痛に歪む。 先端が何か膜のようなものにぶつかり、あっと思う間もなく突き破った。 「っっ………」 唇を噛み締め、何かに耐えるように震える君華。 はっ、として結合部を見やれば、破瓜の鮮烈な赤が目に入った。 「君華っ………!」 衝撃を覚える。 だが思えば、当たり前の事だった。 まだ、年端もいかない君華に、男性経験などあろうはずがないのだ。 「大丈、夫」 慌てて引き抜こうとする俺を、両手両足を絡めて君華が留める。 「でも………!」 「大丈夫だから………ね?」 諭されるように頭を撫でられる。 これでは、どちらが親かもわからない。 何よりも、誰の侵入も受け入れた事のない膣道によって齎される新鮮な悦楽によって、ペニスはさらに硬さを増していってしまう。 (もう我慢できない………っっ) 「すまん………!」 謝罪し、君華の軽い体に覆い被さる。 正常位で繋がり、できるだけゆっくりと腰を動かす。 「―――っ、――っ……んっ……あんっ♥」 最初は強張っていた君華の表情が徐々に緩み、声音も甘くなっていく。 それにつれて、膣も柔らかく蕩け、ペニスに絡みつき、扱きあげる。 「あん♥あん♥お、父さん……♥ジンジンって響くよぉっ♥」 すっかり“女”の表情で喘ぐ娘の姿に、腰の奥が疼く。 「君華っ♥君華っ♥」 「お父さんっ♥気持ちいいっ♥気持ちいいよぉっ♥あんっ♥あんっ♥」 徐々に動きを早くしていくと、君華の喘ぎ声は甲高いものに変わり、膣もぎゅむぎゅむと万力のような力でペニスを締め上げてくる。 「あぁぁっ♥来るっ♥なんか来りぅうぅぅっ……♥♥」 君華の身体が初めての絶頂にがくがくと震える中、 「くぁっ…お、俺もっ…もうっ……出るっ♥♥」 射精の瞬間、俺は最後の意地でペニスを引き抜いた。 びゅくんっ♥どびゅっどびゅっ♥びゅるるるるっ♥♥ 大量の白濁液を、君華の胸にぶちまける。 実の娘を犯してしまったという罪悪感と、これまでに感じた事のない解放感に震えながら。 *** 次の日以降、俺はイライラを感じる度に、ついつい五円玉を括りつけた糸に手を伸ばしてしまうようになった。 ダメだとわかっているのに。 やめなければならないとわかっているのに。 それを見た君華が妖艶な笑みを浮かべるだけで、ペニスが疼くのだ。 身体を内側から焦がすような情欲の火に焙られて。 甘美な背徳感に倫理観をぐずぐずに溶かされながら、五円玉を揺らし、催眠術を掛けていく。 その手に扱かれて。 その口にしゃぶられて。 その胸に擦りつけて。 その足に踏まれて。 そのおまんこに搾り取られて。 何度も何度も、“女”として今まさに開花しようとしている瞬間の裸身に白濁液をぶちまける度、俺のストレスは浄化され、暴力や暴言に訴える事はどんどん減っていった。 そんな日々が一か月、二か月、三か月と続く内、俺の変化を見て、妻は浮気を疑い始めたようだった。 しかし、もう俺には留まる事はできなかった。 暴力や暴言に走る自分に戻ってしまうのが怖かった。 だが、何よりも、もはや君華が与えてくれる快楽を手放す事ができなくなっていたのだ。 びゅくんっ♥どびゅっどびゅっ♥びゅるるるるっ♥♥ 吐き出された精液が畳を汚す。 「あーあ。また出ちゃったね、お父さん♥」 君華は笑いながら、俺の肛門に舌を突き刺す。 頬を床に押し当て、尻を突き上げた状態でうねうねと蠢く舌に腸を抉られ、まるで牛の乳絞りのようにペニスを両手でぐっちょぐっちょと扱かれて。 さらに、すっかり性感帯として開発されてしまった両乳首を自分自身でぐりぐりと弄りながら、俺は「あへ♥あへ♥」と気持ち悪い声を出して喘ぐ。 ここ数日、この体勢で俺を犯すのが君華のお気に入りだった。 娘を犯してしまった。 そんな罪悪感を抱くような関係は数日で逆転し、あっという間に俺は一方的に犯されるようになっていた。 びゅくんっ♥どびゅっどびゅっ♥びゅるるるるっ♥♥ がくがくと震えながら、この日6回目の射精で畳を汚す。 お茶を零したとか、ジュースを零したとか、様々な理由で誤魔化すのももはや限界な程、畳は多くのシミに覆われていた。 「ふふ。じゃあ、今度は仰向けになって♥」 言われるまま、力なく四肢を投げ出して仰向けになった俺の腰を跨ぎ、騎乗位でペニスをずっぽりと飲み込んでいく君華。 最初の時に比べれば、その動きは遥かに滑らかで。 その膣は俺のペニスの形を写し取ったかのようにぴったりで。 ぱんっぱんっぱんっと肉がぶつかり合う音を立てながら激しく、髪を振り乱して小さな体が乱舞する。 この方が興奮するでしょ?という理由で、裸の上に背負っているランドセルが激しく揺れ、教科書や筆箱が周囲に散乱する中、強すぎる快楽によって俺はあっという間に高みへと押し上げられてしまう。 「あぁっ♥は、激しっ♥だめぇぇぇっ♥♥」 そこで、ぴたっ、と君華が動きを止めてしまう。 寸止めを食らって、俺は酸素不足かのように喘ぐ。 「あぁっ、どうしてっ、どうして止めるんだ……」 「だって、もうすぐお母さん帰ってきちゃうよ?」 「あぁっ………」 指摘されるまで、思い出しもしなかった。 壁に掛かった時計を確認すると、確かにそろそろ、妻が仕事から帰ってくる時間に近づきつつあった。 君華が帰ってきてすぐに体を重ねてから既に2時間も経過していたのだ。 「だから、今日はこの辺で―――」 「ま、まだ大丈夫だから!」 腰を浮かし、ペニスを引き抜こうとする君華の太ももを抑えて、声を上げる。 「えー?」 「す、すぐ!すぐイくから!だから……我慢なんて無理だからぁ……」 にやにやと笑みを浮かべながら見下ろす娘に対し、父親としての威厳などかなぐり捨てて懇願する。 「お願いだから。イかせてぇ………」 「私の中に出したいの?」 君華がゆっくりと円を描くように腰を動かす。 「んふぁぁ……♥……出したいよぉ………♥♥」 「実の娘の中に、どびゅどびゅって?」 「出したい!お願いしましゅぅぅ……」 「お父さん、君華の事好き?」 「好き♥好きに決まってるぅぅっ♥♥」 「一番?」 「一番♥一番しゅきぃぃぃっ……♥♥」 「ふふ。ありがと。私もお父さんの事好き♥だから、いいよ♥どぴゅどぴゅさせてあげる♥」 「あ、ありがとう!ありがとうございまひゅぅ………」 再び君華が腰を動かし始める。 俺も、懸命に腰を動かし、そして、10分と耐えられず、娘の一番奥に白濁液を注ぎ込んだ。 だが、今度は射精したにも関わらず、君華は動きを止めなかった。 それどころか、さっきよりも早く、激しく振り続ける。 「んあぁっ♥も、もうイってるからぁぁっ……♥♥」 「だぁめ♥まだできるでしょ?」 既に7回も射精しているというのに、許してくれない。 その日の気分のままに、気ままに。 こちらの事情や心境に忖度する事もなく。 「あひぃっ……♥♥」 膣で締め付けられ、足の親指と人差し指で器用に乳首を捻りあげられるだけで、ペニスはむくむくと硬さを取り戻してしまう。 毎日毎日、根こそぎ精を全部搾り取られていた。 泣いても叫んでも、やめてくれない。 金玉が空っぽになっても犯して犯して犯し尽くされて。 もはや、俺の心は君華一色に染められていた。 もう、君華なしでは生きていけないだろう。 どんなわがままでも、君華の言う事には従ってしまう。 全てを君華に捧げよう。 俺はもう、そんな風に作り替えられてしまっていた。 このままではいずれ、人として壊されてしまうという危機感はあった。 (いや―――) 輝くような汗を飛散させながら小さな体が跳ねまわり、壊れたように屹立し続けるペニスをぐちょぐちょと締め付けられて、 「おふぅっ♥」 強力すぎる悦楽に、情けなく喘ぎながら8度目の白濁液を搾り取られる。 そんな自分の姿を客観的に見れば、もはや手遅れなのだろう。 とっくにもう、自分は壊されてしまっているのだ。 けれども。 「ねぇ、お父さん。今、幸せ?」 そう尋ねられれば。 「ああ……幸せだぁ……♥♥」 腑抜けきった顔で答えるしかない。 それは、偽らざる本心だった。 「―――これは、どういう事?」 怒りに震えた、冷え切った声音が耳に届いた。 視線をやれば、部屋の入り口に呆然と立つ妻・華香の姿。 (あぁ………帰ってきたのか………) 怒りと絶望に震える妻を見て、脳裏に浮かんだのはその程度の言葉だった。 「あ。お母さん、お帰り。遅かったね」 俺と繋がったまま、君華が汗にまみれた髪を掻き上げ、笑う。 「貴方………君華……まさか、そんな……貴女だったなんて……」 ぶつぶつと呟きながら華香は台所へ行き、まるで雲の上を歩いているかのような覚束ない足取りで戻ってきた。 その手には、包丁。 きっ、と眦を釣り上げ、君華を睨みつける。 その眼差しは娘に対して向けるものではなかった。 「君華!この淫売!泥棒猫!人でなし!君人さんから離れなさいっ!!」 叫び、包丁を中腰に構えて突進する。 「やめるんだ、華香!」 俺は咄嗟に君華を抱え上げて、華香の突進をかわす。 「なんで………なんで、庇うの。そんな女っ……殺してやるっ!!」 振り返った華香の両目から、大量の涙が零れ落ちる。 さらに、噛み締めた唇は破れ、血が滴っていた。 「華香………そんな女って……娘じゃないか」 「娘と浮気した貴方にそんな事言われたくないっ!父親を寝取るだなんてっ……!!」 いつも温厚な妻だった。 裕福とは言えない生活の中で苦労ばかり掛けたのに、文句一つに言わずに一緒にいてくれた。 そんな妻の、こんな鬼気迫る表情は見た事がなかった。 まさに夜叉という他ない面相だ。 「お母さん、どうして怒ってるの?」 君華は、そんな母親に不思議そうな視線を向けつつ、俺の足元にぺたんと座る。 そして、あろうことか、剥き出しのペニスを握り、軽快なテンポで扱き始めた。 「っ――――」 余りの事に、声もなく立ち尽くす俺と華香。 無音の世界にちゅこちゅことペニスを扱く音だけが響いて。 こんな状況なのに、すっかり手懐けられてしまったペニスはあっという間に硬さを取り戻す。 「あぁっ♥や、やめるんだっ、君華……はふ♥♥」 俺の感じる場所、感じる責め方を熟知している君華の愛撫に、俺は堪らず甘い声を漏らしてしまう。 「お父さん、すーっごく、気持ちよさそうでしょ?」 「あっ♥くっ♥」 右手でペニスを握りながら、左手で睾丸を転がされて。 「ほら。こうやって……」 れろれろと、亀頭に舌を這わされると、ぞくぞくとした感触が背筋を駆け上り、 「あっ……♥♥」 無様にも、どびゅどびゅとこの日9度目の白濁液を床にぶちまけてしまう。 君華は、まるで褒めて欲しいとでも言わんばかりに瞳を輝かせながら母親を振り返って、 「こうやってスッキリさせてあげるとね。お父さんは凄く優しいの。もう殴られたり、怒鳴られたりしなくていいんだよ?」 「何を………何を言ってるの……?」 肩を震わせながらも、既に華香は泣き止んでいた。 その目はまるで、単なる黒い穴のように虚ろで。 全身から陽炎のように殺気が立ち昇っていた。 「どうしたの?お母さん。これでまた家族三人仲良く―――」 「ふざけないでっ!」 叫び、再び華香が君華に向けて突進する。 「お父さん、お母さんを止めて」 俺は寸前で二人の間に割って入り、華香を抱き止めた。 それは、果たして自分の意思だったのか。 それとも、君華の命令に従っただけなのか。 判然とはしなかったけれども、 「うぐっ………」 脇腹を貫かれる激痛に、思わず顔が歪む。 「あっ…き、君人さん……」 ふらふらと距離を取った華香は、俺の腹に刺さった包丁と、溢れ出す血潮を見て青褪めた。 「なんで、そんな、私……あ、ああ、あああっ……き、君人さんっ、ご、ごめ、ごめんなさいっ……!!」 その場にぺたんと頽れ、顔を覆って慟哭する妻を、俺は精一杯の優しさを込めて抱き締めた。 「俺が悪かった。だから、気にしないでくれ」 体中の熱が流れ出していくような感覚によろめき、膝をつく。 寒さと、急激な眠気が襲ってきた。 様々な感情が込み上げてくる。 だが、それらすべてを伝える時間はなさそうだ。 「君華を許して……やって……くれ……」 華香の服をもべったりと赤く汚しながら、崩れ落ち、俺の意識は途絶えた。 *** 父さんが動かなくなってから暫くして。 お母さんは顔を挙げると、父の遺骸から包丁を引き抜いた。 「許さないから……私は……君人さんさえいればよかった。君人さんを愛して。君人さんに愛されて。それだけで幸せなの。だから……君人さんを独占するために…社長に体を差し出して、君人さんの仕事を他に回すようにお願いしたのに……君人さんに私だけを見てもらうために、ゴムに細工して子供まで孕んだのに……君人さんが私の側に居てくれたから……ここまで頑張ってこられたのに…貧乏なんて、苦労なんて、どうでもよかったのよ………あんたなんか…私から君人さんを奪うあんたなんか………絶対に許さない……」 怨嗟の籠った眼差しを私に向け、呪いの言葉を口にする。 「貴女は殺さない。地獄で、私はまた君人さんと一緒に暮らすわ。あの人には私が必要なの。あの人の傍にいて良いのは私だけ………ふふ、そうよ、今度は二人っきりで……もう絶対に離れない、放さない………貴女なんか要らない…今度は貴女なんか産まないから!」 凄絶な笑みを浮かべ、母は、父を刺した包丁を、己の喉に突き立てた。 噴き上がった鮮血は天井を濡らし、私に降り注ぐ。 生ぬるい血を雨のように浴びながら、私の意識は暗闇へと堕ちていった。 それから、どれくらいの時間が経ったのか。 気づいた時には私は毛布に包まれて、呆然と部屋の隅に座っていた。 部屋の中では、警察官たちが忙しそうに動き回っている。 ―――どうして? ―――なんでこんなことに? ―――私はただ、家族三人で仲良く暮らしたかったはずなのに。 ―――どこで間違ったの?何が間違っていたの? 心が寒い。 目の前が真っ暗な闇に包まれているかのようだった。 肩を擦られて、視線を向けると。 佐伯さんの優しい笑顔があった。 高級そうな絹のハンカチで、私の頬についた血を拭い、 「大変だったわね」 そう言って、私を抱き締め、髪を撫でてくれる。 包容力の塊のような優しい温もりに、冷えた心が温められていく。 「貴女は何も間違っていないわ」 「じゃあ……なんでこんなことに………」 声を震わせる私の問いに、佐伯さんはゆっくりと首を振る。 「いずれわかる時が来る、とは言わないわ。選ばなかった選択肢の先に何が待っているかなんて、誰にも分らないの。でも、これだけは信じて?お父さんは、自分の意思で、貴方を助けようとしたの。身を捨ててね」 「お父さん………」 「貴女には、男が命を賭けるだけの価値がある。それは忘れないで。貴女は素晴らしい」 「価値………。素晴らしい………」 「そう」 佐伯さんの声が心地いい。 その言葉が、深く心に刻まれていくのが分かった。 「私はずっと、貴女のような子を探していたの」 「私、みたいな………?」 「そう。今度、栗園さんに新しい事業を立ち上げてもらおうと思ってるの。君華ちゃんみたいな身寄りのない子たちが一緒に暮らす事のできる施設よ。貴女さえよかったら、私たちは歓迎するわ………」 「君が、佐倉井君華ちゃんだね?」 新たな声に視線を上げると、トレンチコートを着た刑事らしき男性が立っていた。 その傍らには栗園さんが寄り添うように立ち、その右手は他の警察官には見えないようにトレンチコートの中へと伸びている。 「あふっ♥……じ、状況から見てっ……んんっ♥……ご、強盗のせいだと……あぁっ♥……思うけどぉぉっ……ど、どう?♥♥」 弛緩した表情で、涎を垂らし、びくびくと震えながら尋ねられて。 私は佐伯さんと栗園さん。 そして、遺体袋に収容されていく両親の亡骸を見てから。 「………はい」 小さく、頷いていた。 「両親を殺したのは、強盗です。怖かったので、顔は見てません………」 *** その後、身寄りがなかった私は栗園さんが院長を務めるヴェイン孤児院へと引き取られた。 そこで、同じような境遇の子供たちと共に中学卒業まで育ち、全寮制の私立ヴェイン学園第二分校に入学する事となる―――。 毒蟲集う、壺の中へと―――。 壶中毒4 满电车 「うわー、人一杯だね、歩夢」 駅の改札を通り、ホームに出たところで傍らから嫌そうな声が聞こえた。 ホームはびっしりと人で埋もれ、熱気がもわもわと立ち込めているようだった。 思わず顔を顰め、傍らを振り返る。 「ごめんな、絵梨。生徒会の仕事が長引いたばっかりに……やっぱ、先に帰って貰っとけばよかったな」 「いいっていいって。待ってるって言ったのは私だもん。学校で待ってるのも、映画館前で待ってるのも一緒じゃん。なら、一緒に帰る方がいいって」 セミロングの薄明るい茶髪を振りながら、絵梨が朗らかに笑う。 「絵梨………ありがとな」 (めっちゃ、ええ子やぁ………) 心の中で、しみじみと噛み締める。 「じゃ、行くか」 「うん!」 差し出した右手を、絵梨が恋人握りで握る。 僕―――工藤歩夢は、恋人である宮川絵梨の手を引きながら、少しでも空いている列に並ぼうと帰宅ラッシュの中を掻き分け、前進を開始した。 そんな、どこにでもいる初々しい恋人たちの姿を、目を細め、薄く微笑を浮かべながら見つめている人物がいることなど全く気づきもせずに。 *** 今日これから観に行く映画の話をしているうちに時間は流れ、聞き取りづらい早口のアナウンスに続いて、電車がホームに滑り込んでくる。 先頭車両の1番前の扉。 真ん中あたりの車両に比べれば、まだわずかにマシという程度の混み具合。 さして珍しい電車でもないのに、カメラを構えて夢中でシャッターを切りまくる撮り鉄たちを横目に、開いた扉から吐き出されてくる人々を通すために脇に寄る。 やがて、降りてくる人の列が途絶えると、人の流れが電車の中に吸い込まれていく。 何とか角を確保して絵梨を導き、彼女を守るように両手を壁に当てて踏ん張る。 背中にガンガンと鞄やら何やらが当たり、足はげしげしと踏まれたり蹴られたり。 「大丈夫?」 思わず顔を顰めると、上目遣いに絵梨が心配そうに訊いてくる。 「な、なんとか……うおっ」 頷こうとした瞬間、強い衝撃とともに押し退けられ、よろめく。 その拍子に絵梨の傍から強い力で引き離されてしまった。 「歩夢!」 「だ、大丈夫!」 心配そうな絵梨の声に慌てて返事を返す。 絵梨との間に、数人の客が容赦なく流れ込んでくる。 小柄な絵梨は人並みに飲まれ、サラリーマンの肩越しに鼻から上ぐらいが見えるだけになってしまう。 ぎゅうぎゅう詰め状態の中で人を掻き分けて絵梨の元に辿り着くのは難しそうだった。 まるで天の川によって引き裂かれた彦星と織姫かのような。 (とか、さすがにバカップル過ぎるな……) 一瞬抱きかけた妄想を、苦笑と共に振り払う。 (ま、まぁ、絵梨は角にいるし、大丈夫だろ……) こちら側の扉は、5つ先の駅までは開かない。 そして、その駅は二人が降りる駅だった。 (まぁ、後で、ジュースでも奢るか……) 一緒に帰ろうと待っててくれていたにもかかわらず、あっさりと引き離されてしまったことに罪悪感を覚える。 償う方法を考えつつ、少しでも体勢を安定させようと吊り革を探してきょろきょろしていると、ふと、鼻先を甘い香りが過った。 肩越しに視線を向けると、後ろに立っている女性から香っているようだった。 俯いているために顔は見えないが、サラサラの黒髪ロングがとても美しい。 僅かに見える白い肌もとても綺麗で、顔が見えなくとも、きっととんでもない美人なのだろうと想像させる、そんな女性。 こんな暑苦しい空間にも関わらず、汗一つ掻いていない。 汗臭い匂いに満ちた鉄道の中で、彼女だけさながら清涼な水辺に佇んででもいるかのような静けさや涼やかさを醸し出していた。 その身を包んでいるのは自分たちが着ているものとは違う高校のものだったが、見覚えはあった。 というよりも、この辺りでは有名な高校のものだった。 (これ……ヴェイン学園の……) 私立ヴェイン学園。 新興財閥ヴェイン・グループが運営する私立高校である。 美人の多い学校として、男子高校生の中で熱く注目されている高校だ。 もっとも、同時にさながら都市伝説かのような俄かには信じがたい噂話も多く耳に入ってくる高校でもあるが。 と、視線に気づいたのか、女性が顔を上げる。 やはり、鼻筋の通ったとんでもない美人だった。 切れ長の美しい瞳と目が合ってしまい、鼓動が高鳴ってしまう。 「あ、す、すいません」 慌てて視線を前に戻す。 (絵梨というものがありながら……) 見知らぬ女性に思わずときめいてしまった事に微かな罪悪感を覚える。 「もしかして……工藤君?」 まるで、軽井沢高原に吹く風の様な涼やかな声音が、罪の意識に僅かに唇を噛んでいた僕の耳朶を震わせた。 「えっ……」 僕は驚いて、肩越しに振り返った。 女性の、形の良い艶やかな唇に、微笑が浮かんでいた。 「私の事…覚えてない?」 そう言われて、改めて女性の顔をまじまじと見つめる。 閃きは、すぐに訪れた。 「もしかして……千鳥先輩ですか?」 「ふふ。当たり♪」 嬉しそうに、女性が笑う。 まるで、一輪の花が華開いたかのような、艶やかな笑顔だった。 千鳥緋葉(ちどり・あけは)先輩。 僕が中学時代に所属していた文芸部の先輩だった。 当時よりもだいぶ大人びた風貌になっていたため、先ほどの一瞬では気づくことができなかったのだが、改めてよく見てみれば、左目尻にある3つの小さな泣きボクロは昔のままだった。 「久しぶりだね、工藤君」 「ど、ども、ご無沙汰してます」 「だいぶ背伸びたんじゃない?」 「そ、そうっすかね……千鳥先輩は……なんか、すげぇ綺麗になりましたね」 「ふふ、そう?ありがと」 千鳥先輩が嬉しそうにはにかむ。 その顔を見て、思わず鼓動が高鳴ってしまう。 彼女は僕にとって、憧れの存在であり、初恋の相手でもあったのだ。 結局、思いを伝えられぬまま、彼女は卒業してしまい、それ以来、一度も会っていない。 ふ、と千鳥先輩の視線が僕の肩越しに流れる。 その視線の先を追うと、絵梨がいた。 こちらの様子に気づく事もなく、スマホを弄っている。 「―――彼女さん?」 「え?……は、はい」 「可愛い子ね」 「そ、そうっすね」 「否定しないんだ」 くすくすと笑いながら千鳥先輩が首を傾げ、上目遣いに僕を見る。 「嘘は吐きたくないんです。絵梨は……僕の大切な彼女なんで」 千鳥先輩の視線を感じつつも、絵梨の方を見たまま答える。 恥ずかしさで、耳まで真っ赤になっている事だろう。 「良いと思う」 千鳥先輩の声が、さっきより近い。 僕の肩に、とん、と小さな顎を乗せてくる。 「あ、ありがとうございます」 どくん、どくんと、鼓動が早鐘を打っていく。 千鳥先輩の方を振り返る事ができない。 「工藤君のそういう処、昔から変わってないね」 「そうですか?」 「うん。いつも私の事、褒めてくれた」 千鳥先輩の吐息が、耳朶を擽る。 「それは……先輩が綺麗な人であるのは事実ですから」 「ふふ、嬉しい。じゃあさ………」 すーっ、と先輩の両腕が脇の下を通って僕の前に回り込んでくる。 密着度が強くなり、背中でむにゅりと柔らかなものが潰れる感触に頭の中が沸騰しそうになる。 中学の頃は、胸が大きいという印象はなかった。 少女から女性へ。 先輩の成長ぶりに、戸惑ってしまう。 「私と彼女さん。どっちが可愛い?」 「せ、先輩っ……」 抱き締められながら、耳元に囁かれた意地の悪い質問。 (そういえば昔からこういう悪戯をよくする先輩だったっけ………) 自分の容姿がずば抜けて秀麗であることを知っているのか知らないのか、人がドギマギするのを見て楽しんでいるかのような、そんな先輩だった。 「や、やめてください。もし絵梨がこっちを見たら……」 「ふふ、どうなっちゃうんだろうね……」 「だ、だめですよ、こんなこと……」 千鳥先輩の温もりと甘い香りに包まれながら、首を横に振る。 「じゃあ教えて?私と彼女さん。どっちが可愛い?」 ふぅっ、と耳に吐息を吹きかけられ、前に回された両手がさわさわと胸元を撫でてくる。 「んぅっ…ど、どうしてこんなこと……」 「どうしてかなぁ。もしかしたら、ヤキモチかも」 「や、ヤキモチって………」 「私、ずぅっと工藤君の事、好きだったんだよ?」 「う、嘘です……」 「あら。どうして?」 「だって、僕なんか……先輩には釣り合いません」 「そんなことないよ。可愛くて、優しくて、でも頼りになって。工藤君も、私の事、好きだったでしょ?だから、告白してくれるの、ずうっと待っていたんだよ。卒業式の日も部室でずぅっと。でも、君は来なかった」 「そ、それは………すいません」 「ふふ、いいよ。もう、昔の事だから」 もし、あの日、部室に行って先輩に告白していたら、付き合っていたのだろうか。 憧れだった、初恋の千鳥先輩と。 (だけど、今の僕には絵梨がいるんだ……) 込み上げて来そうになる後悔を押し殺す。 昔のことを後悔するのは、今を否定する事になってしまうから。 「っっ……」 くるくる、と乳首の周りを丸くなぞられ、ぴくっと体が震える。 「敏感なんだね。可愛い」 淡々と囁く千鳥先輩の感情がわからない。 「か、からかわないでください……」 「ごめんごめん。幸せそうだったから、ちょっと意地悪したくなっちゃって」 「か、勘弁してください……絵梨と先輩のどっちが可愛いかなんて、答えられません」 「ふーん……それってつまり、私を選ぶと彼女さんに申し訳なくて、彼女さんを選んじゃうと嘘になっちゃうからって事?」 「っ、そ、そんな事は………」 「目、めっちゃ泳いでる。ふふ、工藤君の気持ちがわかって私、嬉しいな」 電車が隣の駅に到着し、反対側の扉が開く。 何人かが降りて、何人かが乗ってくる。 その動きに合わせて、千鳥先輩と距離を取るべきだったのかもしれない。 だが、僕が動くよりも、千鳥先輩が動く方が早かった。 「あっ………」 手が掴まれ、引っ張られる。 バランスを崩した僕の身体が半回転し、千鳥先輩と向かい合う格好に。 今度は両腕が背中に回され、正面から抱き寄せられる。 甘い香りを柔らかな肢体が、僕の両腕の間にすっぽりと収まってしまう。 僕は電車の壁に両手を突いて、何とか身体を支えた。 その姿は、傍目には抱きあう恋人以外の何物にも見えないだろう。 肩越しに絵梨の方を窺うが、相変わらずスマホに夢中で、こちらの様子には気づいていないようだった。 最近始めたスマホゲームにハマっているという話を思い出した。 僕と一緒に居る時は、意識的にスマホを触らないようにしているとも。 「っっ、せ、先輩……何を……」 ホッとしたのも束の間、股間を襲う甘い刺激に、思わず声が上ずる。 千鳥先輩が僕の両足の間に足を差し込み、太ももで股間を擦り上げてきたのだ。 「あんまり大きな声出さないでね、工藤君」 薄く微笑を浮かべながら、千鳥先輩が僕の唇に立てた人差し指を当てる。 その間にも、規則正しく動かされる太もも。 スベスベで、弾力のある感触が、ズボン越しであるにも関わらず、官能的な刺激を齎してくる。 「抵抗したら、痴漢ッて、叫ぶから」 楽しそうに目を細めながら、千鳥先輩が耳元で囁く。 「そんな事になったら……彼女さん、どう思うかな?大好きな恋人が痴漢行為だなんて。幻滅するかな。怒るかな。それとも……泣いちゃうかな。きっと、一生のトラウマだよね。男性不信になっちゃうかも」 「やめて……ください……お願いですから……」 擦れた声で懇願する。 昔から悪戯好きな先輩ではあったが、さすがにこれは度が過ぎている。 脳裏には、嘆き悲しむ絵梨の姿が浮かんでいた。 「簡単なゲームだよ。工藤君が降りる駅まで我慢できたら工藤君の勝ち。我慢できなかったら、私の勝ち。あと、駅4つ分。余裕でしょ?」 「が、我慢って………?」 「ふふ、勿論。おちんちんからぴゅっぴゅってする事だよ」 「っ……」 先輩の口からナチュラルに飛び出してきた淫猥な言葉に、衝撃を受ける。 「わかった?」 「わかり……ました」 何故、僕たちが降りる駅を知っているのか。 そんな疑問が脳裏を過ったが、元より、僕にはこの提案を断る選択肢などない。 (なんとしてでも我慢して見せる……) 「いいお返事♪……彼女さんにバレない様に、ヒ・ア・ソ・ビ❤…楽しみましょ」 柔らかな感触が首筋に押し付けられ、濡れた感触が上下に動く。 キスされ、舐められている。 その事実を前に、身体が硬直してしまう。 そんな僕の初心すぎる反応を見て、千鳥先輩が目を細める。 「こういうの、初めて?」 「は、はい……」 「そうなんだ。ふふ、これ、リップの跡つかないから安心して。それとも……キスマーク付けてほしい?ちゅぅって、鬱血するぐらい思い切り吸ってあげようか?まるで、私のモノって証明するような刻印を刻むみたいに」 「や、やめてください……そんなことしたら、絵梨にバレる……」 「ふふ、そうだよね。でも、ちょっと期待してくれた?おちんちん、ぴくってしたよ?」 「っ……」 確かに一瞬、脳裏にキスマークを付けられた自分を想像してしまった。 慌てて、その淫らな妄想を振り払う。 だけど、男子高校生の健全な身体はとても素直だった。 「もう、こんなに……ふふ」 笑いながら、今までよりも強く太ももを押し当ててくる。 僕の股間は完全に勃起し、ズボンにはっきりとその形を浮かび上がらせてしまっている。 「っ―――」 柔らかな太ももにめり込む程の強さで押し付けられて、思わず声が出そうになるのを、千鳥先輩が掌で僕の口を覆って押し留める。 「声出しちゃ、だぁめ❤」 目を白黒させている僕の耳元で囁きながら、くすくすと笑みを零し、円を描くように太ももを動かす。 「分かってる?ここ、電車の中だよ?」 その電車の中で、このような悪戯を仕掛けてきている張本人の言葉とも思えない言葉を紡ぎつつ、僕の唇を割って、人差し指と中指が侵入してくる。 僕の舌が、先輩の二本の指に挟まれる。 千鳥先輩の指。 何故か微かに甘ささえ感じる千鳥先輩の指の味に、頭がくらくらしてくる。 「ふふ、夢中でしゃぶってる。私の指、美味しい?」 その問いに頷くのは屈辱的だったが、気づいた時には頷いてしまっていた。 千鳥先輩が僕の口中から指を引き抜き、唾液塗れの指に舌を這わせる。 ピンク色の厭らしい舌が、千鳥先輩の綺麗な指を這いまわり、僕の唾液を舐め取っていく。 現実とは思えない淫靡な光景に、鼓動がどんどん早くなり、股間に血が勢いよく流れ込んでいく。 千鳥先輩の指を舐める舌、押し付けられる唇。 そんな光景を眺めているうちに、口内に唾液が溜まっていく。 「キスもはじめて?」 問われて、無言で、こくり、と頷く。 「そっか」 千鳥先輩が嬉しそうに頷き、至近距離で唇を尖らせる。 所謂、キス顔。 僕がキスをするのを待っている。 (ファーストキスは絵梨と………) そんな思いも過った。 だが、艶々と輝くぷっくりとした唇の魅力に抗う事はできなかった。 僕は吸い寄せられるように顔を寄せ、唇を重ねてしまう。 重ねた瞬間、ちくり、と胸が罪悪感に痛んだ。 だが、そんな罪悪感も、伸びてきた千鳥先輩の舌によって、舌を絡めとられ、器用に扱かれるうちに桃色に塗り潰されていった。 千鳥先輩の両腕が僕の首に回され、後頭部をロックする。 より深く、千鳥先輩の舌が侵入してきて、僕の口内を我が物顔に暴れまわる。 ゾクゾクとした快感に、思考能力がどんどん奪われていく。 (キスってこんなに……気持ちいいのか……) 生まれて初めて味わう感覚に、酔い痴れてしまう。 手から力が抜け、学生鞄がすとん、と床に落ちる。 流し込まれる唾液を、こくこくと飲み干してしまう。 身体中がカッと熱くなるような感覚。 左腕で僕の後頭部をロックしたまま、千鳥先輩の右手が胸元を撫でまわす。 器用に片手でボタンが外され、シャツの中にひんやりとした手が侵入してくる。 くるくると乳輪の周囲を指が這いまわり、じれったさが募ってきたところで乳首の先端をカリカリと弄られる。 (っっ……!!) 喘ぎ声を発してしまいそうになるのを何とか堪える。 千鳥先輩に口を塞がれていなければ、果たして我慢できたか怪しいものだ。 乳首を弄り回される度、ズボンの下でペニスがぴくぴくと震え、先端から我慢汁が滲みだしてくる。 このままでは、太ももによる愛撫で、ズボンの中に精をぶちまけてしまいかねない。 隣の駅まで、ほんの数分で着くはずなのに、その時間が永遠にも感じられる。 千鳥先輩が口を離す。 二人の間に繋がった銀色の糸がキラキラと輝き、ぷつりと切れた。 はぁはぁと息も絶え絶えの僕に対し、千鳥先輩は呼吸一つ乱していない。 僕の肩に顎を乗せ、ふふ、と笑みを漏らす。 「工藤君のおちんちん、すっごく熱い。それにもう、ズボンの上からわかるぐらいヌルヌルになってるね」 左腕もシャツの中に侵入してきて、両乳首を同時に抓られる。 「んんっ―――!!」 思わず声を上げそうになって、自分の左手で思い切り口を塞いで何とか堪える。 「乳首弄られるのも凄く気持ちよさそう……。昔から思ってたけど、工藤君って絶対、Mだよね」 そんなつもりはなかった。 至って普通だと、今の今まで思っていたぐらいだ。 だが、千鳥先輩の愛撫によって他愛もなく踊らされている自分を顧みると、否定できない気もする。 それに、否定しようにも、手を外したら喘ぎ声を上げてしまいそうで、手を離せない。 「―――ね、工藤君。このままイきたい?私の太ももでスリスリされて、どっぴゅんって出しちゃいたい?きっと、凄く気持ちいいよ❤」 千鳥先輩の誘惑に、僕は思い切り首を横に振る。 「ふふ、頑張るね。彼女さんの事大好きなんだね」 確かに、このまま射精するのは気持ちいいだろう。 だが、それだけはできない。 絵梨を裏切るわけにはいかないのだから。 電車が緩やかに減速し、駅に到着した。 残りは、駅3つ。 (絶対に耐えて見せる………) やがて扉が閉まり、電車が動き出す。 「っ、先輩っ……!」 動き出してすぐ、僕は目を剥いた。 千鳥先輩の右手が、股間を撫でまわし、あろうことかズボンのファスナーを下ろし始めたのだ。 ぶわっと全身に冷や汗が浮かんでくる。 (そんな、まさか……電車の中で……!?) ファスナーを下ろす音が、いつもよりも大きく聞こえて、鼓動がバクバクと早鐘を打つ。 この音に誰か気づくのではないかと思うと気が気ではない。 しかし、周囲の乗客たちは二人の様子に気づく事もなく、それぞれの世界に没入している。 それは、絵梨も同様だった。 (き、気づかないのか……これでも……) 気づかれたい訳では決してなかったが、車内の乗客がここまで周囲で起きている出来事に無頓着だという事実は正直に言って衝撃だった。 そんな事を考えているうちに、ファスナーが下ろされ、千鳥先輩のひんやりとした手がズボンの中に侵入してくる。 パンツの上から形や大きさを確かめるように握られる。 「大きい。それに凄く熱い。血管が浮いてて。めっちゃヌルヌルしてる」 手で確かめたことを、耳元に囁かれる。 口ではどうとでも言える。 だが、身体は正直だ。 快楽を求めてギチギチに勃起し、ヌルヌルと我慢汁に塗れているペニスが何よりの証。 手がパンツの中に侵入してきて、直接握られた。 「―――っ……」 熱いペニスを握る冷たい手の感触が、震えるほど心地いい。 脳髄を直撃する快楽に声を上げそうになるのを、唇を噛み締めて何とか耐える。 中学の頃、憧れを抱いていた女性。 憧憬の念が強すぎて、情欲の対象として見たことなどなかった。 そんな相手に自身の勃起した醜いペニスを握られる事は、喜びではなかった。 まるで、神聖なものが汚れたものによって冒涜されているような。 心の奥底に仕舞っていた大事なものに、ひびが入っていくような。 だが、彼女を汚しているものも、傷つけているものも自分であるという現実が、余計に理性を狂わせていく。 親指と人差し指で作った輪っかを、カリに引っ掛けながら、扱かれる。 ぞくぞくとした快美感が背筋を駆け上っていく。 悲しみ。快楽。 怒り。悦楽。 屈辱。愉悦。 喪失感。逸楽。 齎される相反した感情が、心をぐちゃぐちゃにしていく。 負の感情が膨れ上がって、目尻から流れ落ちていく。 右手でペニスを扱きながら、左手で乳首を転がされ、さらに首筋にれろれろと舌が這わされる。 淫らな3点責めに、どんどん射精欲が込み上げていく。 未だ童貞の男子高校生に、このような刺激に耐える術などあろうはずもない。 睾丸が持ち上がり、亀頭が膨らみ、身体が射精に備えて硬直する。 (ごめん、絵梨―――!) 心の中で、恋人に謝罪する。 その次の瞬間、僕が射精しそうになる瞬間を完全に見切って、千鳥先輩が手を止めた。 根元をぎゅっと握って、射精を押し留める。 「っ、ぐっ、ぁっ……」 僕は苦悶に身体をよじりながら、歯を食い縛って声だけは我慢する。 だが、歯の間から漏れる呻き声だけは抑えようがなかった。 「そうそう、工藤君。もし、もう降参~、これ以上我慢できないから、イかせてぇ~って思ったら、彼女さんより私の事が好き❤って言ってね」 千鳥先輩の言葉に愕然とする。 「っっ、そんな事っ、い、言えるわけっ………」 「ふふ、じゃ、我慢しなきゃ。我慢すれば、工藤君の勝ちなんだから」 余裕の微笑を崩すことなく、千鳥先輩が笑う。 溢れ出した我慢汁をペニス全体に広げ、ぬるぬると扱きながら。 「ぜ、絶対に……我慢してみます」 はっきり言って、自信などない。 だが、千鳥先輩の思い通りになる訳にはいかない。 (僕が愛してるのは、絵梨なんだから………) 「ふふ、楽しみだなぁ。嘘を吐けない工藤君が、私に告白してくれるの♪」 笑みを零しながら、千鳥先輩があろうことかペニスをズボンから引っ張り出す。 沸騰しそうな熱の塊に外気が触れて、ぞくりと背筋が震えた。 「ちょっ、先輩っ!これはさすがにバレます!!」 慌てて抵抗しようと伸ばした右手に押し付けられたのは僕がさっき床に落としていた学生鞄だった。 「大丈夫だよ。鞄で隠してれば。ちゃんと隠しててね」 無茶苦茶な状況であるにも関わらず、千鳥先輩は余裕の態度を全く崩さない。 僕は慌てて鞄で反り返ったペニスと、そんなペニスを逆手で握る千鳥先輩の手を、学生鞄で他の乗客の目線から遮る。 とはいえ、小さな鞄一つで、あらゆる角度からの目線を遮る事など不可能だ。 冷や汗を存分に掻きながら周囲の様子を窺うが、こちらに視線を向けている乗客は一人もいなかった。 千鳥先輩が手を動かす。 大量に溢れ出した我慢汁を手に絡めながら扱き上げられて、一度は沈静化しつつあった射精欲があっと言う間に込み上げてくる。 僕は右手で学生鞄を持ち、左手で喘ぎ声を零してしまわぬように自身の口を塞ぐという体勢で、ひたすら快楽に耐えるしかない。 窓の外を流れる風景に視線を向ける余裕すらなく、あとどれぐらいで次の駅なのかもわからない。 千鳥先輩の手の動きに合わせて、くちゅくちゅと淫らな音が脳裏に響く。 電車の走行音に紛れているとはいえ、この音に気付く乗客がいるかもしれない。 肝が冷えるとはまさにこの事だ。 歯を食い縛り、必死に快楽に耐える。 だが、あっという間に限界を超え、頭の中が真っ白になっていく。 しかし、射精まであと1歩というところで、千鳥先輩は手の動きを緩め、最後の一押しをくれない。 「ふふ、降参?」 寸止めの苦悶に顔を歪める度、楽しそうに先輩が囁く。 その度、僕は首を横に振る。 そして、再び千鳥先輩が手を動かし始め、僕の全身を快楽が貫いていく。 その連続。 時間にすれば、ほんの数分だったはずだ。 だが、その時間は僕にとって無限にも等しいものだった。 だんだんと意識が朦朧としてきて、ここがどこで、自分が今何をしているのかもわからなくなってくる。 「彼女さんと私。どっちが好き?」 千鳥先輩の問いかけに、思わず頷いてしまいそうになる。 「え……え、絵梨……」 「ふふ。ざーんねん」 それを懸命に、ぎりぎりのところで堪える。 だが、もはや僕は崖っぷちに追い詰められていた。 このままでは、千鳥先輩の問いに頷いてしまうのも時間の問題だろう。 とはいえ、明けぬ夜がなく、止まぬ雨がないように、駅に着かない電車もない訳で。 やがて電車が減速し、車内アナウンスが次の駅に到着した事を告げる。 「よく頑張ったね」 微笑みながら、千鳥先輩が自身の右手を僕に見せる。 僕の我慢汁に汚れた右手。 その指一本一本に、千鳥先輩が厭らしく舌を這わせ、唇を押し付け、淫らな音を立てながら吸い付く。 「ちょっとしょっぱい。これが、工藤君の我慢汁の味なんだね」 厭らしいことを囁きながら、千鳥先輩がうっとりとした表情で笑う。 電車の扉が開き、人が動き出す。 やがて、扉が閉まり、走り出す。 残りは、駅2つ。 だが、動き出してすぐ、僕は異変に気付いた。 (千鳥先輩が……いない!?) 目を離したのは一瞬だったはず。 だが、視線を戻した時、目の前にいたはずの千鳥先輩の姿がなかった。 しかし、次の瞬間―――。 「んひぁぁっ……」 思わず声が漏れてしまった。 いきなり、股間を濡れた感触が包み込んだから。 予想外の出来事に快楽の声を抑えることができなかった。 慌てて視線を下ろして、愕然とする。 千鳥先輩はいなくなったのではなかった。 その場に、しゃがみこんでいたのだ。 そして、僕の勃起したペニスを咥え込んでいた。 狭くて、温かくて、とろとろの口の中で、柔らかな舌がうねりながらペニスに絡みついてくる。 無論、これまでに味わったことのない快楽だ。 一瞬にして、頭の中が桃色に染まる。 目の奥で、ばちばちと閃光が踊る。 睾丸の中で、精液が放出を求めてぐつぐつと煮え滾る。 溢れ出しそうになる喘ぎ声を、懸命に左手で口元を抑えて防ぐ。 「―――歩夢?大丈夫?」 「っっ……!!」 掛けられた声に、愕然とする。 声のした方を振り返ると、絵梨が居た。 先ほどよりも近い位置。 サラリーマンの男性一人を間に挟んでいるから僕の全身を見る事はできないだろうが、裏を返せば、二人の間にはサラリーマン一人しか遮るものがない状況。 ちょっとでもサラリーマンが体勢を変えれば、僕の股間を咥え込んでいる先輩の姿が絵梨の視界に入ってしまう。 絵梨は僅かに眉間に皺を寄せ、不審そうに僕を見ている。 僕は左手を外し、ぎこちなく笑いかけながら、何とか右手に持った学生鞄で、千鳥先輩の姿を隠す。 「だ、大丈夫だよ、絵梨」 「ほんとに?なんか顔色悪いし、凄い汗」 「う、うん……ち、ちょっと、んんっ、酔っちゃった、っっ、みたいで……」 絵梨と会話しているのもお構いなしに、千鳥先輩が顔を前後に動かす。 舌、頬粘膜、唇によって扱かれ、気を抜くと思い切り喘いでしまいそうだった。 ぶちゅっ、ずちゅっ、んちゅっ……。 淫らな音が聞こえる度、快楽と恐怖心に震える。 「酔ったの?大丈夫?」 心配そうに眉根を寄せる絵梨に、 「う、うんっ、だ、大丈夫、だからっ、お、おふっ、ぁぁぁっ…ん、んぐっ、し、心配しないでっ………」 何とか安心させようと笑みを浮かべるが、きっと物凄くぎこちない笑顔になっている事だろう。 「うん。あともうちょっとだから頑張って」 「あ、あぁ、ありがとう……」 (そ、そうだっ、あと、もう少しっ………) 千鳥先輩の頭が動く度、じゅっぷじゅっぷと卑猥な音が響く。 もしこの音に、誰かが気づいたら、終わりだ。 そんな事は千鳥先輩も先刻承知のはずなのに、まるでバレても構わないとでも思っているかのように容赦なく責め立ててくる。 だが、僕が射精しそうになると、動きをスローダウンさせ、根元をぎゅっと握って射精させてくれない。 「っぐぅっ……」 苦悶に顔を歪める僕を上目遣いに見上げて、目を細める。 言葉はなかったが、その度に脳裏に千鳥先輩の言葉が再生する。 ―――降参する? ―――私の事、彼女さんより好き? (くそっ、ぜ、絶対に耐えてみせる………!) その時、電車がゆっくりと減速していった。 (次の駅に着いたのか……) そう思って車窓に視線を向けるが、様子がおかしい。 ホームが見えない。 怪訝に思っていると、車内アナウンスが流れた。 聴き取りにくい声だったが、要するに前方の駅で線路内に人が立ち入り、確認のために暫く停車するという内容だった。 (そんな………) 心に絶望感が広がっていく。 「えー。もう少しだったのに、最悪。歩夢、大丈夫?」 絵梨が心配そうに尋ねてくる。 「あ、あぁ、ほんと災難だな。ま、まぁ、暫く待てば動き出すよ、きっと」 「うん。まぁ、まだ映画の時間まで余裕あるしね」 僕が何とか笑顔を浮かべて答えると、絵梨は頷き、再びスマホを取り出してゲームを始めた。 「―――折角もう少しで終わりだったのに。ふふ、これじゃいつまで掛かるかわからないわね」 いつの間にか立ち上がっていた千鳥先輩が耳元に囁く。 「っ………」 ひくひくと戦慄くペニスがサラサラの感触に包まれる。 視線を下ろして確認すると、白いレースがついた布だった。 一瞬ハンカチかとも思ったが、すぐにそれは違うとわかった。 「ふふ、びくんっておちんちん跳ねたわよ。わかったんだ、これが私の下着だって事♪」 千鳥先輩が笑う。 巻き付けた下着越しにペニスを握り、しこしこと扱き上げられる。 「可愛いデザインでしょ。白くて、サラサラで、フリフリで。これ、紐パンなの。ほら、見て。こんなに小さいのよ」 見せつけられる下着の面積の小ささに、ごくりと生唾を飲み込んでしまう。 これが、先輩の大事な場所を覆っていた布だと思うと、頭が沸騰しそうになる。 そのクロッチで亀頭を覆うように巻き付けられると、それだけで射精感がこみ上げてくる。 「もう射精したくて射精したくて、溜まらないんでしょう?」 (そんなの、射精したいに決まってる………) 何度も何度も射精寸前でお預けを食らって、もはや身体も心も限界だった。 「降参しちゃえばいいのよ」 「っっ……それは、できません……」 千鳥先輩の言葉に、心はぐらつく。 「でも、絵梨を裏切る事なんて僕には―――」 「射精できなくていいの?」 僕の言葉を遮って発せられた言葉に、どくんっ、と鼓動が大きく跳ねた。 (そうか………このまま降参しなければ……射精できない……) それはそうだ。 僕はそれを、望んでいたはずだ。 だというのに、どくんっどくんっと鼓動が早鐘を打つ。 (射精できない。このまま……?そんなの……おかしくなってしまう……) ぐるぐると思考が渦を巻く。 「実は、私は次の駅で降りるの。最寄り駅だから。だから、次の駅に着いたら、このゲームは終わり」 (次の駅………) まだもう一駅分あると思っていたのに。 (次で終わり………?) 「今日、家には誰も居ないの」 混乱してぐるぐると渦を巻く頭の中に、千鳥先輩の言葉が浸透していく。 「それってどういう………」 「ふふ。来る?」 意味深な微笑を浮かべた千鳥先輩が僕の左手を握る。 そのまま、自身のスカートの中に誘導される。 指先に、くちゅり、と柔らかく、濡れた感触が触れた。 「っっ………!」 衝撃に言葉を失う。 だが、当然だろう。 本来、ここにあるべき布は今、僕のペニスに巻き付けられているのだから。 電車内という公共空間の中で、今、千鳥先輩は―――ノーパンなのだ。 そして、指先に感じる柔らかな秘所の感触。 そこがぐっしょりと濡れているという現実を前に、思考能力は全く働かなくなってしまった。 「目が血走ってる。ちょっと怖いよ、工藤君♪」 野獣の如く吐息を荒らげる僕に、千鳥先輩が嬉しそうに笑う。 そして、僕の耳元に顔を寄せ、甘える様な声で囁く。 「―――ね、次の駅で降りましょう?彼女さんの事は放っておいて、私と気持ちいい事、しましょうよ。ね、工藤君♪」 満員電車の中で突き付けられた二つの選択肢。 僕が選んだのは―――。 降りる → 2ページへ 降りない → 3ページへ 車内アナウンスによって運転再開が告げられた後、ゆっくりと電車が動き出す。 ざわざわとしていた車内に、少しだけホッと安堵するような弛緩した空気が流れた。 「―――ふぅ、やっと動いたね」 絵梨も笑顔を浮かべて、スマホを仕舞う。 「………」 だけど、僕は答えなかった。 絵梨の声は聞こえていたにも関わらず。 電車が駅に滑り込む。 反対側の扉が開いて。 僕は―――千鳥先輩の手を掴み、人垣を掻き分けて電車を降りた。 「えっ、歩夢!?降りるのここじゃ―――」 驚きに目を見開く絵梨が僕を追いかけようとするが、人垣に阻まれ、彼女を車内に残したまま、その眼前で扉が閉まる。 絵梨の視線が僕と、僕の手と、僕と手を繋いでいる千鳥先輩とを忙しなく移動し、やがて何かを理解したようにその表情が絶望に歪む。 その目から涙が溢れ出す。 何かを叫びながら、窓を叩く絵梨。 周りの乗客たちの驚いたような顔。 だが、その声は届かず、その姿はやがて動き出した満員電車によって僕の視界から運び去られていった。 するり、と千鳥先輩が僕の腕に抱き着いてくる。 「じゃ、行きましょうか♪」 「―――はい」 心が張り裂けそうな罪悪感と。 睾丸がはち切れそうな性欲と。 その両者を抱きながら、僕は頷いた。 千鳥先輩の家まで、腕を組んだまま、無言で歩いた。 「ただいまーって、誰も居ないんだけど。どうぞ、上がって」 「お、お邪魔します」 ドキドキしながら、靴を脱ぎ、家に上がる。 通された千鳥先輩の部屋は、女の子らしくかわいい小物で溢れ、なんだかとてもいい匂いがした。 「―――さて、先にシャワー浴びる?それとも……すぐにする?」 部屋の中をきょろきょろと彷徨っていた視線が、やがてベッドに固定される様子を眺めつつ、千鳥先輩が制服を脱ぎ捨てる。 ブラジャーと靴下だけという、酷くアンバランスで、だけどとても美しく、そして途轍もなく蠱惑的な姿を前に、ごくりと喉が鳴った。 「もう…我慢できません」 電車の中で散々焦らされて、駅からここに来るまでの間も全く勃起が収まる事がなかった。 もう、一刻でも早く、精液をぶちまけたかった。 そうしなければ、罪悪感にズキズキと痛む心も鎮まらないだろうから。 自身の裸体に獣のような血走った目線を向ける僕を見て、千鳥先輩が笑う。 「がっつく感じ、男らしくて素敵よ。ほら、工藤君も脱いで」 促され、僕も慌てて服を脱ぐ。 一瞬躊躇したが、下着も一気に。 勃起しきったペニスが勢いよく腹を打つ。 「素敵」 我慢汁に塗れながらぴくぴくと震えるペニスを見て、千鳥先輩はうっとりと目を細めた。 数歩僕に歩み寄り、反り返ってひくひくと震えているペニスの裏筋を、つぅっと撫で上げる。 「うっ………」 それだけで、先端からぷくりと我慢汁が溢れ出し、竿を流れ落ち、カーペットに滴り落ちていく。 その様子を見つめていた千鳥先輩は、僕の傍らを通り過ぎ、ゆっくりとベッドに仰向けに寝転がり、両手を広げた。 「―――おいで」 「千鳥、先輩……」 逸る気持ちを堪えて、ゆっくりと千鳥先輩に覆い被さる。 シングルベッドが軋み音を上げる。 「挿れるのは、ここよ」 千鳥先輩が、自分の秘所を指で開いた。 濡れてキラキラと輝く淫肉が、僕のペニスを待ち詫びてひくひくと震えている。 ごくり、と唾液を飲み込んで、僕は慎重にペニスの先端を、千鳥先輩の秘所に押し当て、押し込んでいく。 ぬるりとした襞が絡みつき、ずぶずぶと奥へ吸い込まれていく。 やがて、先端が何かの抵抗を突き破る。 「っく……」 千鳥先輩の顔に浮かんだ表情を見て、はッとした。 慌てて結合部に目をやれば、我慢汁や愛液に混じって、赤い液体が流れ落ち、シーツに染みを作っていくところだった。 「先輩……初めて……だったんですか……」 「ふふ。そうよ。私がヤリまくってる淫売だとでも思っていたの?」 痛みに耐え、目尻に涙を浮かべながら、それでも千鳥先輩の口元には微笑が浮かんでいた。 僕の首に両手を、腰に両足を絡め、きつく抱き寄せる。 ずぶずぶと、ペニスが千鳥先輩の奥深くへと引きずり込まれていく。 「う、あぁっ………」 未知の快楽に包まれて、僕の口から嘆息が漏れる。 「童貞卒業、おめでとう♪」 引き寄せられ、唇を重ねた。 千鳥先輩の中はとても熱く、その圧力にペニスが潰されてしまいそうなほどきつかった。 瞬く間に射精欲がこみ上げてくる。 「せ、先輩っ、も、もうっ、出ちゃいそうですっ……!」 「いいよ」 「だ、だめっ、な、中に出しちゃうっ!!」 「いいよ。一番奥に出して」 「そ、そんなっ……ぼ、僕、あぁぁぁっ……っっ!!」 腰を引き抜こうとしても、両手両足を巻き付けられて固定されていて無理だった。 引き剥がそうにも、快楽のせいで体の力が抜けて、華奢な千鳥先輩にも関わらず、力負けてしまう。 もがく間にも身体は射精の準備に余念なく、睾丸がきゅっと押しあがり、亀頭がぷくっと膨らんでいく。 その先端に、何か口のようなものが先端に吸い付いてきた。 「あっ、な、なにこれっ、んんっ……!!」 「ほら、私の子宮も、工藤君を欲しがってるの♪」 戸惑う僕を見ながら、千鳥先輩が笑う。 何とか耐えようとしたが、耐えられるはずもなかった。 絡みつく快感に負けて、腰を振ってしまう。 腰を動かすのを止められない。 その度に、千鳥先輩が甘い喘ぎ声をあげる。 その官能的な響きが、さらに僕から思考能力を奪っていく。 「ち、千鳥先輩っ……!!」 千鳥先輩の名を呼びながら、その最奥に精をぶちまけた。 散々寸止めを繰り返され、ゼリー状になるほど濃縮された精液の塊が、時折竿の中でつっかえながら、千鳥先輩の子宮口に吐き出される。 同時に絶頂を迎えたらしい千鳥先輩もがくがくと体を震わせる。 その動きがさらに膣壁の動きに不規則性を齎し、予期しない快楽が僕を再度、絶頂へと押し上げ続ける。 子宮を満たした精液が逆流し、結合部からごぼごぼと泡立ちながら溢れ出してきた。 血が混じって薄いピンク色に染まった白濁液が、シーツを汚していく。 それでも、射精が止まらない。 2度、3度と連続して絶頂の波が押し寄せてくる。 僕の目尻から涙が溢れ、頬を伝っていった。 涙を流しながら、腰を突き入れ、先輩を犯していく。 その胸を揉み、唇を貪りながら。 千鳥先輩はそんな僕を、微笑を浮かべつつ見つめ、優しく頬を濡らす涙を拭ってくれる。 「好きなだけ突いて、工藤君。その悲しみも苦しみも辛さも、全部私の中に注いで。でもその代わり、教えて頂戴」 顎を持ち上げ、自身の目線に僕の目線を合わせる。 「彼女さんと私。どっちが好き?」 ぶわぁっと涙が溢れ出す。 喉の奥で嗚咽が漏れる。 そして、千鳥先輩の中で、精を吹き出す。 「―――千鳥、先輩です……。僕は、千鳥先輩が……好きです。昔からずっと。い、今も……」 「ふふ、私もよ、工藤君。貴方の事が大好き♪昔も。今も。これからも、ね」 自分が酷い裏切り行為をしてしまったという自覚はあった。 今頃、絵梨はどうしているだろうか。 そんな思いも過った。 泣いているだろうか? 怒っているだろうか? 憎まれてしまっただろうか? 様々な思いが、脳裏をぐるぐると回り続け、胸が痛む。 だから僕は、そんな思いが胸の中から消え去り、頭の中が真っ白になるまで、ただひたすら千鳥先輩を突き続け、その中に精を注ぎ続けた。 3333333 車内アナウンスによって運転再開が告げられた後、ゆっくりと電車が動き出す。 ざわざわとしていた車内に、少しだけホッと安堵するような弛緩した空気が流れた。 「―――ふぅ、やっと動いたね」 絵梨も笑顔を浮かべて、スマホを仕舞う。 「………」 だけど、僕は答えなかった。 絵梨の声は聞こえていたにも関わらず。 電車が駅に滑り込む。 扉が開いて。 「―――ごめんなさい、先輩」 「…。そう」 謝る僕に一つ頷き、千鳥先輩が笑みを浮かべる。 「謝る必要はないわ。ゲームは工藤君の勝ち。それ、あげるから♪」 そう言い残して、千鳥先輩は颯爽と人垣を掻き分けて電車を降りて行った。 「―――あれ、今の人、知り合い?」 千鳥先輩の背中を目で追いながら、絵梨が尋ねてくる。 「うん。中学の先輩」 「へー。綺麗な人」 満員電車が動き出し、千鳥先輩の姿が流れる景色と共に消えていく。 「―――ふぅ」 知らず知らず嘆息を漏らす僕を、絵梨が横目で軽く睨んでくる。 「何それ。もしかして、初恋の人とか?」 「まぁね」 「えー」 頷く僕に、絵梨が不服そうに唇を尖らせる。 「怒らないでよ。今、好きなのは絵梨なんだから」 「ふーん、だ。罰として今日の映画は歩夢の奢りね!」 「はいはい、喜んで」 心が張り裂けそうな罪悪感と。 睾丸がはち切れそうな性欲と。 その両者を抱きながら僕は頷き、ポケットにねじ込まれた我慢汁と愛液でヌルヌルになった下着を指先でまさぐっていた。 勝利しただなんて思っていなかった。 股間にはまだ千鳥先輩に齎された快楽の余韻が熾火のように残っている。 だが、それも絵梨と一緒にいれば。 先輩から距離を置けば。 時間が経てば。 収まるだろうと思っていた。 そうすれば、何事もなかったかのように、この先も、絵梨との日々を過ごしていけると。 だが、全然ダメだった。 絵梨と一緒に映画館で映画を見ている最中も、スクリーンに一切集中することができなかった。 脳裏で再生されるのは、電車の中で千鳥先輩にされた事ばかり。 その声。その香り。その肌の感触。そして、齎された快楽。 ズボンの中でペニスは痛いほどに勃起し続け、パンツはぐっしょりと我慢汁に濡れて気持ち悪いことこの上なかった。 そして、無意識に僕はポケットの中にある千鳥先輩の下着をまさぐり続けていた。 (いっそここで………) そんな思いがぐるぐると頭の中で渦を巻く。 この暗い映画館の中であれば、自慰行為をしてもバレないのではないか、と。 だが、そんなことをする勇気はなかった。 (忘れろ、忘れろ……) 傍らでスクリーンに集中している絵梨の横顔を時折盗み見つつ、ただひたすらに心と体を内側からジリジリと焼き尽くしていくかのような欲情に耐え続けるしかなかった。 まるで、千鳥先輩とのゲームが続いているかのようだ。 この場に千鳥先輩はいなかったが、その幻影だけでも僕を限界にまで追い詰める事など他愛もないことだったのだ。 「あー、面白かったねぇ!」 「あ、ああ」 ご満悦の様子で伸びをしている絵梨に生返事を返す僕。 何とか映画館で自慰行為に耽るという誘惑には耐えたものの、どっと疲れてしまった。 早く帰って眠りたい。 「大丈夫?歩夢」 絵梨が心配そうに顔を覗き込んでくる。 「う、うん、まぁ、ちょっと疲れて―――」 なんとなくそう答えていた僕だったが、絵梨の肩越しに見えた看板を見て立ち尽くしてしまった。 それはいわゆる、ラブホの看板で。 映画館の帰り道。駅の近道だったことから、いつもこの繁華街を通り抜けていた。 しかし、いつもは目に留めることもなく素通りしていた看板だった。 《ホテル》 《休憩》 そんな言葉が脳裏でぐるぐると渦を巻き、どくんっどくんっと鼓動が異様に高鳴る。 腕を組んだカップルが、下品な笑い声をあげながら建物の中に吸い込まれていく。 ごくり、と唾を飲み込んで。 「―――ごめん、絵梨。ちょっと休憩していかない?」 絵梨にそう提案する声は不自然に掠れ、震えを帯びていた。 「え。いいけど……って、え……」 頷きかけた絵梨が僕の視線を追い、驚いたように固まる。 「行こう」 「ちょ、ちょっと待って!」 歩き出した僕の手を掴んで、絵梨が引き留める。 その顔が真っ赤だった。 何しろまだ僕らはキスすら交わしたことがなかったのだ。 別に結婚するまでは控えようとか、そんな古風な考えを持っていたわけではない。 いずれは、自然とそういう関係になるのだろうと、漠然とは考えていた。 きっとそれは、絵梨も同じだろう。 僕からすれば、そのタイミングがちょっと早まったに過ぎない。 しかし、絵梨からすれば、あまりにも唐突だと感じられたとしても何ら不思議ではない。 むしろ、いきなりホテルに行こうと言われれば、躊躇するのが当然だ。 だが、僕にそこまで絵梨の気持ちを慮る余裕が残されていなかった。 「何?」 「そ、その!た、確かに私たちは付き合ってるけど、こ、こういうことをするのはまだちょっと、は、早いかなって……」 「絵梨。僕の事嫌い?」 「ず、ずるいよ……わ、私だって……歩夢の事、大好きだもん」 「だったらお願い。僕を助けると思って」 千鳥先輩の事を忘れるために、絵梨で上書きする。 それは、欲情に濁り切った思考の中で、一筋の光が差したような名案に思えた。 「で、でも……こ、心の準備とか、し、下着だって……」 絵梨が困ったような顔でごにょごにょと零す。 何を言っているのかはよく聞き取れなかったが、普段の僕であれば、絵梨がこんな顔をしたら、すんなりと提案を引っ込めていただろう。 だけど今日は、ちょっといろいろと切羽詰まりすぎていて。 「セックスがダメなら、手でも口でもいいんだ。お願いだ、絵梨」 強引な僕の態度に驚いた顔をした絵梨の口元が一瞬歪んだ。 「あ、歩夢、やめて。なんだか……怖いよ」 その目に浮かんだ感情は恐怖・嫌悪・軽蔑。 すーっと、絵梨の中で僕への愛情が死んでいくのがはっきりと分かった。 今までに見たことのないその表情を目にして、遅まきながら漸く僕は我に返った。 「ご、ごめん、絵梨。怖がらせるつもりは―――」 「触らないで!」 安心させようと伸ばした手を振り払われる。 驚いて立ち尽くす僕を、何かおぞましいものでも見る様な目で見る絵梨。 その目の中で、怒りの火がはっきりと燃えていた。 「信じらんないっ。最っ低!」 吐き捨て、そのまま走り去ってしまう。 「絵梨………」 その場にたった一人残されて、僕の心はバキバキに折れ、砕けて、暗い闇へと墜ちていった。 翌日。 学校内で絵梨に何度も謝ろうとしたが、その度に逃げられてしまった。 そして放課後。 「絵梨はもう工藤とは会いたくないって」 「あんなに泣き腫らした絵梨、初めて見たよ。何したの、あんた。まぁ、私らには関係ないけどさー」 「僕は……」 「とにかく、ウチらは伝言伝えたんで」 「これ以上絵梨に纏わりつくようなら先生にチクるんで。OK?」 絵梨の友人二人から、ゴミを見る様な冷たい眼差しと共にそう告げられて、僕たちの関係は完全に崩れてしまった。 抜け殻のようになりながら生徒会の仕事を終わらせて。 気づいたら、昨日と同じ時間の電車に乗っていた。 満員電車に揺られると、昨日の出来事が蘇ってきて、悔恨と欲情が頭を擡げてくる。 昨日あの後、どうやって家に帰ったかは覚えていない。 すぐに眠ってしまおうとベッドに倒れこんで、でも眠れなくて。 気づいたらズボンから、千鳥先輩の下着を取り出していた。 眺めているうちに引き寄せられるように鼻に押し当て、その匂いを嗅いでいた。 匂いを嗅いだ瞬間、猛烈な欲情を覚えた。 だから、自慰をした。 涙を流し、嗚咽を零しながら。 電車内での千鳥先輩の声や香りを思い出しながら、ひたすらペニスを扱き続けた。 千鳥先輩の技巧とは比べるべくもない拙い動きだったが、下着の匂いに興奮を掻き立てられて、あっという間に絶頂を迎えた。 1回では全く収まらなくて。 電車内と同じように千鳥先輩の下着をペニスに巻き付けて扱き上げて、何度も何度も精を吹き上げたのだ。 絵梨との思い出を、快楽で上塗りしようとするかのように。 ふわっと背後から優しく抱き締められた。 鼻を掠めた甘い香りを嗅ぐだけで、ただ1点を除いて全身から力が抜けていく。 「―――ね、教えて?彼女さんと私。どっちが好き?」 ぶわぁっと涙が溢れ出す。 喉の奥で嗚咽が漏れる。 ズボンに張ったテントの先端をカリカリと弄られる。 「―――千鳥、先輩です……。僕は、千鳥先輩が……好きです。昔からずっと。い、今も……」 「ふふ、私もよ、工藤君。貴方の事が大好き♪昔も。今も。これからも、ね」 自分が酷い裏切り行為をしてしまったという自覚はあった。 今頃、絵梨はどうしているだろうか。 そんな思いも過った。 泣いているだろうか? 怒っているだろうか? 憎まれてしまっただろうか? 様々な思いが、脳裏をぐるぐると回り続け、胸が痛む。 電車の窓に、泣き腫らした顔をした男と、後ろからその肩に顎を乗せて微笑む女の姿が映っていた。 この日、僕と千鳥先輩は4つ目の駅で降りた。 新宫 尼子晴久の妻は、新宮党党首・尼子国久の娘であり、晴久にとっては従姉妹に当たる。 二人の間には、嫡男の義久を含む四男二女が生まれているが、晴久にとっては妻を介して叔父に監視されているようで息苦しさを感じる毎日だった。 さらに、晴久が文芸に傾倒し、国久率いる新宮党との関係が悪化すると、息苦しさは増していった。 そんな晴久に一時の心の安らぎを与えてくれる存在が居た。 それは、宗養が伴ってきた者たちの中にいた女座頭―――盲目の按摩師である角都である。 日々の憂さからの解放を求め、晴久は度々、角都を自室に招き、按摩を受けていた。 布団の上に俯せになり、施術を受ける。 柔らかな手がツボに入り込み、凝りが解されていく。 そのひと時が、何にも代えがたい癒しの時となっていた。 「今日はまた一段と、凝ってらっしゃいますね」 角都の声は、まるで鈴虫の鳴き声のように耳に心地いい。 「あぁ………」 身体を揉み解される気持ちよさに身を委ねつつも、晴久の眉間に皺が寄る。 「ここ最近、気が滅入る出来事が多くてな」 「気が滅入る出来事でございますか」 「ああ。家臣に、中井平蔵兵衛尉という者がおってな。立派な髭をいつも自慢しておるのだ」 「お髭を。それほどご立派なのですか?」 「うむ。さながら関羽雲長のようにな」 「まぁ」 くすくす、と角都が笑う。 「だが、今日、出仕してきた中井は髭を剃っておった。しかも、片方だけな」 「それはまた、どうしてです?」 「最初は、ふざけているのかと思った。それで、儂は叱責したのじゃ」 「中井様はなんと?」 「誠久よ」 その名を口にするだけで、腸が煮えくり返りそうになる。 「誠久様」 角都が、思い出すように名を舌の上で転がす。 「儂の従兄弟であり、義兄でもある。新宮党党首・国久叔父上の子じゃ」 「まぁ……その、誠久様がなんと?」 「中井の髭を詰ったそうな。さしたる武功もないのに生意気だ、とな」 「それは……お可哀想」 「中井の髭を、儂は愛でておった。それを知った上での暴言よ。だが、新宮党の勢威に家臣は逆らえん。中井も泣く泣く髭を剃る事にした」 「ではなぜ片方だけ?」 「儂が、中井の髭を愛でておったからよ。すべてを剃るのは、儂に対する無礼になる、とな。愛い奴じゃ」 「それは酷いお話にございますね」 「全くだ。まだあるぞ」 「まだあるのでございますか?」 「ああ。今度は熊谷新右衛門という家臣の話じゃ。誠久は横暴にも、自分の目に見える範囲では馬に乗る事罷りならんと命じおってな。だが、この熊谷新右衛門という男は、剛の者。この命令にそのまま従うのは業腹だと、牛の背に鞍を置いて乗ったのじゃ」 「まぁ、牛に」 「そうだ」 晴久は頷きつつ、微かに笑みを漏らす。 「ま、何をお笑いに?」 「何。この話はちと愉快でな」 「愉快な話と聞いては気になります。どうぞ教えてくださいませ」 「うむ。熊谷新右衛門が牛に跨って進んでいると、これを見咎めた誠久が下馬を命じたのよ。熊谷新右衛門はどうしたと思う?」 「先ほど、殿は新宮党の勢威に家臣は逆らえないと仰せでした。やはり、熊谷様も泣く泣く従われたのでしょうか」 「さにあらず。熊谷新右衛門はそのまま誠久の前を通り過ぎた。その際、なんと言ったと思う?」 「分かりません。勿体ぶらずに教えてくださりませ」 「いいぞ。教えてやる。だがな―――」 晴久は起き上がると、きゃっと小さく驚きの声を漏らす角都を、すっぽりと自身の両腕の間に抱き締めた。 「と、殿?一体………」 「答えを教える。その代わり、夜伽を務めよ、角都。儂の女になれ」 耳元に顔を寄せ、熱い吐息を吹きかける。 角都がぴくっと体を震わせ、その白い肌が朱に染まっていく。 身を固くはしているものの、晴久を振り解こうとはしない。 「わたくしは……身分卑しき、ただの座頭にございます。お戯れは―――」 「戯れではない」 角都の小さな手を取り、自身の股間に宛てる。 そこは固く勃起し、熱く滾っていた。 「おぬしの按摩を受けて、儂の一物も逸っておる。このような気持ちになった女は、おぬしが初めてなのだ」 「お、奥方様が………」 「奥など気にするな。夫婦の契りなど、もはや幾年もない。あやつは……所詮、新宮党の女だ。儂はな、角都。おぬしを欲しておる」 「殿………」 「おぬしの目に、儂の姿は映らぬだろう。だが、儂の目におぬしははっきりと見える。誠に美しい。愛しき女じゃ。宗養と共に参ったおぬしを始めて目にした時に、儂は身体の内を雷が走ったのかと思ったのじゃ」 抱き締める両腕に力を籠め、顔を柔らかな髪に埋める。 息を吸い込むと、甘く華やかな香りが肺を満たしていく。 滑らかで美しい黒髪。 陶磁器のような白い肌。 可憐な花弁の如き唇も。 嫋やかな肢体も。 全てが愛おしく感じられてならない。 常人ならば忌避するであろう白く濁った盲目すらも、この世ならざる神秘的な美しさに花を添えているように感じられた。 「最初はただ按摩を受けるだけでよかったのだ。おぬしの巧みな技術により、心が解放され、体が軽くなるような心地を味わうだけで。だが、やがて、それだけでは満足できなくなってきた。常に、おぬしの姿が脳裏から離れぬ。そしてその度、儂の一物は滾るのじゃ」 「勿体なきお言葉にございます………」 恐縮しながらも、角都は振り解こうとはしない。 そして、股間に押し当てられた手を放すことも。 「…。教えてくださいませ、殿。熊谷様はなんとおっしゃったのですか?」 意を決したように顔を上げて、角都が尋ねる。 その問いの答えを聞くことがどういう意味なのか、無論分かった上での問いだろう。 自分の思いを受け入れてくれた喜びを噛み締めつつ、晴久は答えた。 「ああ。熊谷はこう言ったのじゃ。『命じられたのは下馬にござろう?拙者が跨っておるのは、馬にあらず。牛にて候。しからば御免』とな。どうじゃ、痛快無比とはまさにこの事であろう」 「くすっ、誠に愉快なお話にございます」 「うむ」 晴久は満足そうに笑みを零し、一層強く角都を抱きしめる。 「よいな。今から、そなたは儂の女ぞ」 「はい、私は殿の女にございます………」 晴久は角都の顎に手を添えて、上を向かせる。 そして、その桜色の唇に、そっと己の唇を重ねた。 唇に舌を這わせると、おずおずと開く。 勇躍して舌を潜り込ませ、柔らかな舌を絡め取る。 どことなく甘ささえ感じる唾液を啜り上げ、堪能する。 それだけで、身体が痺れ、熱くなっていく。 角都の姿がどんどん魅力的に見えていく。 愛しさが込み上げ、爆発してしまいそうだ。 唇を放すと、両者の間に糸が引いた。 「夢のようでございます………」 角都の目尻に涙が浮かぶ。 それを指で拭ってやる。 ふと、空に目をやると、三日月が浮かんでいた。 「雲が晴れたようじゃな。三日月が出ておる………」 「美しゅうございますか?」 「ああ。凛として、冴え冴えとしておる」 「それはようございました」 見えぬ目を虚空に向ける角都の儚げな姿に、胸が締め付けられるような思いがした。 「おぬしの目は生まれながらか?」 「はい………」 「さぞや、艱難辛苦を重ねたであろうな」 「その艱難辛苦も、報われたように感じます。殿に抱かれる日が来ようなどとは」 「儂が必ず、おぬしを幸せにしてみせようぞ」 「角都はもう……幸福にございます」 「足りぬ。もっと、もっとじゃ」 「ならば、雲より出でる三日月に祈ると致します。ここは、出雲の地、月山富田城故」 「なんと祈るのじゃ?」 「我に、七難八苦を与えたまえ、と」 角都の言葉に、思わず苦笑する。 「幸せにすると言うておるに。艱難辛苦を望むのか?」 「禍福は糾える縄の如し、と申します故」 「愛い奴じゃ」 溢れ出るような愛情に身を任せ、角都をきつく抱きしめる。 「角都……角都……」 名を呼ぶ度、愛しさが膨らんでいくようだった。 「角都……角都……」 熱に浮かされたように何度も何度もその名を呼びながら、襟に手を差し込み、乳房をまさぐる。 着物の上からではわからなかったが、角都の乳房は掌に収まりきらないほどに大きくて、まるで水菓子のようにふわふわと柔らかかった。 このまま、永遠に触れていたいと思えるほどに。 「んっ❤」 先端の蕾を指先で弾いた瞬間に零れ落ちた甘い角都の喘ぎ声が、より興奮を高めていく。 「おぬしも、触ってくれ」 褌を緩め、これまでに経験したことがない程に滾る一物を取り出す。 「はい………」 おずおずと角都の白い手が醜く屹立し、のたうつ蛇が如く血管が浮き出た一物に伸び、長く細く美しい指が巻き付く。 「うっ………❤」 ただ、握られただけだというのに、まるで雷のような快楽が背筋を駆け上っていく。 「とても熱くて……硬くて……逞しい……❤」 うっとりとした角都の囁き声が、さらに興奮を高めていく。 角都の手が、ゆっくりと動き出す。 ただ上下に扱く単調な動き。 だが、それでも信じられないほど気持ちいい。 絶妙な力加減に体が震え、傘に輪が引っかかる度にびくん、と体が震えてしまう。 「あっ❤んぅっ❤……ふあっ❤」 情けなくも、喘ぎ声を止められない。 なんとか主導権を取り戻そうと胸元を肌蹴させる。 白くまろやかな乳房の膨らみが露になり、その先端で、ぷっくりと膨らむ桜色の蕾が視線を奪う。 「美しい………」 「恥ずかしゅうございます」 「恥ずかしがることなどない。そなたは美しい。さながら吉祥天の如しじゃ」 「嬉しゅうございます」 はにかむ角都の顔を見るだけで、呼吸が早鐘を打つ。 「まぁ、殿。また一段と硬く………❤」 角都が嬉しそうに囁く。 その手の動きが、徐々に複雑なものへと変化していった。 ただ上下に扱き上げるだけの動きから、捻りを加えたり、5本の指がバラバラに亀頭を舞い踊ったり。 もう片手が睾丸を掌中に収め、やわやわと揉みたててくる。 「くあっ❤あぁっ❤お、おぉっ❤」 齎される複雑な快楽に、息つく間もなく喘ぎ声が零れ落ちる。 睾丸の中で、白濁液が次々に生産され、放出の瞬間を待ち侘びて煮え滾る。 按摩を生業とする座頭だからか。 盲目故に、視覚ではなく触覚や聴覚でどこをどう触ればより感じさせることができるのかをより巧みに焙り出すことができるのかもしれない。 「凄く濡れてきましたよ、殿。気持ちいいですか?」 先端から大量の我慢汁が分泌され、角都の動きをより滑らかに、より淫らなものに変貌させていく。 「き、気持ちいいぃっ……❤❤」 人の上に立つ大将の矜持も、もはやない。 ここにいるのは、無様に喘ぎ、涎を垂れ流すただの一人の男に過ぎなかった。 父が討ち死にし、尼子の次期当主となってより、全てを曝け出す等、一度たりとも許されなかった。 だが、角都の前でだけは、ただ一人の男でいられる。 そんな気がしていた。 くちゅっ❤ぐちゅぐちゅぐちゅっ❤さわさわさわ❤ ねちょっにちゅっ❤かりかりかり❤ずちゅずちゅっ❤ 「あっ、あぁぁぁ……❤❤」 心も体も蕩け、頭の中が桃色の霞に覆われていく。 何か縋りつくものが欲しくて、角都を抱きしめ、その胸元に顔を埋める。 華やかな香りに包まれて、肺を満たすだけで、快楽がより高まっていく。 口の端から涎が零れ落ちていった事も、まるで気にならない。 舌を伸ばし、夢中で乳房にむしゃぶりつく。 身体の奥底から、射精欲が込み上げてくる。 「か、角都……も、もうっ……❤」 手淫が始まって、まだ僅かばかりの時しか過ぎていないことは分かっている。 これまでの人生で、これほど早く、絶頂に追いやられた経験などない。 だが、角都の巧みな手技の前に、限界はあっという間にやってきた。 「は、放つぞっ、角都っ」 「はい、ご存分に❤」 切羽詰まった声を上げる自分に対し、慈愛の籠った角都の声からは余裕すら感じる。 両手10本の指が一物に絡みつき、まるで10匹の白蛇が獲物に纏わりつき、身体を絡ませ、締め付け、窒息させようとするかのように縦横無尽に動き回る。 「あっ❤がっ、あぁぁぁっ❤」 もうこれ以上はないと思っていた快楽の上限をいとも容易く突き抜け、炎のような快楽が頭の中を真っ白に燃やし尽くす。 そして、呆気なく絶頂に追いやられてしまった。 どびゅっ❤びゅるるるるっ❤❤どびゅっどびゅっ❤びゅくびゅくびゅくっ……❤❤ 一物が爆発したのではないかと本気で心配したほどの勢いで、白濁液が噴きだし、角都の手を、身体を、髪を、顔を汚していく。 それでも角都は一物から手を放すことはなく、びゅくんびゅくんと拍動するのに合わせてゆるゆると扱き、最後の一滴まで搾り取ってくれた。 至高の幸福感と解放感に満たされる。 まるで、空を自在に飛ぶ鷹にでもなったような気分だった。 身体から力が抜け、布団の上に仰向けになる。 見上げた天井にも、点々と白濁液が付いていた。 (あんな高さにまで飛ばしてしまったのか………) 荒い息を吐きながらそんな事を思っていると、一物がぬめった感触に包まれた。 「っ………」 下半身に目をやると、あれほどの射精にも関わらず全く硬さを失っていなかった一物が、角都の口中に収められていた。 「か、角都………ぅふあぁっ❤」 ぬるり、と舌が棹を舐め上げ、驚きの声がふやけた喘ぎ声に変えられる。 先端が柔らかな頬粘膜に押し付けられ、えもいわれぬ快感が齎されるのも溜まらない。 光のない白濁した眼差しが、上目遣いにこちらを見やる。 その綺麗な顔にも、点々と白濁液がこびりついている。 その淫らな光景に、背筋がぞくぞくとする。 見えてはいないはずだが、身体から力が抜けていく様子から咎めだてされることはないと判断したのか、角都がゆっくりと頭を上下に振る。 じゅっぽ❤じゅっぽ❤ぐっちゅ❤ぐっちゅ❤ 「くっ❤ふぁあっ❤ぁぁあっっ❤」 空気が漏れる厭らしい音と唾液が攪拌される淫らな音。 その音が響く度、興奮が高まり、一物がより硬くなっていく。 角都は、音を聞かせるためにわざと大きく動いているのだ。 一物に舌が絡みつき、先端が喉奥の柔らかな粘膜にこすりつけられる。 常人ならば、えずいて思わず吐き出してしまうだろう。 だが、角都は顔色一つ変えず、頭を振り続ける。 じゅっぷっ❤じゅっぷっ❤じゅるるっ❤れろぉっ❤❤ 「んんっ❤んひぃっ❤あふぁぁっ❤うぅっ❤」 時折、頭を捻ったり、角度を変えて亀頭を頬粘膜に押し付けたり、或いは先端に吸い付いて我慢汁を啜ったり、棹全体に舌を這わせたり。 多様な動きに、一瞬たりとも気を緩めることができない。 まるで、得体の知れない生き物にでも咥え込まれ、咀嚼されているかのような気分になってくる。 角都を責めるどころか、気持ちよすぎてその身を跳ね除ける事すらできず。 ただただ、さながら乙女のように布団を握りしめ、びくびくと体を震わせ、時に仰け反らせながら、喘ぎ声を垂れ流す事しかできない。 あっという間に射精感が込み上げてくる。 だが、先ほど手淫で他愛もなく絶頂に押し上げられたばかりである。 口中に収められてから、百を数えるほどの時間しか経っていない。 これほど容易く絶頂するのは、尼子家当主としての沽券に関わる。 そう思って歯を食い縛り、布団を力一杯掴んで、何とか快楽に耐えようとする。 「んふ❤」 身体の強張りから、そんな心持ちを見透かしたのか、角都が小さく笑みを零す。 そして、我慢など許さないとばかりに頭を振る速度をより早くしていく。 じゅぶじゅぶじゅぶっ❤じゅるぅっ❤ぢゅぶぢゅぶぢゅぶぢゅぶっ❤❤ 「――――っ!!!」 思いきり叫んでしまいそうになり、慌てて両手で口元を抑える。 角都を呼び出して按摩を受ける際、家臣には人払いを命じている。 とはいえ、声を掛ければ駆け付けられる場所に控えているのは間違いない。 悲鳴など上げてしまえば、何事かと駆けつけてくるだろう。 そして、無様に白濁に塗れる主君の姿を目にするのだ。 もしそんな事になれば、信望は地に墜ちる。 噂が広がれば、新宮党こそが尼子を率いるに相応しいという声がさらに高まるのは間違いない。 だから――― 「んぅっ――っっ❤❤」 漏れだしそうになる声を必死に堪えながら、もはや暴虐的とさえ言える快楽に耐えるしかなかった。 しかし、そんなこちらの心の内など我関せずとばかり、角都の責めはさらに容赦のないものへと変貌していく。 どんどん早く。 どんどん奥深く。 口の端から、涎と我慢汁の交じりあった泡が溢れ出し、飛び散る。 「―――ぐぁぁぁっ、ぐっ、んぐぅぅぅぅっ❤❤」 歯を食い縛る隙間から、涎と共に声が漏れてしまう。 暴れまわる身体も、太ももを抑えられて押し留められる。 瞼の裏がちかちかと明滅する。 頭の中で、ぶちぶちと糸が切れるような音がする。 じゅぶじゅぶじゅぶっ❤じゅるぅっ❤ぢゅぶぢゅぶぢゅぶぢゅぶっ❤❤ じゅるるるるるるるっっっっじゅぶじゅぶじゅぶっ❤じゅるぅっ❤ぢゅぶぢゅぶぢゅぶぢゅぶっ❤❤じゅるるるるるるるっっっっじゅぶじゅぶじゅぶっ❤じゅるぅっ❤ぢゅぶぢゅぶぢゅぶぢゅぶっ❤❤ じゅるるるるるるるっっっっ❤❤❤ 咥え込んだ一物の形がはっきりと浮き上がるほどに頬を窄め、一気に吸い上げられる。 その刺激に、我慢は呆気なく決壊した。 どびゅっ❤どびゅぅっ❤びゅるるるるっ❤びゅくびゅくびゅくっ❤どぴゅっ、どぴゅっ❤❤ 「――――っっ!!」 声だけは出すまいと自身の手を噛みながら腰を突き上げ、角都の口中にありったけの白濁液をぶちまける。 じゅるじゅると竿の中に残る白濁液も一滴残らず吸い上げられる。 口の中に血の味が広がっていく。 視界が白く濁り―――ぐるり、と世界が回った。 吸われるままに引っ張り上げられ、海老反り状態になっていた身体から力が抜け、どさっ、と腰が布団に落ちる。 ちゅぽんっ、と音を立てて一物を吐き出し、放たれた大量の白濁液を飲み下していく。 「ふふ」 だらりと力なく四肢を投げ出して意識を失っている晴久を見下ろし、角都は小さく笑った。 鍛え上げられたくのいちの手練手管を以てすれば、男の心を奪う事など造作もない事。 媚薬と欲情のツボを刺激する按摩による肉欲を、恋情や愛情と勘違いさせ、優しく受け入れてやれば事足りる。 武将にしては優し過ぎる顔を見下ろし、その頬を撫でる。 そして、男を篭絡する最大の要諦は、心の底から愛する事にある。 男の心が最も蕩けるのは、愛情を向けられた時だから。 幼い頃より愛情を向けられたことのない哀れな男など、一溜りもない。 「私は殿の女。殿は私の男。身も心も捧げます故、共に地獄に参りましょう。尼子最期の日まで………❤」 意識を失っても尚、硬さを失わない一物を握って位置を確かめ、ゆっくりと膣に飲み込んでいく。 特に腰を動かしたりはしない。 しかし、自在に動かせるまでに鍛え上げられた襞が、優しく淫らに絡みつき、一物を締め上げ、睾丸の中にある最後の一滴まで容赦なく搾り取っていく。 ほどなくして晴久の顔は恍惚としたものに変わり、角都の膣奥を白く染め上げた。 *** 角都が晴久の寵愛を受けるようになってから1年余り。 ますます勢威を増す新宮党と晴久との関係はさらに悪化の一途を辿っていた。 月山富田城北麓、新宮谷。 立ち並ぶ新宮党居館の一室において。 「た、頼むっ、も、もうっ、たえ、耐えられないっ……!!」 咽び泣くような声と共に、男の懇願する声がする。 仄かな燈火に照らされ、蠢く二つの裸体。 一つは、赤銅色の肉が湯気を立てるような筋骨隆々の男。 その身には幾多の刀創、矢傷が刻まれ、歴戦の猛者であることを示している。 一つは、白く、少し力を入れれば折れてしまうのではないかと思う程の嫋やかな女。 染み一つない裸身は、この世ならざる幽玄の美しさを醸し出している。 「あら。新宮党次期党首ともあろうお方がこの程度で情けない」 一見すれば、男女の睦言以外の何事でもない。 だが、苦悶の声を上げる男とは対照的に、女の声からは余裕が感じられた。 鈴虫の鳴き声が如き、流麗な声音である。 仰向けに転がる男の腰に跨る女。 男の逸物は、女の蜜壺にずっぽりと飲み込まれている。 女は特に動いているわけではない。 だが、男の額に浮かぶ汗、苦悶に歪む顔が、その身を襲う壮絶な悦楽を容易に想起させる。 何とか女を跳ね除けようと四肢をバタバタと動かすが、女は余裕の表情で乗りこなす。 「あっ❤ああぁぁっっ❤❤」 程なくして男の体が硬直し、弓なりに反りかえり、やがて弛緩して泥のように沈む。 「ふふ、これで7度目です❤」 精の奔流を自身の最奥で受け止めながら、女は嫣然と微笑んだ。 蜜壺の襞、自在に動く一枚一枚が、精を吐き出したばかりの一物にねっとりとしゃぶりつき、やわやわと揉みたてて、萎えることを許さない。 「気持ちいいでしょう?」 「も、もう、許してくれぇぇっ……❤」 歴戦の猛者という風貌に反し、男の声は弱弱しい。 最初に、その蜜壺を貫いた時は、あまりの快楽に、まるで極楽浄土を揺蕩っているような陶然とした気分になった。 2度目、3度目と精を放つ度、恍惚の度合いは深まっていった。 だが、4度目、5度目と精を搾り取られるうち、快楽は徐々に苦痛に成り代わっていく。 6度目、7度目ともなれば、もはや命を削り取られているにも等しい。 それがわかっているというのに、数日も間が空くと、その肌が恋しくて溜まらなくなる。 その声を聞き、その香りを嗅ぎ、その肌に触れ、その蜜壺を貫くこと以外、何も考えられなくなる。 殿の―――晴久なんぞの寵愛を受けていると知った時には、嫉妬の炎に焼け死ぬのではないかとさえ思った。 だが、女―――角都は、晴久の寵愛を受けるようになった後も、自分の前に度々姿を現した。 暗い情念を刺激され、獣のように交わる。 だが、いつも、簡単に主導権を奪われ、最後は精も根も尽き果てるまで犯し尽されることになる。 「し、死ぬっ、死んでしまうっ……ひぃぃっ❤」 「私はやるべきことは徹底してやる主義なのです。貴方と違って」 「た、頼まれたことはやった……やったじゃないかっ……くひぃっ❤」 反論の言葉は、乳首を捻られるだけで喘ぎ声に変えられてしまう。 男でも乳首で感じてしまうなど、今まで全く考えたこともなかった。 角都が出雲へやってきてすぐ、城中で声を掛けられた。 そのまま手を引かれて納戸部屋に連れ込まれ、求められるままに抱いた。 京の女とはこれほどまでに性に奔放なのかと驚いたが、するすると着物を脱いでいく様には息を飲んだ。 そして、露わになった裸身の美しさ、妖艶さに目を奪われた。 例え、白眼の座頭だったとて、このような美女に求められて、断る理由など見つかる筈もない。 角都が齎す快楽は、これまでに経験した事もないもので、ずぶずぶと泥沼に沈んでいくように、その快楽に溺れてしまった。 関係は1年以上も続き、もはや角都から離れられる気がしない。 「不十分なのですよ、あれでは」 両乳首を強くひねられる。 同時に、一物の先端に何かが吸い付き、吸い上げられる。 「ああああああっ❤❤」 絶望と苦痛、それを塗り潰して余りある快楽に顔を歪めながら、8度目の精を注ぐ。 「貴方様は新宮党次期党首。尼子氏の今があるのもすべては新宮党のおかげ。なのに、いつまで晴久殿に遠慮する必要があります?」 「だ、だからぁっ、は、晴久の家臣をっ、ぐ、愚弄して、ちょ、挑発してる、んあぁっ❤…じ、じゃないか……」 全身を襲う快楽のせいで、舌さえうまく回ってくれない。 「まどろっこしい」 何も見えていないはずの白眼。 その苛立たしげな声が耳朶を打つ度、背筋がぞくりとする。 その冷たい眼差しに貫かれる度、恍惚としてしまう。 ―――尼子氏の今があるのもすべては新宮党のおかげ。 その通りだ。 ―――晴久殿に遠慮する必要があります? いや、ない。 (だが、だからと言って………) 晴久の首を取ってまで、その座に成り代わりたいと思ったことはない。 新宮党は飽くまでも剣なのだ。 尼子家当主を守る剣。 尼子氏の敵を討ち平らげる剣。 それ相応の敬意と待遇が得られれば、それで十分。 謀反を起こす気など、毛頭ない。 「いいですか。私の言うままに、文を認めてくださいまし」 「ふ、文……?」 「ええ、そうです。宛先は―――毛利右馬頭殿❤」 角都が舌なめずりをする。 ちろりと覗く赤い舌が、異様に艶めかしい。 その姿を見ているだけで、何度も搾り取られて精も根も尽き果てているはずの一物が、むくむくと硬さを増していく。 どんどん頭が回らなくなっていく。 じりじりと崖際に追い詰められているような。 まずいことになるのではないか、という気がする。 だが、その冷たい白眼に見据えられ、蜜壺の中で一物を甘く締め上げられるだけで、何もかもがどうでもよくなっていった。 「わ、わかった、い、言う通りにするからあぁぁっ❤❤」 万力のように締め付けられ、思いきり背を仰け反らせながら、9度目の精を注ぐ。 地獄に落ちていくような気分と、天に舞い上がるような気分。 その双方を骨の髄まで味合わされて、心が壊れそうだった。 いや、或いは、もうすでに壊れてしまっているのかもしれない。 *** 「角都、と言ったか」 尼子誠久の部屋を出て、玄関に向かう途中で声を掛けられた。 若さ弾ける、まだやや甲高い声音は元服して間もないと思われる若武者のものだろう。 「はい」 返事を返しながら振り返り、僅かに身を屈める。 「何故父上を篭絡する。狙いはなんじゃ?」 投げかけられたのは、あまりに直接的な詰問の言葉だった。 思わず浮かべかけた苦笑を寸前で押し留める。 「貴方様は?」 「尼子誠久が嫡男・孫四郎氏久じゃ」 穏やかな声音での問いに、硬い声で返事が返ってくる。 「氏久様」 誠久は子沢山で、6人の男児に恵まれている。 とはいえ、そのいずれもがまだ年端もゆかぬ童に過ぎない。 嫡男の氏久と雖も、まだ14、5歳の、戦場にも出たことがない若年だろう。 「聞き耳を立てておられたのですか?」 「っ………」 角都の指摘に、動揺する気配が伝わってくる。 きっと、耳まで赤くなっている事だろう。 (初心な事………) 瞬きをする一瞬に音もなく近づき、腕を掴む。 「なっ………」 どうやって近づかれたのかもわからないのだろう。 目を白黒させ、あたふたとしている様が、見えずとも手に取るようにわかる。 慌てて振り解こうと力を籠める。 さすがは新宮党と思わせる膂力だ。 だが、させない。 まだ武骨さを感じさせない手を、襟の中に引っ張り込み、乳房にめり込ませる。 「っっ………!」 息を飲み、硬直する氏久。 その初心な反応からすると、女に触れたことすらないに違いない。 その懐に潜り込み、もう一方の手を股間に当てる。 思った通り。 若き一物は隆々と勃起し、ふんどしはぬるぬると濡れていた。 聞き耳を立てながら何をしていたのか、これでは隠しようもない。 「お部屋に参りましょう、氏久様。そこでゆ~っくりと、お話致します❤」 耳元に唇を寄せ、熱い吐息を吹きかけ、一物をゆるゆると扱きながら囁く。 角都を振り解こうと全身に込めていた力が、すーっと抜けていった。 案内された氏久の居室に入るなり、角都は着物を脱ぎ捨てた。 「ぁ………」 氏久が呆けたような声を上げる。 見えずとも、その視線が自分の裸体に注がれていることを肌で感じる。 さすがは親子と言った所か。 誠久の前で初めて裸身を露にした時とそっくりの反応だ。 きっと同じような阿呆面を晒しているに違いない。 その顔を見てみたいという気持ちが、少しだけ湧いてきた。 「な、何を………」 「何を、されたいですか?」 擦れた声音に、ふ、と笑みを向けつつ首を傾げて見せる。 「な、何を………」 氏久の声音が動揺する。 どんな想像を、その脳裏で繰り広げている事か。 豊満な肢体を見せつける様にくねらせながら、ゆっくりと近づく。 氏久に逃げる気配はない。 ごくり、と生唾を嚥下する音が、どくどくと高鳴る鼓動の音とともに聞こえてくる。 緊張に強張る身体を包み込むように抱き締め、おもむろに唇を重ね、ねっとりと舌を絡め、たっぷりと唾液を流し込む。 氏久の体を妖艶に撫で擦り、女体の柔らかさを堪能させ、甘い香りをたっぷりと吸わせてやりながら緊張を解し、着物を脱がしていく。 「あ、ふあぁぁぁ……❤」 裸の胸を擦り、乳首を弾いてやるだけで、ふやけた喘ぎ声を漏らす。 (他愛もない………) 内心で呟きつつ、弾力のある若々しい筋肉に覆われた瑞々しい肢体を押し倒していく。 「氏久様❤私と父上の痴態を盗み見て、何を期待されていたのですか?」 「そ、それは………」 「ふふ、教えてくださらなくて結構ですよ。何を期待されていたにせよ、それを遥かに上回る事をして差し上げますから❤」 「ひ―――」 悲鳴を飲み込むように唇を重ね、未だ女の悦楽を知らぬ身に一つ一つ、快楽を教え込んでいく。 びくびくと体を震わせ、甲高い声で喘ぎ、逃げようと身を捩るのを抑え込み、絶頂へと押しやる。 手で、口で、乳房で、髪で、脇で、太ももで、そして秘所で。 何度も何度も。 その身に、常人とのまぐわいでは絶対に得られぬであろう極度の悦楽を烙印のように刻み込んでいく。 栗の花のような青臭い精を放つ度、その心が雁字搦めにされていく。 「はひっ……❤……角都……様ぁ……❤あへ……❤」 角都が帰った後の居室で、氏久は大量の白濁液に塗れ、とろとろに蕩けた顔を虚空に向け、ただただ愛し気にその名を口にする木偶と化していた。 ぴくぴくと体が震える度、快楽の余韻だけで一物の先端から白濁液を垂れ流しながら。 *** 1554年、新宮党党首・国久の娘である晴久の正室が亡くなる。 愛娘の死を哀しみ、涙と鼻水と涎を垂れ流しながら人目も憚らずに大声を上げて号泣する国久の姿を、晴久はまるで樋熊のようだと思いながら冷ややかな眼差しで眺めていた。 愛する妻を失ったという感慨はなかった。 あるのは、その身に巻き付く幾本もの鎖、その内の1本が千切れたという晴れ晴れしさだけ。 涙一つ流さない晴久に対し、国久や誠久ら新宮党の面々の心の内では、憎悪の炎が燃え盛った。 葬儀が終わると、泣き腫らした幾対もの視線に睨まれながら、晴久は早々にその場を立ち去った。 そして、その足で居室に戻り、角都を呼び出した。 「お悔やみを………」 角都が畏まろうとすると、 「無用じゃ」 言葉を遮って、角都を押し倒す。 裾を割り、屹立した一物をいきなり挿入する。 「漸くじゃ。漸く、この時が来た………」 目を血走らせ、角都の唇を吸い、無茶苦茶に腰を動かす。 角都は晴久の腰に両足、背中に両腕を絡め、襞を締め上げて晴久を絶頂へと追いやる。 「んぅっ……くっ、ふっ、あははっ……」 どくどくと精を放ちながら、口元に獰猛な笑みを浮かべる。 「ええ、まさに今こそ、鎖から解き放たれる時です……」 晴久の耳元に熱い吐息を吹きかけながら、角都も笑みを零した。 「殿は、尼子の正統なる当主。幾ら武勲ある新宮党とはいえ、殿を蔑ろにすることが許されるはずはありませぬ」 「ああ…おぬしの言う通りじゃ……許さぬ……新宮党……誠久め……」 晴久の瞳に暗い炎が揺れる。 誠久と角都の関係も、その耳に入っていた。 だが、角都に心を絡め取られている晴久には、これを糾弾する勇気はなかった。 筋骨逞しい誠久と比べ、自分が男として劣っているのではないかという劣等感故に。 嫉妬の炎は憎悪を駆り立てる。 そして、その憎悪は、ただ只管に、誠久と新宮党に向けられていた。 同時に、嫉妬の炎は角都に対する欲情をも膨れ上がらせる。 誠久に抱かれている時、角都はどんな顔をするのか?どんな声で喘ぐのか? そんな事を考える度に、気が狂いそうになる。 (角都は儂の女ぞ………!誠久になぞ、取られてなるものか……) 晴久の荒い息と角都の甘い喘ぎ声が交錯し、どくどくとその最奥に精を注ぐ。 「もっと、もっとだ、角都……!」 与えられる快楽に意識が朦朧としてくる。 いつしか体勢が入れ替わり、角都が上になる。 指を絡めるように両手を握り、角都が体を動かすのに合わせて、その最奥に精を注ぐ。 何度も何度も。 命の灯を削るように。 「か、角都!おぬしは、儂の女ぞっ……!」 「はい、私は殿の女。殿は私の男にございますっ。共に参りましょう❤」 その言葉を、以前も聞いたような気がする。 しかし、いつの事だったか思い出すことはできなかった。 「は、放つぞっ」 「はい、ご存分に❤」 最奥に精を放つ。 視界が狭まっていく。 もはや、角都以外、何も見えない。 「孕め、角都っ。わ、儂の子を産んでくれっ……」 「はい、孕みます❤産みます、殿の御子を………❤」 角都が上体を倒し、唇を重ねてくる。 舌を絡め、唾液を啜り、互いの境目がなくなるのではないかと思う程にきつく、きつく抱きしめ合う。 二つの影が重なり合い続けるのを、天高く、凛として冴え冴えと、三日月が見下ろしていた。 *** 晴久の正室が世を去ってから10日程―――。 晴久派と新宮党が、例え廊下ですれ違う際にも目すら合わせないような一触即発の緊迫した空気が流れる中、事件は起きた。 月山富田城の門前で、不審な動きをしていた巡礼者が捕らえられ、取り調べの結果、衣の中に編み込まれていた密書が発見されたのである。 それは、毛利元就から新宮党党首・尼子国久に宛てた書状だった。 内容は、国久が晴久を暗殺すれば、国久による尼子家継承を毛利家が後押しするというもの。 当然ながら、国久は身に覚えがある訳もなく、偽の密書だと主張。 あまりにも見え透いた離間工作に尼子家中も概ね、国久に同情的だった。 しかし、更なる取り調べの結果、国久の嫡男・誠久が毛利元就に宛てた書状が発見される。 その筆跡が間違いなく誠久のものであったことから、風向きが変わり、新宮党は言い逃れできない状況へと追い込まれていった。 国久は身の潔白を主張し続けた。 その信念は、文字通り巌のような体躯の通り、決して揺るがないように見えた。 しかし、そんな国久に比べ、誠久の主張は歯切れが悪く、潔白を証明するには至らなかった。 しかも、新宮党内部からも二人を告発する者が現れる。 それはなんと、誠久の嫡男である氏久であった。 将来の新宮党継承者たる氏久の告発は、国久や誠久に止めを刺すのに十分すぎるものであった。 この告発に対し、晴久の動きは速かった。 新宮党に同情する者が現れ、かつての塩冶興久の反乱の時のように家中が二つに割れてしまう事を恐れたのだ。 まず登城途中だった国久を暗殺。 さらに電撃的に新宮谷を急襲した。 誠久の弟である豊久、敬久ら新宮党の主だった幹部は弁明の機会すら与えられずに自害させられた。 誠久に至っては自害すら許されず、大西十兵衛、立原備前守の両名によって文字通り八つ裂きにされた。 さらに10代だった誠久の次男・吉久、四男・常久、六男・通久らが粛清され、三男の季久は行方不明となる。 生き延びたのは、誠久の嫡男で、父と祖父を告発した氏久と五男の勝久だけである。 新宮党は氏久が継承し、勝久は京に上り、東福寺の僧となった。 *** 新宮党粛清に先立つ事半年、毛利元就は1554年5月に盟友だった陶晴賢と決別している。 世にいう、「防芸引分」である。 翌1555年には厳島の戦いが起こる。 毛利元就は僅か5千の兵力で3万の大軍を率いる陶晴賢軍に対し、奇襲攻撃を敢行。 これを撃破する大勝利を挙げる。 敗れた陶晴賢は自刃に追いやられる事となった。 新宮党が粛清されたことにより、尼子氏の軍事力は大きく減退した。 尼子晴久は祖父に比べて凡将という評判に反して、厳島の戦いに勝利して勢いに乗る毛利軍と石見国忍原で戦い、大勝を遂げるなど、尼子氏の全盛期を築くに至る。 とはいえ、新宮党なき今、積極的に遠征を行う力はなく、領土を守るので精一杯だった。 1557年には大内氏最後の当主・大内義長が自害に追い込まれ、旧大内領の大半が毛利領となり、毛利による尼子への圧力は強まる一方となる。 だが、それでも、尼子晴久は再三にわたる毛利元就による侵攻を跳ね除け続けた。 しかし、そんな崖っぷちの尼子家を更なる悲劇が襲う。 1561年、尼子晴久が突如として急死したのである。享年47。 誰もが呆然としてしまうような、予期せぬ突然の出来事だった。 この死について、尼子家中では不可思議な噂が流れた。 ―――尼子晴久は、妻に毒殺された。 というものである。 だが、尼子晴久の正室は1554年に亡くなっている。 噂の語る、尼子晴久の「妻」とは誰なのか。 その答えは、歴史の中に埋もれている。 後を継いだ嫡男・義久の下で、尼子家の命運は遂に尽きてしまう。 毛利軍の猛攻の前に1566年、月山富田城は開城を余儀なくされるのだ。 ここに、かつて山陰に覇を唱え、繁栄を謳歌した尼子氏は滅亡する。 1568年、尼子家の旧臣は京で僧となっていた誠久の五男・勝久を還俗させ擁立。 10年に亘る尼子家再興を図る戦いを始める。 この戦いで、勝久を支えたのが《山陰の麒麟児》こと山中鹿之助。 晴久を支えた家老・山中満幸の子とされるが、生年は不明。 山中満幸が27歳で亡くなっている事もあり、1590年代後半に成立した世間話集『義残後覚』では尼子晴久の落胤ともされる謎多き人物である。 尼子晴久の落胤ならば、母親は誰なのか? それもまた、歴史の謎である。 そんな彼は三日月に向かって、こう祈った逸話で夙に有名である。 ―――願わくば、我に七難八苦を与えたまえ、と。 株主 株主優待とは、株式会社が一定数以上の自社株を権利確定日に保有していた株主に与える優待制度の事。自社製品の詰め合わせや自社のサービスが受けられる割引券などその種類は様々である。 *** 『間もなく到着します!』 騒音の中、装着したヘッドセットからパイロットの怒鳴る声が頭の中に響く。 何も不機嫌なのではなく、怒鳴らなければ掻き消されてしまうのだ。 その言葉を受けて僕―――穂村俊一郎は、座り心地が快適とは言えないヘリの硬いシートに座り直し、窓の外に視線を受けた。 南国の強い陽光を浴びてキラキラと輝く紺碧の海。 白い砂浜。 小高い山とそれを取り巻くジャングル。 空を舞う見たこともない鳥。 そして、海岸っぺりに聳える巨大なホテル。 絵に描いたような、THEリゾート地である。 ヘリは機体を傾け、轟音を轟かせながら、ホテルのヘリポートへと勢いよく舞い降りていった。 扉が開けられると生暖かい風と轟音が吹き込んでくる。 僕は差し出された手を掴み、身を屈めるようにしてヘリから降り、手を引かれるままヘリから離れた。 「―――ようこそ、常夏の楽園《ヴェイン・リゾート》へ!」 声を掛けられて漸く、手を引いてくれている相手がまだ若い女性であることに気づいた。 綺麗な黒髪が風に靡き、頭に付けた花飾りが風車の如く回る。 煌めく瞳に輝くような笑顔。 今までの人生でお目にかかった事のないような美人だった。 「あ、ど、どうも」 その容姿に見惚れていたことを隠すように、視線を空へと逃がす。 どこまでも突き抜けているかのような青空が広がっていた。 ヘリポートからホテルの中に入ると、漸くヘリの轟音が聞こえなくなり、ホッと安堵の吐息を漏らす。 乗り慣れない乗り物に乗っていたせいで、身体の節々が痛んだ。 だが、静かになった訳ではなく、轟音の代わりに、リゾート地らしい浮足立った喧噪に包まれるだけだった。 行き交う客は皆、裕福そうな人ばかり。 (場違いだな、僕………) 気後れと共に、脳裏でそんな愚痴を零す。 しがないサラリーマンである僕など、本来であればこの場に居てはならないのだろう。 完全に住む世界が違う。 身体がのめり込むようなふかふかなソファに案内されて、腰を下ろすと、居心地の悪さを感じる暇さえ与えまいとするかのように、すぐに細長いグラスに注がれたしゅわしゅわと泡の立つ飲み物が供された。 無論、サイダーではない。 「ウエルカムドリンクです」 「あ、ありがとう」 受け取り、一口含む。 飲みやすくて爽やかな味だったが、きっと自分の給料ではとても手が出ないような代物なのだろう、と思える味だった。 ヘリポートからここまで案内してくれた美女が、恭しく一礼し、向かいのソファに浅く腰を下ろす。 「改めまして、本日はようこそ、ヴェイン・リゾートにお越しくださいました。申し遅れましたが、私は穂村様のご滞在中、担当コンシェルジュを務めさせていただきます若宮ありさと申します。未熟者ですが、穂村様に少しでも快適にお過ごしいただくべく務めてまいりますので、何かお困りの際は何なりとお申し付けくださいませ」 「こ、これはご丁寧に。僕の方こそ、勝手がわからないものでいろいろとご迷惑をおかけするかもしれませんが、よろしくお願いします」 立て板に水とはまさにこの事という感じの流麗な口上に気圧されつつ、後頭部に手を当てながらへこへこと頭を下げる。 我ながら絵に描いたような小市民っぷりである。 「そう畏まらないでください。穂村様はVIPなのですから」 「VIPだなんて………」 今まで自分に向けられたことのない言葉に、びっくりして顔を上げると、若宮さんの輝くような笑顔を目の当たりにしてしまい、年甲斐もなく鼓動が高鳴ってしまう。 と、そこへ黒服の男性が近づいてきて若宮さんに封筒を差し出した。 元軍人と言われても違和感がないような、隙の無い身のこなしだった。 若宮さんが受け取ると、黒服の男性は僕に一礼し、その場を立ち去っていった。 「チェックインの手続きが完了いたしましたので、穂村様のご用意がよろしければお部屋にご案内いたします」 「あ、は、はい」 僕は頷き、シャンパンを一気に飲み干した。 *** 「おー……凄い……」 案内された部屋は、今までに見たこともないほど綺麗で豪華で、窓からは一面に輝くような海を一望できる素晴らしい部屋だった。 気の利かない感想を漏らしつつ、きょろきょろと辺りを見渡す。 「こ、ここって幾らぐらいなんだろう………」 すぐに金額が気になってしまうのも、小市民の悲しい性である。 「シーズンによってレートは異なりますが、凡そ1泊10万円から20万円でご案内しております」 「20万っ………!」 思わず零した呟きに返ってきた答えにびっくりしてしまう。 僕の給料では、とてもとても手が出る価格ではない。 調度品に触って指紋を付けるのすらなんだか申し訳ない気がして、そわそわしてしまう。 「穂村様」 神妙な若宮さんの声に振り向くと、若宮さんが深々と一礼する。 「穂村源一郎様の事、改めてお悔やみ申し上げます」 「あ、いえ、そんなご丁寧にありがとうございます」 若宮さんの改まった声音に、慌てて僕も一礼する。 そう、僕がこんな場違いなリゾート地に来ているのは、祖父である穂村源一郎に起因するのである。 僕自身はしがないサラリーマンであるが、穂村家は元々新潟県で多くの土地を持つ地主であり、資産家だったのだ。 特に、祖父である源一郎は新興財閥のヴェイン・グループに多額の投資をしていた。 親しい訳ではなかったが、祖父にとって僕はただ一人の孫であり、その死去に際して僕は祖父の遺言に従って広大な土地や財産と合わせ、ヴェイン・グループの株を100万株相続する事となったのだ。 本来ならば祖父の子である僕の父が相続すべきなのだろうが、父は祖父よりも早く5年前に他界している。 3年前には母も亡くしており、財産を相続できる人間は僕しか残されていなかったのだ。 そのヴェイン・グループでは株主優待として、10万株以上を持つ株主を年に1回、この南国のリゾートに招待している。 その招待に応じて、僕は今ここにいる、という訳である。 「えと、若宮さんは祖父をご存知なんですか?」 単なる社交辞令ではない気がして尋ねると、若宮さんは頷き、僕の肩越しに外に視線を向け、僅かに目を細めた。 「ええ。源一郎様には毎年ご利用いただいておりまして、わたくしもいろいろとよくしていただきました」 「そうだったんですか。僕は父が新潟を離れた関係で、あまり祖父とは会って来なかったものですから。もしかしたら僕より若宮さんの方が祖父について詳しいぐらいかもしれませんね」 「いえ、そんな事は……」 視線を僕に戻し、僅かに困惑したように首を振る。 「あ、ごめんなさい。若宮さんを困らせたかったわけでは………そうだ、若宮さん、祖父がここでどんな風に過ごしていたか教えてもらえますか?」 「源一郎様が、ですか?」 「ええ。もし差し支えなければ、ですが。何せ、こういうリゾート地に足を運ぶのも初めてなもので、何事にも勝手がわからず」 「いえ、差支えはございません。お客様のご要望にお応えするのが、我々コンシェルジュの役目ですので」 「では、よろしくお願いします」 「畏まりました。それでは……」 「えっ……」 笑顔を浮かべ、若宮さんが取った行動に思わず硬直してしまう。 涼しげなワンピース風の制服に身を包んでいた若宮さん。 しゅるり、と衣擦れの音がしたかと思いきや、そのワンピースが、するりと足元に滑り落ちていくではないか。 下に着ていたのは、花柄の可愛らしいビキニタイプの水着である。 思いの外大きな胸、きゅっと括れた腰、程よい肉付きのヒップと太もも、すらりと長い脚。 「ちょ、わ、若宮さんっ!?」 慌てて目線を反らすが、そんじょそこらのグラビアアイドルならば裸足で逃げ出すのではないかと思うほど、素晴らしいプロポーションが目に焼き付いて離れない。 「源一郎様はよくマッサージを受けてらっしゃったんです。ここにいらっしゃる道程で、どうしても身体が凝ってしまうと仰られて」 思わずきょどってしまった僕に対し、若宮さんは全く態度を変えることなく説明してくれる。 「な、なるほど」 確かに僕自身、ヘリ移動のおかげで体の節々が痛むのは確かである。 「け、けど、水着になる必要がありますか?」 「本来であれば必要ありません。ただ、源一郎様は施術の際に水着姿をご希望される事も多く。これは、ほんのサービスですのでお気になさらないでください。それよりも、穂村様もマッサージ、いかがですか?」 「ま、マッサージ………」 ごくり、と唾を飲み込んでしまう。 こんな水着美女にマッサージをされたら、いろいろとまずいことになりかねない。 (じ、爺ちゃんっ………) あまり話したこともない祖父だったが、いつも厳格なオーラを身に纏っていた印象がある。 だというのに、これは………。 (まさか、単なるスケベじじぃだったんじゃ………) そんな疑念を抱かざるを得ない。 「マッサージはお嫌いですか?」 若宮さんがしゅん、とした表情で首を傾げる。 (ぐはっ、可愛すぎる………!) 上目遣いと言い、その表情は反則だ。 「い、いえ、お、お願い、します………」 「畏まりました♪」 僕が頷くと、満面の笑みに早変わり。 その変わり身の早さに若干の騙された感を覚えつつ、 「ええと、僕はどうすれば……?」 「まずはシャワーをどうぞ。その間に、準備をしておきますので。下はこれでお願いします」 そう言って差し出されたのは、マッサージには付き物の、あの極小紙パンツだった。 *** シャワーを浴び、しばしの躊躇を挟んだのち、ええいままよと覚悟を決めて紙パンツを履いて戻ると、既に若宮さんは準備万端整えて待っていた。 ベッドは掛布団が外されて、敷布団の上にタオルが敷かれ、枕元にはアロマディフューザーが南国チックな甘い香りを漂わせている。 傍らのナイトテーブルには何本かのボトルとタオルケット。 そして、水着姿の若宮さん。 思わずそちらに吸い寄せられそうになる視線を辛くもベッドに向けて誤魔化す。 「お、お待たせしました」 「いえいえ。それではまずは、うつ伏せでお願いします」 「は、はい」 微かな緊張を覚えつつも、ベッドにうつ伏せになる。 (ただのマッサージだ、落ちつけ、僕。変に意識するんじゃない………) 「それでは、失礼します」 ベッドの上に若宮さんが上がり、僕の太ももの辺りに腰を下ろす。 (うっ………) 互いに半裸状態。 素肌と素肌が密着する感覚に、思わず声が漏れそうになるのを何とか堪える。 (スベスベだぁ………) 「ローション垂らします。ちょっとひやっとしますよ」 「は、はい……んっ、冷たっ……」 背中にローションが垂らされる。 予め言われていたにもかかわらず、その冷たさに思わず声が漏れる。 若宮さんは自身の掌にもたっぷりとローションを乗せ、ボトルをナイトテーブルに置く。 手に馴染ませるように指を動かす度、ぐちゅっ、ぐちょっと卑猥な音がする。 この音だけを聴いていたら変な気分になってしまいそうだ。 「では、肩甲骨の辺りから解していきますね」 「お、お願いします」 平静を装うと言う努力も虚しく、どもってしまう。 (お、落ちつけ。これじゃ、童貞丸出しじゃないか……) ローションを塗り広げるように若宮さんの手が背中を這いまわり、肩甲骨を解すように揉み込んでくる。 「力加減、いかがですか?」 「んっ、とても、気持ちいいです……」 「リラックスしてくださいね♪」 「ひゃ、ひゃい………」 気持ちよすぎて、思わず変な声が出てしまう。 それほど、若宮さんのマッサージ技量は卓越していた。 「穂村様、カチコチですよ……お仕事、大変なんですか?」 「っ、えぇ、まぁ……」 不意に若宮さんが上半身を倒し、耳元で囁いてくる。 「身体の力を抜いて、私に身を任せてくださいね」 ぎゅっ、ぎゅっと体のコリを解されながら、少し低い落ち着いた声音で囁かれると、頭の中がボーっとしてくる。 「足の方もやっていきますねー」 「ふぁ、ふぁい………」 返事をするのもだんだん億劫になってきた。 旅の疲れが出たのか、だんだん眠たくなってくる。 だが、この極上の感触。 寝てしまうのはもったいなくて、何とか眠気を払いのけようと首を振る。 「大丈夫ですか?」 「だ、大丈夫です」 「では……」 足にローションが垂らされ、筋肉を解すように足先まで揉み解されていく。 解された箇所の血流がよくなったのか、徐々にポカポカとしてきた。 「だいぶ解れてきましたね。それではもぉっとリラックスしてください❤」 若宮さんの声色が変わった気がする。 そう思ったのも束の間、僅かな重みと共にふにゅぅっ、と柔らかな感触が背中全体に広がっていく。 「あっ………」 僕に覆いかぶさるように、若宮さんが密着しているのだ。 その豊満な乳房が背中で潰れ、その柔らかな感触に頭が真っ白になる。 「わ、若宮さん、当たって……」 「当ててるんです❤気になさらないでください❤……れろっ❤」 「んっ!み、耳っ……」 耳を舐められて、びくんっと体が震える。 「くす。耳が敏感なんですね。それではもう一度……ぺろっ、んちゅっ、れろぉっ❤❤」 「んあぁっ、ちょ、こ、こんな……!こ、これっ、ま、マッサージ、ですか!?」 「ええ、マッサージですよ。源一郎様お気に入りの♪……穂村様はお嫌いですか?こういう……マッサージ❤」 手が脇の下を通って体の前面に潜り込んでくる。 その指先が、両乳首をさわさわと撫でていく。 「んんんっ……」 思わず上ずった声が漏れてしまった。 「くすっ、乳首も敏感なんですね。ふふ。コリコリになってきました❤こちらも解していかないとダメですね❤」 耳や首筋に舌を這わせながら、乳首を弄られる。 活性化された血流が股間に勢いよく流れ込み、紙パンツの中で痛いほどに肉棒が勃起する。 齎される快楽に身動ぎする度、股間がタオルに擦れ、甘い刺激が生まれ、呼吸が荒くなっていく。 「あら、解しているのにどんどん硬くなっていますね……ちゅっ❤れろっ❤ちゅぱっ❤」 「あっ❤んんっ❤❤んひぃっ❤」 愛撫されて解れるはずもなく、乳首はどんどん硬さを増していく。 落ち着いた声音で囁かれ、耳を咥えられて舌が這いまわる感触もどんどん性的興奮を高めていく。 「ふふ、腰が持ち上がってきていますよ。どうされました?」 淫らな愛撫を続けながら、白々しく問われる。 耳を口中に含まれ、甘噛みされ、舐め、しゃぶられ、吸われる。 勃起した乳首は、親指と人差し指で摘ままれ、くにくにとこねくり回される。 若宮さんが上下に身体を揺する度、ローションのねちゃねちゃという淫らな音が耳を犯し、柔らかすぎる若宮さんの肢体の感触が身体に刻みつけられていく。 「あっ❤んあぁぁっ❤❤」 「可愛らしい声♪……気に入ってくださったようで何よりです。源一郎様も、このマッサージを受けられると、とても可愛らしいお声を出されてましたよ❤」 腰を持ち上げようにも体に力が入らない。 若宮さんの体重はとても軽いにもかかわらず、跳ねのける事が出来ない。 齎される快感によって、抵抗しようとする気力さえもどんどん奪われていく。 「あっ、あぁっっ❤き、気持ちいいぃっ……❤❤」 びくびくと体が震える度、タオルに肉棒を擦り付けてしまう。 窮屈な紙パンツの中で次々に溢れ出す我慢汁に塗れ、肉棒が限界に追いつめられていく。 (ま、まずい……イっちゃう……❤❤) 口の中に溢れた涎が、口の端から零れ落ち、射精を覚悟した瞬間。 「はい、背中は完了です♪」 「へっ……」 あと少しで射精できるというタイミングで、若宮さんが背中を降りてしまう。 (そんな……) 「ふふ、どうされました?」 「い、いえ……なんでもないです……」 「何かございましたら、遠慮なく仰ってくださいね。それでは………次は仰向けになってください❤」 「っ………」 一瞬、お預けを食らって情けない気持ちになったものの、次に齎された言葉に、今度は嬉々として従ってしまう。 ぐるりと仰向けになると、紙パンツに収まりきらずに露出した亀頭が見えた。 我慢汁に塗れ、赤黒く腫れあがり、びくびくと震える愚息に、急に恥ずかしさが込み上げてくる。 「では、ローション垂らしていきますね♪」 そんな僕の様子に構う事もなく、若宮さんが、僕の胸にローションを垂らしていく。 さらに、それを塗り広げるように撫でられる。 「あふぁっ❤」 敏感な乳首やわき腹を撫でられる感触に、思わず身をよじってしまった。 「穂村様❤」 ぐっと顔を近づけてくる若宮さん。 綺麗な黒髪が、僕の額や頬をくすぐる。 その綺麗な瞳には、欲情に歪んだ醜い男の顔が写っていた。 (爺さんも、こんな………) あの厳格そうな雰囲気を醸し出していた祖父が、孫ほども年の離れた女性にいい様に蕩けさせられていたとは、あまり考えたくはなかった。 「お口にも、ローション欲しくないですか?」 ぺろり、と柔らかそうな唇を舌で舐めながら、若宮さんがそんなことを尋ねてくる。 どくんっ、と鼓動が大きく高鳴った。 男としての矜持が、どろりと溶けていく。 「ほっ、欲しいっ……です……」 「良いお返事です♪…それじゃ、お口をあーんって大きく開けてください❤」 「あ、あーん……」 言われるまま、大きく口を開く。 そんな僕の直上で、若宮さんが口を開き、舌を伸ばす。 彼女の唾液が、舌を伝い、その先端から僕の口の中へときらきらと煌めきながら滴り落ちていく。 口の中が微かに甘い香りのする若宮さんの唾液で満たされていく。 「まだ飲んじゃだめですよ❤」 若宮さんの顔が下りてきて、唇を重ねられる。 舌が、僕の口内に溜まる唾液を攪拌しながら、僕の舌に絡みつき、扱き上げる。 呼吸が上手くできない。 (お、溺れるっ………!!) パニック状態に近くなるが、いつの間にか両手は恋人握りで拘束されていて逃れられない。 「零しちゃダメですよ❤」 至近距離で窘められて、身体が暴れだしそうになるのを何とか堪える。 このまま殺されるのではないか―――とさえ思った。 その一方で、股間では肉棒が痛いほど勃起している。 死を覚悟した時、雄の生殖本能は子孫を残そうと最も強く掻き立てられるのだという。 そんな雑学が脳裏を過った。 時間にすれば、僅か5分足らずだっただろう。 だが、無限とも思える時間だった。 漸く満足した若宮さんが顔を上げ、微笑む。 行いは悪魔のようなのに、その笑顔は女神のようだった。 「どうぞ。飲んでください❤」 許可を受け、口の中一杯に溢れそうになっていた若宮さんと僕自身の唾液が混じり合った混合液をごくごくと飲み干していく。 美味しいとか、美味しくないとか、そんな感覚はなかった。 にもかかわらず、全身が熱くなり、紙パンツは我慢汁でぐっしょりと濡れていく。 人間として、或いは男として、大切な何かを奪われたような、胸のどこかに穴が開いたような感覚。 「よくできました❤」 すべてを飲み干した僕の頭を、若宮さんが撫でて褒めてくれる。 じんわりとした幸福感が、胸に空いた穴を埋めていく。 それが、心地よい。 身体だけでなく、心も解されていくような………。 若宮さんの顔が僕の胸元へと降りていき、乳首が口中に含まれる。 硬く勃起した蕾を舐め、しゃぶられ、吸われ、時折甘噛みされて、そのぞくぞくとする快楽に身体が震える。 「ふふ、穂村様。おちんちんがすごぉく、カチコチになっていますよ❤」 「あ、ぁぁっ❤……わ、若宮、さんっ……も、もうっ❤❤ 紙パンツの上から、爪先だけでつぅっと撫でられて、思わず背が仰け反ってしまう。 「もう……?」 ちろちろとふやけた乳首を舐めながら、上目遣いに首を傾げる若宮さん。 「もう、何ですか?❤」 「さ、触ってください……!」 もはや限界だった。 既に、頭の中は射精する事だけで一杯だ。 「何をですか?」 「あぁっ……お、おちんちん……を……」 意地の悪い問いかけに消え入りそうな声で、答える。 恥ずかしさで身体が燃えるように熱い。 だが、その熱さは性的興奮と同義だった。 「触ってますよ?」 「ああっ……か、紙パンツの上からじゃ、なくて……ちょ、直接……!」 僕の懇願に、若宮さんが微笑む。 「そういえば……穂村様。弊社の株券はどうされるおつもりなんですか?」 「へ………」 不意のタイミングで飛び出た想定外の質問に、思わず硬直する。 紙パンツの上からしか触ってくれないもどかしさに悶えながらも、その視線が空を彷徨う。 「そ、それは………」 「売却される……おつもりですか?」 「あっ、あぁぁっ……❤❤」 若宮さんの手が紙パンツの中に入ってきて、我慢汁でどろどろの肉棒を握る。 「どうして、売却されてしまうんですか?」 「あっ❤ちょっ❤あぁっ❤あぁぁっ❤」 紙パンツに亀頭を擦り付けるように、しこしこと上下に扱かれる。 気が遠くなるような快楽に、涎が溢れ出す。 「折角、こうしてお近づきになれましたのに。寂しいです……」 寂しそうな表情をしながら、肉棒を扱き続ける手は一向に休めない。 先ほどから焦らされていた事もあり、あっという間に射精欲が込み上げてくる。 「あっあっ、も、もうっ………」 「ダメです❤」 射精に備えて身構えたところで、若宮さんが根元をぎゅっと握ってくる。 「あぁぁあっっ………」 射精を押し留められる焦燥感に、苦悶の呻きが漏れる。 若宮さんが紙パンツの紐を切る。 束縛が解けて、大きく反り返った肉棒が腹を打った。 「ふふ、とても硬くて……解し甲斐のありそうなおちんちんですね❤❤」 ひくひくと震える裏筋を、つぅっと撫でられる。 「な、なんで、そんな事を、知って……あぁぁっ❤❤」 玉袋を揉まれ、言葉が途中から喘ぎ声に変わる。 若宮さんの言う通り、僕は祖父から相続したヴェイン・グループの株を売るつもりだった。 だが、それは知り合いの証券マンにしか相談していない事だ。 「何かご不満な点でも?」 不満な点あらば………あった。 「む、無配当、だからっ……うひぃっ……❤❤」 射精の波が若干引いたところで、シコシコと軽快に扱き上げられる。 カリ首に引っ掛ける様な扱きに、びくんびくんと体が跳ねてしまう。 「なるほど。無配当だから……ですか」 ヴェイン・グループは今、急成長している新興財閥グループだ。 株価も順調に上昇しており、このまま継続して保有していてもいずれは大きな利益を得られるだろう。 しかし、できる事ならば、毎年入ってくる配当金を貰える方が僕個人としてはありがたかった。 もし、ヴェイン・グループが日本企業の平均である2%の配当金を出してくれれば、僕はそれだけで毎年2000万円近くを得られるのだ。 しかし、ヴェイン・グループは更なる成長に向けての投資という名目で、これまで一度も配当金を出したことがない。 「だから、弊社の株を売り、配当率の高い企業の株を購入されようとされているんですね」 射精するぎりぎり手前でコントロールするように愛撫する手を緩めながら、若宮さんが小刻みに頷く。 確かにヴェイン・グループが優良株であることは間違いない。 しかし、唯一無二の選択肢という訳ではない。 現在、東証一部だけでも約2300社が上場しているのだから、ヴェイン・グループよりも優れた企業も多いのが現実である。 売る前に一度ぐらいヴェイン・グループが誇るヴェイン・リゾートを楽しんでみようと思ったのが、今回この地へ足を運んだ本当の理由なのである。 「困りましたねぇ……」 若宮さんがローションのボトルを手に取り、肉棒の上で傾ける。 とろとろの液体が肉棒をコーティングしていく。 そして―――両手で握る。 ぐっちゅうぅぅぅっ❤❤ 「うひぃぃぃいっっ……❤❤❤」 思わず耳を塞ぎたくような淫らな音と共に、これまでに経験したどのような快楽をも上回る悦楽が全身を貫いていく。 「弊社では、個人投資家の皆様に、是非弊社の応援団―――安定株主になっていただければと考えておりまして」 まるで雑巾を絞るかのように、ぎゅちゅっ❤じゅちゅぅっ❤と肉棒を刺激しながら、若宮さんが本当に困ったような顔をする。 「ぁぁっっ、うひぁぁぁぁっっ❤❤❤」 激しい快楽に、あっという間に射精欲が込み上げてくる。 だが、あと一歩で射精できるというところで、若宮さんが手を放してしまう。 「考え直していただけませんか?」 「そ、そんな事言われても…ぉぉぉぉっ❤❤」 最後まで言わせて貰うこともできず、再びヌルヌルの肉棒を扱かれ、快楽の悲鳴を上げさせられる。 だが、やはり射精の一歩手前で刺激が止まってしまう。 「そんなこと仰らず。ね?❤❤」 乳首をカリカリと刺激され、耳を咥えられる。 唾液を流し込み、啜り上げる。 ちゅぱっ、ちゅぷっ、じゅるるるっ、と淫らな音が頭の中に響く。 「ひぃぃぃぃっ❤❤ゆ、許してぇぇぇっ❤❤」 ドアノブを回すように亀頭を責められ、大きく体が跳ねてしまう。 「あ、ダメですよ。お約束いただくまでお預けです❤❤」 「あぁぁぁっっ❤❤」 絶頂寸前で根元を強く握られ、苦悶の声が漏れる。 「『株は売らない』ってお約束いただけたら、私の手マンコでどびゅどびゅって気持ちよく射精させて差し上げますから❤❤」 耳元で囁かれ、ぐずぐずと理性が崩れていく。 「おっ、おぉぉぉっ……❤❤」 「ほら、タマタマもパンパン。あまり溜めすぎるのもお体に毒ですよ?」 限界まで膨れ上がった睾丸をヌルヌルの手でもみゅっもみゅっと揉み込まれ、頭を左右に振り乱しながら苦痛の声を漏らす。 過ぎたる快楽は、もはや拷問に等しい。 「もっ、もぅっ、あぁぁあっっ❤❤お、おかしくなるぅぅぅっ❤❤」 「立派ですよ、穂村様。源一郎様ならもうとっくに……ふふ❤❤」 「あっ、あぁぁっ……❤❤」 (じ、爺ちゃん………も………こんな目に……) 株を相続した時、何故祖父が配当金も出さないヴェイン・グループに投資していたのかが謎だったが、その理由の一端が知れた気がした。 「ほら。意地を張らずに。ね?楽になってしまいましょう?」 何度も何度も寸止めを受けて、心に罅が入っていく。 (もう……いいや……) ここはヴェイン・グループが運営する南国のリゾート地。 都会の喧騒から隔絶されたこの地で、誰に気兼ねする事もなく羽を伸ばすことができる。 それが、このリゾート地の売り文句である。 それは、裏を返せば、逃げ場がないという意味でもあるのだ。 この島のすべてがヴェイン・グループの掌中にあるのだから。 それは、島を訪れる客も例外ではない。 ここで抵抗したとしても、若宮さんから逃げることはできない。 この地獄の様な寸止めを延々と繰り返されるだけだろう。 そんなの………おかしくなってしまう。 そんな事になってしまうぐらいなら………。 「わ、わかった。う、売らない、から………」 「お約束いただけます?」 「や、約束するぅぅぅぅ、だから、イかせてぇぇぇっ……お願いしましゅぅぅ❤❤」 涙と鼻水でぐずぐずの顔をしながら、僕は若宮さんに懇願する。 「わかりました。ありがとうございます、穂村様❤」 若宮さんが満面の笑みを浮かべる。 その行動は悪魔そのものなのに、やはりその笑顔は純真な女神のようで。 「それでは、タマタマの中にパンパンに堪ってるもの、ぜぇんぶどびゅどびゅって私の手マンコの中に出しちゃってください❤」 まるで祈りを捧げるかのように両手を組み合わせる。 (これはまずい………) 頭のどこかで、最後に残った理性の欠片が呟く。 あれは絶対に気持ちいい。 たぶん、この快楽を知ってしまったら、もう後戻りできなくなるほどに。 だが、心の大部分は、その瞬間を待ち焦がれてしまっていた。 組み合わせた両手の中に、醜悪な肉棒がずぶずぶと飲み込まれていく。 「うぎっ❤ぃぃぃぃぃっ―――❤❤」 手マンコとはよく言ったもので、本当に女性の膣に挿入しているかのような快楽に全身の神経という神経がオーバーヒートを起こしていく。 若宮さんが両手を上下に振る。 ぐっちゅ❤ぐっちょ❤と、淫らな音が部屋に響く。 それはさながら、咀嚼音のようだった。 ローションと我慢汁が潤滑油となり、指一本一本が襞のように絡みつき、肉棒が蕩けてしまうのではないかと思うほどの快楽に頭の中が真っ白になる。 「ああああっ、も、もうっ、これ、ダメっ、ダメですっ❤…あぁぁっ、出るっ!出ますっ!あぁあっっ、いぎゅぅぅぅっ❤❤」 数度にわたる寸止めによって押し留められていた大量の精液が、その瞬間めがけて込み上げてくる。 「いいですよ、イっちゃってください❤」 若宮さんの許可を受けて、僕は思い切り腰を突き上げる。 まるで本当に、膣奥にすべてを注ぎ込もうとするかのように。 子宮口を突き抜ける代わりに、組み合わされた掌の間から亀頭が突き出る。 「あぁああああっ❤❤❤❤」 絶叫と共に、僕は決壊した。 どびゅるるっ、どびゅっどびゅっどびゅっ、びゅるるるるっ、どびゅどびゅっ、どびゅぅぅぅぅぅ、びゅるるるっ、どびゅっどびゅっ、どびゅるるっ……!! 寸止めによって濃縮された精液は粘度の高い塊となって吹き上がり、べちゃべちゃと若宮さんに降り注ぎ、その柔肌を白く染めていく。 若宮さんは最後の一滴まで精液を搾り取ってくれた。 僕は四肢を投げ出し、放心状態で天井を見上げている。 意に反する約束をさせられたはずが、何故か嫌な気分はしていなかった。 *** 「な、なんだこれ………」 「源一郎様はプールもお好きでしたので。参りましょうか」 タオルで身体を拭った後、若宮さんにそう言われるままホテル内のプールにやってきた僕。 だが、そこで目にした光景に、思わず立ち尽くしてしまった。 プールの中でも、プールサイドでも、当たり前のように男女が淫らな行為に耽っているのだ。 プールの縁に手をついた女性を後ろから貫く男性。 プールの縁に腰を下ろした男性の股間に顔を埋める女性。 水面に浮かんだ男性の肉棒を胸で挟んでこねくり回す女性。 チェアに寝そべった男性の上で腰を振る女性。 公共の空間だと言う事もお構いなしに、性を謳歌する人々。 背徳と堕落の狂宴。 笑い声と喘ぎ声が混じり合った狂乱の喧騒が、白昼堂々、僕の眼前で展開されていた。 「いかがされました?」 そんな光景が、さも当たり前だとでもいうのか。 表情一つ変えることなく、若宮さんが僕の顔を覗き込む。 「こ、これは………」 「我々コンシェルジュの役目は、お客様が快適にお寛ぎいただくのをお手伝いさせていただく事ですので。お望みとあれば、どのような事でもさせていただきますよ❤」 戸惑う僕に身を寄せ、そっと股間に手を這わせてくる若宮さん。 先ほどあれほど射精したにもかかわらず、目の前で繰り広げられる淫らな宴と、若宮さんの瑞々しく、厭らしい肢体を前に、僕の水着ズボンにははっきりとテントができていた。 ごくりと唾を飲み込み、若宮さんに手を引かれるまま、僕もまたその狂乱の中に身を投じていく。 とはいえ、色々と浮いていそうなプールにはさすがに入る気になれず、僕たちはプールサイドのチェアに腰を下ろした。 飲み物を持って巡回している黒服からシャンパンを受取り、とりあえず乾杯する。 その間も、四方から淫らな嬌声が聞こえてきて、落ち着かない事この上ない。 隣のチェアでは、60過ぎのおっさんが四つん這いになって、尻穴を女性に舐められながら肉棒を扱かれ、まるで豚の様な醜い喘ぎ声を漏らしている。 思わず嫌悪感を抱くような、物凄く、醜悪な図だった。 だというのに、股間の高ぶりはさらに増していく。 「あの方は、次期幹事長とも噂される与党の有力国会議員様なんですよ。毎年ご利用いただく常連様です」 添い寝するように身を寄せてきた若宮さんが耳元で囁く。 「えっ……」 驚いて視線を向けた先で、おっさんがびくびくと体を震わせながら白濁液をぶちまける。 国家を導かねばならない立場の男が、なんと無様な………。 そんな思いとは裏腹に、肉棒がひくひくと震える。 「ふふ……興奮されてるんですか?」 「んんっ……」 膨らんだ股間に、若宮さんが太ももを擦り付ける。 剥き出しの乳首に指が這いまわると、ぞくぞくした快楽に体が震えてしまう。 「あの方は最高裁判事。あちらは有名な俳優さんですね。あの方は一流企業の会長様。あちらで踏まれて喜んでいらっしゃるのは警視総監。その隣で並んで踏まれていらっしゃるのは大手新聞社の編集長。プールに浮かんでいらっしゃるのは、あの舌鋒鋭い野党のホープ様です。今はとても気持ちよさそうな顔をしていらっしゃいますね。皆様、いずれもVIPの方々です」 プールの周りで快楽を享受している男たち。 それを一人一人示しながら、若宮さんが、その素性を明かしていく。 そのいずれもが、高い社会的立場や権威、権力を持つひとかどの人物たちだった。 そして、そんな男たちは例外なく誰もが、快楽に蕩け切った顔をしている。 ヴェイン・グループがいかにこの国の深層に浸透しているのかが、このプールに集う人々を見るだけでわかるわけだ。 きっと、僕も彼らと同じ顔をしているのだろうが。 「皆様、弊社を支えてくださる大切な株主様たち。勿論、穂村様もそのお一人です❤」 耳が咥えられ、舌が這いまわる。 手を掴まれ、胸元へと誘導される。 誘われるまま、たわわな乳房を握ると、柔らかすぎて、指がずぶずぶと沈み込んでいってしまう。 荒い息を吐きながら、若宮さんの目を見る。 その目には、優しくすべてを許すような光があった。 或いは、それは僕が抱いた勝手な願望だったのかもしれない。 しかし、その光に甘えるように、僕は若宮さんの胸の谷間に顔を埋めた。 ふわふわと柔らかくて、しっとりと滑らかで、ほんのりと温かくて、ふんわりと甘い香りに包まれる。 両手で乳房を揉みしだいて、その感触を堪能する。 ギンギンに勃起した肉棒が、掌中に包まれ、シコシコと扱かれる。 幸福感が心を満たしていく。 まるで、天国にいる様な気分だった。 日本を動かすVIP達がこぞって足を運ぶ理由もわかる気がした。 乳首を口に含み、舌で転がす。 ちゅうちゅうと吸いながら、無言のまま遠慮なしにどぶどぶと大量の精を放った。 「お望みがあれば、どのような事でも仰ってください、穂村様❤」 射精して尚、一向に硬さを失わない肉棒を精液に塗れた手で優しく扱きながら、若宮さんが囁く。 「おっぱいで………して……」 その言葉に甘えて僕が望みを口にすると、若宮さんは微笑みながら頷いてくれた。 「畏まりました❤」 僕の両足の間に身体を潜り込ませる若宮さん。 屹立し、快楽への期待にひくひくと戦慄く肉棒をゆっくりと、僕に見せつけるように身体を厭らしく揺すりながら、谷間へと収めていく。 とても柔らかくて。 とても温かくて。 肉棒がふわぁと蕩けていくような快感に、頭の中までトロトロになっていく。 「気持ちぃぃぃ……❤❤」 「ふふ、とても幸せそうなお顔で、私まで嬉しくなってしまいます❤」 若宮さんは微笑みながら、胸の両脇に手を添え、ゆっくりと圧力を高めていく。 「ふ、ふわぁぁっ……❤❤」 思わず天を仰いだ僕の口の端から、涎が一筋、二筋と零れ落ちていく。 もにゅもにゅと柔らかな空間に捉えられ、全身の力という力をすべて吸い取られているかのような感覚に襲われる。 ある程度圧力を高めた後、今度はゆっくりと力を抜いていく。 もっちりとした胸肉が、まるで別れを惜しむかのようにねっとりと離れていく感触が、これはこれで気持ちいい。 「はうぅぅんぅっ❤❤」 そしてまた、ゆっくりと圧力を高めていく。 まるで、水面に浮かび、ゆっくりと漂っているような。 寄せては返す波間にたゆたゆと浮かび、温かな日差しを浴びているような幸福感に全身がふにゃふにゃと弛緩していく。 穏やかな快楽が、精嚢における精の作製をより一層促す。 弛緩する全身の中で、唯一硬さを失わない肉棒は赤黒く腫れあがり、血管が浮かび上がり、先頭からは圧力の高まりに従って、ぴゅっぴゅっと我慢汁が噴き出していた。 噴き出した我慢汁は肉棒を伝い、若宮さんの双乳を汚していく。 周辺の喧騒も徐々に意識の外に追いやられ、この空間に自分と若宮さんしかいないような錯覚を覚える。 ただただ、若宮さんに意識を集中させ、少しでも快楽を享受しようと自らももぞもぞと腰を動かしてしまう。 気持ちいい。 だが、射精には至らないぎりぎりのライン。 もう少し。 あと少しだけ、早く胸を動かしてくれれば、気持ちよく射精できるというのに。 徐々に、もどかしさが募っていく。 射精したいという思いが強くなっていく。 「わ、若宮さん………」 思わず切なげな声で、懇願するかのように名を呼んでしまう。 若宮さんは胸を動かしながら、穏やかに優しく微笑む。 まるで、聖母か女神のように。 「―――ところで、穂村様。買い増しのご予定はないんですか?」 「え………」 唐突な問いに、思わず戸惑いの声が漏れる。 「か・い・ま・し、です❤」 一音一音区切って発音しながら、若宮さんがチェアの下に手を伸ばす。 戻ってきた手には、ローションのボトルが握られていた。 蓋を外し、自身の胸の谷間めがけて、どぼどぼと中身を振りかける。 「あっ❤あぁぁっ……❤❤」 少しひんやりとするローションが、若宮さんの胸を、胸の谷間を、そしてその谷間に捉われている肉棒をコーティングしていく。 若宮さんがボトルを仕舞い、再び両手を胸に添えて動かし始めると、ぬちゅっ❤ずちゅっ❤もちゅっ❤にちゅっ❤と卑猥な音が脳髄に響く。 「ひぃぃぃいいっ……❤❤」 先ほどまでとは段違いの快楽に、思い切り腰が浮き上がる。 頭の中に閃光が迸り、睾丸がぎゅっと押しあがる。 先ほどまでの穏やかな快楽が嘘のような、嵐のような暴虐の快楽。 抗う術もなく転覆し、溺れてしまう。 だが、射精する!という瞬間に根元を握られて押し留められてしまう。 「現在、穂村様がお持ちの弊社株は100万株ですが、もう少し買い増しされてはいかがかと。例えば……あと、50万株とか❤」 そんな悪魔のような囁きを、女神のような微笑を浮かべたまま口にし、容赦なく胸をぐりぐりと動かして僕を責め立てる若宮さん。 「うぎぃぃぃぃっ❤❤」 肉棒を激しく揉み込まれて、涙やら鼻水やら涎やら、穴という穴から液体が溢れ出していく。 だが、一番液体を発射したい穴だけが、それを許してもらえない。 絶頂寸前の快楽にびくびくと震える僕を巧みに捌きながら、最後の一押しだけはどうしても与えてくれない。 「いかがですか?」 「そっ、そんなの無理ぃぃぃっ❤❤」 「あら、どうしてですか?」 ぶるぶると首を左右に振る僕に、若宮さんはわざとらしく首を傾げて見せる。 「お、お金が、な、ない、あふぁぁぁぁっ❤❤」 僕はしがないサラリーマンに過ぎない。 50万株ものヴェイン・グループ株を買う金などある訳もなかった。 だが、若宮さんはふふ、と笑みを漏らし、 「そんなことはないでしょう?穂村様が源一郎様から相続されたのは……株だけではないのですから❤」 片手で両胸を抱え、上下に揺すりながら、もう片手を僕の胸に伸ばす。 すっかり勃起し、切なげに震えている乳首を摘まみ、捻られる。 「あふぅぁぁぁぁっ……❤❤」 唐突に与えられた激しい快楽に、思い切り仰け反ってしまう。 (だ、ダメだっ、こ、こんなのぉぉっ❤❤……だ、誰か、助け―――) 霞む目を瞬きながら、何とか救いを求めようと隣を見ると―――。 「ぶひっ❤買うっ❤50万でも100万でも買うからっ❤❤あへっ、イっ、イかせてぇぇぇっ❤❤ぶひぶひぃっ❤❤」 次期幹事長とも噂される与党の有力国会議員は、思わず目を背けたくなるような太いペニスバンドを付けた女性にアナルを貫かれ、ブタの鳴き声を上げながら射精を懇願していた。 「畏まりました。存分にイってらっしゃいませ❤」 若宮さんとそっくりな微笑みを浮かべた女性が、政界の重鎮に覆い被さりながら囁き、思い切り腰を突き上げながら片手でペニスを、もう片手で醜く勃起した乳首を思い切り扱き上げる。 「ぶひぃぃぃぃぃぃっ❤❤❤❤」 激烈な3点責めに醜悪な鳴き声を上げながら全身をがくがくと痙攣させ、どばどばと大量の白濁液をぶちまける国会議員。 60過ぎの老人とは思えぬ量だったが、やはりそれだけの射精をするのは体力的にも厳しいのだろう。 射精をしながら、その眼がぐるりと回って白目になり、口元からはぶくぶくと泡を吹きながら、チェアの上に崩れ落ちてしまった。 そのアナルから引き抜いたペニスバンドからは、湯気さえ立ち上っている。 (―――っ………!) 思わず男性から背けた目が、女性と合ってしまう。 無言で、微笑みを浮かべる女性。 今、一人の男性を絶頂に至らしめたとは思えない、穏やかな女神の様な微笑。 それを見て、思わず背筋がぞくりと震えた。 慌てて辺りを見渡すと、最高裁判事も、有名俳優も、一流企業の会長も、警視総監も、大手新聞社の編集長も、野党のホープも、この世を動かす権力や権威を持ったVIPたちがよがり声を上げ、アヘ顔を晒し、口々に株の買い増しを約束しては精を搾り取られていた。 それは、まさに阿鼻叫喚の地獄絵図。 地獄の鬼たちに絞り尽される、哀れな咎人のようだった。 「―――どうかされましたか?穂村様」 声のした方を見れば、若宮さんが微笑みながらこちらを見つめている。 あの、女神のような微笑を。 「わ、若宮さん、これは………」 「これは?」 若宮さんがたゆんっと胸を動かす。 その谷間に捉えられた肉棒の先端から、我慢汁が溢れ出す。 こんな状況にも関わらず―――いや。 こんな状況だからこそ、僕のそこは、これまでの人生で経験した事のないほど硬く勃起していた。 「我々コンシェルジュの役目は、お客様が快適にお寛ぎいただくのをお手伝いさせていただく事ですので。お望みとあれば、どのような事でもさせていただきますよ❤」 若宮さんが口にした台詞は、先ほども耳にしたものだった。 「望みとあれば………」 このプールで行われている痴態も、すべては客が望んだことだと若宮さんは言いたいのだろう。 そして、僕が望みさえすれば、この目を剥き、泡を吹いて気絶している国会議員のように、身を破滅させるような悦楽を味わえるのだ、と。 その引き換えは、ヴェイン・グループの安定株主になる事。 多くの株を買い増し、配当金を求めないという事。 恐らくは、株主総会で議案に反対票を投じる事すら許されないのではないだろうか。 誰が、どの議案で、どのような票を投じたのかなど普通であればわかるはずがない。 しかし、もはやヴェイン・グループならば何でもありなのだろう。 若宮さんが、ひくひくと震える肉棒の先端にキスをし、そのまま裏筋に舌を這わせていく。 「穂村様が源一郎様から相続された土地をもし売却されるのでしたら、弊社のグループ会社をご紹介する事もできます❤」 ずぶずぶと肉棒が口中に飲み込まれ、吸われる。 気の遠くなるような快楽に、一気に射精感が込み上げてくるが、若宮さんはすぐに肉棒を吐き出し、射精に至らぬように加減しながら舌を這わせ、キスをまぶしていく。 睾丸を口に含み、ちゅぽんっ❤と卑猥な音を立てながら吐き出す。 「どうされますか?」 そして、僕に尋ねる。 僕がどんな顔をしていたか。 僕にはわからない。 だけどきっと、この場に居る男たちと同じ、快楽に蕩け切った顔をしていたのだろう。 それは、絶望や諦念と同義だった。 「100万株………買いますぅ❤❤」 「ありがとうございます♪」 若宮さんがぺこりと頭を下げる。 「それでは、私のおっぱいとお口で、穂村様に溜まっているもの、ぜぇんぶ吸い上げて差し上げます❤…勿論、この後も源一郎様がお好きだったお食事やお風呂もお楽しみください♪明日、お帰りになられるその時まで誠心誠意、尽くさせていただきます❤」 ずぶずぶと肉棒が飲み込まれ、思い切り吸い上げられる。 僕は天を仰ぎ、ありったけの精を若宮さんの口中に吐き出しながら、プールに木霊する嬌声の渦に身を投じた。 *** あれから半年―――。 僕の生活に、特段の変化はなかった。 相変わらずのしがないサラリーマン生活だ。 祖父から相続した土地も財産もすべて金に換え、ヴェイン・グループの株式購入に投じた。 株価は順調に上昇している。 だから、特段の損はしていない。 個人投資家の多くが、買い増しこそすれど、売却することがないのだから当然と言えば当然だ。 つけっぱなしのテレビから、与党の幹事長が交代したというニュースが流れていた。 新たに幹事長に就任した男性の顔は、あの日、あの場所で見た顔とはまるで別人のような引き締まった顔つきをしていた。 株主優待であのリゾート地を訪れることができるのは年に1度。 僕はその日を楽しみに、日々を生きている―――。 绝对领域实验 「あーもう、何なんだよこの問題、わかんねーよ!」 「つーかさぁ、あの先生教えんの下手じゃね?」 「静かにしてよー! 集中できないでしょ!?」 「あ、ノート貸して! この前の板書まだ写してなくて......」 「もう、今回は......捨てよう...寝よう......」 テスト前日の昼休み。 ある者は足掻き、ある者は諦め、それぞれ思い思いの言葉を口にする。 「くあぁ...............」 そんな中、俺は教室の隅で惰眠を貪っていた。勿論諦めたからじゃない。今回の範囲はとっくに網羅し終えているからだ。そもそも前日に詰め込むなんぞ愚の骨頂。テスト前日の昼休みはこうやってお茶でも飲みながらゆっくりするに限る......また眠くなってきた...... バチンッ! こくりこくりと船を漕ぎ始めたところ、背中に平手打ちを食らう。ぴりりとした刺激につられ、目蓋はゆっくりと持ち上がっていく。やっぱりそうだ。俺の知る限りこのクラスにこんなことをするやつは一人しかいない。 「いよっ、余裕だねぇ」 叩いた手をぷらぷらさせながら笑うそいつは、 俺の数少ない友人......親友と呼んでもいい仲の男子。 「人を叩いて起こす癖、直せって言ってるだろ......で、お前はどうなんだよ?」 「俺のことはいいじゃねーかよ。それにどうせまたお前が学年一位なんだろ?」 「努力の成果だって。必然必然」 「まぁお前勉強以外ほとんどポンコツだもんな」 「うっせ」 そう、こいつの言う通り俺はこの学校に入学してからことテストにおいては学年一位以外取ったことがない。そのせいか教師陣からの評判は大変良く、代わりに一部の生徒から物凄くやっかまれている。おかけで友人と呼べる友人はこいつとあともう一人しかいない。 「二人は相変わらず仲がいいんだね」 そしてそのもう一人が、この学年で俺に次ぐ成績優秀者の笹嶺(ささみね)さん。俺はこいつに茶化され、こいつは俺の反応を見て笑い、そのやり取りを目にした笹嶺さんがまた笑う。これが俺達三人のいつもの昼休み。 「で、笹嶺さんは今回どう? やれそう? 俺、そろそろコイツが首位転落するとこ見てみたいわ~」 「お前なぁ......」 俺が友人の冗談に呆れていると、笹嶺さんが困った表情で俺を見る。まるで助けを求めるように。 「ごめん、笹嶺さん。こいつの冗談は聞き流してくれていいから」 「ううん、そうじゃなくてね。実はその、今回の範囲で分からないところがあって、そこを教えて欲しくて......」 「......え? そうなの? そういうことならいつでも言ってくれればよかったのに」 俺がそう言うと笹嶺さんは安心したのか、表情を少しずつ和らげていく。分からないところを前日まで放っておくなんてちょっと彼女らしくない気もするけど、力になれるのなら俺としては嬉しい限りだ。というのも、彼女の容姿と性格は学業以上に優れており。うら若き健全男子学生の一人として、今よりもっとお近づきになりたいという下心があったりもするわけで。......たまにお近づきになるといい匂いがするし。 「ごめんなさい、助かります。放課後私の家に来て欲しいんだけれど......」 「わかった。制服のままでいい?」 「ええ。あんまり時間を取らせるわけにもいかないしね」 返事では平静を取り繕いながらも、内心では強く浮き足立つ。しかしまぁ、女の子の家にお邪魔になるというシチュエーションもさることながら、その対象があの笹嶺さんとあらば浮くのも立つのも致し方ない。主に俺の足は悪くない。 「お、そういう話なら俺はパスだな。笹嶺さんが分からない所を俺が分かるわけねーし」 そしてこういう時のこいつは理解が早くて助かるというか、本当に気が利く。尤も、このにやついてる面は癪でしかないが。さらに十中八九明日の昼メシ代は俺持ちになる訳だが。 「ふふ、ごめんね。彼のこと、ちょっと借りるね」 「いーっていーって」 親友は笹嶺さんにそう言うと、俺に目配せをして。音を出さずに、唇の動きだけで、(頑張ってこいよ)と。そう告げる。 (さんきゅ。明日色々返す) (おう、いっちょ毎度あり) それに対し、俺もまた唇の動きだけで応える。そんなやりとりをしている間に、五限の予鈴が鳴るのだった。 ・・・・・・ 「お邪魔します......」 「お構いなくー」 放課後。 校門から出て、自転車を漕ぐこと20分。さも普通な玄関を一歩跨ぐ。瞬間。 ふわり。 甘やかで柔らかな香りに身体を包まれるような感覚。笹嶺さんにお近づきになった時にほのかに感じるのと似たそれが、俺の鼻腔と理性をひっきりなしにくすぐろうとしてくる。 それがいわゆる『気になっている女の子の家補正』......つまりプラシーボに近いあれなそれのおかげなのか、それとも何か他の要因によるものなのか、俺が図りかねている時。 「どう? いい匂いとかしない? アロマ、焚いてるんだけど」 「アロマ?」 「ええ。リラックスできて、いつもより集中できるようになるの。今日は元々君を呼ぶつもりだったから、あらかじめ焚いておきました」 ああ、よかった。いくら俺が健全男子学生であったとしても、女の子の家補正に嗅覚を支配されていたとしたら中々にやべーやつだ。 ......それはともかく。このアロマの香りが普段から彼女の身体に染み付いているのだと思うと少しばかり平静が揺らぐ。結構......いや。かなり好きな香りだ。 「さ、上がって上がって。私の部屋はこっち」 靴を揃え、笹嶺さんの後ろについて。香りのもとに導かれるように歩みを進める。どんどん濃くなっていく。眠くなるような、頭が冴えるような。ぼーっとするような、はっきりするような。不思議で不思議で癖になってしまいそうな香りが、そこに近づくにつれ強くなる。 ばたんっ 笹嶺さんがドアを閉める音にはっとする。歩くうちにいつの間にか彼女の部屋の中に居たらしかった。そんなことにも気づけないほどこの香りに夢中になっていた。外に漏れ出す事がなくなったそれが、部屋の中で少しずつ濃度を増す。熟れたラズベリーに周りを取り囲まれていくような感じ。 「......あれ? なんか眠そう? もしかしてちょっと疲れちゃってる? それともアロマが合わなかったりする?」 目を軽く細めた笹嶺さんが、不意に俺を覗き込む。いつもより距離が近い気がする。いつもよりいい匂いがする。いつもよりどきどきする。多分だけど、違う。アロマは合っていないんじゃない。合いすぎてるんだと思う。 「や」 「ふふ、いいよ別に。慣れてないと眠くなったりぼーっとしちゃう人もいるらしいし。だから......」 笹嶺さんは俺から離れ、カーペットの上にちょこんとあひる座りをする。それから、自分のふとももをぽん、ぽんと叩くと。 「ひざまくら。興味ない? すこーしだけならいいかな、なーんて」 しゅり。 かすかな衣擦れの音。なめらかな肌となめらかな布が静かに奏でたそれを、俺の耳は必死になって拾おうとする。笹嶺さんがほんの少しだけスカートをまくる。ほんの少しだけ肌色の面積が増える。視覚と聴覚が脳に柔らかさを訴える。脳が欲にそれを伝える。欲に突き動かされた喉が勝手に鳴る。うるさい。 「え......いい、の?」 疑問を口にしながらも、意識と視線はとうにそこから逸らせなくなっていて。膝上数センチの僅かな楽園。プリーツスカートと紺色のオーバーニーの隙間からのぞく肌色の官能。つまりは絶対領域。 「いいよお。分からないところを教えてもらうお礼、ってことで」 心が強く揺れ動く。いいのか。いいんだろうか。恐らく学園の大多数の男子の脳内で、夜な夜な邪な世界が繰り広げられているであろうそこを、俺の後頭部が独り占めしていいんだろうか。 そんなことを考えつつも、体は正直で。既に彼女に背を向けて、少しずつ腰を落として、頭をゆっくりと下げていて。けど。 唐突に背中に笹嶺さんの体温を感じる。多分後ろから抱きつかれてる。どうしたんだろう。やっぱり膝枕をするなんて嘘だったんだろうか。そりゃそうだ。俺にとって都合が良すぎるそんな話...... 「ちがうちがう。あおむけじゃなくて、うぅ、つぅ、ぶぅ、せぇ......♡」 甘く可愛らしい猫なで声が耳たぶをくすぐる。わざとらしいくらいにはっきりと区切られた言葉が鼓膜を軽く揺さぶる。それだけのことで身体の芯がかあっと熱くなる。心拍の間隔がぐんと短くなる。 「な、な、な」 「君はいつも寝るとき、うつ伏せ? 仰向け? どっち?」 「うつ......ぶせ......」 「じゃあうつぶせじゃなきゃ。できるだけいつも通りの方がリラックス出来るし、その方が起きた時に頭も働くと思うし」 言われてゆっくりと身体を翻す。恥ずかしいとかみっともないとか。そういう感情より期待が勝ってしまった。しょうがない。全国の男子諸君がこの人とこの人のふとももの持つ魔力に勝てるとは思わない。なら俺がこの誘惑に負けてしまうのも必然で―――― くにゅり 「ふあ」 変な声が出る。脳に並べた言い訳と御託が水のように流されていく。そこに顔を埋めた瞬間から、論理と理性は使い物にならなくなり。耳が熱い。頬が柔らかい。鼓動が止まらない。呼吸が治まらない。そんな稚拙な感想さえ述べられなくなりそうで。 「ふともも、気持ちいいんだ。でも興奮しすぎちゃだぁめ。リラックス、リラックス」 ふっくらした五指が頭皮と髪の先の間にするりと侵入してくる。指の腹が描く半円が心地よすぎてうっとりしてしまう。火照り始めた脳が優しくほぐされていく。 「ほらほら、深呼吸だよー。私のふとももの間で、たぁっぷり深呼吸しようね。はい、すってー」 ゆっくりと息を吸い込んでみる。あのラズベリーみたいな匂いが肺いっぱいに広がる。アロマの匂いだと分かっているのに、まるで笹嶺さん自身の匂いであるかのように錯覚する。頭の中が少しずつ笹嶺さんと甘い匂いで満たされていく。 「はいてー」 またゆっくりと、今度は息を吐く。この匂いを自分の身体から逃がしたくない。行かないで欲しい。そう願ってしまう。けど身体は驚くほど笹嶺さんの声に従順だった。半ば俺の意思とは無関係に、肺から匂いが抜けきるまで、頭の中から笹嶺さんがいなくなるまで息を吐き続ける。 「またすってー」 「んああ」 言葉に操られるみたいに、勝手に口が開いて鼻腔が広がる。巡る、巡る。循環する。心地よさと甘い匂いと笹嶺さんが俺の中に戻ってくる。呼吸しながらふぬけた声を出す。けど気にする余裕もない。 「ふふ。もうあたまとろけちゃったんだ。深呼吸するのじょうずだね。すぐとろとろになれてえらいねー」 また笹嶺さんが頭を撫でてくれる。指がつむじを通りすぎる度に何かと何かの境界線が曖昧になる。どろっどろに熔けて無くなっていく。 「それじゃあこれから、私から君にいくつか質問をします。私の言葉に続いて、『はい』と答えてください」 「は、い......」 少し怖いくらい自然に声が出る。分からない。分からないけど、笹嶺さんの声に従いたくてたまらない。言われた通りにするのが凄く気持ちいい。 「私のふとももは、やわらかいですかー?」 「はい......」 「よくできましたー」 ぎゅう。 頬と頬が肉と肉に挟まれて包まれる。顔の力が柔らかさに吸い取られる。代わりに幸せが溜まっていく。ふとももに触れた全てがだらしなく弛んで、どこにも力が入らなくなる。どこにも幸せが逃がせなくなる。 「私のふとももは、きもちいいですかー?」 「っ......はい」 顔のどこにも力を入れられない筈なのに、声だけは出すことが出来た。返事をする度に頭を撫でてもらえることに気づく。頭を撫でられるともっと従いたくなる。頭を撫でられたいから笹嶺さんの言葉に従って返事をする。 「最後の質問です。私のふとももは、すきですかー?」 「は......い......っ!?」 ぞくり。 質問に答えた瞬間、背中が仰け反りそうになる。それから、ふとももの間に挟まれた頭がぐつぐつと煮え立っていく。その熱が全身にじんわりと伝わっていく。どうなってるんだ、これ。 「はい。よく言えましたー。君は私のふとももが好き。すき、すきすきっ......♡♡♡ だぁ~いすき♡♡♡♡」 「ひ......あ......あ......!?」 今日一番の甘ったるい声が、煮えたぎった頭に注ぎ込まれる。腰の奥にじぃぃぃんと響く。笹嶺さんの体温を強く感じるようになる。彼女のふとももとの熱と自分の頬の熱が混ざり合ってどっちがどっちか分からなくなる。 「これで君は私のふとももが大好きになりました。これから、ふとももが大好きになった君にいくつかの"おまじない"をかけます。もっとふとももが好きになれる素敵なおまじないです。もっと好きに、なりたいですよね?」 「やっ......まっ......!」 心のどこか。ぎりぎりの瀬戸際で生きていた自我が、消え入りそうな小さな音で警鐘を鳴らす。何かおかしくはないか。そもそもの目的はリラックスではなかったか。なら少し異常じゃないか。この匂いも、この快楽も、この状況も、目の前の彼女も。そう告げているようだった。 「だめ......♡ 自分のきもちにうそついちゃ、だぁ~め♡♡」 「ひう............!!」 笹嶺さんは俺の首元に手を添えると、それをぎゅううっと抱き寄せる。すべすべでなめらかでやらしい肉の間に顔が沈み込む。ふとももに溺れて息継ぎができなくなる。したくなくなる。溺れたままでいいと思ってしまう。甘い甘い肌色の沼から這い上がってこれなくなる。小さな自我の小さな鐘の音は、もっともっと小さくなって。そのまま聴こえなくなってしまった。 「もう一度質問します。もっと好きに、なりたいですよね?」 「はい......」 そう答えた。そうとしか答えられなかった。笹嶺さん。ふともも。匂い。甘い。好き。頭の中はそれだけで、他のことは何も考えられなかった。 「うんうん。えらいこ、えらいこ。無理して聴こうとか、おまじないにかかろうとか、考えなくていいからね。頭をらくに......らくーにして、ただ私の声を受け入れてね。それじゃあいくよー」 『君は私のふとももが大好きになりました』 『私のふとももが大好きな君は、私のふとももがちらつくと何事にも全然集中できません』 『私のふとももが大好きな君は、私のふとももから目を離すことができません。ふとももが揺れるとそれを目で追ってしまいます』 『私のふとももが大好きな君は、私のふとももが視界に入ると次第に興奮していきます。射精のことで頭がいっぱいになります。絶対に勃起してしまいます』 「うあ......」 いつもより低く静かな笹嶺さんの声が、身体にじぃんと響き渡って、ゆっくりと染み込んでいく。けど、それを言葉として受け取ることができなかった。脳に届く前に身体のどこかに吸収されてしまったようだった。 「はい、おまじないおしまい。ね、だしたい?」 不意に、いつものトーンの笹嶺さんにそう聞かれる。今度は言葉がはっきりと認識できる。出したい。何を。分からない。すごく身体が熱い気がする。強いもどかしさを感じる。 「射精......したくない? びゅー、びゅうーって」 言われて自分の欲に気づく。もどかしさの正体に気づく。いつの間にか射精したくてたまらなくなってる。全身の熱と血がそこに集まって、何かを押し出そうとする。自分の身体とカーペットの間でそれがどんどん大きくなるのが分かる。もう痛いくらいに張り詰めてる。下着の中で軽く擦れるだけで甘く疼いて声が出そうになる。それを荒い吐息で誤魔化す。誤魔化すたびに笹嶺さんの匂いが肺の内側でさらに濃度を増す。 「ふふ。息、止まんないね。だしたいんだぁ。でもだぁめ。出すのはもうちょっとだけおまじないかけてから。ね?」 また彼女の言葉に身体が従う。今すぐにでも情けなく床にそれを擦り付けて出してしまいたい。そんな欲がどれだけ大きくなっても俺の身体は動かない。彼女に許されていないからそうすることができない。 「それじゃあ君に、もう一度おまじないをかけます。またらくーにしててね。ぼーっとしたあたまで、ぼーっと聴いてようねー」 『君はこれから、私の匂いで頭をいっぱいにしながら射精してしまいます。私の匂いで頭がいっぱいになると、自然と我慢ができなくなります』 『私の匂いで頭がいっぱいのまま射精すると、普段の倍気持ちよく射精できます』 『私の匂いで頭がいっぱいのまま射精すると、普段の倍の量の精液が出てしまいます』 『私の匂いで頭がいっぱいのまま射精すると、普段の倍射精が長引きます』 『私の匂いで頭がいっぱいのまま射精すると、普段の倍の快楽が身体に焼き付いて離れなくなります。必ず病みつきになってしまいます』 「......はいおしまい。どう? 私の声、ちゃんと聴こえてる? お返事、できる?」 「............はい」 声が震えてる。喘ぎ声みたくなりそうなのを無理矢理押さえつけて返事をする。なんなんだ。なんでこんなに身体が熱いんだ。今すぐにでも冷まさないと自分の体温で火傷するんじゃないかってくらい熱い。でもそれが全然嫌じゃなくて、何かに触れている部分が全部気持ちいい。火にかけられた砂糖のように感覚が甘くとろけて、自分が固体なのか液体なのか分からなくなる。 「声、かわいいね。我慢させちゃってごめんね。もう動いていいからね。ううん、勝手に動いちゃうよ。止まらなくなっちゃうよ」 許された。許されてしまった。自分の意思で彼女に溺れることを許されてしまった。ずっと動かなかった手を腰に回す。出せる限りの力で彼女を抱き寄せる。もっと近づいて欲しかった。どこにも行かないで欲しかった。俺はずっとそこに居たかった。 「んっ......結構がっつくね。がっつかなくても私はここに居るし、ふとももはどこにも逃げないのに。がっついてもいいけど」 がっつく。言われなくともがっつく。肌色を掻き分けてどこまでも。彼女と彼女の匂いから少しでも離れたくなかった。自分から窒息しにいった。頭に酸素が行かなくてもいい。そんなものよりこっちが欲しくて。頬を撫でるむっちりすべすべのこれが好きで好きでしかたなくて。あああ。 「ほらほら、腰止まってるよ? 止めちゃだめでしょ? 出せなくなっちゃうよ?」 命令に従う。みっともなく。恥も外聞もなく。そうするときっと彼女はご褒美をくれる筈だから。やっぱり。頭を撫でてくれた。へにゃりと下半身から力が抜ける。そこの筋肉だけほぐれてゆるむ。流れを塞き止めていた栓が外される。腰の奥で渦巻いていた熱が射精管をじんわりと犯す。じん、じぃんと競り上がってくる。止めようがなかった。 「ふふ。もういっちゃう? いったらおまじない解けなくなっちゃうけど、それでもいっちゃう?」 ふとももの付け根の、一番柔らかいところ。ぷにゅりと膨らんだそこが、ぎゅうって。俺を包んで。幸せの塊で包んで。甘い匂いで閉じ込めて。逃げられなくなって、抜け出せなくって。頭を撫でられるたびに、脳みそがでろりと蕩けていって。びくんびくんと身体の下でそれが喜んで、溢れそうになって。でちゃう。いっちゃう。ごめんなさい。あああああ。 「きもちいいね。いっちゃうね。おまじない、解けなくなっちゃうね。でもガマンできないんだもんね。いっちゃうよね。ほら、いって」 どくどくどくどく。とぷん、とぷんっ......とっくん............. ............ゆっくり、ゆっくり。長い時間をかけて身体の熱が抜けていく。心地のいい放出感に浸っている間も、笹嶺さんはずっと頭を撫でていてくれた。そのせいだろうか、射精はもう止まっている筈なのに思考がはっきりしない。強い恍惚感が身体から抜けない。 「いっちゃった......みたいだね。いっちゃった後って、けだるいし、頭とろんってしちゃうし、眠いの我慢できなくなっちゃうよね」 笹嶺さんがそう言うと、目の周りを暖かい空気が包み込む。それに誘われる形で目蓋は自然と重くなっていく。柔らかなまどろみに抗えなくなっていく。 「眠いの我慢するのも身体に良くないだろうし、このまま寝ちゃおっか。寝て起きたら今日のことは思い出せなくなっちゃうけ ど、気持ちよくなれる"おまじない"は君の心と身体が覚えててくれるから。だから、安心してまぶたを閉じてねー」 視界の肌色が少しずつ黒に変わっていく。自分が今起きているのか眠っているのか分からなくなる。笹嶺さんが俺の後頭部に手のひらをぽんと軽く置と、もとより消えかけていた意識はふっと弾けて、ふとももの間へと沈んでいった。 で? で? 昨日はどうだったよ?」 教室の扉をくぐり、席についてすぐのこと。 開口一番、挨拶よりも速く友人にそう聞かれる。 「それが......よく覚えてないんだけど、勉強教えてる途中で寝ちゃったみたいで......」 「はあ? よく覚えてない? 寝ちゃった?」 そう。昨日笹嶺さんの家にお邪魔してからの記憶はかなり曖昧で、俺自身あまりよく覚えていない。勉強を教えている途中で寝てしまったというのも、起きた後に笹嶺さんから聞いた話だった。なんでも、「すごく気持ちよさそうに寝てたよ? きっと疲れてたんだね」とのことで。そう言ってはにかむ彼女が、とてもとても愛らしかったことくらいしか思い出せない。正直申し訳ない事をしたと思う。笹嶺さんはもちろん、こいつにも。ああしてチャンスを作って貰ったのに、得たものが笑顔の記憶一つというのはあまりに不甲斐ない。 「なんだろ、疲れてたのかな......悪い、折角気を回してくれたのに......」 「かーっ、ほんとだよまったく。どうせ寝るなら膝枕くらいして貰えば良かったのになー」 「あのなあ。膝枕って、おま............っ!?」 どくっ...........♡ 膝枕。ひざまくら。 その言葉を聴いて、頭で理解してすぐのこと。強く鼓動が高鳴ると同時に、心の中が笹嶺さんでいっぱいになる。彼女のふとももが頬を包み込んでいく妄想が止まらない。感触さえ、柔らかさと体温でさえ鮮明に思い描く事が出来た。笹嶺さんに膝枕されたことなんてない筈なのに。喉の奥から唾液が湧き上がってくるのを感じる。脳に靄がかかっていく。 そうして、異様なくらいの多幸感に身体が包まれ始めて。 一秒。 二秒... 三秒...... 四秒経って、やっと。 すーっとそれらが引いていく。脈が正常になって、元の自分に戻っていく感覚。荒くなっていた呼吸を整え、大きく息を吐く。 「......おい? おーい? どした? 何かあった? もしかして割とマジで疲れてる感じ?」 そんな俺の姿を心配したのか、友人は目の前で手をひらひらと動かして見せる。今、俺の身体に何が起きたのかは自分でも分からない。何があったのかこっちが教えて欲しいくらい。けどそれよりも。これ以上こいつに気を遣わせたくない。その気持ちが勝ったらしかった。 「はぁっ......いや、大丈夫......」 かろうじてそう紡ぐと、友人は少しばかり眉をひそめて。 「えぇ......ほんとかよ......俺はもう席に戻るけど、体調悪かったら試験官やってる先生に言えよ? 保健室でも受けられるだろうし」 いかにも釈然としないといった顔をしつつも、自分の席の方へと歩いていく。なんとか撒けた。自分を心配してくれている友人に対して「実は女の子のふともものことを考えていたらこうなっちゃいました」とは、とてもじゃないけど言えない。 ......にしても。あの感情は、さっきの発作のようなあれは何だったのか。恋か。思春期なのか。多分違う。そういう甘酸っぱい類のものじゃなくて、何か灰色な欲が自分の中で渦を巻いているような気がする。昨日まではこんなこと一度も無かった筈なのに。なら一体昨日何があったのか。あの小さな部屋で、俺が眠っている間に。笹嶺さんに何かされたのか。そんなことを考え始めた時。 とすっ 右斜め前の席から聞こえた音が、思考を遮る。机に鞄を置く音。意識がそこに向く。釣られて視線も動いて、その先で。ゆらりと、二本のそれがたゆたう。むっちりしていて、すべすべで。キメが細かくて、真っ白で。造形美としか言いようのないそれが、俺を誘うように揺れ動いた。 少し上に視線を向ける。これまた悩ましげに波打つスカートの、そのチェックの数がいつもより明らかに少ない。危うささえ感じさせる丈の短さは、恐らく校則ギリギリのギリギリで。すぐ下に伸びる生肌の魅力をどこまでも際立たせていて。 気づけば、視線はその幸せ空間に囚われて、抜け出せなくなっており。視覚で感触を感じ取ってしまいそうなくらい、そこだけを見つめていて。 そして。不意に。 「ふふ。いつまで見てるのかなー?」 しゃん、と。宙から降り注いだ鈴の音ような声。その声を聴いて、やっとのことで。俺の視線は、危うい桃源郷から脱出することができた。けど。 「おはよ......♡」 抜け出した先で、また。細めた目から放たれるまなざしに、視線を絡め取られて。にっ、と弓なりに反った口元に、心をくすぐられて。どこからともなく漂う甘い香りが、嗅覚をさわさわと撫でて。鈴のような声の持ち主が、彼女だと気づいてしまって。俺を秒で虜にしてしまった二本のそれは、笹嶺さんのふとももであったと気づいてしまって。 それで―――― どくんっ♡♡♡ 「っ......ぁ......♡」 さっきより遥かに強い多幸感が、思考を埋め尽くす。沸き上がる幸せを抑えることができずに、くぐもった声を僅かに漏らしてしまう。それを聴いた笹嶺さんが、手を口に当てて笑う。ひどく愉しげな顔をしたまま、俺のそばに寄り添う。ラズベリーみたいな甘い香りが、ぐんと強くなる。 笹嶺さんはそのまま、俺の耳を舐めるかのように唇を近づけて。 「今日のテストが終わったら、ぜーんぶ教えたげるね......♡」 そう囁くと、自分の席へと戻って行く。 俺は、彼女の後姿から目が離せなくて。ひかがみからスカートの端までを、視線で何度も往復して。一往復する度に、呼吸の間隔が短くなって、甘い残り香が肺を満たしていって。馬鹿みたいに大きくなったそれが、机の下にくっつくんじゃないかって勢いで、下着を押し上げていて。 そんな状態でテストに集中なんて、出来る筈もなかった。 ・・・・・・ 「どうだった? 今回も良い点取れそ?」 放課後、空き教室。 笹嶺さんはまた口元に手を当てて笑うと、鈴のような声でそう聞いてくる。 その質問には答えるまでもなかった。今までで一番ひどい出来だった。まず間違いなく笹嶺さんには負けていると思う。 テスト中、俺の思考がやっと落ち着いたタイミングで、笹嶺さんは足を組み替えた。俺だけに肌が見えるような角度で、スカートの位置を直したり、小さく座り直したりした。果ては、シャーペンでふとももをなぞり上げたりもしてみせた。 それだけのことで、まとまり始めた思考は霧散してしまって。すぐに頭の中がふともものことでいっぱいになった。あのペンの代わりに、自分の指を這わせたら......とか。そんなことしか考えられなくなった。 「一体、俺に何をしたの......っ」 「うん、いいよ。教えたげるね。じゃあまずは、昨日のこと......思いだそっか」 笹嶺さんはそう言って、右手の中指と親指の腹をぴったりとくっつけると。 「これから、私が指を鳴らすと、君は昨日のことを全部思い出します。ほらっ」 「ちょ、何言っ――――」 ぱちんっ 俺が喋り終わる前に指を弾いて、小気味良い音を奏でた。それを聴いただけなのに、昨日の放課後の事を全て思い出す。今朝、あんなに頭をひねっても、何一つ思い出せなかったのに。 「あ......あ......」 同時に、あの快楽を思い出してしまう。 暖かくて柔らかくてむちむちのふとももに顔を包まれて、あやされるみたいに頭を撫でられながら、床にこすりつけて......そのまま、そのまま...... 「うんうん、うまくいったみたいだね。どうかな? あたまぽわぽわ~ってしたまま、きもちよ~くおしゃせーしちゃったこと、思い出せた?」 「あ、う......♡」 笹嶺さんの言葉に誘導されて、考えないようにしていたことを考えてしまう。骨盤が強く火照る。その熱に耐え切れなくなって、ペニスを小さく跳ねさせてしまう。下着と擦れた先端が甘ったるく疼く。それがバレてしまったのか、彼女は目を細めた。 「あ~あ......♡ 君は頑張って思い出さないようにしてたのに、おちんちんが思い出しちゃったね......♡」 隆起したその先端を、ほっそりした人差し指が「とんとんとん......♪」と叩く。スラックス越しの軽い刺激で、甘い疼きが倍に膨れ上がって、どんどん切なくなってくる。その指をなんとか振り払って、声を絞り出す。 「なんでっ、こんなことっ......」 それを聴いた笹嶺さんは、「待ってました」とでも言わんばかりに、一層愉しげに笑って。わざとらしく、ぺろりと舌なめずりまでしてみせて、それから。 「それはねぇ......♡♡ 君のことが好きだから......だよ♡♡♡」 耳にキスでもしそうなくらいの距離で、そう囁いた。 蒸気を多分に含んだ吐息が、たっぷりと耳にかかる。どくんと鼓動が高鳴る。身体の芯に、ぼうっ、と火が灯る感覚。 ......違う。違う違う違う。これは嘘だ。 本当に、俺の事が好きなら。俺の成績が下がるような、俺に嫌われるようなことはしない筈じゃないか。 「うんうんうん。嘘だーって、思っちゃうよね。顔に書いてある。でも嘘じゃないの。私って欲張りだから。学年一位も欲しいけど、君のことも欲しいの......♡」 「そんなの、信じられるわけ......!」 「ふふふ、そうだよね。信じられないよね。私だってまだ信じられないもん。私、元々君のこと大っ嫌いだったしね」 「え......」 「わかんないかなぁ。考えてみてよ。それまでの人生で『1』って書いてあったところに、『2』って書いてあるんだよ? あの時はびっくりしちゃったよ。それで、私より頭がいい男の子って、どんな子なんだろう......って見に行ってみれば、君は誰にもいばったりなんかしないで、飄々ひょうひょうとしてるし。それを見てたら、なんかすっごくイライラしちゃってさ」 笹嶺さんの言うことは、確かに辻褄が合っていた。今から一年半くらい前、まだ俺と彼女が別のクラスだった頃。この学校に入学して初めてのテストで一位を取って、友人に茶化されていた時。教室の外から俺を見つめる彼女と、目が合ったのを覚えてる。 「......でも、それからね。毎日君のことばっかり考えるようになっちゃったんだ。私が一位を取った時、君はどんな顔をするのかな、とか。私に負けた君が、悔しがるところを見てみたいなー、とか。そういうことを、何度も、ずーっと考えるようになっちゃってた。そんなことを続けてたら、いつの間にか好きになってたんだよね。私よりも頭がいい君の、弱くて可愛いところとか、なさけなーいところとか......い~っぱい見てみたいなー、知りたいなーって、思うようになってたんだ......♡」 「そんな、そんなの......っ」 「変かな? ふふ、変だよね。おかしいよね。私もそう思う。だからさ、責任取ってよ。私をおかしくさせちゃった責任......♡♡♡」 すべすべした指が、俺の頬にからみつく。とろんとした瞳が、俺の目を覗き込む。その視線から逃げられない。脱け出せない。魅入られそうになってしまう。その数拍の隙を、彼女が見逃してくれる筈もなくて。 「んー......♡」 ゆっくりと唇が重なる。ぷにぷにのそれが押し付けられる。あの熟れたラズベリーみたいな匂いが俺を満たしていく。直接肺に注がれてるみたいな感じ。 「ん......っ!」 長いキスが続く。頬に絡んでいた指が、首の裏に回って、背中の方に下りてくる。ぎゅっと抱き寄せられて、胸と胸がくっつく。カーディガン越しでも分かるくらいに、笹嶺さんの身体は熱くなってた。 「ふはぁ......♡ 心臓、ばっくんばっくんしてるね......♡ うれしいなぁ......♡♡ 君もどきどきしてるんだぁ......♡♡♡」 唇が離れて行く。新鮮な空気が戻ってくる。でも余韻が消えない。濡れた唇から目が離せない。笹嶺さんに移された熱が抜けない。うっとりするくらいの恍惚感に酔ってしまう。身体にうまく力が入らない。彼女に抱き寄せられてないと、倒れてしまいそうだった。 「キス......そんなによかった? それじゃあ君に、おまじないをかけます。次にキスをすると、君と私は両想いになります......ん♡」 「まっ......だ......め......んんぅ......♡」 また唇が重ねられる。甘ったるいキスが心をいっぱいにする。笹嶺さんの「好き」が身体に流し込まれて、自分のものになっていくような感覚。それが心地よくて拒めない。後頭部をゆったりと撫でられる。柔い手のひらが、脳に好意を塗りたくる。定着して離れなくなっていく。 「ん......ふぅ......♡ おめめ、とろんってしてきたね......♡ 私のこと好きになっちゃうの、やめられないね......♡♡♡」 「うぁ......そんな、こと......っ♡」 「そんなこと、あるよ......♡ そもそもね。私のおまじないは、ほんとに嫌われてる人には効かないの。1を100にはできても、0を1にはできないんだよ。だからね。元々私のことが好きな人だけが、かかっちゃうんだよ......♡♡♡」 俺の右手首を、笹嶺さんの左手が掴む。スカートの下からその内側に入り込んで、手のひらがふとももの付け根に押し付けられた。手の中心から指先へと、じんわりと熱が伝わっていく。指の一本一本が、柔らかい肉に沈む。甘い感触に包まれる。指に肉感が馴染んでいくような感覚。 「ほら、君って前から私のふともも好きだったもんね......♡ 授業中とか、たまーにやらしー目で見てたこと、知ってるんだよー?」 耳元でぽそぽそと囁きながらも、俺の手首を離さない。 耳が幸せ。脳が幸せ。手のひらが幸せ。指が幸せ。 幸せでだめになる。だめになりたいと思ってしまう。だめなのに。 「これからはさ、このふとももを君の好きにしていいんだよ......♡ ひとりじめしていい、君専用のふともも......♡ だから......ほら♡ 指のあと、い~っぱいつけちゃおう?♡♡♡」 弾みをつけてもう一度。むぎゅう、と食い込んじゃいそうなくらいの力で押し付けられる。俺の指の形に合わせて、むちむちの肉がいやらしく歪む。それだけで、痛いくらいにペニスが勃起する。ふとももと笹嶺さんのこと以外、どんどん考えられなくなっていく。 「私のふともも、もっと好きになって......♡ もっとおててに覚えさせて♡ ペンを持つたびに、私のふとももを思い出して♡♡ ひとりでする時に、『この手であのふとももを触ったんだー』って、思い出すようになって♡♡♡」 付け根から少しずらされて、内ももの方を触らされる。もう片方のふとももが、俺の手を挟む。ひらだけじゃなくて甲も幸せにされる。倍幸せになる。倍気持ちよくなる。性欲が倍に膨らむ。倍の熱に手が熔かされる。倍の心地よさに浸っているうちに、ふとももとふとももが擦り合わせられる。なめらかな肌が俺の手をもみくちゃにする。一度擦り合うたびに全てが倍になって、ペニスから濃いカウパーがどくりと溢れ出す。竿が下着の中で思い切り跳ね上がる。 「あ、ふふふふふ......♡ そうだよね。おちんちんも、私のふとももがだいすきなんだもんね......♡ おててばっかりずるいよね、君も気持ちよくなりたいよね......♡ ふとももの間で、どぷどぷどぷー♡♡って、したくなっちゃったんだよね......♡♡♡」 「ひ......あっ♡♡♡」 むちむちのふとももが、ペニスの先端を勿体ぶるように舐め上げる。我慢できなくて、情けない声が漏れる。スラックスの表面に、じわぁっと染みが広がっていく。一気に射精感が強くなる。出したくて出したくてたまらなくなってくる...... 「いいよお♡♡♡ ほらおちんちんさん、でておいで~......♡♡♡」 笹嶺さんは、スラックスのジッパーを優しく下ろすと、下着をそっと脱がしてくる。全然抵抗できなかった。期待と射精欲と笹嶺さんとふとももが、俺の脳を支配していて、それで。 「それじゃ......ふともものなかで、ぬくぬくしましょーねー......♡♡♡」 ぬぷぅ......っ♡♡♡ ぴっちりと閉じたふとももに、ゆっくりとペニスが飲み込まれていく。一番敏感な部分が、すべすべの肉を掻き分けていく。その感触がたまらなかった。このとろけそうな快感の逃がし場を求めて、笹嶺さんの肩にしがみつく。けれど、指先が震えて力が入らない。その代わりに、悲鳴みたいな声が、口から勝手に零れていく。 「これっ......これぇ......っ♡♡ だ、め.......だめに、なっちゃっ.....♡♡♡」 「いいんだよ、だめになっても......♡ だって、君をだめにする為にやってるんだから......♡♡ だめだめのどろどろになるところ、いーっぱい見せてね......♡♡♡」 笹嶺さんのふとももがまったりと動く。カウパーに濡れ始めた肌を、ペニスがぬるんと滑る。腰の奥で、精液がちゃぷんと波打つ。けれど動きが遅いせいで、ぎりぎり射精に届かない。波が引いて落ち着いてくるタイミングで、またふとももが動く。射精直前の甘く切ない快楽が、どこまでも引き伸ばされていく。思考が射精欲でぐずぐずになっていく。 「ね......知ってる? 男の子ってね。お射精のちょっと前が、いっちばん無防備なんだよ......♡ 頭も心も空っぽで、何を言われても素直に受け入れちゃうの......♡ だからね。君は今、おまじないにと~ってもかかりやすくなっちゃってるんだよ......♡♡」 ぐずぐずになった頭を、あやすみたいにして撫でれられる。脳に響く笹嶺さんの声を、手のひらがさらに広げていくような感じ。一度撫でられるたび、意識が真っ白にとけていく。 「ふふ。空っぽで、真っ白になった君に、おまじない......かけていくね。あなたはこれから、私のふとももで射精します。我慢はできません。私が10から数字を数えて、それが0になったら、必ずいってしまいます。それじゃあ、数えるよ......」 「じゅう」 「私のふとももで射精すると、おちんちんが私のふとももを覚えます。忘れられなくなってしまいます」 「きゅう」 「私のふとももで射精すると、ひとりでする時に、わたしのふとももを必ず思い出すようになります」 「はち」 「もしかしたら、他のことを考えながら、ひとりですることもあるかもしれません」 「なな」 「そういう時でも、射精する瞬間は、私のふともものことであたまがいっぱいになります」 「ろく」 「それが何回か続くと、ひとりでするだけでは満足できなくなってきます」 「ご」 「私のふとももがほしくてほしくてたまらなくなります。普段から、私のふともものことばっかり考えるようになってしまいます」 「よん」 「はい、おまじないおしまい。どうかな? そろそろいきそうになってきた~?」 「さん」 「あ、ふふ......♡♡ おちんちんでお返事してる......♡♡♡ いいよお♡♡♡ た~っぷりおもらし、しましょーねー......♡♡♡」 「に」 「ほら、熱いのがおちんちんのすぐそこまでのぼってきてる......♡♡♡ ううん。もう、ちょっと出ちゃってる......♡♡♡ もう止められないよ......♡♡♡♡♡」 「いち」 「ほら、くるよ......♡ きちゃうきちゃうきちゃうきちゃう......♡♡♡ あたまのなかは、私のことでいっぱい......♡♡♡」 「ぜ~ろ......♡♡♡ ほらっ、いっちゃえっ......♡♡♡♡♡」 最後のカウントと同時に、笹嶺さんは俺の背中に線を引く。ワイシャツ越しのそこを、ほっそりとした指が流れるようにくすぐった。その不意打ちに負けた俺の身体は、大きく反り返る。反動でぺニスが根元から勢い良く跳ねて、むちむちでぬるぬるのふとももに舐め上げられた。 「――ひぁ―――――♡♡♡♡♡」 ひくん...........どぷっ......♡♡♡ どぷどぷどぷっっっ♡♡♡♡ 「ふふ、イってるイってる......♡ でも、もっと出すの......♡ 熱くて重くてこってりしたの......ぜ~んぶ出して......♡♡♡ 私のふとももに、君のせーえきなじませて......♡♡♡♡ ふとももにおしゃせーするの、やみつきになるまでやめちゃだ~め......♡♡♡♡ ん、ぁ~......♡♡♡♡♡♡」 笹嶺さんが俺の耳にしゃぶりつく。吐息混じりの命令が、脳に直接注がれる。声と言葉がべっとり染み付いて取れなくなる。びくんびくんと痙攣しながら射精する竿を、肉感たっぷりのふとももが捕えて、互い違いにもみくちゃにする。 「んはぁっ......♡♡ すき......♡♡♡ すきだよぉ......♡♡♡ 私のふとももに負けて、私に溺れて、私のことしか考えられなくなってる君がだいすき......♡♡♡ だから、またイくとこ見せて......♡♡♡ もうイってても、またイって......♡ イきながらもう一回イって......♡♡ ほらっ、イけイけイけ♡♡♡♡♡」 「やっ♡♡♡ ひっ♡♡♡♡ まだ、だめ、ぁ――――――♡♡♡♡♡♡♡」 どくっ......♡♡ どぷ―......................っ♡♡♡♡♡ 前の射精が終わってないのに、次の射精が始まる。深すぎる絶頂から戻ってくることができない。一瞬味わっただけでも忘れられなくなってしまいそうな快楽に、ずうっと浸り続ける。笹嶺さんとふとももが、脳も身体もだめにしていく。それに抗えない。だめにされる感覚を、だめにされる幸せを覚えてしまう。 とく......♡♡♡ とく......んっ............♡ 射精が止まっても、余韻は抜けなかった。強い恍惚感が俺を支配してる。どろどろになった頭をやわやわと撫でられると、ため息が出てしまう。 「......はい、射精おつかれさま。いっぱいでたね。まだけだるいよね。しばらく私にもたれかかってよっか」 そう言われて、笹嶺さんの身体から離れようとしたけど出来なかった。ぎゅっと抱き寄せられて、押さえ込まれてしまう。今の俺じゃ、力ですら彼女に敵わなかった。 「ふふ。全身ふにゃふにゃの、よわよわさんだ......♡ 君が疲れきって寝ちゃうまで、ずーっと抱き締めてててあげる。だからこのまま、寝ちゃおうね......」 笹嶺さんの言葉に身体が引っ張られて、眠気がぐんと強くなる。目蓋がずーんと重くなる。 「それじゃあ、今から私が3つ数えると、君の目蓋は閉じてしまいます。さー......ん......にー......い......いー......ちっ......」 意識を保てたのはそこまでだった。あのラズベリーみたいな甘い匂いに包まれながら、視界が黒にとけていって。いつしか、ふっ......と途切れてしまった。 ・・・・・・ 「......古文92点、現文95点......これで最後かな? 合計で10点差。うんうん、惜しかったねー。次はも~っと勉強しないとね?」 あれから一週間。テストの結果は、当たり前のように俺の負けだった。「惜しかった」と言う割に、彼女の声はひどく嬉しげで。にんまりと目を細めていて。 「ああ、でも......♡ 勉強するのとふとももするの、君はどっちが大事なんだっけ? 君が大事だと思う方を、選ぼうね......♡」 笹嶺さんが、ふとももをぽんぽんと叩いて。肌色の官能に目が吸い寄せられて。頭の中は、ずっとそのことでいっぱいで。それで、もう、俺は。 今日もまた、そこに。大好きな彼女のふとももの間に、顔を滑り込ませた。 看守 「ふー。終わったあ」 誰もいない事務室の木椅子で大きく伸びをする。 右手に伸びる影も僕の動きに合わせてぐいっと大きくなる。影は部屋で唯一の光源である卓上ランプの炎が揺らめくのにあわせて微かに揺れている。 退勤時間を大幅に遅らせて書いた渾身の報告書を上長の机に放り投げ、帰り支度をする。 本当なら数時間前の交代時間でさっさと帰ることができたはずなのに……。 「ったく、なんで俺が錠前の修繕手配なんてやらなきゃいけねえんだよ……」 たまたま目に入った通用口の錠前が破損していた。みつけた手前ほっておくわけにもいかず先輩看守に報告し、返ってきた言葉は「みつけたなら鍵屋の手配よろしく」だけだった。 馬鹿正直に報告した結果として錠前屋を手配し、修理させ、そして今までこの件についての報告書を書いていたのだ。 「もう次からは見て見ぬ振りしてやろっと」 そんな悪態をつきながらランプの灯りを消し、事務室を出る。 廊下は天井近い高さに掲げられた松明で照らされているが人の気配はない。 もうまもなく日付が変わる時間。この時間はこの監獄には地下に広がる牢獄の囚人と看守、それから通用口の守衛、敷地内の別棟で待機する警備兵たちしかいない。 (というか今思えば鍵の手配も守衛がやっとけばよかっただろ…!) やはりあの先輩の判断には納得いかない。 どうもあの先輩は最近おかしい。 日中の職務中はどこか上の空で、その割にやたら地下牢の夜勤に名乗りをあげている。 推測でしかないがあのラウラとかいう盗賊団の親玉に見惚れてしまっているのだろうか。 まあ見惚れたか否かはどうでもいいが、仕事はしっかりしてほしい。 「はあ……」 我々の仕事をなんだと思っているんだ。 ついこのあいだまで真面目だった人なのに……情けなくてため息が出る。 あの女盗賊ラウラが捕まってしばらく経ったが、市中の窃盗騒ぎはなんら収まっていない。 現場の状況から明らかにラウラが率いていた窃盗団の手口のはずだが、肝心のラウラは牢屋の中だ。 ラウラが特殊能力を持っているという話は聞かない、となるとやはり別のリーダーがいるのだろうか。 (もしくは…) 自分の腰に巻かれたベルト、そこに紐で結びつけられた小さな石に目を落とす。 伝心石。近年発見された魔法石で、握りながら任意の相手を頭に思い浮かべることで、意思を伝えることができる。 相手と直接対面したことがあり、且つお互い伝心石を持っていなければならないという制約はあるが、魔術の心得がなくても離れた人間とコミュニケーションを取れる有益なアイテムだ。 まだ産出量も極めて少なく、悪用の恐れもあることから政府は厳密に管理しており、伝心石は一部の政府高官や王族、僕らのような治安維持に関わる人間にのみ携帯が許されている。 盗賊団がこれを活用している可能性。 ありえないと否定はできないが、そもそも囚人のラウラはそんなもの携帯できるはずがない。 いずれにせよやはりあの女を捕まえただけじゃダメってことだ……。 ドン! 「うおっ」 ???「あっ!」 曲がり角、突然胸元に強い衝撃が加わる。 出会い頭に何者とぶつかってしまったようだ。 どうやら相手はその拍子で倒れてしまったらしい。 こんな時間だ。きっと自分のように残っていた人間だろう、と考えを巡らしながら倒れた相手に声をかける。 「す、すみませ……!?」 目の前の床には明るい髪色をしたショートカットの女性が倒れていた。 女性「いてて…」 頭を押さえながら女性が身体を起こす。 石造の無機質な建物の中に似つかわしくない可愛らしい女性。だが明らかに不審であり、こちらにも緊張がはしる。 「おい、動くなよ」 警棒を構えて女性と距離を取る。 女性「あ、待って!待ってください!あやしい者じゃなくて…!」 怪しくない人間はそんなこと言わない。 「いいからそのまま手をあげるんだ」 女性「あー…わかりました…」 女性「誰もいないって話だったのに…ボソッ」 女性は何か聞こえない声で呟きながらも、指示どおり両手を天に突き出す。 背丈はさほど大きくなく、見た目は幼い。10代後半、下手すれば前半と言われても違和感のない、目の大きな色白の童顔だ。 しかし、顔の幼さとは相反して上半身は黒のチューブトップのみ、下はホットパンツと露出の多い服装をしている。 何より身体のメリハリが効いてて、胸と尻、腰のくびれは大人も顔負けなスタイルだ。 特に胸、まさに爆乳という言葉がふさわしいだろう。乳房ひとつが女性の顔よりも大きい。 窮屈だと言わんばかりに衣服を押し上げており、正中線上には見事な谷間がみえる。 女性「あの、いつまでこうしてれば?」 女性の声にハッと我に帰る。煽情的な身体に目を奪われてしまっていたようだ。 「あ、ああ。じゃあそのまま連行する。ついてこい」 まさか見惚れていたなんて言えない。なんとか取り繕って後をついてくるよう促す。 女性「え、もう行くんですか?」 「は?」 予想外の言葉に思わず聞き返してしまう。 女性「こういう時って普通やりますよね?ボディチェック」 そのとおり、こういう時まずは凶器などを持っていないかチェックする必要がある。 「う、うるさい、そんなことはお前がどうこう言うことじゃないだろ」 女性「あの、ちゃんとリザって名前があるので、そちらで呼んでください」 リザ「ほら、私が凶器を隠してるかもしれないし…♡しっかり確認したほうがいいと思いますけど♡」 女性、いやリザは馬鹿にするような口調で続ける。 リザ「それとも触れない理由がなにかあるんですかー?くすくす♡」 「な、なんだよ急に…」 こいつ、こっちが女性に不慣れだからって馬鹿にしやがって…! 「わかったよ。やればいいんだろ…!」 どうもこういう女性は苦手だ。 たしかに自分に女性経験がほとんどないことは事実だが…。 こんなことなら多少は酒場にでも出入りすべきだったな…。 そんなことを後悔していても仕方ないので、ボディチェックをはじめる。 まずはゆっくり一回転するように命令する。 リザは言われたとおりにその場でゆっくりと動く。 首筋、脇、そして乳首こそ見えないが柔らかそうな乳房の上半分が丸見えで、肉体美をこれでもかというくらい見せつけている。 手を頭上で組むような姿は酒場の踊り子たちがみせる妖艶なポーズそのものだ。 リザ「どうしたんですか♡もう一周しましたから、はやく触ってください♡」 たぷん♡たぷん♡ リザがその場で身体を揺らし、それに合わせて双乳がゆさゆさと踊りだす。 「わかってる…いま調べるから…!」 両手をおそるおそるリザの身体へ近づけていく。 衣服に下半分だけ隠れた白く大きな二つの乳房にいよいよ触れる…! リザ「もう♡おそいです♡」 不意に両手を掴まれ、引っ張られる。 もにゅ♡ 「!!」 引っ張られた両手はリザの胸を下から持ち上げるように支えてしまっている。 手に広がる弾力のある魅惑の質感。 ずっしりとした重量とぬくもり。 男性を虜にする心地よさが両手から脳へ伝わる。 リザ「あの、わかってるんですよ♡お兄さんが見てたの♡」 「見てたって…?」 リザ「とぼけないでください♡男の人の視線、結構わかるものなんですよ?」 リザ「兄さんがわたしの胸をずっと見てたのバレバレというか…」 リザ「おっぱいから目を離せなくなってるし♡」 ふよん♡ふよん♡ リザ「それでいて触るとなると尻込み♡」 リザ「お兄さんもしかして、童貞?くすくす♡」 「う、うるさい!からかうんじゃない!」 相手の胸に手を伸ばしたままそんなこと言ってもまるで意味のないことだった。 リザ「くすくす♡顔真っ赤ですよ。ほらもっとよく調べましょ…♡」 リザ「ほら、谷間も♡いろいろ隠せそうじゃないですか?こうやって…♡」 リザが手を胸の間に誘導する。深い谷間に両手を突っ込み、谷間をこじ開けるように動かす。 重量感のある胸肉が指に押し広げられたかと思えば、すぐに指を包み込んでしまう。 リザ「ちゃんとこういうあやしいところも捜索しないと…♡」 むにゅ♡むにゅ♡ 僕の両手を胸に挟んだまま、外側から自分の両手で圧をかけてくる。特大の胸が僕の手のひらを完全に覆いつくす。 「う、うお…!」 女性経験のない自分にとって刺激が強すぎる。 リザ「どうしたんですか?顔が真っ赤ですよ♡」 リザ「分かりますよ、おっぱい気持ち良くてもっともっと触りたいんですよね♡」 リザ「お兄さんがよければ、もっと気持ちいいことしてあげてもいいんですよ♡」 そう言うと僕の片手を谷間から解放し、そのまま口に近づける。 リザ「お口に不審なものがないか、チェックしないとダメですよね…ぁむ♡」 谷間の感触が残ったままの指が口内に放り込まれる。 リザ「じゅる…んむ♡あむ…ぇろれろれろ♡」 人差し指を丁寧に舐めしゃぶる。 強く吸い付いたと思えば指先に舌をチロチロと這わせ、頬の内側に擦り付ける。 童顔に似つかわしくない卑猥な技だった。 (もしこれが指じゃなくて…!) そう思うだけで股間が更に熱を帯びる。 リザ「んふふ……♡どうされましたか?」 リザ「仕事中なのに、我慢できなくなってきましたか…♡」 仕事中、そうだ僕はこいつを捕まえて…! 「や、やめろ!!」 これ以上はやばいというタイミング、仕事という言葉にハッとして声を張り上げる。 リザに触れていた手指をすぐさまこちらに戻す。 「はあ…!はあ…!」 リザ「わー、こわいです〜♪」 くすくすと笑いながらからかうようにおどけている。 あと少しでまずいことになってた。 「ボ、ボディチェックはもういい!手を後ろにまわして」 リザは命令に従って両手首を腰のあたりで合わせる。 僕は携帯していた手錠でその両手を繋ぎ止める。 「あらら、捕まっちゃいましたー」 「…ついてこい」 とりあえずすぐそばの取調室に入り、伝心石で守衛の奴らを呼ぼう。 暗い廊下を突き当たりまで進み、取調室の前にたどり着いた。 鉄扉を開くために一度止まる。 むにゅん♡ 「な…!」 急に背中を襲った柔らかな感触に思わず振り返ると、至近距離でリザが笑っていた。 むにゅ♡ リザ「あん♡ごめんなさい♡急に止まるからぶつかってしまいました♡」 悪びれる様子もない。リザがしなだれかかることによって胸が背中に押し付けられ、魅惑の感触が広がる。 ふよん♡ふよん♡ 服越しに当たる乳房の柔らかさと伝わってくる体温から下着をつけていないことがわかる。 「い、いいからはやく離れろ…!」 動揺を隠すようにリザに入室するよう命令する。 リザ「はぁーい♡」 取調室に入り、扉に鍵をかけてリザを備え付けの丸椅子に座らせる。 ひとまず簡単な聴取だけでもしておこう。 「名前は?」 リザ「リザ・クラウゼ」 「年齢は」 リザ「黙秘しまーす」 「おい」 リザ「え?黙秘は当然の権利ですよね?くすくす♡まあお兄さんよりは若いと思いますよ♡」 「…もういい、仕事は?」 リザ「黙秘しまーす」 「ここへ来た目的は?」 リザ「黙秘しまーす」 「なめやがって…!」 もはやまともに答えた名前すら信憑性が感じられない。 リザ「あ、取調べでそういうこと言っちゃいけないんですよ?」 「ぐぬぬ」 この調子では拉致が開かない。 さっさと守衛に連絡して引き継いでもらおう。 腰に下げていた伝心石を取り出し、当番へ連絡を取るため意識を集中させる。 リザ「あ、それ伝心石ですよね!みせてください!」 手に持つ石が見えたのだろう、急に見せるようねだってくる。 「うるさい、少し静かに…」 リザ「見せてくれたら…♡」 リザの艶っぽい声色に一瞬反応して言葉を止めてしまう。 リザ「ふふ♡反応しちゃいましたね♡伝心石、ちょっと見せてくれたら、私の身体好きにしていいんですよ♡」 さっき廊下でみせた蠱惑的な一面。椅子に座ったまま、端正な顔が上目使いでこちらを見つめてくる。 「な、なに言ってるんだ…?」 リザ「なにってそのままですよ♡」 リザ「その石で、他の方にご連絡しようとしてたんですよね♡」 リザ「でも連絡する前に、ちょっとわたしにみせてくれたらなんでもいうこと聞きますよ♡」 リザ「さっきからわたしのこといやらしい目で見てるのバレバレ♡」 リザ「ムラムラしてるんですよね♡お顔に書いてありますよ♡」 「…………。」 だめだ。絶対罠に決まっている。 リザ「たしかに不審者を捕まえたんだからすぐに連絡すべき♡」 リザ「でも本当は、ムラムラすっきりさせたいんじゃないですか♡」 リザ「そのムラムラの原因になったわたしの身体で♡」 リザ「わたしが責任取りますよ♡ほら、すっきりしましょ♡」 リザの艶めかしい唇が開き、淫猥な舌がだらりと垂れる。 リザ「さっきは指でしたけど♡」 リザ「今度は…ふふ♡」 リザ「舐めてほしいんですよね♡」 リザ「お・ち・ん・ち・ん♡」 リザ「この口に入れてください♡」 リザ「さっきの指よりももっともっと気持ち良くして差し上げます♡」 舌をれろれろ動かして誘惑してくる。 リザ「くすくす、目が釘付け♡」 リザ「どうして迷うんですか?」 「うう…!」 リザ「一回だけ♡すっきりしてからお仲間呼びましょ♡」 リザ「そうじゃないと身柄の引き継ぎに支障が出ちゃいます♡」 リザ「ムラムラしっぱなしだと悪い女に騙されちゃうかも♡」 たしかに、このまま溜めていたらこの女に誘惑されっぱなしだ。 一度抜いておいたほうが…。 リザ「さっき廊下でからかったお詫び♡わたしの身体、好きに使っていいですよ♡」 リザ「私の身体でエッチな気持ちになったんだから、私で処理したほうがいいに決まってますよ♡」 「じゃ、じゃあ…」 リザ「うん♡伝心石は私に預けておいて♡」 リザ「万が一エッチな声が他の人に伝わったら大変ですから♡」 「あ、ああ…」 言われるがまま、伝心石をリザに渡す。 リザは受け取った伝心石をしばらく見つめた後、すぐそばの机に置く。 リザ「これで、なにかトラブルがあってもすぐにお兄さんも伝心石拾えますよね♡」 たしかに。これなら何か不測の事態が起きても大丈夫だろう。 「わかった。わかったから…!」 僕は早くもズボンを下ろし始める。 下着も脱ぎ、下半身丸出しの姿になった。 廊下でリザの胸を触って以来、既にペニスは完全に硬直していた。 リザ「くすくす♡そんなガッつかないでください♡逃げたりしませんから♡」 リザ「どこで気持ちよくなりたいですか…?」 そんなの決まってる。 「くち!口で舐めて…!」 リザ「くすくす♡分かりました♡とろとろに舐められたくなっちゃったんですね♡」 リザ「それじゃ♡んぁ…ここに入れてください♡」 リザが椅子から腰をあげ、床に両膝をついて口を大きく開く。 「…………」 リザの前に仁王立ちになり恐る恐るペニスを差し出す。 先っぽが口に触れるか触れないかの位置にくる…! リザ「あむ♡」 それまでじっと待っていたリザが急に動き、亀頭をパクリとくわえた。 「んあ!!」 いつ刺激が訪れるか、待ち構えていたペニスが快感に包まれる。 「お、おお…!」 急な亀頭への刺激に両脚が震える。 リザ「ん…♡じゅ♡じゅううううう♡」 「んおおおお!!!」 咥えたまままるでストローで飲み物を飲み干すかのように吸引される。柔らかくプリプリした唇が亀頭に吸い付く。 リザ「んじゅうううう♡れる♡れるれろ♡」 唇で吸い付いたまま、今度は口内で舌に蹂躙される。かり首や亀頭の平たい部分まで素早くねっとりと舌が這い回る。 「あっそれやば…!」 激しい亀頭責めに悶え顔を歪ませると、リザがニヤニヤとした目でこちらを見てくる。 僕が感じる姿を愉しんでいるようだ。 「じゅる♡れろ♡じゅるるる♡」 「じゅぽ♡じゅるるるる♡」 そのまましばらく口内亀頭責めが続けられる。 耐えがたい快感がペニスを襲い、僕は喘ぎ声を出し続けている。 凄まじく気持ちいい。気持ちいいのだが…。 リザ「んんんんん♡ちゅぽん♡……あれ、どうされましたか?」 一際強く吸い付いてからペニスを解放したあと、リザがこちらを見上げてくる。 リザ「気持ちよくなかったですか?おしまいにしますか?」 「ちがっ…!そうじゃなくて…!」 気持ちいいのだが、先端だけへの刺激では到底射精へたどり着けない。 これでは亀頭を襲う快感だけが蓄積されるだけで、もはや生殺しでしかない。 リザ「あは♡わかってますよ♡」 股間をいきり立たせたままもじもじしている僕を見てニヤニヤ笑っている。 リザ「ちゃーんとおちんちんをぜんぶ♡しっかりじゅぽじゅぽしてほしいんですよね♡」 その言葉に僕は首を縦に何度も振る。もうリザの口の中で射精することしか考えられない。 リザ「私もぜひそうさせていただきたいんですが…両手がこの状態ですとやりにくくて…」 リザが後ろ手に手錠を掛けられた両手を見る。 リザ「もし、これを外してくれたら♡」 リザ「本気、出しちゃうんだけどなあ♡」 でもそれは…! リザ「ふふ、いいじゃないですか♡」 リザ「手が自由になったところで丸腰の女になにができるんですか?」 リザ「それより両手でおちんちん支えられて♡たっぷりじゅぽじゅぽ♡されちゃいましょ♡」 「わかった!外す!外すから…!」 散々亀頭を嬲られたいま、断る精神力は持ち合わせていなかった。 脱ぎ捨てたズボンから急いで鍵を取り出し、手錠を外してやる。 リザ「ふうー。短時間とはいえ、鬱陶しかったからよかったですー」 座ったままの姿勢でのびをして、すぐに元の姿勢に戻った。 リザ「それじゃ♡本気で気持ちよくしてあげますね♡」 片方の手で根本を持ち、ペニスを口に対してまっすぐに向ける。 口の中には唾液が溜め込まれているようで、舌舐めずりをすると唇がいやらしく照りかがやく。 「はやく…!舐めて…!」 リザの勿体ぶるような仕草、もう欲情が抑えきれない。 リザ「それじゃ改めて、いただきまーす…ぁむ♡」 ずぷぷ♡ リザ「んふ♡おふまへくわえへはひあへまふ♡(奥まで咥えて差し上げます)」 「んあ!!」 待ち焦がれたペニス全体への快感。ねっとりとした口内の肉壁にペニスが晒される。 リザ「じゅるる♡ん♡じゅぽ♡じゅぽ♡じゅぽ♡じゅぽ♡じゅぽ♡」 「あ!急に!あっ!あっ!あっ!」 リザは吸い付いたまま一定の速度で頭を前後に動かしはじめる。 さっきまでの焦ったい責めと異なる射精を要求する動き。 こしょ♡こしょこしょ♡こしょこしょ♡ 空いている手で睾丸がくすぐられる。ペニスから垂れた唾液と我慢汁が潤滑油となり、甘い刺激を増幅させる。 「それだめ!たまたまこしょこしょ好き…!」 こしょこしょこしょこしょ♡こしょこしょ♡もにゅもにゅ♡こしょこしょ♡こしょこしょ♡もにゅ♡ 感じる僕を見てリザの指捌きが激しくなる。 リザ「……んぱぁ♡もう限界って感じですね♡」 一旦ペニスから口を離し、手で優しくシゴきながら声をかけてくる。 リザ「このままタマタマもいっぱいマッサージしながらおちんちんしゃぶってあげますから、いつでも好きなときに出してください♡」 「う…うん」 リザ「ふふ、ちょっと前まであれだけ真面目な顔してたのに♡」 リザ「いまは射精することしか考えられてないんですね♡」 「う、うう…!」 リザ「かわいいです♡満足するまでいっぱい気持ちよくしてあげます♡」 「は、はい……♡」 ほんとはすぐ牢屋に入れなきゃいけないけど、仕方ない…♡ ここはひとまずいっぱい舐めてもらおう…♡ リザ「それじゃ♡ノンストップでいきますね♡」 リザ「イクときはちゃんと声出してください♡」 「わかった♡わかったから…♡」 リザ「はいはい♡それじゃ……じゅうう♡」 「あおお♡」 またもやペニスが妖艶な口に食べられる。 じゅぽ♡じゅぽ♡じゅぽ♡じゅぽ♡じゅぽ♡ さっきよりも早いリズムでペニスが唇に扱かれる。 ペニスの細胞ひとつひとつに唇の柔らかさを覚えさせるような吸いつきは変わらない。 「んむ♡じゅる♡れろれろれろ♡じゅぽ♡」 その一方で口内では舌が乱雑に動き亀頭を蹂躙する。 こしょこしょ♡こしょこしょ♡ 睾丸への愛撫も激しさを増す。 「ああ♡これやばい♡すごい♡」 ペニスと睾丸で受ける魔性のテクニック。女性経験の少ない僕が耐えるなんてどだい無理な話だ。 僕の顔を見て絶頂が近づいているのを悟ったのか、リザの口淫のスピードが一段と速くなる。 「あ♡無理♡そんなはげしいのだめ♡」 あまりの気持ちよさに腰がくの字に曲がっても彼女はペニスを離してくれない。 「ああ♡無理♡いぐ♡でる♡」 否応なしに注がれる快楽に身体が屈する。尻の奥あたりに力が入り、ペニスが大きく膨らむ。 リザ「ぢゅうううううう♡♡♡」 そのタイミングを知っていたかのように、リザはとどめと言わんばかりに根元まで咥え込み、これまで一番の吸引を行ったとき、ぼくは限界を迎えた。 「あ♡ああああああああああ♡」 びゅる!!びゅるる!!!びゅくっ!!びゅびゅ!!! 亀頭を嬲られ、睾丸を愛撫され溜まりに溜まった精液がペニスの律動に合わせて溢れ出る。 多量の精液がペニスを駆け上っていく度に、自分で扱いたのでは絶対に辿り着けない快感が押し寄せる。 リザ「ん……凄い量……♡」 射精している最中もリザは口を離さず放出された精液を受け止めていた。射精中もゆっくりとしたストロークを続け、ペニスを萎えさせてくれない。 リザ「ん…んはぁ♡ほら、見てください♡」 リザが口を開けて白濁に汚れた口内を見せつけてくる。 リザ「ん…ごく♡あぁ♡全部飲んじゃいました♡」 口内射精した精液を見せつけ、ごっくんまで…! 今までの人生で味わったことのない妖艶さに射精したばかりのペニスがピクリと反応してしまう。 目の前の痴女がそれを見逃すはずがなかった。 リザ「あ♡おちんちんまた反応しちゃいましたね♡」 「い、いや…もういいから…!」 リザ「ふふ、おちんちんに聞きますから大丈夫ですよ♡」 ガシっ! リザが膝立ちのまま両腕を僕の腰に回し、がっちりホールドする。 リザ「これで逃げられませんよ…ぁむ♡」 再びペニスが口内に収められる。 「あ゛…♡待っで…♡」 射精したばかりのペニスが温かく濡れた感触に包まれてしまう。 リザ「れるれる♡ぢゅちゅう♡れろれろ♡」 「あひ♡先っぽだめ♡敏感だからっ♡」 射精後のペニス、特に亀頭を責められることがどれほど男にとってつらいのか、おそらくわかってやっているのだろう。 あまりの刺激に腰を引こうとしても両腕に引き戻されてしまう。 「やめ゛っ♡ああ゛♡離して♡♡」 腕の力で引き剥がそうとしても、苛烈な亀頭責めが邪魔をして力が入らない。 そんなことをしてる間にペニスが完全に復活してしまう。 リザ「んふ…♡じゅぽ♡じゅぽ♡じゅぽ♡じゅぽ♡」 そしてそのままあのストロークが再開される。 射精を我慢することを決して許さない魔性の口淫。 正確無比な唇と舌の動きに責め立てられる。 「ああ♡なんで♡さっきよりきもちいい♡」 僕にとっては慣れない刺激だった1回目のフェラチオよりも、一回射精した分だけペニスが慣れ始め、快楽をより受け入れやすくなってしまっている気がする。 リザ「んふふ♡気持ちいいですね♡もう一回♡お口にぴゅっぴゅお願いします♡」 こしょ♡こりこりこり♡ 僕が快楽を受け入れる体勢になったことに気づき、腰に回していた腕を睾丸マッサージにまわす。 「ああ♡それだめえええ♡」 さっき射精まで到達した責めとまったく同じテクニック。慣れるどころかさらに快楽の虜になり翻弄されている。 2度目の絶頂を迎えるのにそう時間はかからなかった。 「あ…♡またイク♡いっちゃう…♡」 尻の奥に力が入り、睾丸がきゅっと縮まる。 リザ「んん…♡ぢゅうううう♡♡」 「あ゛♡いぐ♡いぐううううう♡♡」 どびゅ!!!びゅる!!びゅるるるるる!!! 二発目にもかかわらず、大量の精液が放出される。 その流れ出る精液をリザは相変わらずペニスを咥えたまま口で受け止めている。 リザ「………♡♡」 ゴクリ。 口に溜め込んだ子種を嚥下する音が聞こえる。 「はあ………はあ………」 未だ味わったことのない快楽を受け、休みのないまま二連続で搾られてしまった。 蓄積された疲労感で身体が重く感じる。 「も、もう十分…だから……」 リザに早くペニスを解放するように促す。 リザ「……ぱぁ♡くすくす♡そんな遠慮しないでください……ぁむ♡」 「お゛あ゛っ!!!」 一旦解放されたと思ったのに三度リザに咥えられ、咀嚼される。 二度の射精でさらに敏感になった分身に甘美で暴力的な刺激が襲いかかる。 先ほどと同様どれだけ腰をくの字になって逃れようとしても逃れられない。 リザ「れろれろれろ♡れろれろれろれろれろ♡」 やめてほしいと懇願しているのに続けられる亀頭責め。 「ああ゛だめ!!!ほんとに壊れる!!!ちんちん壊れるから゛!!!」 あまりの刺激に頭の神経が焼き切れると思ったときだった。 リザ「……ぷはぁ♡くすくす♡」 リザが口をペニスから離してくれた。 「……はあ……はあ……」 自分の真横にある、ちょうど伝心石を置いている机に手をつく。 守衛たちを呼ぶ前に荒くなった呼吸をなんとか落ち着けなければ。 身体の疲労もすさまじい。一旦座ろう……。 ガシっ!!! 「えっ」
女王小说
SM小说
调教小说
成人色情小说
Femdom Novel
Femdom Book
Femdom Story
精彩调教视频