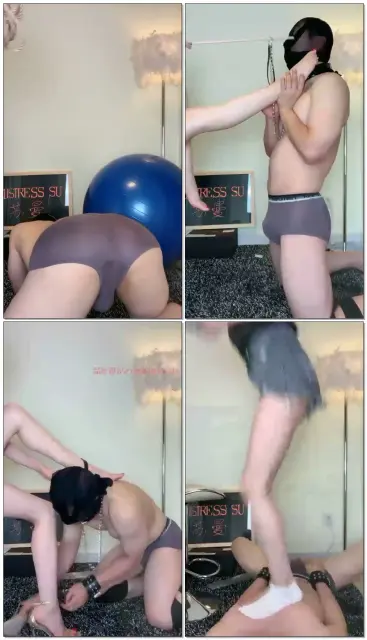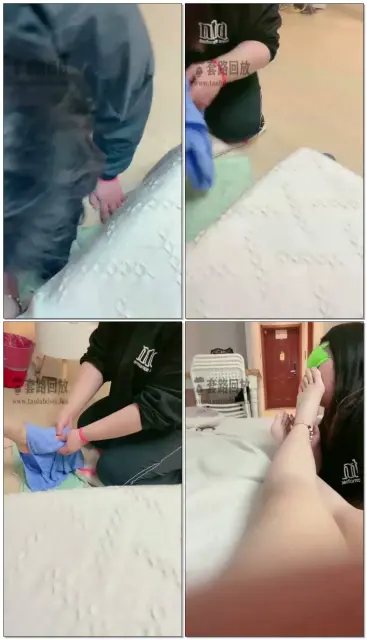日文655
1,354
以下为收费内容(by http://www.prretyfoot.com)旧校魔女 ―――あらゆる真実は一度発見されれば理解するのは容易だ。肝心なのは真実を発見することだ。 ガリレオ・ガリレイ 多くの人が学校の七不思議について聞いたことがあるだろう。 その多くが恐怖心や先入観、勘違いが生み出した、取るに足らない他愛もないものである事は言うまでもない。 だからと言って、将来ジャーナリストの道を歩もうと考えるのならば、どれほど荒唐無稽だからと言って無視してよいと言うことにはならないのもまた自明の理。 《例え徒労に終わったとしても、真実を確かめる事には確かめないこと以上の価値がある。》 代々、新聞部の先輩から後輩へと語り伝えられてきた部のモットーを胸に、僕―――私立ヴェイン学園2年生、熊崎晴夫は夜、学園の旧校舎へと足を踏み入れていた。 ―――学園旧校舎の元・理科室に、《魔女》が出る。 そんな、七不思議を確かめるために。 事の発端は、今日の昼休み。 仲のいいクラスメート数人と食事をしていた際、たまたま七不思議に話題が及んだのだ。 その際、冗談交じりで爆笑する学友たちの中で一人だけ、他とは異なる反応を示す生徒がいたのだ。 高月浩太。 笑顔で話しに合わせてはいたものの、その笑顔がぎこちないことに僕は気づいた。 そこで、トイレに行くと言う名目で彼を連れ出した僕は、彼を問い詰めた。 そして、この学校で語り継がれる七不思議の一つ、《月下美人》の話を聞いた。 彼は、「とある友人の話」だと断った上で語ってくれたのだが、古今東西、この切り出し方は十中八九、自らの話であると相場が決まっている。 高月浩太は、七不思議を実際に体験したのだ。 俄かには信じがたい話だったが、彼が嘘を吐く理由も動機もない。 無論、高月浩太がこのような淫らな与太話を好んで吹聴するようなタイプの人間でないことは友人である自分がよく知っている事である。 だとすれば、七不思議は実在すると言うことになる。 少なくとも、そのうちの一つは。 ならば、他の七不思議も検証してみる余地があるのではないか、と僕は考えた次第である。 *** 旧校舎は古い木造で、床に穴が開くなど、ところどころ崩壊が進み、安全とは言い難かった。 長く人の手が入っていなければ、それも仕方がないのだろう。 夜の学校と言う独特の雰囲気に、若干の恐怖心は覚えざるを得ない。 だが、その恐怖心故に、何かを見間違えたり、見てもいないものを見たと思い込んでしまう事は避けたい。 僕の手にはビデオカメラ。 人間の目はいざと言う時には頼りにならない。 その点、ビデオカメラの映像であれば、より証拠能力は高いだろう。 高月から聞いた《月下美人》が実在すると言う話からして、僕は僕なりに仮説を立てている。 つまり、七不思議とは霊的な怪奇現象などではなく、生身の人間が何らかの意図を以て流しているものだ、と言うことだ。 しかも、複数の人間によって引き継がれている可能性が高い。 《月下美人》に関する話も、寡聞にしてその発祥がいつなのかは知らないが、ここ2~3年、つまり高月が出会ったと言う姫月と言う上級生が入学する前からある話であることは間違いないのだから。 理科室は2階の一番奥にあった。 階段を上がり、2階の廊下に出た時点で、異変に気付く。 廊下の突き当り右側、すなわち理科室の扉から微かに明かりが漏れている事に。 (やはり………) 誰かが夜の旧校舎に侵入し、理科室で何かを行っている。 さしずめ七不思議は生徒を寄せ付けないように流されたものか、或いは逆に好奇心旺盛な生徒を誘き寄せるためのものと判断できる。 学生の悪戯レベルならまだしも、犯罪の可能性すらある。 何らかの罠、と言う可能性もある。 何せこの学園では、社会でより良い地位を築くため、人を利用し、蹴落とすことが推奨されているのだから。 (だが、もし事実を突き止められれば大スクープだ) 僕は足音を立てないように気を付けながら、慎重に廊下を進み、理科室の扉の前まで到達した。 中から人の気配は感じられない。 念のため扉に張り付き、耳を押し当ててみるが、中からは物音一つしかいなかった。 (誰もいない………?) さすがに緊張を覚え、喉が渇く。 口中の唾液を溜めてごくりと飲み干し、僕はゆっくりと引き戸を開けていく。 恒常的に誰かが利用しているのか、扉は意外にもスムーズに開いていく。 咎める声がしないことを確認し、扉の中に体を滑り込ませ、後ろ手に扉を閉める。 部屋の真ん中、丸テーブルの上に置かれたランタンの明かりが光源だった。 微かに揺らめくオレンジ色の光を浴びながら、ホルマリン漬けにされた蛇やら蛙やらが空虚な眼差しを向けてくる。 半ば予期しながら周辺を見まわし、不気味な人体模型を見つけて、一瞬跳ねそうになった心臓を、やはりあったかと言う呟きを漏らすことで無理やり抑え込む。 古めかしいテーブルや椅子、ソファなどが並ぶ中で、いくつか並んでいるビーカーだけが真新しいように見えた。 それぞれに、オレンジ色、赤、緑、紫、黄色など中身がわからない薄気味悪い液体が入れられている。 その周りには銀色のケースに大切そうに入れられたいくつもの注射器。 何かの製造或いは実験だろうか。麻薬や覚せい剤の類と言う可能性もある。だとすれば紛れもなく犯罪だ。 興味は湧くが、触る気にはならなかった。 一通り、部屋の中の物を映像に収めていく。 いずれにせよ、この映像を分析し、教職員に報告しなければならない。 その上で記事にし、大々的に発表する。 七不思議の一つ、その真実を暴いたとなれば、スクープ間違いなしだ。 新聞部の歴史に、自身の名を刻むこともできよう。 そろそろ撤収しようかと思ったところで―――突然、何の前触れもなく、部屋の扉が開いた。 焦り、隠れようと思う間もなく、誰かが部屋に入ってくる。 「―――あら?」 中途半端な態勢で固まっている僕を見て、小首を傾げる。 その相手を見て、僕もまた固まっていた。 何の冗談かと思うような紫色の長髪に、カラコンでもつけているのか、紫色の瞳。 その細身の肢体を白衣に包んだ女性だった。 年齢は、僕よりも上。学生だとすれば上級生だろう。 大人と言われてもわからないほどの大人びた風貌の美人だった。 僕の脳裏に、《魔女》と言う言葉が浮かぶ。 ローブではなく、白衣ではあったが、魔女と形容するにふさわしい雰囲気をこの女性は放っていた。 「あ、えっと………」 なんとか言い訳の言葉を口にしようとする僕だったが、女性の視線が、僕が手に持つビデオカメラに動くのを見て諦めた。 「―――僕は、新聞部の熊崎晴夫です。七不思議の一つ、《魔女》の真相を確かめるためにやってきました」 開き直って、女性にカメラを向ける。 「―――まず、勝手に部屋に入った点は謝罪します。貴女が《魔女》ですか?ここで何をしているんですか?夜間の学校を使用することについて、学園側の許可を得ているんですか?」 立て続けに質問を口にする。 体力に自信はないが、女性一人に負けることはない、と思う。 いざとなれば隙を突いて逃げ出せばいいのだ。 それよりも、せっかくのチャンスなので女性から少しでも多くの情報を引き出そうとする。 カメラを向けられても、女性は動揺する素振りを見せはしなかった。 ただ、薄く笑みを浮かべる。 思わず背筋がぞっとするような、綺麗だが、薄気味の悪い笑みだった。 「私が《魔女》かと言われれば、その通りよ。ここで何をしていたかと言えば、まぁ、とあるお薬の実験と言ったところかな。ちなみに、名前は柴田香織。老けてるってよく言われるけど、ここの3年生。まだぴちぴちの女子高生よ。ここの使用許可を受けているかどうかはノーコメントで♪」 「薬?」 「そう。血行が良くなって、身体が温まって、凄く元気になれる……そんな素敵なお薬♪……貴方も試してみる?」 「結構です」 怪しい笑みを浮かべながらの申し出を即座に断る。 「そんなこと言わずに。せっかく来たんだから、ちょっと飲んで意見を聞かせてよ。別に体に悪いもんは入ってないから」 そう言いながら白衣のポケットから市販のエナジードリンクぐらいの大きさをした一本の瓶を取り出す。 「新聞部で宣伝してくれたらありがたいし。先輩からのお・ね・が・い❤」 くねくねと媚びるように体を揺らす柴田先輩。 はっきり言って女性経験のない僕は、それだけの事で耳まで真っ赤になってしまう。 「あら。初心でかわいい。ふふっ、なら手伝ってくれたら色々教えてあげる♪……他の、七不思議の事とか。新聞部員さんなら興味あるんじゃない?」 「っ………」 確かに、七不思議の一人である彼女ならば、他の七不思議について何かを知っている可能性は高い。 肝心なことははぐらかされているものの、話した印象では明るく気さくで、悪い人間ではないようにも思える。 「……。本当に、悪いものは入っていないんですね?」 「入ってないよー。人の口に入るものは安全第一♪」 朗らかに笑いながら瓶のキャップを外し、押し付けるように渡してくる。 押し切られるように受け取ってしまい、取り合えず匂いを確認する。 「柑橘系のいい匂いでしょ。ほら、ぐいっと」 まるでおじさんのように奨めてくる柴田先輩。 確かに不快さや警戒感を呼び起こすような類の匂いではない。 柴田先輩の期待に満ちた眼差しから逃れる様な思いで、一息に瓶の中身を飲み干す。 「どうどう?」 「味は……悪くないです」 「そう。体の方は?」 「体の方?」 「そう。ぽかぽかしてこない?」 「ぽかぽか……?確かに、言われてみれば、身体が温かくなって……」 「でしょ。血行が良くなって、元気になるの。だから……」 柴田先輩の雰囲気が一変する。 妖しい笑みを浮かべながら、ゆっくりと白衣を脱ぎ捨てる。 なぜだか頭がふわふわし、辺りの風景がぐにゃりと歪むような、これまでに経験した事のない感覚の中、まるで時間感覚さえもおかしくなってしまったのかと思うほどゆっくりと、白衣が床に落ちる。 「あ………」 そして、僕は白衣を脱ぎ捨てた柴田先輩の姿に呆然と言葉を失ってしまった。 ちょっとエッチな漫画やアニメの中だけのものだとこれまで考えてきた、ボンテージ姿。 しかも、乳房を隠す機能は放棄されたのか、大きくて柔らかそうな乳房も、桜色の乳首も露になってしまっている。 「う……し、柴田……先輩……」 あまりにも淫らな姿に、全身の血と言う血が股間に向かって流れ込んでいく。 ズボンの中でむくむくと隆起し、あっという間にテントを張ってしまう。 「どう?元気になりすぎて、見てるだけでたまんないでしょ❤」 くねくねと体を揺らして見せる柴田先輩。 その動きを見ているだけで、先端から我慢汁が滲み出てくる。 「ふふ、夢中になってガン見しちゃって。効果覿面って感じね」 「こ、この、薬……」 「そう。媚薬よ。この学校では、いい商売になると思って♪」 テーブルに寄りかかり、片足を上に乗せる。 「ほら、見て………❤」 柴田先輩の手が、自身の股間を摩る。 僕は目を血走らせ、はぁはぁと荒い息を吐きながら、柴田先輩の股間を凝視する。 大事なところを守る部分に、用途不明のチャック。 柴田先輩が、ゆっくりとチャックを下ろしていく。 「う………」 現れたのは、女性の大事な部分。 ピンク色で、ぬらぬらと淫らに輝き、何かを求めるようにひくひくと震えている。 ズボンの中で、ペニスが痛いほど勃起する。 鼻の奥がツンと熱くなる。 ぬるりとした液体が鼻腔から流れ出し、床を点々と赤く汚していく。 「窮屈で苦しいでしょう?解放してあげなさいよ」 柴田先輩の言葉に、僕は慌ててズボンを脱ぎ捨てる。 今までに経験したことがないほど勃起したペニスが勢いよく現れ、床に我慢汁が飛び散る。 「わお。意外といいもの持ってるじゃない。あ、意外ってのは失礼か。ごめんごめん♪」 柴田先輩の軽口は、ほとんど僕の耳には届いていなかった。 性的興奮を高めること以外にはほとんど何の効果も発揮しないであろう柴田先輩の格好だったが、目的特化型であるだけに、その破壊力は抜群だった。 「うっ、はぁっ、んんっ……❤❤」 人前だと言うのに、僕は恥も外聞もなくペニスを握り、柴田先輩の股間を凝視しながら、 扱きあげる。 頭の中で幾筋もの電光が迸るほどの快楽に、涎が止まらない。 ペニスの先端から次々に我慢汁が溢れ出す。 あっという間に射精衝動が込み上げてくる。 「あら。もう逝きそうなの?」 「あ、も、もうっ、出ますぅっ……!!」 人前であるにもかかわらず、僕は全身をがくがくと震わせながら絶頂し、床にこれまでに経験した事がないほどの量の精をぶちまけてしまった。 栗臭い匂いが周囲に広がっていく。 「ふふ、いい匂い❤……それに、気持ちよさそうな顔しちゃって❤」 柴田先輩は醜態を晒す僕の様子がおかしくてたまらないという様子で笑みを零す。 「見てるだけで逝っちゃうなんて、なかなか有望ね❤……でも、まだまだ全然足りないんでしょう?」 「はぁはぁはぁ、な、なんで………」 その指摘に、僕も驚きを隠せない。 普段自慰行為をする際は、一度射精すればそれで満足してしまう。 だと言うのに今は、大量に射精した直後だと言うのに、一向に収まる様子がなかった。 そんな僕に、柴田先輩がゆっくりと歩み寄ってくる。 両手を広げ、笑みを浮かべながら。 厭らしい愛液が太ももを伝い、淫らに光っている。 「ね、熊崎君❤―――私の助手にならない?」 「じょ、助手………」 柴田先輩が一歩前に進む度、柔らかそうな乳房が厭らしく震える。 そして、僕のペニスもぴくぴくと震え、我慢汁がぽたぽたと床に滴る。 「そう。この商品が完成すれば、多くの人を元気にしてあげられる。とても画期的な商品になると思うの♪」 ―――人を邪な道に引き込むため、悪魔が真実を言う事がある。僅かな真実で引き込んでおいて、深刻な結果で裏切るために。 ウイリアム・シェイクスピア そんな過去の偉人の言葉が脳裏を掠めたが、頷いた結果、今度僕の身に起こる事を想像すると、あまりに甘美すぎて。 とても即座に断ることなどできなかった。 ただ、即座に頷くこともできなくて、ただ黙して立ち尽くすことしかできなかった。 「毎晩毎晩、お薬を調合して❤」 柴田先輩の指が頬を撫でる。 「毎晩毎晩、その効果を確かめ合うの❤」 手が後頭部に回り、ゆっくりと頭が胸の谷間に迎え入れられる。 香水なのか、先輩自身の香なのか。 甘酸っぱい香りがする。 思わず深く息を吸い込んでしまう。 肺の中が、その香りで満たされると、まるで眩暈のように視界が歪んでいく。 「薬の効果が切れるまで気持ちいいことをして❤」 限界まで勃起したペニスが、むっちりとした太ももに挟まれ、愛液に塗れていく。 「完成したら、学園中で売り捌くの❤」 顎を持ち上げられ、胸の谷間から柴田先輩の顔を見上げる。 その紫の瞳に魅入られる。 「素敵でしょう?」 艶のある唇が言葉を紡ぎ、ゆっくりと僕の唇に重ねられる。 入ってきた舌に、僕自身も舌を絡めていく。 甘い。 先輩の唾液も、先輩の香りも、先輩が齎してくれる快楽も。 何もかもが甘くて、頭の中が桃色に染まり、ぐずぐずと溶けだしていく。 太ももに挟まれたペニス、その亀頭が先輩の掌に包まれて。 くるり、くるりと捻られ、刺激される。 むっちりで、ぬるぬるの空間に挟まれた竿はまるでそのまま溶けてしまうのではないかと思う程に蕩けてしまって。 頬を包む乳房の感触に、まるでどんどん子供に帰っていくような感覚すら覚える。 「先……輩……ふわぁ❤❤」 蕩け切ったまま、柴田先輩の掌中でどびゅどびゅと精を放つ。 途轍もなく甘美な射精。 だが、それでも、僕のペニスは硬さを失わない。 むしろ、更なる快楽を催促するかのようにひくひくと震えている。 「ね、いいでしょう?」 顔を離し、先輩が訊いてくる。 二人の唇の間に、淫らな糸が伝う。 思わずこのまま頷いてしまいたくなる。 だが。 だけど。 それでいいのか? 微かに残った理性が問いかけてくる。 これは、明らかに危険な薬だ。 それに、柴田先輩自身も、決してシロではない。 将来、ジャーナリストになる事を志す者として、彼女の誘惑に屈する訳には。 それでは、新聞部の歴代の先輩たちにも申し訳が立たないのではないだろうか。 「僕は………」 「ね、熊崎君。もし助手を引き受けてくれたら、私の身体、好きにできるのよ?」 「っ………」 どくん、と鼓動が高鳴る。 柴田先輩が僕から身を放し、ソファに横になる。 そして、股間を指で広げて見せる。 「ぁ………」 ピンク色の、綺麗な淫肉が何かを求めるように蠕動し、愛液が溢れ出している。 「ほら、見てぇ❤❤」 柴田先輩が秘所に指を突っ込み、弄繰り回す。 「熊崎君、聞こえるぅ?私のおまんこがくちゅくちゅって言ってるの❤❤」 「う………あ……」 「切なくてぇ❤熊崎君のぶっとぉいおちんぽが欲しくて欲しくて溜まらないの❤❤」 「お………ふ………」 「おっぱいもぉ。乳首がビンビンに勃起しちゃってるのぉぉ❤……熊崎君に舐めてほしいのぉ❤❤」 股間を弄繰り回しながら、おっぱいをぐにゅぐにゅと揉み、先端で硬く勃起した乳首をこねくり回す。 淫らな公開オナニーショー。 白い肌が桜色に上気し、汗を浮かべ、淫らで切ない表情と甘く官能的な喘ぎ声。 そんな光景を見せつけられて。 耐えられるはずがなかった。 僕の中で、新聞部としての熊崎晴夫が死に、一匹の雄としての熊崎晴夫が目覚めてしまった。 「な、なります、なりまひゅっ!」 「ふふ、ありがとう❤………ほら、いらっしゃい❤❤」 「し、柴田先輩っ❤❤」 両手を広げ、僕を誘う柴田先輩。 僕は誘われるままに飛び込む。 その柔らかな体に包まれ、それだけで幸福感を感じたのも束の間。 ペニスが、ぬるり、と何の抵抗もなく柴田先輩の中に飲み込まれていく。 「あっ、あぁぁあっっ❤❤」 幾重もの襞が絡みつく刺激は、童貞の僕にとっては強すぎた。 頭が真っ白になり、一瞬たりとも我慢できずに精を放つ。 「ふふ、入れただけで逝っちゃったの?」 「あ、あぁっ、ご、ごめんなさい、先輩、僕、先輩の中に………っ!!」 生で中出しをしてしまった。 その事実に愕然としていると、先輩の両腕が首に、両足が腰に巻き付き、僕をがっちりとホールドしてしまう。 密着度が増し、彼女の中により深く沈み込むペニスに、ねっとりと襞が絡みつき、締め上げてくる。 「いいのよ❤あなたは大事なモルモ―――研究仲間なのだから❤❤……私の中にぜぇんぶ、吐き出して❤❤」 「は、はひぃぃぃっ❤❤」 何か聞き捨てならない言葉が一瞬聞こえてきた気がしたが、ペニスの先端に子宮口が吸い付いてくる感触に蕩け切っていた僕にとってはどうでもいい事だった。 へこへこと腰を振り、何度も何度も柴田先輩の膣の一番奥に精を吐き出す。 何度出してもペニスは全く萎えることなく。 ずっぽりと柴田先輩の身体に突き刺したまま、何度も何度も震えては精を噴射する。 口づけを交わし、乳首をしゃぶり、乳房の感触を堪能しながら。 夜が明けるまで、僕は精を放ち続けた。 次の日も。 その次の日も。 その次の日も。 僕は夜の旧校舎に忍び込み、そこに棲む《魔女》に逢いに行った。 そんな僕の様子に高月浩太は何か言いたそうな顔をするものの、結局何かを言って来る事はなかった。 そして、その手で。 その口で。 その胸で。 その足で。 その膣で。 そのお尻で。 髪でも、太ももでも、膝でも、脇でも。 ありとあらゆる場所、ありとあらゆる方法で、僕は逝き続けた。 ドリンクの量、濃度を変えて。 持続時間や射精量の変化を観察される。 そして、どれほどの期間常用すると廃人に至ってしまうのかまで、柴田先輩にデータを提供し続けた。 僕の身体を使っての実験データは、数年後、柴田先輩が入社したヴェイン製薬の製品へと結実することになる。 エネルギードリンク、ヴェイン・エナジーZへと。 その報せを、僕はヴェイン病院のベッドの上で聞いた。 聞いたが………理解することはできなかった。 その時、僕の心はもう壊れていたから。 興味を示すのは、ただ紫色のもののみ。 紫色の物を見た瞬間、僕は興奮し、射精する。 ただの、廃人と化していたのだ―――。 月夜の滝行 龍門寺は龍門山の南斜面山腹にある龍門の滝の上に位置し、金堂、三重塔、六角堂、僧房などの伽藍が立ち並んでいる。 ここで、道鏡は修行に明け暮れる日々を送った。 境内の隅々まで掃除をし、本尊に向かって座禅を組んで、『解深密経』を一心に唱え、龍門の滝に打たれる、と言う日々である。 そんな日々を送る事、およそ半年。 遣唐使船を難波津で見送った際には、麗らかな春だった季節も、そろそろ厳しい冬になろうかとしていた。 (今頃、遣唐使の方々は長安に着いた頃だろうか………) はらはらと舞い落ちる落葉を見つつ、そんな事をふと思う。 実際に、遣唐使が大唐帝国の都・長安に着くのは、10月1日である。 滝の勢いは強く、打たれていると体の芯まで凍えていく。 だが、思考はどんどん透徹になっていき、やがて体の底からふつふつと熱がこみ上げてくる。 そしてだんだんと、感覚が研ぎ澄まされ、知覚できる世界が広がっていく。 全ての感覚を圧倒していた滝の轟音、水の冷たさ、痛みすらも感じなくなっていく。 代わりに感じるのは、風の音。 濡れた岩に貼り付く苔の呼吸する音。 遥か空の高みを流れる雲の音。 遥か地の底を流れる霊気の音。 まるで、自分が大いなる自然と同化していくような感覚。 その時、くすくす、と言う若い女の笑い声が聞こえた。 人里離れた山の中。 況や、女人禁制の霊場である。 女の声など、聞こえるはずもない。 気のせいだろうと、意識の外に追いやる。 「わぁ、凄いね、お兄さん♪」 だが、声は徐々にはっきりと聞こえてくる。 まるで、すぐ目の前に居るかのように。 (煩悩か………?) 無論、女など知らぬ身である。 これまで、色欲などに思いを馳せる遑すらない、修行の毎日を送ってきた。 「こんなの、見たことない❤」 美しい声だった。 その声を聞くだけで、脳裏に嫋やかな美女の姿が思い浮かぶ。 「ねぇ、触っていい?」 良い訳がない。 そもそも、ただの煩悩であれば、体に触れる事などできるはずもないのだ―――。 にぎっ。 「はうんっ!?」 思わぬ場所を握られる感触に、おかしな声が漏れ、思わず目を見開いてしまった。 「っ、あ………」 そして、言葉を失う。 座禅を組み、時を忘れて大自然との融合を堪能しているうちに、いつの間にか夜になっていたらしい。 暗い夜空にぽっかりと満月が浮かんでいた。 その満月を半ば遮り、ほんの目の前に、膝下までを滝壺の水面に沈め、美しい女が立っている。 宙から降り注ぐ月の光を集めたような、キラキラと煌めく黄金の髪。 陶器のような、白い肌。 高貴な輝きを帯びた、紫色の瞳。 鮮血のような、紅い唇。 その身を包むのは、滝の雫を浴びて肌に張り付く薄い衣のみ。 帯も結んでおらず、前が開いてしまっている。 そのために、豊満な乳房も、引き締まった腰も、尻の柔らかな膨らみも、淡い下腹部の茂みも、ほっそりとした太ももも。 そのすべてが、露になっており、吸い寄せられるかのように視線を動かすことができない。 いや、その尋常ならざる美しさを前に、息すらも忘れていたかもしれない。 その、とても人とは思えない美しさを持った女の両手が伸ばされた先は、僕の股間。 白装束から引きずり出された肉棒が、その柔らかな手にしっかりと握られていた。 「ぁ………」 自分の肉棒に、美しく白い指が絡みついている。 それを知覚した瞬間、心臓がどくんっと大きく跳ねた。 体が熱を帯び、どくどくと血流が下半身に流れ込んでいく。 血管が浮き上がり、肉棒が赤黒く、怒張していった。 その光景に、女が目を丸くする。 「凄い、さらに大きく………両手で指が回らないなんて………」 醜く腫れ上がり、びくびくと震える肉棒を目にして、女がぺろりと舌なめずりをする。 その淫靡な光景に、僕は慌てて女の手を振り払った。 「さ、触るな!」 「きゃ。何よもう………」 女は唇を尖らせる。 だが、その視線は、僕の肉棒にくぎ付けだった。 「ね、触らせてよ」 「だ、駄目だ」 「えー、どうして」 「僕は僧侶だぞ」 「だから何?」 「女性と交わる事は戒律で禁じられているからだ」 「何それ。男女で交わらなきゃ、子供も生まれないじゃない」 「そっ、それは、俗世を生きる人に任せるっ」 女の容姿は美しく、この世の物とも思えなかった。 日本人とも、朝鮮や中華の人とも違う。 書物でしか聞いたことのない遥か西、「日の沈むところに最も近い大国」と呼ばれる「大秦国」の人間だろうか。 その国には、白い肌と青い瞳を持つ人がいるという。 この女は、青ではなく、紫の瞳をしているが、青が居るなら紫が居たとしても何ら不思議はない。 でなければ、妖、神仙の類とでも言うつもりか。 「ふーん。じゃあ………興味ないの?」 そんな事を言いながら、女が自身の半裸の肢体に手を這わせる。 豊かな乳房を下から掬い上げ、落とす。 たぷんっ、という擬音が頭の中に響いた気がした。 指が滑らかな腹を滑り降り、弾力のありそうな太ももを撫で、股間の淡い茂みをさわさわと掻き分ける。 途轍もなく淫らな光景に、息をするのも忘れて見入ってしまう。 「くすっ❤……興味、あるんじゃん❤」 笑われて、赤面する。 「ば、馬鹿を言うなっ!ぼ、僕は―――」 「はいはい、むっつりスケベなのね。でも、勿体ないよぉ。こんなに大きいのに。ね、触らせて?気持ちよくしてあげるから❤」 女が空中で何か筒状のものを扱くような動作を見せ、妖しく笑う。 「っ…」 その動作を見るだけで、口の中に唾液が溢れ、肉棒がぴくんと震えてしまう。 反論の言葉も出てこない。 滝行によって感覚が鋭敏になっているためか、女に握られた時の、指の甘美な感覚が未だに肉棒に残っていた。 それだけで、心がざわつく。 (不甲斐ない。しっかりしろ………) 己を叱咤し、女を無視しようとするが、ついつい、その姿を目で追ってしまう。 雫に濡れ、月光を浴びて艶やかに輝く白い肌。 ちょっとした動きで、ふるふると魅惑的に揺れる乳房。 滑らかなお腹。 下腹部の淡い茂みの奥がどうなっているのかも、気になってしょうがない。 溢れてくる唾液を飲み下し、 「い、いいからもう帰りなさい。どこから迷い込んだのか知らないが、本来、ここは女の来るような場所ではないのだ。修行の邪魔になる」 座禅を組み直し、ふつふつと込み上げてくる熱を無視して、修行に集中しようとする。 だが。 ふにゅり、と柔らかな感触が背中に押し付けられる。 「なっ………!」 驚きに目を見開き、身を捩るが、背中側から抱き着く女を振り払えない。 逆に、しがみついてくる体の柔らかな感触に力が抜けていってしまう。 「だったら、修行、手伝ってあげる、道鏡ちゃん❤」 耳元で、女が囁く。 その手が脇の下を通って前に伸ばされ、僕の胸板を這い回る。 「っ、くふっ………な、なんで僕の名前を……」 未知の感覚に、食い縛った歯の間から息が漏れだしてしまう。 「私が凄いから❤私の事は真魚とでも呼んで❤ほらほら、そんな事より、今はちゃんと集中して。ブッダは5人の娘からの誘惑を跳ね除けて悟りを開いたのでしょう?あなたを誘惑するのは私1人。そんな誘惑にも耐えられないようでは、修行したところで意味なんかないわよ」 「っ……」 女犯の戒律も知らなかった割に、ブッダの逸話は知っているらしい。 見え透いた挑発だったが、悟りの境地を目指す僧侶としては受けて立つより他にない。 「どんな誘惑にだって、耐えてみせる………」 「ふふ、いいわよ、その調子♪久々に骨のある修行者ね。最近の子は私の姿を見るだけで押し倒してくるような子ばかりだったから。貴方のような子は、十年振りぐらいかしら」 「いつも、こんな事を………」 「そうよ。もう、ず~っと、前からね❤」 そう言いながら、首筋を舌が這っていく。 ぞくぞくとした感覚に、再び身体が熱を帯びていく。 ずーっと前、と言う真魚の言葉で、僕は久米仙人の逸話を思い出していた。 この龍門山に住んでいた久米仙人が神通力で空を飛んでいた所、川で洗濯をしていた若い女性の白い脛に見惚れて、神通力を失い、墜落したという逸話である。 それに、10年前と言えば、ちょうど兄弟子である良弁が修行のために龍門山に入っていた頃だろう。 まだ僕は出家する前だったので、詳しい話は知らないが。 良弁も、この試練を受けたのではないだろうか。 (だとすれば、僕も負ける訳にはいかない………) 歯を食い縛り、修行に集中する。 水は冷たく、滝に打たれるのは激痛が伴う。 自分と同じように滝に身を晒す真魚が、長く耐えられるとは思えない。 だが、修行に集中しようと感覚を研ぎ澄ませれば研ぎ澄ませるほど、真魚の柔らかな肢体の感覚もまた鋭敏に感じ取ってしまう。 冷たい胸板を這い回る掌の温かさが心地よく、乳首を撫でられる度、ぴりぴりとした感覚が背筋を駆け上っていく。 さらに、柔らかな舌が、首筋、頬、耳にまで這い回る。 どくどくと血が下半身に流れ込んでいき、肉棒を滾らせる。 「わぁ❤また大きくなった。座禅を組んでいると膝が三つあるみたいに見えるんだけど♪こんな凄いの、見たことないわ❤」 肉棒を見て、真魚が感嘆の声を漏らす。 熱を帯びた吐息が首筋を擽って、こそばゆい。 自分のそれが、他人のそれよりも大きいという事は自覚していた。 しかし、ここまで驚かれる程だとは考えていなかった。 何しろ、女性に見られるのも初めてなのだ。 僕の腰を挟むように前に伸ばされた女の綺麗な白い足が、醜く怒張した肉棒を挟み込む。 「んんぁぁっ………❤」 大地など一度たりとも踏みしめた事がないのではないかと思わせるほど柔らかく、温かく、すべすべの感触に、溜まらずに声が漏れてしまう。 「あはは❤足でされるの気持ちいいんだ?それにしても、本当に大きいねぇ❤」 大きさや感触を確かめるように、柔らかな足が肉棒を這い回る。 「な、何これ❤あ、足なんかで❤足なんか❤なのに、なのにぃ………❤❤」 この、ゾクゾクとした感覚が、気持ちいいというものなのだろうか。 これまでに味わったことのない感覚だ。 まるで、ふわふわと身体が浮き上がっていくような。 「あはは。いいよ、道鏡ちゃん。その顔可愛い❤きゅんってしちゃう❤❤もっと、もぉっと、その顔見せて?」 真魚がわきわきと足指を動かす。 不規則な動きが、予想もつかない刺激となって、脳髄を直撃する。 「あっ❤はぁっ❤んんっ……❤❤」 耐えようとする思いも虚しく、いとも容易く喘ぎ声が漏れてしまう。 「もう蕩けちゃってる♪まだまだ、修行はこれからだよぉ❤❤」 顔を後ろに傾けさせられ、唇に、真魚の唇が重なる。 蕩けそうに柔らかな唇の感触。 伸ばされた長い舌が、僕の舌に絡みつく。 上から下へ。 真魚の舌を伝って、唾液が流し込まれる。 本来なら、不浄なもののはずである。 にもかかわらず、僕はこくこくとその唾液を飲み込んでいた。 濃密な甘い味が口の中に広がり、食道を伝い、胃を満たしていく。 鼻から吸い込む真魚の甘い香りが、肺を満たす。 それらは血管を通じて全身に広がり、快楽となって肉棒をさらに滾らせ、脳を蕩けさせていく。 カリカリと弄られる乳首も硬くしこり、弾かれる度にびくんっと快楽に体が震えてしまう。 肉棒を挟む白い足が、しゅこしゅこと剛直を扱き上げる度、先端から我慢汁が噴き出していく。 (気持ちいいっ……気持ちいいっ❤……気持ちいいっ❤❤) 性に対する経験も免疫も持たない身である。 裏筋、カリ首、亀頭、鈴口など敏感な部分を刺激される度、意識が飛びそうになってしまう。 緩急を弁えた絶妙な力加減と速度、時折捻りを加える技巧によって与えられる快楽が、瞬く間に頭の中を桃色に染めていく。 (こんなの、耐えられないっ❤❤……あ、頭がおかしくなりゅぅぅ……❤) 睾丸の中で精液が沸々と煮えたぎり、射精の瞬間を求めてびくびくと震えている。 「ぷはぁっ❤❤」 たっぷりと僕の口内を貪った真魚が唇を放す。 二人の間には、銀色の淫らな糸が引いた。 「どう、道鏡ちゃん、気持ちいい?」 真魚に見つめられる。 美しい紫色の瞳に、蕩け切った自分の姿。 「あは❤気持ちいい……ですぅ……❤❤」 締まりを失った口の端から、涎が零れ落ちていく。 自分自身では座禅を組んでいるつもりだったが、実際にはすでにその体からは力が抜けて、後ろから抱き締めてくれる真魚の乳房に後頭部を押し付け、体重を預け切っている状態だった。 「どびゅどびゅって、射精したい?」 真魚が問いを重ねる。 視線を下半身に向ければ、これまでの生涯で見たことがない程大きく勃起した肉棒を、真魚の綺麗な両足が挟み、ずりゅずりゅと淫らな音を立てながら扱き上げているのが見えた。 肉棒は、滝の雫でも流し落とせないほど大量の我慢汁によってぬるぬるの状態だ。 それを絡めながら扱き上げられる度、得も言われぬ快楽が全身を貫いていく。 真魚の足が、睾丸を甲に乗せて、まるでその重さを確かめようとするかのように揺する。 「たまたまもパンパン♪精液でもう、はち切れちゃいそうなほど、たぷんたぷん❤射精したければ、させてあげる❤これまでに味わった事がない程気持ちいいよ、きっと❤」 真魚が甘く、淫らに囁く。 (したいっ❤気持ちよくなりたいっ❤❤) 快楽に蕩け切った脳裏に、色欲に狂った己の声が響く。 が、同時に聴こえてきたのは、啜り泣く様な子供の声。 どきっ、とした。 思い浮かんだのは、幼い少年の姿。 薄汚れた格好で、大粒の涙を流しながら、自分よりも少しだけ大きな、子供の頃の僕にしがみつく、2つ下の弟である。 (浄人………) 胸が締め付けられる。 僕たちが生まれたのは後世、長瀬川と呼ばれることになる河内国若江郡、大和川の畔にある貧しい家だった。 かつて栄華を誇った一族の末裔と雖も、没落した家ならばどこも同じようなものだろう。 物部氏自体は、守屋の兄や弟の系統が“石上”と名を変えて残り、当主の石上麻呂は朝臣の姓を与えられ、左大臣の要職まで昇り詰めている。 今年の春、麻呂が亡くなると、朝廷からは従一位の位階も追贈された程の重鎮だ。 だが、物部守屋の末裔である弓削の者たちは捨て置かれ、犬畜生のような扱いを受けてきた。 先祖が物部守屋だと言うだけで、白い目で見られ、石を投げられ、唾を吐きかけられる事さえ日常茶飯事だったのだ。 石上の者たちも、朝廷から睨まれる事を恐れたのか、弓削の里にすら寄り付こうとはしなかった。 若い頃は下級の役人だったという父は、病弱だったが故に職を辞した程で、満足に畑仕事もできなかった。 幼心に覚えているのは、よく、家に知らない男性がやってきていた事。 時には役人。時には商人。時には武人。時には農民だった事もある。 様々な身なりをした、様々な男たちが。 その度に、僕と弟は父に手を引かれ、と言うよりは半ばそのあばらが浮くほどに痩せ衰えた体を支えながら、一族の氏神を祀る弓削神社や長瀬川の畔で時間を潰した。 夕方になって家に戻ると、若い頃は巫女をしていたという母は疲れを感じさせながらも、美しい顔に優しい笑顔を浮かべて迎えてくれた。 いつも、家の中になんとも言えない生臭い匂いが漂っていたことをよく覚えている。 そう言った日の夕飯は、いつもよりも少しだけまともだった。 それを噛み締めながら、いつも父は泣いていた。 嗚咽を漏らし、「済まない」と何度も何度も、母に頭を下げながら。 母は何も言わず、父の背中を擦りながら、優しく微笑んでいた。 弟は、ただ無邪気に、夕飯をがっついていた。 母が何をしていたのか。 父がなぜ、謝りながら泣いていたのか。 馬鹿な僕がそれを知ったのは、母が死んだ時だった。 近所の子供たちから、お前の母親は「傀儡女」だったと言われたのだ。 それが、「身体を売る」仕事であると知ったのも、その時だ。 その時、浄人は、「違う!」と叫んでいた。 薄汚れた格好で、大粒の涙を流しながら、自分よりも少しだけ大きな、子供の頃の僕にしがみつきながら。 「違う!母様は、僕たちのために一生懸命働いていたんだ!」と。 「兄様からも何か言ってやって!」とせがまれたが、僕は何も言えなかった。 全てを理解してしまったから。 父が悲しそうに、小刻みに体を震わせながら、唇を噛んでいるのを見て。 どれほど悔しいだろう。 どれほど悲しいだろう。 どれほど情けない思いをして。 どれほど怒りを抱えて。 どれほど、病弱な己が身を呪っただろう。 それでも尚、父は耐えていたのだ。 噛み締め過ぎた唇からも、握り締め過ぎた拳からも血を流しながら。 浴びせられる無遠慮な好奇の眼差しと侮蔑の笑い声の中で。 父が耐えているのに、どうして僕が激昂できるだろう。 その時だ。 僕が、将来絶対に栄達して、物部氏を復興させようと心に決めたのは。 どんな手段を使っても、である。 父はそのすぐ後に血を吐いて死んだ。 葬儀を開く金もなく、僕は父の亡骸を埋め、泣きじゃくる弟を、いつか必ず迎えに行くからとなだめて親戚に預けて、龍蓋寺の門を叩いた。 物部氏を再興させるためには、その末裔である弓削を名乗っていては難しい。 名を捨て、やり直すならば、仏門に入るのが一番手っ取り早いと思ったのだ。 だから。 だから! 「い、要らないっ………!!」 こんな所で、色欲に溺れている場合ではないのだ。 僕はありったけの力で身を起こし、真魚を振り解いた。 「きゃっ!」 振り払われた真魚は滝壺に落ち、全身ずぶ濡れになりながら、驚いたようにこちらを見上げている。 「ぼ、僕は……こんな誘惑には屈しない!」 僕は決然と告げ、再び座禅を組む。 真魚の顔に、ゆっくりと笑みが浮かんでいく。 「凄い。これで堕ちないなんて………良弁ちゃんは、すぐに射精させてぇっっ❤❤って、可愛くおねだりしてきたのに♪」 ぎょっとした。 「っ、良弁ちゃん………だって?」 真魚は立ち上がって、ゆったりとした仕草で髪を掻き上げる。 白いうなじから香り立つような色香に、一瞬息を飲む。 「そう。良弁ちゃん」 頭が真っ白になる。 脳裏に、穏やかで優しい兄弟子の顔が過る。 「良弁ちゃん、生まれは相模の鎌倉なんですってね。でも、お母様が野良仕事をされている最中に鷲に攫われちゃって。大和の二月堂前の杉の木に引っかかっているのを義淵ちゃんに助けられて育ててもらったって言ってたわ。その恩を返すためにたくさん勉強をして。立派な僧侶になるんだって。でも、足でしこしこされてあへあへって喜びながらどびゅどびゅって射精してたわ❤」 「う、嘘だっ……りょ、良弁様に限ってそのような………」 「嘘なんかじゃないわよ。と~っても可愛かったのよ。『もっと踏んでください!もっと❤もっとぉっ❤❤お願いしますぅぅっ❤❤❤』って」 「っ………」 脳裏に、将来は僧正にもなれるのではないかと言われている偉大な兄弟子が情けなく嘆願の声をあげながら、真魚に踏まれて喜んでいる姿が思い浮かぶ。 涙を浮かべながらみっともなく全身を痙攣させながら射精し、真魚の足を汚す様を。 びくん、と肉棒が疼いた。 「あら。もしかして、想像して、自分もしてもらいたくなっちゃった?」 真魚が片足を上げ、わざとらしく足の指を動かして見せる。 その淫らな様に、肉棒はさらに滾り、口の中に涎が溢れてくる。 先ほどの快楽を思い出してしまう。 あのまま、真魚の足によって射精させられたら、一体どれほど気持ちいいのだろうか。 「いいわよぉ、その欲望に濁った眼。ぞくぞくしちゃう❤……でも、駄ぁ目、もう足ではしてあげませ~ん❤」 (そんな………) 真魚の言葉に対して、込み上げてきた感情は悲しみに近いものだった。 「そんな可愛い顔しても駄目よ。素直に気持ちよくしてください❤ってお願いしてくれたらよかったのに。だから次はもっと素直に、ね❤」 真魚が歩み寄ってくる。 真っ赤な舌が、唇を舐める。 ゆっくりと、自身の体を見せつける様にくねらせながら、僕の前に跪く。 その美しい顔の眼前に、怒張した肉棒。 真魚の目が三日月を描く。 口元に笑みが浮かび、伸ばされた舌が、裏筋を下から上へと、浮かび上がった血管をなぞり上げる様に、ゆっくり舐め上げていく。 「あっ❤あぁぁっ……❤❤」 背を反らし、後ろ手を岩に突いて何とか快楽に耐える。 柔らかな舌がカリ首を一周し、亀頭を舐め、鈴口を擽っていく。 「んんっ❤おっ❤こ、これ、あぁぁっ❤❤」 「んふ♪」 懸命に快楽に耐える僕を上目遣いに見つめつつ、真魚がゆっくりと口を開いていく。 背筋を、恐怖感が駆け上がる。 「や、やめっ―――」 ずぶずぶずぶ❤❤ 「――――っっ❤❤❤」 制止しようとする間もなく、亀頭が真魚の口の中に飲み込まれていく。 唇、舌、頬粘膜が絡みつき、温かくぬめった唾液の海の中でしゃぶられる。 僕は思いきり身体を反らし、声にもならない悲鳴を上げていた。 まるで、肉棒が溶けていくような悦楽。 我慢汁と唾液の混合液が泡立ちながら竿を流れ落ちていく。 その液体を指に絡め取りながら、肉棒を握り、扱き上げる。 「あぁぁっ❤❤ひぃぃっ❤❤」 「―――ぷはぁっ。大きすぎて、亀頭しか咥えられない❤本当に凄いよ、道鏡ちゃん♪」 しこしこと肉棒を片手で扱き、もう片手で睾丸をたぷたぷと弄び、亀頭にれろれろと舌を這わしながら、真魚が笑う。 「おふっ❤んあぁっ❤んひっ❤❤」 真魚の齎す強すぎる快楽によって、理性にどんどん罅が入っていく。 「ほら、どうするの、道鏡ちゃん?まだ我慢するぅ?それとも、私のお口の中に、濃厚な精液をどびゅどびゅって出しちゃう?気持ちよーく、たまたまの中に溜まってるもの、一滴残らず絞り出してあげちゃうよ❤❤」 あ~ん、と大きく口を開けて、ずぶずぶと亀頭を頬張り、両手でごしゅごしゅと激しく扱きながら、頭を上下に振り、頬がへこむほど吸引する。 「んぎぃゃあぁぁあっっ❤❤」 齎される暴虐的な快楽によって、僕は恥も外聞もなく悲鳴を上げる。 多少は滝の轟音によって掻き消されるだろうが、下手をすれば、滝の上にまで届いてしまうかもしれない。 龍門寺は興福寺の末寺扱いという事もあり、それほど多くの僧侶が居る訳ではない。 かといって、無人という訳ではないのだ。 もし、誰かにこのような痴態を見られでもしたら………。 そんな危機感も、心のどこかにはある。 しかし、その危機感と向き合うには、与えられる快感が強すぎて、思考が纏まらない。 ぐつぐつと煮え滾る射精欲に、飲み込まれそうになる。 じゅぶじゅぶじゅぶじゅぶと厭らしい音が頭の中に鳴り響く。 (こんなの………無理ぃっ❤❤) 絶望に、心が塗り潰されていく。 抵抗しようとする心が折れ、射精に身構える。 精液がぐるぐると渦を巻きながら上がってきているのがわかった。 その瞬間。 (出ちゃうっ❤❤あっ❤あっ❤も、もうっ❤だめぇぇぇっ❤❤) 「―――ぷはぁっ❤」 絶頂に向けて駆け上がっている最中に真魚が肉棒を吐き出し、さらに根元を両手で強く握って、精液を堰き止めてしまう。 「うあぇっ………??」 突然、快楽が消えて、僕は戸惑いの声を上げてしまった。 そんな僕を上目遣いに見上げ、嬉しそうに笑みを見せる真魚。 「これでも堕ちないなんて、やるじゃん♪道鏡ちゃん❤」 「あ……え?」 訳が分からなかった。 今、僕は完全に“堕ち”ようとしていたのだ。 後、数秒、責められ続けていれば間違いなく僕は、真魚の口中に白濁液をぶちまけていただろう。 「感心感心!玄昉ちゃんなんて、私の頭を掴んで思いきり喉奥にぶちまけたのに。よく我慢したね、道鏡ちゃん」 「げ、玄昉様が………」 あの、思わず糞を付けたくなるほど真面目で勉強以外にほとんど何にも興味を示さない兄弟子が、そのような痴態を晒していたとは。 驚きと共に、心中には羨ましいという感情も湧き起こっていた。 僕も、真魚の柔らかくて温かな口内にあのまま精をぶちまけたかったのだと、思い知らされる。 あの瞬間、僕の脳裏に修行の事など欠片も残っていなかったのだ。 お預けを食らい、涙のように我慢汁を流している肉棒をしこしこと軽く扱き上げる真魚。 それだけでも、全身を貫くような快楽を感じる。 しかし、同時に物足りなさも覚えた。 「なーに、その物欲しそうな目は?もしかして、本当は私のお口にどびゅどびゅって出したかったのかしら?」 「っ、そ、それは………」 もし、頷いたら、してくれるのだろうか。 鼓動が跳ね上がる。 だが、真魚は意地の悪い笑みを浮かべ、 「でも、駄ぁ目♪…素直に、気持ちよくしてくださぁいっ❤って言えない子にはしてあげない❤❤」 「そ、そんなぁ………」 「泣いても駄ぁ目❤」 「な、泣いてなんか……これは滝の雫が……」 「はいはい。じゃ、次♪」 僕の強がりを軽く流して、真魚は自らの乳房を持ち上げて見せる。 白くて、綺麗な乳房。 桜色の先端が、美しく、かつ、どうしようもなく淫らに見える。 柔らかそうで、温かそうで、弾力がありそうで、とても重そうな肉の塊。 「あは。凄い目❤」 ぶるり、と体を震わせえ、真魚がうっとりと目を細める。 僕は、どんな目をしていたのだろうか。 きっと、これまでに浮かべたことがない、獣欲にまみれた顔をしていたのだろう。 真魚は楽しそうに笑い、ゆっくりと左右に広げた乳房の間に肉棒を挟み込んでいく。 「ふわぁぁぁぁぁぁっっっっ❤❤❤❤❤❤」 瞬間、誇張表現でもなんでもなく、極楽が見えた。 ふわふわ。 もふもふ。 もっちり。 もにゅもにゅ。 肉棒を包み込む、極上の感触。 蕩け切った声が漏れるのを、全く抑えられない。 口の端から、だらだらと涎が零れ落ちていく。 「どう?気持ちいいでしょ?」 「気持ちぃぃぃぃぃぃ………❤❤❤」 「もっと、気持ちよくしてあげる♪」 「えっ、あっ、あふぁぁぁぁぁっ……❤❤」 真魚の言葉に、一瞬だけ疑念を抱いてしまった。 これ以上、気持ちいい事など、ありえるのだろうか、と。 だが、それはあり得た。 しかも、圧倒的だった。 乳房に両手を添え、上半身も揺すりながら、左右の乳房を互い違いに動かす。 その谷間に囚われた肉棒は蕩けそうな快感の中でもみくちゃにされ、まるでどろどろに溶けていくような悦楽に包まれる。 「あががががっ………❤❤❤」 快感のあまり、舌の根が震え、言葉にならない。 危険極まりない程の快楽だった。 人間の価値観を、根底から覆してしまいかねないような。 この快楽を味わうためなら、もはやすべてを擲っても構わない。 そんな風にさえ、思ってしまう。 いや、思わされてしまう。 滝行によって凍えた体が人肌のぬくもりで溶かされていく。 同時に、心までも溶かされてしまう。 ぱちゅんっ❤ぱちゅんっ❤もちゅんっ❤もちゅんっ❤ずっちゅんっ❤ずっちゅんっ❤ 真魚の乳房の動きに合わせて、聞くに堪えないほどの淫らな音が耳朶を打ち、脳に響く。 とても、座ってなど居られなかった。 仰向けに倒れ、びくびくと体を震わせる。 「ほらほら❤気持ちいいでしょ❤溜まらないでしょ❤」 ぐりぐりと乳房を動かし、肉棒を締め付け、もみくちゃにし、扱き上げながら、真魚が瞳を輝かせる。 「イきたいなら、イきたいって言って♪ほら❤ほら❤」 僕を追い込もうと、さらに激しく乳房を動かす。 (もうっ、無理ぃぃぃぃっ❤❤……イかせてっ、イかせてくださいぃぃぃっっ……❤❤) 理性の壁は、乳房に肉棒を包まれた時点で、すでに崩壊している。 頭の中ではバチバチと閃光が迸り、もう、射精する事しか考えられなかった。 懸命に、叫ぶ。 いや、叫んでいるつもりだった。 「ひぃぃぃあぁぁっ、がっ、はあぁぁぁぁっ……❤❤❤」 だが、実際には、僕の言葉は一切、言葉の体を為していなかった。 「しぶといわねぇ♪」 紫色の瞳を爛々と輝かせながら、真魚がさらに乳房を激しく動かす。 ばぢゅんっ❤ずぢゅんっ❤もぢゅんっ❤どぢゅんっ❤ぶぢゅんっ❤ぬぢゅんっ❤ 肉と肉がぶつかり合う音が、滝の轟音をも押し退けて辺りに響く。 「――――っ❤❤❤―――っ❤❤❤―――っ❤❤❤」 だが、もはや、僕には屈服の言葉を発する力すらも残っていなかった。 白目を剥き、ぶくぶくと泡を吹きながら、声にならない悲鳴を上げ続けるのみ。 僕が屈服しない限り、射精させるつもりはないのだろう。 真魚は、僕が射精しそうになるタイミングを完全に見切って、後ほんの一瞬というところで乳房の動きを緩やかにしてしまう。 だが、僕が喋れるようになるほどの休憩時間は与えてくれず、再び激し過ぎる快楽責めが再開される。 (こ、こんなの、死んじゃうっっ―――っ❤❤❤だ、誰か、助け、助けてっ……じゃなければ、いっその事、このまま殺して―――っ❤❤❤) 耐えがたいほどの快楽に、思わず死すら願ってしまう。 そんなことが幾度となく繰り返された末、やがて、真魚はゆっくりと乳房の動きを止め、我慢汁に塗れた肉棒を解放した。 「天晴よ、道鏡ちゃん!行基ちゃんなんて、びゅー❤って虹が架かるほど激しく射精しちゃったのに」 (僕も………出したかった………) 内心で、そう主張するものの、ぜぇはぁと荒い息を吐くので精一杯で、言葉にならなかった。 「ちょっと休憩。ほら、道鏡ちゃんも」 手を引かれ、滝壺から出て、飛沫の当たらない位置にある岩に二人並んで腰を下ろす。 「はぁ、はぁ、はぁ………」 濡れた体に夜風が当たって、本来であれば凍えるほど寒いはずである。 だが、今は体が火照って溜まらなかった。 今すぐにでも、真魚を押し倒し、その体を貪り尽したかった。 だが、度重なる寸止めによって体力を根こそぎ奪われ、休憩を欲していたのも確かである。 「道鏡ちゃんは、そこまでして何を成し遂げたいの?」 ここまでの試練に耐え抜いた(と、真魚は思っているのだろう)事で、僕に興味が湧いたらしい。 改まっての問いに、僕は呼吸を整えつつ、自分が仏門に入った経緯を説明した。 「ふーん」 真魚は聞き終えると首を傾げ、 「それってさ。それ、使った方が早くない?」 そう言って指差したのは、湯気が立つほど熱く滾ったままの肉棒だった。 「これを………使う?」 だが、僕には真魚の言葉の意味がよくわからなかった。 「そう。だって、こんなに立派なの、そうそうないよ?大抵の女だったら、こんなの見せられたらもう………あそこが、きゅんきゅんしちゃって、上の口でも下の口でもしゃぶりたくて溜まらなくなるってものじゃない」 「………。そう、なの?」 「そりゃそうよ。だってほら………」 真魚が僕の手を取り、自身の秘所に誘う。 女性のその部分に触れる経験など、無論これが初めてである。 どぎまぎしながらも柔らかな感触に沈み込んでいく指先の感触に集中する。 「私もこんなに濡れてるでしょ」 そう言われても、元々滝でびしょ濡れになっているのだから、よくわからない。 「ぬるぬるしない?」 「……。少し……」 言われてみれば確かに、指先にぬめりを感じる。 これが、“濡れている”という事なのだろうか。 困惑している僕に真魚が身を寄せ、耳朶を甘噛みする。 「日本の婚姻形式は妻問い婚でしょ?結婚しても男女が一緒に住むわけではなく、男性が女性の下に通う訳。つまり、男性はシたい時に女性の家に行けばいいけど、女性はシたくても男性が来てくれないとできない」 「そう………なるな、確かに」 何とか頷くものの、意識の過半は耳元を這い回る唇と、押し付けられる柔らかな肢体にくぎ付けだった。 「だから、悶々としている女性は多い訳。特に、身分が高くなればなるほど、ね」 つぅーっと裏筋を撫で上げられる。 それだけで、先端からぴゅっと我慢汁が噴き出した。 「例えば、私だってそう」 「え………?」 「道鏡ちゃんから見たら、好き放題やっているように見えるかもしれないけど。私も“決まり”に縛られているの」 「………。先に進めるのは、僧侶が試練を耐え抜いた時だけ?」 「そう!」 真魚が笑顔を見せる。 「例え、シたいと思える相手だったとしても、足で扱いただけでどびゅどびゅしちゃったら、そこで終わり。口でも、乳房でも。最後までできる人なんて、それこそ何十年に一人しか現れない」 「なるほど………」 それで合点がいった。 僕は、口に咥えられている時、確かに途中で心が折れた。 あの場で、失格になっていてもおかしくなかった。 にも拘わらず、未だに失格になっていないのは―――真魚が、そう望んだからだ。 僕が屈服の言葉を言えないようにしていたわけだ。 「そんな風に悶々としている女の前に、こぉんなに、太くて❤長くて❤硬くて❤熱い❤おちんちんを差し出したら………どうなると思う?」 僕の両肩に手を置き、真魚がゆっくりと僕の腰を跨ぐ。 ポタポタと、雫が亀頭に落ちる。 それは、水なのか、それとも―――。 「女は―――狂うしかないの❤」 妖艶な笑みを浮かべながら、真魚が腰を下ろす。 ずぶずぶと、肉棒が秘所に飲み込まれていく。 「ぁあんっ❤❤こ、これよっ❤❤初めて見た時から入れたかったのぉぉっ❤❤」 歓喜の声を上げながら、真魚が身を仰け反らせる。 「あっ❤あぁっ❤あぁぁぁぁぁあっ❤❤❤」 だが、僕の口からも激しい喘ぎ声が迸る。 肉棒に幾重もの襞が絡みつき、締め上げ、吸い上げ、奥へ奥へと誘われていく。 先端が、唇のような狭いものに当たる。 本能的に、もっと奥へ突き入れたいと思った。 その欲望のままに、僕は真魚の腰を掴み、己の腰を突き上げていた。 亀頭が、狭い部分を貫いていく。 「んぎぃぃっ❤❤こ、これっ、凄いっ❤❤お、奥までっ❤❤一番奥まで届いてるぅぅぅっ❤❤」 真魚が狂っていた。 白目を剥き、舌を突き出し、涎を垂れ流しながら、びくんっびくんっと体を痙攣させ、きゅうっきゅうっと肉棒を締め付けてくる。 その快楽に、僕が耐えられるはずもなかった。 「も、もうっ……❤❤」 「いいわっ❤来てっ❤❤私の中に全部出してぇぇっ❤❤」 「うおおおおおっ―――っっっ❤❤❤」 真魚の腰を掴み、無我夢中で腰を振る。 やめろと言われても、もはや止まれなかっただろう。 真魚の甲高い喘ぎ声が脳裏に響く。 ぎちぎちと締め付けられた膣を行き来する度、頭がおかしくなりそうな快楽が全身を貫く。 そして―――。 僕は、ありったけの精を、真魚の最奥に注ぎ込んだ。 どびゅどびゅるるるるっ❤❤どびゅぅぅぅぅぅぅっ❤❤❤びゅくんっびゅくん❤びゅるるるるっ❤❤どびゅぅぅぅっ❤❤どびゅどびゅっ❤❤びゅくびゅくっ❤❤ 「ひぃあぁ――――っっ❤❤」 真魚が仰け反り、絶叫する。 その爪が肩に食い込み、血が迸る。 だが、そんな事どうでもよかった。 どびゅどびゅるるるるっ❤❤どびゅぅぅぅぅぅぅっ❤❤❤びゅくんっびゅくん❤びゅるるるるっ❤❤どびゅぅぅぅっ❤❤どびゅどびゅっ❤❤びゅくびゅくっ❤❤ 絶頂のままに真魚が肉棒を締め付ける。 射精の最中であるにもかかわらず、その快楽が僕をさらなる絶頂へと押し上げる。 「もっと、もっとっ!!」 目を血走らせながら、快楽を渇望する。 どびゅどびゅるるるるっ❤❤どびゅぅぅぅぅぅぅっ❤❤❤びゅくんっびゅくん❤びゅるるるるっ❤❤どびゅぅぅぅっ❤❤どびゅどびゅっ❤❤びゅくびゅくっ❤❤ 「いいわっ❤もっと突いてっ❤私の事、めちゃくちゃにしてぇぇっ❤❤」 真魚の言葉で、僕の中の箍が完全に外れてしまった。 想像以上に軽い体を持ち上げ、滝壺の中に押し倒し、上から伸し掛かって圧し潰すように無茶苦茶に腰を動かす。 真魚は僕の腰に両足を、首に両腕を巻き付け、叫び、喘ぎ、痙攣する。 その度に肉棒が締め付けられ、真魚の最奥に精をぶちまける。 さらに、岩に手をつかせ、尻を突き出させて、獣の如く背後から貫く。 覆い被さり、その豊かな乳房を握りしめ、むちゃくちゃに揉みたてながら、がくがくと腰を振り続け、どびゅどびゅと精を注ぎ続ける。 二人の結合部から流れ出した白く濁った液体が、神聖なる水の流れに白い筋を刻んでいく。 正面から抱きしめ合って。 後ろから抱きかかえて。 僕の上に真魚が馬乗りになって。 様々に体位を変えながら、僕たちは夜が白々と明け始めるまで、交わり続け、僕は真魚の中にありったけの精を注ぎ続けた。 「はぁ❤はぁ❤……最高❤❤」 僕の白濁液に塗れながら、真魚がぐったりと地面に横になる。 「こんなに激しいの………義淵ちゃん以来だわ………❤❤」 「お、お師匠様………」 今は、まるで枯れ木のような老僧である義淵も、若かりし頃に龍門山で修行をしている。 ここまでの流れで、その名が出るのも半ば予期していた。 その頃の師に並んだというのは、単純に嬉しい事だった。 それどころか、良弁様、玄昉様、行基様と言った、尊敬すべき兄弟子たちを越えることができたのだ。 この国の仏教界を担っていくのであろう、偉大な男たちを。 ただ一人を除いて。 「まぁ、義淵ちゃんはその後、龍も調伏しちゃったぐらいだし。さすがよね」 そんな僕の思いを汲み取ったのか、真魚が笑う。 義淵僧正の名を世に知らしめたのが、飛鳥の地で暴れまわっていた龍を調伏した事だ。 一説によれば、天武天皇の皇子で非業の死を遂げた大津皇子が変じたものと言われている龍である。 龍蓋寺にしろ、龍門寺にしろ、この功績によって建立が許されたものだ。 龍蓋寺は、義淵にとって幼馴染である草壁皇子が住んだ岡宮の跡であり、龍門寺は若い頃に修行をしたという神仙境・龍門山に国家の安泰と藤原氏の栄昌のために建立したと言われている。 「頑張って、偉くなってね♪」 僕の顔を覗き込んで、真魚が微笑む。 その横顔を朝日が照らしていた。 僕はそれを、とても美しいと思った。 もうくたくただったが、必死に手を伸ばして、その頬に触れる。 真魚は、嬉しそうに頬ずりをして、 「―――今夜も修行よ♪道鏡ちゃん」 楽しそうに、そう言うのだった。 その時、どたどたと複数の気配が近づいてきた。 「って、あーーーっ!!真魚!!何やってるの!」 そして、素っ頓狂な声が上がる。 「氷魚」 真魚が、チッと舌打ちを漏らす。 やってきたのは、やはり美しい女性。 但し、髪は青く、瞳は紅だった。 「抜け駆けですよ、これは」 さらに、もう一人。 銀色の髪に、翠の瞳。 「伊魚まで……」 真魚が諦めたように肩を落とす。 新たにやってきた二人は、既にぐったりとしな垂れている僕の肉棒を見て、ごくり、と唾を飲み込む。 「だったら今日の修行は、私だからね!」 氷魚と言う名前らしい女性が、僕の右腕に抱き着く。 「ならば、明日は私が」 伊魚と言う名前らしい女性が、僕の左腕に抱き着く。 左右から押し付けられる柔らかな感触に、力を失っていたはずの肉棒がむくむくと頭を擡げる。 「凄い………」 「これなら………」 氷魚と伊魚が顔を見合わせ、笑みを浮かべる。 『むしろ、今から始めましょう♪』 見事に重なった声。 「だったら、私も!」 真魚がそんなことを言い、亀頭にむしゃぶりつく。 「あっ、ずるいっ!」 「貴女は十分堪能したんでしょう!」 氷魚と伊魚が非難の声を上げつつ、竿に左右から吸い付いてくる。 僕は、3人が齎す快楽に悶え、喘ぎ声を上げながら、今更ながらに師の言葉を思い出していた。 ―――気を付けていってきなさい。但し、仙人“達”には気を付ける様に。 あれは、冗談ではなかったのだ。 その後、約半年間の修行を終えた僕は―――いや、儂は、真魚の助言に従い、持って生まれた肉棒を駆使して、出世の階段をひた走りにひた走った。 まずは、寺の檀家衆の奥方を虜にした。 皆、最初こそ抵抗するものの、大抵の場合は儂の肉棒を見るなり大人しくなった。 その瞳をうっとりと蕩けさせ、頬を上気させ、秘所をしとどに濡らす奥方を犯して犯して犯しまくった。 そこからは芋づる式である。 最近、夫婦仲がうまくいっていない夫婦の情報を聞き出し、“気鬱”に効く治療を施すという名目で寺に呼び出し、虜にする。 そして、また次の相手を紹介してもらう。 その繰り返し。 或いは、お参りにきた良家の子女を虜にし、貴族の館に奉公に出させ、やんごとなき身分の女性たちの寝所に夜這う手引きをさせる。 そうして、虜にした女性の数は、2000人を優に超えただろうか。 正確な人数など、もう覚えてはいない。 そして、761年。 遂に、儂は至高の御方の寝所へと足を踏み入れることになった。 聖武天皇を父に持ち、臣下から初めて皇后に取り立てられた藤原氏出身の光明皇后を母に持つ御方。 日本史上6人目の女帝である第46代・孝謙天皇その人である。 既に758年に位を淳仁天皇に譲られ、今は太上天皇となられている。 平城宮改修に際し、一時的に遷された近江国保良宮にて、“気鬱”の治療をせよと命じられたのだ。 命令を受けた時、文字通り儂は小躍りして喜んだ。 かつて女も知らぬ初心な青年僧侶に過ぎなかった儂も、既に61歳になっている。 まだまだ常人に負けるつもりはなかったが、それでも若い頃に比べれば精力は減退しつつあった。 物部氏を復興させるという夢を果たすための猶予は残り少なくなっていたのだ。 *** 重々しい墨染めの僧衣に身を包んで畏まる儂に、御簾の向こうから声がかけられる。 「―――そなたが、道鏡か」 「はい」 人払いもされ、他に人影もない。 それは、太上天皇様の指示であり、儂の意思でもある。 太上天皇様のそば近くに仕える女官はすべて、儂の虜だ。 明日の朝まで、誰も、この部屋にはやってこない。 「………治療を」 期待と不安、興奮と後ろめたさ、様々な感情を内包したか細い声で命じられる。 「承りました」 儂は無遠慮に立ち上がり、墨染めの僧衣を脱ぎ捨てた。 60歳過ぎとは思えぬ、筋骨逞しい裸身。 太上天皇様が息を飲む気配が、御簾の向こうから伝わってくる。 「失礼致します」 一言断ってから、儂は御簾を開けて、奥へと踏み入れる。 黒く、艶やかな長い髪を蓄えた太上天皇。 その視線が、儂の肉棒を捉えるや否や、瞳が大きく見開かれ、はふっ❤と、その唇から甘い吐息が漏れていく。 「誠に………凄い❤」 欲望に蕩けきった眼差しを浴びつつ、大胆に歩み寄る。 既に我慢汁を滲ませた醜い肉棒を、高貴なる顔の眼前に突き出す。 「ぁ………❤❤」 その淫らな匂いを嗅ぐだけで、女は濡れていく。 「どうぞ、お好きなようになされませ」 促すと、おずおずと、嫋やかな白い手が伸ばされ、肉棒が握られる。 「っ―――」 そのあまりの熱さに驚いたのか、びくんっと手を引くが、少しすると再びゆっくりと握る。 「太くて………あぁ、何たる熱さ………」 ぴくぴくと震える亀頭にゆっくりと舌を伸ばし、我慢汁の雫を舐めとる。 「あはぁっ………❤❤」 上品さなどかなぐり捨てて、亀頭にむしゃぶりつく。 唾液をまぶし、じゅるじゅると啜り、唇と頬で締め付け、舌を這わせる。 全身の細胞が歓喜する。 脳がぐずぐずと溶けていく。 張り裂けそうなほどに鼓動が高鳴り、下腹部がきゅんきゅんと疼く。 「出しますぞ」 宣告するや否や、亀頭が口一杯に膨れ上がり、弾ける。 どぶどぶと、大量の白濁液が喉を打つ。 「おえっ、ごほっごほっ………!!」 初めての経験に顔を背け、えずき、白濁液を吐き出す。 肉棒はそれでも拍動を止めることなく、びゅくびゅくと震えながら、大量の白濁液が太上天皇の横顔や黒髪、着物までを白く染めていく。 強烈な匂いが部屋中に満ちる。 その匂いを嗅ぐだけで、まるで酒に酔ったかのように酩酊し、体がますます燃えていく。 「道鏡………❤❤」 小娘のような甘い声が漏れる。 「御意」 儂は頷き、その細い体を掻き抱く。 「あぁっ……❤❤」 それだけで、歓喜の吐息が漏れる。 生涯独身であることを義務付けられるのが、女帝である。 41年の人生で、その身に触れた男は、儂が初めてだろう。 だからだろうか。 既に老女と言われてもおかしくない程の年齢でありながら、その肌はきめ細かく、美しく、しなやかだった。 男に抱かれることを夢見ながら、一体幾千の夜を悶えながら過ごしてきたのか。 「力を抜いてくだされ。この道鏡めが、天上の極楽へと誘って差し上げます」 「はい………❤」 用意されていた寝具の上に、ゆっくりと至高の身を横たえる。 首筋に顔を埋め、柔肌に舌を這わせつつ、まろやかな膨らみをこねくり回し、既に濡れ切った秘所をゆっくりと解す。 緊張に強張っていた体は徐々に花開き、男を惹きつける馨しい香りを放つ。 (至高のお方と雖も、女であることに変わりはない………) 細い足を小脇に抱え、洪水のように愛液を溢れさせる秘所を、ゆっくりと肉棒で貫いていく。 膜を破る感触。 太上天皇が目を見開き、舌を突き出し、体を痙攣させる。 ゆっくりと腰を動かし、その身に、儂の肉棒の形を覚え込ませていく。 その最奥に精を放つ度。 女が絶頂する度。 両者の体はどんどん離れがたいものへと変わっていく。 そして、女は悟るのだ。 自分を満たしてくれる肉棒が、この世にまたとない事を。 そして、すべてを捧げてでも、その身を貫いてもらいたいと冀う事になる。 二つの裸体が汗にまみれ、湯気が立つ。 そう、弓削が立つのだ。 日陰を生き、虐げられるものとしてではなく、誉れ高く、雄々しき神の末裔として。 その日、太上天皇の宮殿からは夜通し、随喜の叫びが鳴り止むことはなかった。 *** 太上天皇の寵臣となった儂は、763年には「少僧都」に任じられ、764年には権力を握る上で最大の障害となる太政大臣・藤原仲麻呂を誅して、「太政大臣禅師」になった。 同年、太上天皇は重祚され、第48代・称徳天皇として即位なされた。 765年に儂は「法王」に任じられ、意のままに国政を操れるようになった。 親戚に預けていた弟の浄人も、従二位大納言にまで出世を重ね、その他近しい一門の者も次々に登用し、五位以上の位階を有する者は10人に達した。 まさにこの世の春。 弓削の春である。 だが、儂は満足しなかった。できなかった。 ここまで来たならばもう一歩。 この国のすべてを手に入れてみたくなったのだ。 あと、一歩。されど、一歩。 どのような権力者でさえも、越えることの許されない一歩だ。 だが、儂の腕の中で、喘ぎ、咽び泣きながら快楽を貪る「天皇」を見下ろす度、どうしようもなく思ってしまうのだ。 このお方と自分。 何が違うのだ、と―――。 大それた野望だという事は勿論わかっている。 だからこそ、慎重に事を進める必要があった。 天皇に譲位を迫る事は容易い。 最初は抵抗しようとも、一晩も責め続ければ折れるだろう。 だが、それでは群臣たちが納得しないのは目に見えている。 権力者が政争の結果、権勢を失い、失意の中で死んでいくのを何度も見てきた。 729年には長屋王が。 740年には藤原広嗣が。 745年には、兄弟子でもある玄昉が。 750年には吉備真備が。 756年には橘諸兄、奈良麻呂父子が。 そして、764年には藤原仲麻呂が。 彼らは、天皇位を狙った訳でもない。 にもかかわらず、失脚する事となった。 彼らよりも遥かに大それた野望を実現させるには、「神の意思」が必要だった。 即ち、神託である。 そのために儂は、旧物部氏の人脈―――勿論、女性たち―――を辿って、物部系の一族である中臣習宜阿曾麻呂(なかとみのすげ・あそまろ)と接触した。 そして、彼の妻を堕とし、その妻を介して、阿曾麻呂を取り込んだ。 766年、下級官人に過ぎなかった彼を従五位下に取り上げ、767年には「豊前介」に、768年には「太宰主神」に任じた。 769年には弟の浄人を「太宰帥」に任じて準備を整えると、儂自身が宇佐八幡宮に赴き、禰宜である辛嶋勝与曾女(からしまのすぐりよそめ)を堕とした。 神聖な神職であろうとも、女は女。 なかなか強情に抵抗したものの、20回ばかり精を最奥に注いでやったら、自分から体を開くようになった。 都に戻った儂は、宇佐八幡宮から神託が奏上されるのを待つだけでよかった。 そして、769年5月。 待ちに待った神託が齎される。 即ち、「道鏡を皇位に就かせたならば天下は泰平である」という八幡神のお告げである。 しかし、ここで誤算が起きた。 完全に虜にしていたと思っていた称徳天皇が、神託を確認すると言い出したのである。 一瞬、慌てたが、神託を確認するために遣わされる勅使が女官の和気広虫だと聞いて安堵した。 無論、彼女もまた虜にしていたからだ。 だが、ここでまたもや事態が変動する。 和気広虫が病弱で長旅に耐えられそうにないという理由で、勅使が交代することになったのだ。 新たに勅使に任命されたのは、和気清麻呂。 藤原仲麻呂の乱でも活躍した武人であり、「近衛将監」の地位にある男である。 性格は頑固一徹。 権力に阿るという事を知らず、ただただ皇室への忠義を一心に貫くという男だった。 何とか懐柔しようと試みたが、この男には酒も地位も金も女も効果を発揮することができなかった。 突然の交代だったせいもあって、対応策を練る準備も満足にできなかった。 いっその事殺してしまおうと刺客も放ったが、あっけなく返り討ちにされてしまった。 九州に下向した和気清麻呂は、どのような手段を用いたのかはわからないが、辛嶋勝与曾女を翻意させてしまった。 新たに下された神託は、「天の日継は必ず帝の氏を継がしめむ。無道の人は宜しく早く掃いて除くべし」というもの。 ここに、栄華を極めた儂の命運も尽きる事となった。 770年には、頼みの綱であった称徳天皇が崩御され、後ろ盾をも失ってしまった。 新たな後ろ盾を得ようにも、70歳を過ぎ、儂の逸物も物の役に立たなくなっていた。 「造下野薬師寺別当」に任じられた儂は下野国に下向し、その地で没する。 浄人と、浄人の子である広方、広田、広津の三人は捕えられ、土佐国に配流となった。 かくして、夢は―――破れたのだった。 夢を打ち破った和気清麻呂は、俗世では従三位に出世する。 だが、死後の出世は、俗世でのそれに輪をかけて凄まじい。 後世、第121代・孝明天皇に功績を認められ、「神階正一位」と「護王大明神」の神号を賜り、神となってしまうのだから。 それに比べて、儂は、「道鏡は 座ると膝が 三つでき」などという川柳を読まれる始末。 分を越えた望みなど、やはり持つべきではないのだろうか。 成人仪式 2020年、令和2年1月。 全国で122万人が成人を迎えた。 令和初めての成人式だと、メディアは大盛り上がりだ。 全国的に参加者が減少しつつあるとも言われるが、一部地域では1年以上もの間、コツコツと貯金して派手に着飾る一世一代の晴れ舞台と見做される場合もある。 だが、○○県××市△△村、瀬戸内海の離島に浮かぶ過疎村において行われる成人式は、実に寂しい限り。 何しろ、参加者は僕一人だけなのだから。 そして、僕はこの島の最年少の住人である。 限界集落などという言葉が虚しく聞こえるほど、消滅寸前なのがこの村の状況なのであった。 そんな僕とて、普段からこの島に住んでいるわけではなく、東京の大学に通っている身だ。 彼女もおり、将来的にこの島に戻ってくるつもりなど毛頭ない。 小さな公民館に村の人たちが30人ばかり集まって、僕の成人を祝ってくれる。 少ない様に感じるかもしれないが、これでも村民の出席率はほぼ8割だ。 小さな村なので、全員見知った顔ばかりで、こそばゆいような、恥ずかしいような、ちょっと嬉しいような複雑な気分になる。 正直、来るかどうかさえ迷った。 だが、彼女に言われたのだ。 顔見せだけでも行くべきだと。 それに、10年前に海難事故で無くなった両親にも、成人した事を報告すべきだと。 現代っ子の割に、そういう所はしっかりしている。 そんなところも、彼女の美点だと僕は思っている。 嬉しそうにしている老人たちを見るにつけ、その助言に従ってよかったという思いも込み上げてきた。 サイズが合わないのか、入れ歯をふがふが言わせながらの村長の訓話は涙混じりだった事もあって半分どころか、1割も聴き取れなかったが。 村の古老たちは、日本酒を煽り、顔を赤くし、僕の子供の頃の思い出話に花を咲かせる。 彼らにはほんの最近の出来事でも、僕にとっては物心つくかつかないか頃の事で、記憶にはほとんどない。 感涙に咽びながら話を振られても、微妙な相槌を打つぐらいしかできなかった。 微妙な居心地の悪さを感じていると、 「楽しんでますか、海斗さん」 「っ、あ、はい」 突然声を掛けられて、思わず背筋を伸ばしてしまう。 不明瞭な老人たちの話声の中にあって、その明瞭な声音だけが異彩を放っていた。 「どうぞ」 傍らに座り、徳利を差し出す女性。 「ど、どうも」 盃で受けながら、頬が熱くなるのを感じる。 それは、飲み慣れない酒のせいばかりではない。 声をかけてきた女性が、あまりに美人だったからだ。 僕より少し年上だろう。 少し目尻の下がった穏やかな眼差し、すべすべと柔らかそうな頬、柔和な笑みを湛える唇。 こんな島にはまるで似つかわしくない、さながら天女の如き女性だ。 (文字通り、掃き溜めに鶴だな………) 思わず見蕩れてしまう。 「私の顔に、何かついてます?」 「あっ、い、いえ、すいません……」 くす、と笑みを零しながら小首を傾げる仕草も、とても可愛らしい。 彼女の名前は、夏川萌さん。 ヴェイン・リゾート開発に勤めるバリバリのキャリアウーマンである。 そんな彼女がこの島にいるのは、社会貢献活動も兼ねた事業の一環として、この過疎の島を何とか活性化させる為なんだとか。 島にとっては、まさに救いの女神と言った所だ。 (まぁ、効果が出てるとは言い難いけど………) この場にいる老人たちも、あと10年もすれば半分ぐらいになっているのではなかろうか。 この村が消えるのは、まさに時間の問題だ。 (CSRだかなんだか知らないけど、こんな辺鄙な場所に飛ばされた萌さんも可愛そうだなぁ………) とさえ、思う。 「そう言えば、村長さんに聞きましたよ。海斗さん、学生ながら社長さんでもいらっしゃるそうですね。凄いです!」 僕がそんな事を考えているとは想像だにしていないのであろう萌さんは、にこにこと僕が空けた盃に酌をしてくれる。 これほどの美女に目を輝かせながら手放しで褒められて、悪い気はしない。 「ま、まぁ、まだ漸く軌道に乗り始めたばかりって感じですけどね………」 火照った頬を掻きながら照れ笑いを浮かべる。 「ご謙遜を。皆さん、この島の誇りだっておっしゃってましたよ。こちらには戻ってこられないんですか?」 笑顔を浮かべながら、萌さんがぐっと距離を詰めてくる。 膝と膝が密着し、シャンプーなのか香水なのか、とても甘い香りが鼻腔を擽ってくる。 「あ、あはは……そうですね。今のところ、その予定は………」 乾いた誤魔化し笑いを浮かべる。 「海斗さんのお力添えが頂ければ、この島の活性化にもより寄与できるかと思ったのですが………」 「すいません、お力になれず」 正直に言えば、少し心が揺れてしまったが、だからと言って島に戻ってくるつもりにはなれなかった。 「残念です………」 悲しそうな顔をしながら、萌さんがさらに距離を詰めてくる。 (ち、近すぎじゃないか………) そう思いつつも、思わずごくりと生唾を飲み込む。 萌さんも酒に酔ってきたのか、第2ボタンまで外されたブラウスの緩くなった胸元から深い深い谷間が覗いている。 (無防備にも程があるって、萌さん……。てか、でかっ……H……いや、Iぐらいあるんじゃないか………) 目線を逸らそうと思っても、気づくといつの間にか、深い谷間に吸い寄せられてしまう。 老人ばかりの環境にいるせいで、男のそういう視線にも鈍感になってしまったのか。 萌さんは何も言わない。 先ほどのは冗談半分だったのだろう。 もう笑顔に戻って徳利を差し出してくれる。 僕はそれを受け、盃を煽りながらちらちらと萌さんの肢体を盗み見る。 何度も言うが、無茶苦茶可愛い。 お返しに萌さんの盃にも酒を注ぐ。 他愛もない雑談でさえ、とても楽しい。 暫く時が過ぎ、何人かの老人たちが船を漕ぎ始め、なんとなくそろそろ解散かという雰囲気が辺りに漂い始めた。 その時だった。 胡坐を掻き、膝の上に置いた手、その甲に浮かんだ血管をなぞるように萌さんが指を這わせてきたのは。 「っ…」 ぞくぞくとした感覚が背筋を這い上ってきて、顔がさらに熱くなる。 「この後、うちにいらっしゃいませんか?飲み直しながら、お話ししましょう?」 耳元に顔を近づけ、甘く囁かれる。 どくどくと鼓動が高鳴った。 酒に酔って上気した頬。とろんと蕩けた瞳。 凄艶としか言いようがない色香に、くらくらする。 脳裏に、彼女の顔が浮かんだ。 「ね?」 萌さんがさらに身を寄せてきて、僕の腕が柔らかな感触に埋もれる。 その魅惑の感覚に、彼女の顔が消し飛んだ。 *** 宴会がお開きになった後、僕は萌さんに誘われて彼女の家にやってきた。 集落からはちょっと離れた、林の中にある一軒家だった。 「野菜を作れる庭もあって家賃が5千円。とてもありがたいです。さ、海斗さん、どうぞお上がりください」 「は、はい………」 返事をする僕の声は固い。 先ほどは彼女の誘惑に簡単に頷いてしまったが、1月の冷たい夜風に当たった事で、多少酔いも覚めた今となっては、罪悪感に胸が痛んでいる。 だが、今更断って帰るのも気が引けた。 そもそも、萌さんは飲み直しながら、お話ししましょうと誘ってくれただけだ。 その言葉と、柔らかな身体の感触に勝手に淫らな妄想を膨らませたのは僕だ。 もし萌さんにその気がないのに勝手に妄想しているのだとしたら、死ぬほど恥ずかしい。 (ただ、飲んで話すだけ。もしそれ以上の事になりそうだったら、その時に改めて断ればいい………) そう覚悟を決めて、萌さんの家に足を踏み入れる。 萌さんは居間のエアコンと炬燵のスイッチを入れ、 「寒いので、熱燗にしましょうか?」 硬くなっている僕を振り返って尋ねる。 「は、はい、なんでも……」 「分かりました。寒いので、炬燵に入っててください」 「はい……」 言われるまま、炬燵に下半身を入れる。 じんわりと温まってくる感じが、実に心地いい。 暫く待っていると、お盆に徳利と御猪口、それにおつまみを載せて萌さんがやってきた。 炬燵の反対側に体を滑り込ませた萌さんが御猪口を僕に渡してくれ、徳利を傾ける。 「あ、やります」 「ありがとうございます」 徳利を受け取り、萌さんの御猪口に酒を注ぐ。 「それでは、改めて。成人おめでとうございます♪」 「あ、ありがとうございます」 音が出ない程度に御猪口を触れさせ、酒を口に含む。 舌が火傷しそうなほどの熱燗の豊潤な香りが口一杯に広がり、飲み込むと食道や胃の辺りまでがじんわりと温かくなってくる。 「はわぁ、美味し♪」 幸せそうに頬を綻ばせる萌さんは、これまたとても可愛かった。 それからしばらくは、他愛のない世間話に終始した。 僕の東京での暮らしや、萌さんの島での暮らし。 今後の人生設計や、今の仕事の話などなど。 萌さんとの会話は楽しく、彼女が勧め上手な事もあって、お酒もどんどん進んだ。 彼女も同じだけの量を飲んでいるはずなのに、僅かに頬が上気しているぐらいで、あまり酔った様子はない。 そして、その頬を上気させている姿が、また溜まらなく可愛いのだ。 「萌さんとこうして飲めてるだけでも、島に帰ってきた甲斐があったなぁ………」 ふわふわとした酔いと幸福感に揺蕩いながら、思わず本音が声となって漏れてしまう。 「ふふ。私もですよ、海斗さん」 萌さんが目を細め、ぺろりと唇を舐める。 「こんなに楽しいのは、この島に来て初めてです。同年代の方とお話しするのも、実は久しぶりで」 「まぁ、そうですよね……ん?」 頷きつつ、足先に微かに違和感を感じた。 最初は、たまたま萌さんの足とぶつかってしまったのかと思った。 だが、その感触は離れるどころか、脛の辺りをすりすりと何度も上下する。 「どうかしました?」 思わず視線を下げたところで、萌さんが尋ねてくる。 「あ、いえ………っ……」 その声に反応して視線を上げて、ぞくり、と背筋が震えた。 萌さんが笑っていたから。 だが、それはこれまでの穏やかな笑みではなく、悪戯っ子のような笑みで。 片足だけだった感触が、両足になる。 さらに脛から、内ももへとゆっくりと進んでくる。 間違いなく、萌さんの足だ。 ゆっくりと、まるでナメクジが這いまわるような速度で内ももを撫でられる。 妖しい感覚に呼吸が荒くなり、顔が赤くなる。 酒によって促進された血行が下半身に流れ込み、ズボンにテントを作り出す。 「もしかして、炬燵の中に何かいます?」 「あ、いや、何か、というか………」 「たまにあるんですよ。靴下かなぁって思いながら転がしてたら、ネズミだったりとか」 「は、はぁ……んんっ……」 生返事が跳ねる。 とん、とテントの先端を軽く踏まれて。 「確かめてみますね………❤」 萌さんは後ろに両手を突き、上半身を反らしながら、足を伸ばす。 ぐにぐにと柔らかな足裏が、テントをこねくり回す。 「あっ、んんっ………」 「ふふ。ほんとですね。何かいるみたいです。何か硬いものが❤」 片足がテントをこねくり回し、もう片足が内ももを厭らしく撫であげる。 「んぅっ……あぁっ❤」 僕はぎゅっと手を握り、歯を食い縛って耐える。 だが、もぞもぞと萌さんの足が動く度に生み出される快感に甘い声が漏れてしまうのを止められない。 「あら。大変❤……これ、海斗さんのズボンの中に入っちゃってるんじゃないですか?」 ふふ、と笑みを零しながら、萌さんが首を傾げる。 「海斗さん。ズボンのチャック開けてください。私が確かめてあげます❤」 「そ、それはっ、だ、だめっ……ふあぁっ……」 「あら。ダメなんですか?どうしてです?」 両足で挟まれるようにして、テントを扱かれる。 齎される快感に奥歯が震え、口中に唾液が溢れる。 「ぼ、僕にはっ……か、彼女がっ……」 それでも何とか、僕は首を横に振った。 しかし、萌さんは不思議そうな顔をする。 「彼女さんがどうかしました?……今はただ、海斗さんのズボンの中にネズミが入っちゃってたら大変だから確認しましょう、というお話ですよ?」 詭弁だ。 詭弁だったが、酒と欲情によって濁り切った僕の抵抗に罅を入れるには十分だった。 「噛まれたら大変❤病気に感染しちゃうかもしれません❤だから……ね?」 優しく諭すような言葉と同時に、とん、とん、とテントの先端を柔らかくノックされる。 その甘い感触が、僕の心のカギを抉じ開けていく。 「大丈夫ですよ、海斗さん。ここには私たちしかいませんから❤」 萌さんの優しい声音に促されるように震える手を炬燵の中に差し入れ、チャックを下ろす。 その隙間に萌さんの足が入り込み、器用に親指と人差し指でペニスを掴み、パンツの合わせ目から引きずり出す。 そのまま、カリ首から亀頭の辺りを上下に扱かれる。 「あっ❤あぁっ❤❤」 先ほどまでとは段違いの快感に僕は溜まらずに炬燵に突っ伏した。 我慢汁が滲みだす先端をタップされ、さらに、もう片足が竿を撫で上げる。 「あら。ネズミどころか、物凄く硬い蛇がいましたね♪」 萌さんは手酌で御猪口に酒を注ぎ、飲み干す。 「とぉっても、硬くて❤とぉっても、熱くて❤なんだかヌルヌルしてますよ❤」 にこにこと笑みを浮かべながら、硬さや大きさを確かめるように足先がペニスを這い回る。 その感触にペニスはますます硬く勃起し、先端からは止め処なく我慢汁が溢れ出す。 「炬燵に入っちゃう悪い蛇さんは、このまま退治してしまいましょう❤」 楽しそうな笑みを浮かべたまま、限界まで勃起したペニスを両足で挟み込み、上下に扱き上げられる。 「おっ❤おふっ❤んんんっ❤❤」 僕は炬燵の天板にぽたぽたと唾液を零しながら、ただ喘ぐのみ。 頭の片隅では、この異常な状況から逃げ出すべきだという警鐘が鳴り続けていた。 だが、ペニスを柔らかな足裏で挟んで扱き上げ、亀頭をぬるぬると責められ、親指と人差し指に挟まれて扱かれ、玉をたぷたぷと転がされ、爪先で竿や内ももをつぅーっと撫でられるという巧みな技巧の前に頭の中はあっという間に桃色に染められ、思考力が奪われていく。 年上の女性に簡単に、しかも足なんかで弄ばれ、無様に喘ぎ声を上げさせられている事に、屈辱と共に言い知れぬ興奮さえ覚える。 溢れ出した我慢汁が萌さんの足を汚し、扱き上げられる度にぐちゅっぐちゅっと厭らしい音が炬燵の中から聞こえてくる。 その音を聞くうち、身体の奥底から、抑えようもなく射精欲がこみ上げてきた。 「あっ❤も、萌さんっ❤❤も、もうっ……❤❤」 「大丈夫ですよ、海斗さん。もうすぐ蛇さんが降参しますから。白旗びゅーって上げて❤」 萌さんはにこにこと笑いながら、さらに足の動きを激しくして、僕を絶頂へと容赦なく追い込んでいく。 僕の体も、炬燵も、がくがくと震えだす。 そして―――きゅっとカリ首を捻られたのが止めとなった。 「あぁぁぁぁっ❤❤で、出るぅぅぅぅぅっっっ❤❤」 どびゅっ❤びゅるるるるっ❤❤びゅくびゅくびゅくっ❤❤びゅるるるるっ❤❤❤ 頭の中で白い光が何重にも閃き、炬燵の中で僕は盛大にザーメンをぶちまけてしまった。 びゅくびゅくと脈動するペニスを扱き上げ、最後の一滴まで搾り取ってから、萌さんが炬燵布団を捲って中を覗く。 「わぁ❤蛇の体液でどろどろになっちゃいましたね❤」 その白々しい言葉に僕は反応する事も出来ず、ただぜぇはぁと荒い息を吐くばかり。 真冬だというのに、まるで全力疾走したかのように全身に汗が噴き出していた。 そのせいで気づけなかった。 萌さんの姿が消えたことに。 そして、股間に感じる違和感。 あっ、と思った次の瞬間には、ペニスが柔らかくて温かくて、ぬるぬるの感触に覆われていた。 じゅぶっ、ずちゅっ、じゅるるるるっと何かを啜り上げる淫らな音が炬燵の中で響き、 「あぁぁぁっっ❤❤」 今度は背を仰け反らせて、天井に向かって喘ぎ声を発する。 「蛇さん、まだ元気みたいです❤これは、退治のし甲斐がありますね❤」 炬燵の中から、くぐもった萌さんの声がする。 まだこの茶番を続けるつもりらしい。 射精したばかりで敏感になっている亀頭をぺろぺろと舐められ、カリ首を唇で締め付けられ、精液と唾液に塗れた竿を扱かれ、さらに玉まで掌で転がされる。 僕は逃げ出す事すらできず、ただ喘ぐばかり。 口中深くまでペニスを飲み込まれ、頬粘膜で締め付けられると、思わず気が遠くなってしまう。 じゅっぷじゅっぷと淫らな音を立てながら頭を上下に振ると、その動きに合わせて炬燵がガタガタと揺れる。 逃げなきゃ、とか。 止めさせなきゃ、とか。 なんでこんなことに、とか。 彼女に申し訳ない、とか。 様々な思いがぐるぐると脳裏を過るものの、僕の体を動かすには至らない。 (あの萌さんが……僕のを………) あの、天女のように美しい萌さんが。 そんな事を思ったら、無性に炬燵の中が見たくなった。 さっきまで、ぴくりとも動かなかった手が動き、炬燵の布団を捲りあげる。 「❤」 布団の中で、僕のペニスを頬張る萌さんが上目遣いに僕を見る。 その、楽しそうな瞳と目が合った瞬間、腰の奥が甘く痺れ、射精感が込み上げてきた。 「萌さんっ、出るっ❤❤」 「いいふぉ❤だひへ❤」 ペニスを頬張ったまま、萌さんが答え、じゅるるるるっと頬がへこむ程先端を吸引する。 その快楽に、僕は2度目だというのに1度目以上の勢いで精を放った。 びゅくんっ❤どびゅっ❤びゅるるるるっ❤❤びゅくびゅくびゅくっ❤❤びゅるるるるっ❤❤❤ 大量の噴射にも動じることなく、萌さんは吐き出された精液を飲み干していった。 その白い喉が動く度、僕自身が飲み込まれているかのような錯覚を覚える。 最後の一滴まで飲み干し、ちゅぽんっと小気味よい音を立てながら、ペニスを吐き出す。 「ふぅっ、一杯出ましたね~❤」 「萌さん……も、もうこんな事止めませんか?」 2度の射精で正気を取り戻した僕は、楽しそうな萌さんにそう声をかけた。 萌さんは僕をちらりと見やった後、炬燵の中から這い出そうとする。 押し付けられる身体の柔らかさに、どぎまぎしてしまう。 だが、上半身が出たところで、その動きが止まった。 「………」 僕の視線は、萌さんの深い深い谷間にくぎ付けになる。 その位置はちょうど、ペニスの直上。 両腕で自身の体を支えている萌さんが力を抜けば。 或いは、僕が腰を突き上げれば。 ペニスは、その見るからに柔らかそうな双乳の谷間に挿入されることになる。 想像したらまずいと思い至るよりも早く、欲望に忠実なペニスがむくむくと鎌首を擡げていく。 「あらぁ?あらあらあら❤」 その様子を見た萌さんの口元に笑みが広がっていく。 「これは大変❤まだ、蛇さんが元気です❤」 萌さんが上半身を左右に揺する。 その動きに合わせて、豊満な乳房もゆっさゆっさと揺れる。 柔らかさと共にたっぷりとした重量感さえもが伝わってくる動き。 自然と口の中に涎が溢れてくる。 萌さんがブラウスのボタンを一つだけ外す。 現れたのは、途轍もなく魅惑的で、途轍もなく淫らな穴。 そこにペニスを挿入すれば、一体どれほどの悦楽が待っている事か。 想像するだけで、口の中に大量の唾液が分泌される。 「止めちゃいますか?蛇退治❤」 上目遣いに僕を見上げ、ぺろりと舌なめずりする萌さん。 ごくりと喉が鳴る。 思考が白濁し、 「お、お願いします………退治………してください❤」 気づいた時には、そう懇願していた。 「ふふ。じゃあ、蛇さん、いらっしゃ~い❤」 笑みを零しながら、萌さんがゆっくりと腕から力を抜いていく。 ぬぷぬぷと僕の脳内に淫らな擬音を響かせながら、ペニスが穴に吸い込まれていく。 むっちりとした乳肉を掻き分けながら進む感触。 「おっ❤あぁぁっ❤と、溶けるぅぅぅぅっ……❤❤」 温かくて。 柔らかくて。 むっちりと押し包んでくる。 圧倒的なまでの幸福感に、僕の表情が蕩けていくのが自分でもはっきりと分かった。 そんな僕を上目遣いで見つめながら、萌さんが上半身を左右に揺すり始める。 「あっ❤あっ❤こ、これっ❤き、気持ちいいっっ……❤❤」 萌さんの動きに合わせて乳肉が震える。 その振動が波紋となって、ペニスに複雑な快感を齎すのだ。 時にはさざ波のように。 時には大波のように。 寄せては返し、渦を巻く悦楽が、僕を翻弄し、転覆させ、飲み込んでいく。 「海斗さん、大学卒業したら、この島に戻ってきませんか?」 「ふへっ………」 快楽に蕩け切った僕は、萌さんが唐突に発した言葉の意味をうまく理解する事が出来なかった。 萌さんは左右だけではなく、上下、前後、さらに円を描くような動きも加え、より複雑な快楽を僕に与えながら、言葉を続ける。 「私の仕事は、この島を活性化する事です」 「そ、それはぁっ……んんっ❤❤……き、聞きましたっ……」 「その為に、私が村長さんたちに提案させていただいているのが、この島のリゾート化なんです」 「り、リゾート化……おふっ❤❤」 その話は、初耳だった。 「そうなんです❤我々が運営するヴェイン・リゾートシリーズの第2弾として、ホテルや会議場、ヨットハーバーなどを併設したマリンリゾートを開発します♪瀬戸内エリアは海外のVIPにも人気ですので」 「な、なるほど………んひっ❤」 ヴェイン・リゾートは聞いた事がある。 絶海の孤島に浮かぶ南国リゾートで、財界や政界は言うに及ばず、海外セレブにも人気だと。 学生の身には縁遠い話だ。 「そんな超高級リゾートの第2弾を、この島に………?」 萌さんの話に、言い知れぬ違和感を感じる。 脳裏に、村長を始めとする古老たちの顔が浮かんだ。 何より、この村の伝統と静けさを愛する人々だ。 「それ……反対されませんでしたか?」 僕の質問に、萌さんが悲しそうな顔で頷く。 頷きながら、互い違いに乳房を動かし、僕に喘ぎ声をあげさせる。 「そこで、海斗さんにご相談なんです」 「僕に……んっ❤……な、何をしろと……」 「皆さんを説得していただきたいのです。今日、海斗さんの成人式をお祝いしている皆さんの様子を見ていて確信しました。海斗さんは皆さんにとって、まさに希望そのもの。その海斗さんのお言葉であれば、ご納得いただけるのではないかと思うんです」 (なるほど。そう言う事………) 萌さんのようなとんでもない美人が、自分のような男に近づいてきた理由が漸く分かった。 「そういう話であれば、お断―――あひぃぃぃっ❤❤」 断ろうとした言葉が、喘ぎ声によって掻き消される。 萌さんが両側から乳房を圧迫し、ペニスを締め上げたから。 さらに、谷間に涎を垂らし、滑りを良くして思いきり扱き上げる。 「あっ❤あぁあぁぁっ❤❤」 萌さんが激しく乳房を動かす度、ずちゅっ❤ぱんっ❤ぱちゅんっ❤ずちゅんっ❤と肉と肉がぶつかり合う淫らな音が鳴り響く。 先ほどまでの穏やかな快楽とは一線を画する強烈な快楽。 思わず跳ねてしまう僕の体を抑え込み、さらに激しく胸を動かす。 2度射精しているにもかかわらず、一気に絶頂に押し上げられる。 「で、出るっぅぅぅぅっ❤❤」 背を仰け反らせ、絶頂の瞬間に身構える僕。 しかし、あと少しで射精できるという絶妙なタイミングで、萌さんが手を止めてしまう。 「あっ?あぁぁっ、な、なんで………っっ」 絶頂をお預けされて、思わず情けない声が漏れる。 そんな僕に対し、萌さんは穏やかに微笑む。 「お話の途中で決断を急ぐのは、あまりお勧めできませんよ、海斗さん❤」 「あぁぁ……❤❤」 再び、緩やかに萌さんの手が動き出す。 射精には至らない穏やかな快楽が、僕の緊張を解していく。 「勿論、タダで協力してくださいなどと申し上げるつもりはありません。海斗さんにとっても、それ相応のメリットのあるお話なんですよ」 「め、メリット………?」 「ええ。海斗さん、失礼ながら、会社の経営、然程うまくいってませんよね?」 萌さんの指摘に、ずきんと胸が疼く。 「な、なんで、それを………」 「まぁ、それは置いておいて。初期投資が重く、黒字化に時間が掛かっていることからスポンサーがなかなかつかずに資金繰りに窮している。さらに、メインスポンサーからも資金の引き上げを宣告されており、崖っぷち。そうではありませんか?」 さすがはヴェイン・グループという事か。 こちらの事情は完全に調べ尽されているのだろう。 成人式の時に声をかけてきた際、あたかも今日初めて知ったかのような口ぶりだったのも演技だったという事になる。 天女のようだなんて能天気に好意を寄せていた自分が馬鹿馬鹿しくなってきた。 「メリット……というのは?」 薄々予想は着いている。 そして、萌さんは予想通りの事を口にした。 「もし、ご協力いただけるならば、ヴェイン・グループが責任を以て、海斗さんの事業を支援させていただきます」 「僕を……会社ごと買収するって事ですか?」 「ふふ、海斗さんったら❤買収だなんて人聞きの悪い。協力し合いましょう、というお話です。こうやって一緒に蛇退治をしているように❤」 萌さんが手を動かす速度が徐々に加速していく。 それにつれて、僕の身を貫く快楽が再び高まっていき、思考が桃色に染め上げられていく。 一度、射精の寸前にまで追い詰められたペニスは、容易く絶頂へと押し上げられる。 だが、絶頂寸前で萌さんは再び手の動きを緩めてしまう。 (あぁっ……気持ちいい……イきたい……でも……あぁっっ……) 思考が千々に乱れる。 ペニスを谷間に捉えられている限り、じり貧なのはわかっている。 このまま寸止めを繰り返されれば、いずれ頷いてしまうだろう。 だけど、強引にこの場を脱するには、萌さんの齎す快楽も、その提案も魅力的過ぎた。 「いかがなされます?蛇さんはどうやら私の提案に乗り気のようですけど❤」 だらだらと我慢汁を垂れ流す亀頭に向かって唾液を垂らしながら、萌さんが微笑む。 脳裏に様々な顔が浮かぶ。 村の老人たち。 彼女。 会社の仲間たち。 (僕はどうすれば………) 悩んでいるうちにも、萌さんはペニスを攻め続ける。 それがまた気持ちよすぎて、頭がどうにかなってしまいそうだ。 「ふふ、まだ決められませんか?……でも、私の方がもう我慢できません❤」 「えっ……?」 萌さんの言葉に疑問符を浮かべた次の瞬間、 「蛇退治しちゃいます❤」 萌さんがそう宣告し、胸の谷間から覗く亀頭にむしゃぶりついた。 じゅるるるるっ❤と激しく吸い上げられる。 「あっ❤あぁぁっっ❤❤」 さらに、ぎゅぅっと乳房が圧迫され、竿を締め上げる。 萌さんが激しく頭を上下に振り、唇を何度も何度もカリ首に引っ掛けながら、扱き上げる。 「――――っ❤❤❤」 頭の中が一瞬にして真っ白になり、悲鳴は声にもならなかった。 どびゅんっ❤びゅくんっ❤どびゅっ❤びゅるるるるっ❤❤びゅくびゅくびゅくっ❤❤びゅるるるるっ❤❤❤ 3度目とは思えないほど大量の白濁液が萌さんの喉奥を打ち付け、唇の端から溢れ出してブラウスや乳房をも汚していく。 ごきゅごきゅと喉を鳴らしながらザーメンを貪った萌さんは、ちゅぽんっ、とペニスを解放すると、唇に付いた白濁をぺろりと舐める。 「はふ❤……やっぱり、ぷりぷりで美味しいです♪」 満足そうに言いながら、もそもそと炬燵の中から這い出してきて、スカートもパンティも一気に脱ぎ捨てる。 「えっ、ちょ、も、萌さんっ……!?」 驚く僕の腕を掴んで炬燵から引っ張り出し、腰に馬乗りになる。 至近距離から見下ろす顔は上気し、目が潤んでいた。呼吸も荒い。 「もうしなくてはならないお話は終わりました。後の判断はお任せします。ここからはただ、男と女❤」 「ちょ、むっ、むぅぅぅっ!!??」 身体を抑え込まれ、唇を奪われる。 熱い舌と唾液が大量に流し込まれ、溺れそうになる。 さらにシャツを捲りあげられ、乳首を捻られる。 「んん――――っっ❤❤」 豹変した萌さんに戸惑いつつも、身体は正直なもので、3度射精したにもかかわらず、ペニスはあっという間に勃起していく。 「凄い❤」 それを見て、萌さんがうっとりとため息を漏らす。 「やっぱり、若いってイイ❤」 屹立したペニスを掴み、腰を落とす。 前戯など必要ない程濡れそぼった熱い膣に飲み込まれ、幾重にも絡み付いてくる襞にむしゃぶりつかれる。 「あぁあんっ❤❤太くて、硬くて、奥まで届いてっ❤❤最高っ❤❤」 萌さんは完全に、欲情した雌獣と化していた。 まるで別人のようだ。 先ほどまでの、僕を誘惑しようとする行為とはまるで異なる。 ただ只管に、自分が快楽を得ようとする動き。 だがもちろん、それは僕にも強烈な快楽を齎す行為であることに違いはない。 唇を塞がれ、舌を扱かれ、大量の唾液に溺れそうになりながら、ペニスを締め付けられ、しゃぶられ、扱かれ、僕は目を白黒させながら、びくんびくんとまるでまな板の上の魚のように跳ねまわる。 ぱんっ❤ぱんっ❤ぱんっ❤ぱんっ❤ぱんっ❤ぱんっ❤ぱんっ❤ぱんっ❤ ぱんっ❤ぱんっ❤ぱんっ❤ぱんっ❤ぱんっ❤ぱんっ❤ぱんっ❤ぱんっ❤ 部屋に肉と肉がぶつかる淫らな音が何度も何度も響く。 さらに男女の喘ぎ声が合わさり、三重奏のように鳴り響く。 その音は夜明けまで鳴り止むことはなかった。 *** それ以降、結局僕は萌さんの申し出を受け入れ、度々故郷に戻っては、萌さんと共にリゾート化計画に反対する老人たちを説得して回る事となった。 僕の説得に応じてくれる人もいれば、それでも反対を貫く人もいた。 しかし、元々高齢化が進み、消滅間近だった村だった事もあり、時間は僕たちに味方した。 2年後―――。 大学を卒業した僕は本格的に故郷に戻る事にした。 会社も、ヴェイン・グループに買い取って貰った上での移住である。 結局、あれ以降彼女とはうまくいかなくなり、別れてしまった。 僕が頻繁に島に戻るようになった事、自分も一緒に行きたいという申し出を断り続けた事から、浮気を疑われたのだ。 有り体に言ってしまえば、その通りだった。 僕は島に戻る度、萌さんと体を重ねていたのだから。 「おかえりなさい、海斗さん」 桟橋で出迎えてくれる萌さん。 そのお腹は、傍目に見ても、大きくなっていた。 数年後。 僕は村長になり、故郷には一大高級リゾートが無事にオープンした。 消滅寸前だった村には今や多くの観光客が押し寄せるようになった。 雨宿代价 それは突然の事だった。 遂、さっきまで快晴だった空が急に黒雲に覆われ、轟音と共に稲光が煌めく。 思わず竦めた首筋に、ひやりと冷たい感触。 と、思ったら一瞬にして叩きつける様な豪雨に変わる。 「うわっ」 山の天気は変わりやすいとはよく聞くが、まさかここまでとは。 あっという間に全身がずぶ濡れになっていく中、通勤鞄を頭上に掲げ、なけなしの抵抗をしながら走る。 5分ほど走っただろうか、50m程先にバス停が見えてきた。 傍らには、掘っ立て小屋の待合室が併設されている。 天の助けとはまさにこの事。 ボロい待合室が、今日ほど輝いて見えたことはない。 「ひぃ~っ………!」 轟く雷鳴と篠突く雨に追われ、悲鳴とも何とも言えぬ声を上げながら、がららっ、と建付けの悪い引き戸を開けて中に飛び込む。 「あ」 「おぅっ!?」 中からの声に、思わず変な声が飛び出た。 先客がいるとは全く考えもしなかった自分の迂闊さを呪いつつ、 「お、驚かせてしまってすいませんっ」 とりあえず、先客に謝罪する。 「びっくりした~。先生も降られたんですね」 「え、その声……って、やっぱり永尾か」 先客の声が聞き知ったものであることに気づき、遅まきながら相手を確かめると、待合室の中にいたのはよく知る相手だった。 教え子の永尾ゆうかである。 艶やかな黒髪をした少女で、校内一の美少女と名高い。 人当たりもよく、生活態度は優良、学業も申し分ない優等生である。 「お前も降られたのか」 「うん。突然だったからびっくりしました」 永尾も同じく雨に降られたと見え、その制服はびしょ濡れだった。 「っ………」 その姿を見て、慌てて目線を反らす。 雨に濡れたセーラー服が肌に張り付き、思いの外豊満な乳房を包むブラが浮き上がって見えていたのだ。 「どうかしました、先生?」 「い、いや、何でもない」 小首を傾げる永尾に、どぎまぎしながら答える。 「とりあえず、座ってください」 「あ、ああ、ありがとう」 永尾がスペースを空けてくれ、狭い待合室の中で、二人掛けのベンチに横並びに座る。 狭い待合室だ。 二人掛けのベンチの他には、小さな神棚ぐらいしかない。 窓の外に目を向ける以外、目のやり場もない。 「雨、全然止みそうにないですね」 「そう、だな………夕立、なんだろうけどな」 待合室の窓を叩く雨は、先ほどよりもさらに勢いを増しており、雷も頻繁に光っている。 音からして、まだ距離は遠そうだったが。 いずれにせよ、今この待合室を出るという選択肢は取り得ないだろう。 だが、そんな事よりも―――。 顔を正面に向けたまま、横の永尾を窺う。 永尾はこちらの視線に気づくこともなく、外を見つめている。 (睫毛長い………綺麗な横顔だな………) 改めて、永尾の美少女ぶりに息を呑む。 その黒髪は雨に濡れ、しっとりと輝いているかのようだ。 透けてしまったセーラー服のせいで、発育の良い胸が呼吸に合わせて微かに上下する様がわかってしまう。 はっきり言って、目の毒過ぎた。 さらに視線を下ろせば、肉付きのいい太ももが目に飛び込んでくる。 柔らかそうな太ももは水を見事に弾き、玉のような水滴が点々とついている。 重力に逆らえずに流れ落ちた跡も、なぜかとても蠱惑的に見える。 (水も滴るいい女………) そんな陳腐な表現が脳裏を過って、 (いかんいかん。何を考えてるんだ。俺は教師なんだぞ………) 首を左右に振って、何とか邪念を払おうとする。 高校教師になって4年目、初めての人事異動で赴任したのが、このド田舎の高校だった。 赴任当初は同じ県内で、都市部を離れるとここまで田舎になるのかと驚いたものだが、空気も水も野菜もおいしく、人の心根も温かい田舎を、最近では好ましく思うようにもなっていた。 (ここで問題を起こすわけには………) 「くしゅっ」 小さなくしゃみの音に、ハッとする。 「永尾、大丈夫か?」 「はい……でも、ちょっと寒くて……」 確かにいくらもうすぐ夏という季節でも雨に濡れたままでいれば、体温は低下していく。 ズボンを履いている自分でも肌寒く感じる程なのだから、スカートの永尾は尚の事だろう。 「タオルとか持ってないのか?」 「持っていたら、このままにしてないです」 「そ、そりゃそうだな………」 馬鹿な事を訊いたと頭を掻く。 外に視線を向ければ、雨はさらに激しさを増しつつあった。 「先生は持ってないんですか?」 「ああ、俺も何も………そうだ、ワイシャツでも羽織るか?これも濡れてるけど、何もないよりはマシだろう?」 残念ながら、俺もタオルなどは何も持っていなかった。 今、着ているワイシャツをつまんで尋ねてみると、永尾は首を横に振る。 「それじゃ、先生が風邪引いちゃいます」 「永尾が引くよりはマシだろ。俺の事は気にしなくていいから」 「…ありがとうございます」 「よし」 永尾が遠慮がちに頷くのを見て、手早くワイシャツを脱ぎ、一応絞ってみてから、永尾に羽織らせる。 「……温かいです。先生の匂いがする」 「お、おう……臭かったらすまん」 「いえ、好きな匂いです」 「そ、そうか」 「先生、優しいんですね」 「き、教師だからな。当然だろ」 目線が空を泳ぎ、結局窓を叩く雨を眺める事に逃げる。 体が熱い。きっと耳まで真っ赤になっている事だろう。 待合室に、濡れた制服姿の女子高生と半裸の高校教師。 誰かに目撃されたら、あらぬ誤解を受けそうだった。 (頼むから早く止んでくれ……俺の精神がもたん……) 視線は外に向けていても、意識はどうしても永尾に向いてしまう。 彼女の視線が、こちらに向けられている事に、鼓動が高鳴っていく。 「先生って……結構、鍛えてるんですね」 「っ、そ、そんな事は……」 上半身裸姿を、教え子に見られていると思うとむずがゆくなる。 そのむずがゆさが鼻まで昇ってきて、 「はっくしょん!」 盛大なくしゃみとなって飛び出した。 「大丈夫ですか?先生、やっぱり寒いでしょ、それじゃ……」 「いや、大丈夫大丈夫!」 心配そうな顔をする永尾に手を振って答えると、その手を掴まれた。 「え?」 「じゃあ、こうしましょ」 永尾が距離を詰めてきて、俺の腕に自身の腕を絡めるようにしてくっついてくる。 「ちょ、な、永尾……」 思わず声が震えてしまう。 左腕が、まるでマシュマロのような柔らかな感触に包まれる。 何に包まれているのかを想像して、頭が沸騰しそうになる。 「くっついて、互いの体温で温め合うんです。ほら、雪山で遭難した時は人肌で温め合うって言うじゃないですか」 「で、でもな……」 「温かくないですか?」 「っ………」 永尾がこちらを見て小首を傾げる。 至近距離で見るその顔の可愛さに、拒絶する言葉を思わず飲み込んでしまう。 「あ、温かい、な……」 「でしょ」 永尾が笑顔になる。 その笑顔に、どくんっ、と大きく心臓が跳ねる。 (こ、こんなのっ、惚れてまうやろ―――っ!!) 内心で叫ぶ。 こてん、という感じで永尾が俺の肩に頭を預けてくる。 さらに、指と指を絡める、いわゆる恋人握りで手を握られる。 (な、永尾さんっ、積極的すぎるって……!) 何とか左半身を意識しないようにと思うものの、できるはずもなかった。 互いの呼吸に合わせて、ふにふにとした感触が腕に纏わりついてくるだけでなく、永尾の髪からはとてもいい匂いがするのだ。 こんな状況で、平静でいられるはずがない。 いくら高校教師だろうが、二十代の健全な男であることに変わりはない。 どくん、どくんと鼓動が高鳴っていく。 月並みな表現だが、この音は永尾にも聞こえているのではなかろうか。 さらにまずいことに、血流が勢いよく股間に流れ込んでいく。 動いた際にまくれ上がったのか、さっきよりも際どいところまで、太ももが露になっている。 その、白く艶やかな肌が、輝いてみえる。 (勃つな、勃つな………) 懸命に念じるが、永尾の肢体を意識すればするほど、下半身が熱くなっていき、ペニスが固くなっていく。 (こんなの気づかれたら………何とかこの状況を脱する手段は………) 懸命に思考を巡らせるものの、なんだかボーっとしてしまって、考えが纏まらない。 「先生、ごめんなさい。やっぱりこれだけだと寒い………」 謝罪の言葉を口にしながら、永尾が俺から離れる。 「え………」 左半身に感じていた柔らかさや温かさが遠ざかっていき、ホッとすると同時に言い知れぬ寂しさを感じながら永尾の行動を目で追う。 「うぇっ………」 次の瞬間に永尾がとった行動に、俺の思考は一瞬にして真っ白になった。 なんと、俺の腰を跨ぎ、正面から俺に抱き着いてきたのだ。 ひやりとした感触に一瞬遅れて、柔らかな感触が、ふにゃりと裸の胸板一杯に広がる。 ズボンの下で勃起したペニスに柔らかな重みが齎され、甘い刺激が背筋を駆け上っていく。 「先生。ぎゅってして」 「お、おう」 あまりの事態に何も考えることができないまま、耳元で囁かれるままに永尾の背中に両腕を回し、抱きしめる。 柔らかな身体を抱きしめるだけで、全身に甘い快感が走っていく。 「あったかい………もっと……」 永尾が両手を背中に回し、両足で腰を挟み、より密着してくる。 傍目に見れば、それは対面座位で男女が結合しているようにしか見えないだろう。 実際、俺の股間は完全にテントを張ってしまい、永尾のあそこと僅か3枚の布を隔てただけで当たってしまっているのだ。 鎮めようとして鎮められるはずもなく、ますます血流が流れ込み、硬くなっていく。 「くすっ、先生の……大きくなってる」 永尾の囁きに、文字通り顔面蒼白になる。 当たり前だ。 この状態で、気づかないはずがない。 「す、すまん!すぐに離れ―――」 とにもかくにも離れようとするが、永尾はぎゅっと俺にしがみついてくる。 「ダメ。このままでいいよ、先生」 「いいって、お前………嫌じゃないのか?」 ごくり、と生唾を飲み込む。 永尾の言葉によって、理性や倫理観と言ったものに罅が入っていく。 「嫌じゃ……ないよ。先生なら」 至近距離で俺の目をじっと覗き込み、永尾が囁く。 「永尾………」 透き通った綺麗な瞳に、欲情に半ば以上流されつつある男の顔が映っている。 とろり、とペニスの先端から我慢汁が滲みだす。 「だって、女の人と肌を合わせてこうなるのって男の人にとっては自然な事でしょう?」 「ま、まぁ………そ、そう、なんだが……」 「先生が、私の事、女って思ってくれるの、普通に嬉しいよ」 「っ、あ、当たり前だろ……お前は……」 「お前は?」 「い、いや、何でもない」 「えー。教えてください」 「い、嫌だ」 「教えてくれないなら………ふぅっ❤」 「んぁっ……」 「ふふ、んぁっ、だって。先生、耳に息吹きかけられるの苦手なんだ?」 「そ、そうだよ!だから、もう―――」 「ふぅっ❤」 「んんぁっ、だ、だから、やめ―――」 「ふぅ~~っ❤❤」 「ひぃっ……❤」 「止めてほしかったら、さっき言いかけた事、教えて?」 「そ、それは……」 「教えてくれないなら、もぉっと責めちゃいますよ?」 「わ、わかった。言うから……その……笑うなよ?」 「はい。笑いません」 「お、お前は………その、とても魅力的な女性だ………ぶっちゃけめっちゃ可愛い……って言おうと―――」 「ふふ」 「あ、笑わないって言ったろ!」 「ふふ、ごめんなさい。でも、これは先生を馬鹿にしてるんじゃなくて、嬉しかったからですよ。ありがとう、先生」 「お、おう………」 密着して、なんて恥ずかしい会話をしているのだろうと考えると、思わず死んでしまいたくなる。 「だ、だいぶ温まってきたな」 恥ずかしさのせいもあるが、やはり人肌で温め合うというアイデアはこの状況に適した判断だったのかもしれない。 「そうですね……。でも……ね、先生……もっと温まる事、しちゃおっか❤」 至近距離から見つめられての提案。 その提案を、断らなければならないことは、理性ではわかっていた。 だが、本能では―――。 結局、俺は何も答えず、艶やかな唇が近づいてくるのをただ見つめている事しかできなかった。 唇が押し付けられ、その柔らかさに理性がぐずぐずと崩れ去っていくまで。 「ちゅっ、ちゅるっ、んちゅっ……んんっ、先生の唇、とっても柔らかい❤………ほら、もっと舌出して❤」 求められるまま、舌を伸ばす。 その舌に永尾の舌が絡みつき、扱かれる。 永尾の手が俺の後頭部をロックし、より深く舌が永尾の口中に招き入れられる。 温かくて、柔らかくて。 永尾の唾液はなぜか甘く感じた。 無我夢中になって、キスを貪る。 永尾が身体を動かす度、股間が擦られて甘い快感が脳髄に響く。 いつしか自然と、自分も腰を動かしてしまっていた。 今にもズボンを突き破ってしまいそうなほど硬くなったペニスの先端から溢れ出す我慢汁で、もしかしたらシミができているかもしれない。 永尾に体重を掛けられて、ベンチの上に押し倒される。 「先生……❤」 上から見下ろされて、キスをされる。 口中を舌で舐られ、流し込まれる唾液をこくこくと飲み干していく。 身体の力が抜けていく。 永尾の手が、裸の胸をゆっくりと撫でていく。 「くふっ……」 わき腹を撫でられて、息が漏れる。 「んんっ……」 乳首を撫でられて、思わず喘ぎ声が零れ落ちる。 「ふふ、可愛い声❤…男の人でも、乳首で感じるんですね❤……先生の乳首、とてもコリコリしてますよ❤」 「くっ、ふぁぁっ……❤」 勃起した乳首を集中的に撫でられて、先ほどよりも大きな喘ぎ声が漏れる。 優等生の口から飛び出る淫らな言葉が、余計に興奮を高めていく。 「先生の可愛い声……もっと聞かせてください❤❤」 「あっ、あっ、んふぅっ、んんっ……❤❤」 もう片方の乳首を濡れた感触が襲う。 ぺろぺろと乳首を舐めながら、上目遣いに俺の表情を窺う永尾。 俺の反応を見て、どういう責め方をすれば俺をより感じさせられるのかを研究しているかのような表情だった。 「あふっ❤んあぁっっ❤❤」 全身を襲う、これまでよりも強い快感に、びくんっと体が震える。 永尾のすべすべさともちもちさを兼ね備えた最高の太ももが股間に押し付けられ、円を描くように擦られていく。 「先生のおちんちん……もうカッチカチですよ❤」 「ふぁぁっ❤❤んんっ❤おっ、おふぅっ……❤❤」 乳首とペニスの3点攻めに、他愛もなく喘がされる。 「ね、先生。直接触ってほしい?」 ちゅぅっと乳首に吸い付いてキスマークを残しながら、永尾が上目遣いに訊いてくる。 さすがに言葉に出して答えるのは恥ずかしく、無言でこくんと頷く。 「だぁめ。ちゃんと言って?」 だが、永尾はそんな俺の逃げを許してはくれなかった。 「さ、触ってぇ……永尾……」 もはや教師としての体面もかなぐり捨てて、俺は浅ましい懇願の声を上げる。 「じゃあ……名前で呼んで、先生」 「ゆ、ゆうか……触って……あぁんっ❤」 乳首を爪先でひっかかれ、もう片方に軽く歯を立てられる。 若干の痛みは、快楽をさらに強く引き出すスパイスになる。 「ふふ、先生。それじゃわからないよ。何を触ってほしいの?」 普段の優等生な姿からは想像もつかない諧謔的な表情で、永尾―――ゆうかが小首を傾げる。 そのギャップに、俺の心がさらに崩れていく。 「お、俺の……俺の……お、おちんちん、を……」 「『俺』って、あんま先生に似合わないよ?」 「ぼ、僕のおちんちんっ……触ってっ……」 「『触って』?」 「さ、触って、くださいっ……ぼ、僕のおちんちんっ、お願い、しますっ……触ってください……」 「ふふ、可愛い♪……いいよ、先生。触ってあげる❤」 ズボンのファスナーを下ろし、手がズボン、そしてパンツの中へと入ってくる。 冷たい手の感触に、背筋が震える。 「先生の、すっごく熱いよ❤それに、凄く硬くて、びくんびくんって震えてる……あれ?ふふ、先生、先っぽの方、すっごくぬるぬるしてるよ?さっき、凄い腰動かしてたもんね」 ペニスに指が絡みつき、形を確かめるように揉まれる。 「あっ❤あっ❤」 「気持ちよさそうな顔してる♪……気持ちいいんだ、先生?」 「気持ちいいっ❤気持ちいいですぅっ❤」 「ヌルヌルのぉ❤バッキバキでぇ❤アッツアツになっちゃってる先生の、おちんちん❤……どうして欲しいか教えて?」 「扱いてっ、扱いてっ、くださいっ……!」 「ふふ。扱いてほしいんだぁ。いいよ……こう?」 指で輪っかを作り、上下に扱き上げられる。 輪がカリに引っかかる度、頭の中に白い光が炸裂する。 「おふっ❤きもち、気持ちいいっ……❤❤」 「涎出ちゃってるよ、先生❤ちゅるっ、れろっ」 涎を舐められ、そのまま唇を重ねる。 ちゅぱちゅぱと舐められて、 「乳首は何もしなくていいのー?」 耳元で甘く囁かれる。 「こぉんなにビンビンになってるよぉ?」 空いた手で、ペニスに劣らぬほど硬く勃起した乳首を撫でられる。 「ほら。爪で弾いてあげる❤ピンッて❤」 「あふぅっ❤❤んぁぁっ❤」 「喘いでばかりいないで教えて?乳首、どうしてほしいの?」 「あぁっ❤舐めて、舐めてくださいぃっ❤❤」 「くすっ。情けない顔♪……でも、我儘だなぁ、先生。乳首もおちんちんも、両方気持ちよくしてほしいんだ?」 「ご、ごめんなさいぃ……」 「ふふ……いいよ、先生❤……両方、気持ちよくしてあげる❤❤」 「うぁっ、あっ、ありがとう、ございまひゅっ、あふぃんっ❤」 乳首を舐められながら、ペニスを扱き上げられる。 年端もいかない少女にいい様に弄ばれているという事実が、危険な脳内麻薬の分泌を促し、快楽をさらに危険な領域へと高めていく。 我慢の限界はあっという間にやってきた。 「あっ❤あっ❤も、もうっ、出ちゃうっ❤❤」 「えーっ。このままじゃ、パンツの中に出しちゃうよ?いいの?」 「んあぁっ、も、もう、無理ぃぃぃっ❤❤❤」 どびゅるっ、どびゅぅっ、びゅるるるっ、どくんっ、どびゅっ、びゅるるるっ……!! ゆうかの警告に対し、全く我慢する事もできず、決壊する。 噴き出した白濁液が、パンツを、ズボンを汚していく。 ゆうかはぬるぬると扱き、最後の一滴まで搾り取っていく。 「あーあ。パンツもズボンもぐっちょぐちょ。これじゃ気持ち悪いでしょ、先生……ほら、脱ぎ脱ぎしましょーね」 まるで赤ん坊に言い聞かせる様な口調で、ゆうかにズボンとパンツを剥ぎ取られる。 バス停の待合室という公共の場で、靴下以外全裸になっているという事実を前にして、全身が燃える様な恥ずかしさを覚える。 だが、その恥ずかしさはもはや快楽と同義だった。 「ふふ、先生ってば。おちんちんまだまだ硬いままだよ?」 屹立したままのペニスをつんつんと突き、ゆうかが身を起こす。 「だったらさ、先生」 その手が、ブラウスにかかり、ボタンをゆっくりと外していく。 ブラウスを開くと女子高生らしい清楚な白のブラに包まれた、豊かな乳房がふるんと姿を現す。 その魅惑の塊に、言葉もなく見惚れる。 「先生、おっぱい好きでしょ?ずっとちらちら見てたもんね?」 「うっ……うん……」 バレていた事に一瞬気まずさを覚えつつも、素直に首肯する。 ゆうかが四つん這いになり、僕の眼前で大きなおっぱいをふるふると揺らす。 「あ……」 その光景に、馬鹿みたいな吐息を漏らす僕の顔面が、おっぱいに包まれる。 一瞬にして、頭の中が桃色に染め上げられた。 柔らかくて。 しっとりとしていて。 瑞々しくて。 ずっしりとした重みが、幸福すぎて。 僕の顔面をおっぱいで圧し潰しながら、ゆうかが上半身を動かす。 もにゅもにゅ。 むにゅむにゅ。 顔面をおっぱいに揉まれる幸福感の中で、僕は欲望のままおっぱいにむしゃぶりつき、舐めまわす。 (おっぱいおいしい、おっぱいおいしい、おっぱいおいしい、おっぱいおいしい………!) 「先生ってば。赤ちゃんみたい❤……私のおっぱい、おいしい?」 「おいひぃれすぅっ❤❤」 「可愛い❤……先生のおちんちん、もうガッチガチ。気持ちよくして~って、泣いてるみたい♪……ふふっ、大丈夫だよぉ、おちんちんちゃん❤おちんちんちゃんも気持ちよくしてあげるからね❤」 言葉と同時に、おちんちんがむっちりとした気持ちいい感触に包まれる。 「ふあぁっ……❤❤❤」 最初、その快楽がどのようにして齎されたのかがわからなかった。 馬鹿になった頭をフルに回転させて、今のゆうかの体勢を思い浮かべる。 僕の頭の上に両手を置き、僕の顔面をおっぱいで圧し潰している体勢。 その状態からできる事を想像すると―――。 「どう、先生?太ももに挟まれて、気持ちいい?」 「き、気持ちいいいっ……❤❤」 さらに、ゆうかが太ももを互い違いに動かし、おちんちんを扱き上げてくる。 「あっ、ぁあぁっっ❤❤❤」 体勢的にかなり体力を消耗しそうだったが、ゆうかの体力を心配する間もなく、思考が快楽に飲み込まれていく。 おっぱいに懸命に舌を這わせながら、ゆうかの動きに合わせて腰を突き上げる。 「あはは。へこへこ腰振っちゃって、先生ってばお猿さんみたい❤❤」 もう何を言われても構わなかった。 猿だろうが何だろうが、ただただ快楽を享受する事しか考えられなかった。 「あっ、ひゃぁぁっ、も、もうっ、イぐっ、イきますぅぅっっ❤❤」 「いいよっ❤出してっ❤おっぱいにもみくちゃにされながら、太ももに腰へこへこ振って、どっぴゅんって出しちゃって❤」 ゆうかの許しを得て、射精感が一気に込み上げてくる。 我慢しようなどとは一瞬たりとも考えることができなかった。 込み上げてくるままに、そのまま炸裂する。 どびゅるっ、どびゅぅっ、びゅるるるっ、どくんっ、どびゅっ、びゅるるるっ……!! 見る事はできなかったが、容易に想像することができた。 ゆうかの太ももに挟まれ、その間から盛大に精を噴き上げている自身の情けない姿が。 射精している最中もゆうかは太ももでおちんちんを扱き続け、僕もまたへこへこと腰を振り続ける。 「いっぱい出たね、先生❤さっきより出たんじゃない?」 僕の上から降りたゆうかが、白濁液が飛び散った周囲を見回して笑う。 そういうゆうかの背中にも、僕の出した白濁液が点々とついている。 雨と雷に加えて風も出てきたようで、ボロい待合室がガタガタと揺れている。 2度射精して、僕は漸く少しだけ冷静さを取り戻していた。 ベンチに座り直し、頭を抱える。 「ゆうか……いや、永尾……俺は……なんてことを……すまん……」 「なんで謝るの、先生」 「俺は高校教師だ。なのに……」 今更ながら後悔が膨れ上がっていく。 永尾の顔を見ることもできない。 「そう言うの、めんどくさいよ」 「え……」 永尾の吐き捨てる様な強い口調に、思わず顔を上げ、言葉を失う。 永尾の表情は逆光でよく見えなかった。 「だってそうでしょ?教師と生徒という関係以前に、私たちは男と女。それでいいんじゃない?」 「だが………」 「あーもう。うじうじと。そんな事言ってたって―――」 少し苛立った口調で吐き捨てながら、永尾が俺の足の間に身体をねじ込んでくる。 「おっ、おいっ………っっ」 止める暇もなく、2度の射精によって萎えているおちんちんが、ゆうかのおっぱいの谷間に姿を消す。 「あっ、おっ、うぁっ……」 ゆうかがぞんざいに胸を動かす。 乱雑な動きによっておちんちんが揉みたてられ、情けないことにあっという間に硬さを取り戻していく。 「ほら」 上目遣いにこちらを見上げるゆうかの口元に、笑みが戻る。 「御託並べたって、ちょっとおっぱいで揉んであげるだけで、おちんちんはギンギンになっちゃう♪」 「うっ❤…うぅっ❤……んんっ❤❤」 ゆうかが胸の谷間に唾液を垂らす。 きらきらと煌めきながら落ちていく唾液が、おちんちんをコーティングしていく。 ぬめりを増し、感触が変化したおっぱいによって揉みたてられて、あっという間に限界が近づいてくる。 「ほら、先生。気持ちよさそうな顔してる❤難しい事考えなくていいから、今はお猿さんみたいなおバカさんになって、気持ちよくなることだけ考えて。ね?」 優しく諭すようなゆうかの口調に、思考も口元も弛緩していく。 自分が、何に拘っていたのかもわからなくなってきた。 射精寸前で、ゆうかがおっぱいを開く。 おちんちんとおっぱいの間に、いくつもの銀色の橋が架かる。 もう少しでイケるというところで動きを止められ、どうしようもない喪失感に襲われる。 「ほら。先生。どうして欲しいのか、教えて?」 「俺は………」 「教師?それとも………『男』?」 「―――せて」 「ん?」 「イかせて、ください………」 教師としての立場も倫理観も、正義感も忘れて、懇願する。 もう、僕の中には何も残っていない。 今はただ、ゆうかの言葉通り、快楽を享受する事しか考えられなかった。 何かを失った穴を、ゆうかが齎してくれる快楽が埋めていく。 「ふふ。いいよ❤」 とびっきりの笑顔をゆうかが浮かべる。 次の瞬間、快楽を求めてわななくおちんちんが、おっぱいに食べられた。 頭の中に、ぱくんっ❤という魅惑的な擬音が鳴り響き、 「あっ、あぁぁぁっ❤❤❤出るっ、出るぅぅぅっ❤❤❤」 仰け反って喘ぐ。 3度目とは思えぬほど激しい射精感が込み上げてくる。 「出してっ❤私のおっぱいが妊娠しちゃうくらい一杯♪」 どびゅるっ、どびゅぅっ、びゅるるるっ、どくんっ、どびゅっ、びゅるるるっ……!! 「ふふ、一杯出た出た♪」 楽しそうなゆうかの声を聞き、3度目の射精を搾り取られながら、俺の理性、その最後の一欠片が消え去った。 (ああ………もうなんでもいいや……気持ちよければ……) 「先生ばっかり気持ちよくなってズルい。私のここも………ね?」 そう言って、ゆうかがスカートをたくし上げる。 純白のパンツに目を奪われ、俺の喉がごくりと大きく鳴る。 「ゆ、ゆうか」 「お願い、先生❤」 その言葉に突き動かされるように、ゆうかの前に跪き、スカートの中に頭を突っ込む。 むわんとした雌の濃厚な香りにくらくらする。 肉付きのいい、精液と愛液に塗れた魅惑的な太ももを抱え込み、股間に顔を埋める。 ふがふがと鼻を鳴らしながら、スカートの中の空気を貪り吸う。 肺の中をゆうかの香りで満たしたかった。 頭の中が、どろどろに溶けていく。 3度も射精したにもかかわらず、その香りを嗅いでいるだけでおちんちんが硬さを取り戻していく。 「舐めて❤」 言われるのと同時、むしゃぶりつく。 べろべろと舌を這わせ、じゅるじゅると吸い上げる。 濡れているのは、雨のせいなのか、興奮のせいなのか。 口中に少ししょっぱいような、でもずっと味わい続けたいと思える味が広がり、懸命に飲み込んでいく。 「んっ❤んんっ❤く、くすぐったいけど、あんっ❤❤気持ちいいよぉ、先生❤」 ゆうかが俺の頭を抱えながら、嬌声を上げる。 その蕩けた声をもっともっと聴きたくて、舌を這わせ続ける。 愛液と唾液でぐっしょりと濡れたパンツを引きずり降ろし、直接、ゆうかの陰唇に舌を這わせ、ずるずると淫らな音を立てながら淫汁を啜り上げる。 「あぁっ❤❤あふぁぁっ❤❤んんんっ❤❤❤」 特に、クリトリスを舐めるとびくびくと体が震え、嬌声が一段高くなる。 ゆうかを感じさせている。 その事実が、無上の喜びとなっていく。 半ば酸欠になりながらも、懸命に舌と顎を動かし続ける。 ゆうかの嬌声がどんどん大きくなり、がくがくと体が震える。 やがて―――。 「あぁんっ、くるっ、いくっ、いっちゃうよ、先生ッ❤❤ああっ、ぁぁぁあぁっ❤❤❤」 ゆうかが絶叫すると共に、これまでになくその身体が震え、あそこの奥からぶしゃっと大量の愛液が噴き出してくる。 (イったのか………) 「先生………」 「おっ」 とんっ、と肩を押されて、仰向けにひっくり返る。 背中に感じる濡れたコンクリートの感触が冷たい。 だが、見上げるゆうかの目を見て、息を呑む。 爛々と輝く目。 口の端から垂れた涎の跡。 上気した頬。 はぁはぁ、という荒い呼吸に合わせて上下するおっぱい。 「もう我慢できない………いいですよね?」 仰向けになった僕の腰を跨ぎ、隆々と聳え立つおちんちんを握る。 ゆうかがしようとしている事は明らかだった。 「で、でもっ、ご、ゴムとか………」 「要らないです」 「だ、だが、もし子供が出来たら………」 「赤ちゃんできたら………」 ゆうかがうっとりとした笑みを浮かべる。 思わず背筋が寒くなるような、そんな笑みだった。 「赤ちゃんが出来たら、私の事、お嫁さんにしてください❤❤❤」 「ゆっ、ゆう―――あぁぁっ❤❤❤」 名を呼ぼうとした声が、途中から喘ぎ声に代わる。 ゆうかが腰をすとんと落とし、僕のおちんちんがずっぷりとその膣に飲み込まれていく。 たっぷりと潤い、解された襞襞が四方八方からおちんちんに絡みつき、奥へ奥へと引きずり込まれていく。 「せ、先生のっ、おっきくてっ❤❤気持ちいいっ❤❤」 欲情に蕩け切った顔で、ゆうかが笑みを浮かべる。 「あっ、ひぃあぁぁっ❤❤む、無理ッ、こんなのっ、が、我慢できないっっ❤❤」 一方、僕には一切余裕がなかった。 「が、我慢なんかしなくていいよ、先生。私の中に、どっぴゅんって全部出しちゃっていいよ❤」 「い、いいわけ、ないっ……んあぁっ❤❤……良い訳、ないのにぃっ❤❤」 「だぁめ。我慢させない❤❤」 挿入しただけでも限界だというのに、容赦なくゆうかが腰を振り始める。 「あぁぁぁぁっっ❤❤❤ひぃぃぃぃぃっ❤❤❤」 パンッ❤パンッ❤パンッ❤パンッ❤パンッ❤パンッ❤パンッ❤パンッ❤ パンッ❤パンッ❤パンッ❤パンッ❤パンッ❤パンッ❤パンッ❤パンッ❤ 「出してッ❤出してッ❤出してッ❤出してッ❤出してッ❤出してッ❤」 「も、もう無理ぃぃぃぃぃっ!!!」 どびゅるっ、どびゅぅっ、びゅるるるっ、どくんっ、どびゅっ、びゅるるるっ……!! 騎乗位で無茶苦茶に腰を振られ、耐えられようはずもなかった。 大量の白濁液が、ゆうかの最奥めがけて発射される。 「出てるッ❤先生のぷりぷりの精子がっ、私の一番奥に注がれてるっ❤❤」 仰け反り、ゆうかも絶頂に達する。 それが更なる締め付けと快楽を齎し、射精の勢いが全然収まらない。 (ああっ……俺はなんてことを……) 後悔が脳裏を過ったのは一瞬の事。 「一度しちゃったら、二度も同じだよ❤」 そんなゆうかの甘い言葉に誘われるまま。 壁に手をつかせ、尻を突き出させ、バックから突きまくる。 「二度あることは三度ある❤」 最初のように正面から抱きあい、対面座位でおっぱいをしゃぶりながら突き上げて。 「もう四回も五回も六回も一緒❤」 何も考えられないまま、正常位で、側位で、背面座位で。 「雨も止まないし、もうこうなったら十回目指そう♪」 騎乗位で抜かずの連続射精。 延々と搾り取られ続ける。 雷光が煌めく度、楽しそうなゆうかの笑顔が浮かび上がる。 一体どれほど射精したのか、それすれもわからなくなった頃―――。 「あ。先生、雨止んだみたいですよ」 いつの間にか雷鳴も、雨も、風の音も止んで、待合室の窓からは仄かなオレンジ色の光が射し込んでいた。 ゆうかが立ち上がった拍子に、結合部からごぼっと大量の精液が、ぽろんと転がり落ちるおちんちんと共に溢れ出す。 久しぶりに外気に当たったおちんちんからは湯気が立っていた。 精も根も尽き果てた僕が横になったままボーっとしていると、ゆうかは神棚に歩み寄り、何かごそごそと探りだす。 何をやっているのだろう、とその姿を見つめていると、振り返ったゆうかの手にはなんとビデオカメラが握られていた。 「……え……」 無機質なレンズを向けられて、意味なき呟きが漏れる。 「どういう……事……?」 「あはは。先生、すっごく間抜けな顔してますよ。ちょっと待ってくださいね。今、動画確認するんで―――ふふ。撮れてる撮れてる。先生の気持ちよさそうな顔、一杯撮れてますよ♪」 ゆうかは録画した映像を確かめ、満足げな笑みを浮かべる。 「いやー……田舎ってバイト探すのも苦労するんですよ」 未だに混乱から抜け出せない僕に向かって、ウインク一つ。 「で、先生。このビデオ、いくらで買ってくれます?あ。あと………」 さらに神棚の中をごそごそと探って、ずるずると引っ張り出したのはビニール袋。 その中から取り出したものを差し出してくる。 「はい、タオル♪」 意味が分からないままタオルを受け取る。 ゆうかはさらにビニール袋の中から2枚目のタオルを取り出し、手早く自身の身体を拭っていく。 さらに袋の中から取り出した新しいブラとパンツをつけ、ジャージに着替える。 「ふぅ。さっぱり」 この光景を見せられては、いくら搾り取られて馬鹿になってしまった頭でも事態を理解することは簡単だった。 「嵌められた………って訳か」 「ま、簡単に言えば♪……それで、いくらで買ってくれます?それともネットに晒します?」 「動画、お前も映ってるんじゃ……」 「勿論そのまま流したりはしませんよ。編集して、私の事はわからないようにして流しますから♪」 騙されていたと知っても、なぜか怒りの感情は湧いてこなかった。 そんな元気も、搾り取られてしまったと言う事なのか。 通勤鞄を引き寄せ、中から財布を取り出し、入っていた札をすべて抜き出し、差し出す。 受け取ったゆうかは枚数を数える事もなく、ポケットにねじ込んだ。 「悪く思わないでくださいね、先生。それに、先生もイイ思い、できたでしょ?」 「………」 無言でいると、ゆうかはさらにビニール袋の中を漁り、ラミネート張りになったA4サイズの紙を差し出してくる。 受取り、視線を落とすと、《料金表》と書かれた下に手コキ、フェラ、パイズリ、本番などの料金が並んでいる。 「私、こういうのもしてるの♪今日のはお試しって事で。またのご利用お待ちしておりまーす。なんちゃって。じゃね、先生。テープは後日、ダビングしたのをあげるから、オナニーのネタにでも使ってね。それはサービス☆」 無言で料金表を眺めている僕に悪戯っぽい笑みを浮かべて、ゆうかは待合室の扉に手をかける。 「―――でも。ナマでしたのは先生が初めてだから。もし赤ちゃんできちゃったら……ふふ、よろしくね♪」 「えっ………」 慌てて振り向いた時には、既にゆうかの姿はなかった。 開け放たれた扉から、生ぬるい初夏の風が吹き込んでくるだけ。 射し込む眩い夕陽に目を細めつつ、嘆息を漏らすことしかできなかった。 *** ただ雨宿りしようとしただけなのに。 毎年、この季節に雨が降るとあの日の事を思い出すのだ。 「―――また、思い出してるの?」 呆れた眼差しを向けてくる妻に、僕は苦笑を向ける。 「僕の人生を変えた、強烈な出来事だったからね」 そして、妻も笑みを浮かべる。 あの日と変わらない悪戯っぽい笑みを。 「いやー、まさか本当にできちゃうなんてね。ま、結果オーライ♪」 「結果オーライ、ね………」 妻の言葉に、自分の人生を思い出す。 毎年恒例の事だ。 そして、結論はいつも同じ。 あの日を境に、大きく運命が変わった人生だったかもしれないが。 美しい妻と可愛い子供に恵まれて。 「―――結果オーライだな」 雨宿りの代償として、何かを失ったのかもしれない。 だけどきっと、それ以上に得たものが大きかったのだ、と思う。 だから、結果オーライ。 それでいい。 「あれ、佐藤くん……また音楽室? 今日は部活ないよね?」 音楽室に繋がる廊下を急ぎ足で歩いていた僕は、突然後ろから聞き覚えのある声に呼び止められ、ギクリとして振り返る。 「あ、秋帆(あきほ)! そうなんだ、その、今日も川上先生に呼び出されちゃって……」 秋帆は、僕の同級生で、もうすぐ付き合って2か月になる僕の彼女だ。 僕にとって一番大事な存在。 そして……今だけは一番、自分の姿を見られたくなかった存在。 「二週連続で呼び出しかあ。よっぽど悪いことしたんだね」 秋帆が僕をからかうように笑いながら言う。 「違うよ! その、今度の文化祭のことで……」 「わかったわかった。今日も佐藤君と一緒に帰ろうと思って待ってたんだけど……川上先生に取られちゃったって思うとなんかちょっと妬けるなあ。ま、いいわ。明日は一緒に帰ろ。先生と一緒に帰っちゃだめだよ」 「あ、当たり前だろ……」 冗談めかして言う秋帆が、手をひらひらと振りながら去っていく。 その様子を目で見送り、廊下の先へ秋帆の姿が消えたのを確認してから、僕は心の中でつぶやく。 ――ごめん、秋帆。 今日で、今日でほんとに終わりにするから―― ◆ 音楽室に入ると、約束通り川上先生が一人で待っていた。 この場所は放課後、いつもなら吹奏楽部の練習場所になるが、水曜日は部活が休みだから今日は他に誰もいない。 「あらあら、そんなに息を切らせて……よっぽど急いで来てくれたのかな?」 「そ、そんなわけじゃ……」 広い音楽室に僕と先生と二人きり。 放課後の少し傾き始めた秋の日が先生の顔を照らしている様子はまるで芸術作品の様で、この上なく美しかった。 率直に言って、川上先生は美人だ。 川上 泉美(かわかみ いずみ)。年は二十五歳ぐらいだったはずだ。少しウェーブのかかった黒いロングヘアが、清楚な明るい青色のブラウスによく映える。 大きな瞳に長い睫毛。授業中に時々かけている眼鏡姿も知的で素敵だが、今の眼鏡を外した姿はまるで女優の様に端正で、美しさと可愛らしさを備えている。 「女性教師」という単語は、なんとなくキツイ性格を連想させるワードだが、川上先生はむしろ明るく優しい性格の、人気のある先生だ。天真爛漫でいつも笑顔が印象的で、年下の生徒にも同じ目線で分け隔てなく接してくれる。少し子供っぽくて抜けたところがあるのもまた人気の秘密だ。 もちろん、男子生徒の中では一番人気。女子生徒の中にもファンが多い。 「鍵は閉めた? ……うん、それでいいわ、じゃ、奥に行きましょ」 先生の後について、僕は音楽室のさらに奥の、準備室の中に入っていく。 雑然と楽器が置かれた狭い準備室の中に僕と川上先生の二人だけが入ると、先生はその小部屋をしっかり閉める。 そうして、外からでは誰にも見えない状況になった瞬間。 先生は僕の肩を抱き寄せ、背中に細い腕を回し、一気に僕の唇を奪った。 ちゅっ……ぬちゅ…… 狭い準備室の中に、僕と先生の唇が触れ合う音と、お互いの服の衣擦れの音だけが響く。 僕の唇を割って、先生が舌を差し込んでくる。思わず体を強ばらせ、引き離そうとする僕を、先生は抑え込むように抱きしめながら、あたかも僕の唾液の味を確かめるかのようにその口中に舌を這わせる。 ぬちゅ、くちゅ、と卑猥な音を立てて口の中で舌が動きまわるにつれ、僕は徐々に抵抗する気力を失ってしまい、四肢から力が抜けていく。 ――ああ、また、こうなってしまった。 いや違う、こうなることを期待してここに来たのだ。授業が終わって人が減ってきたころを見計らい、秋帆に嘘をついてまで―― 普段の川上先生のイメージ、それは、春に咲く花のように明るく屈託のない笑顔。汚れたことなんて何も知らない、清楚な女性。 綺麗な人なのに、周囲に全く男の匂いがしないことがその人気に拍車をかけていた。ひょっとすると男性と付き合ったことがないんじゃないか。生徒の間では、期待も込めてそんな噂すら流れていた。 少なくとも僕は、その噂を信じていた。先週、先生に突然呼び出され、この同じ場所で、唇を奪われるまでは……。 先週、突然川上先生に音楽室に呼び出された時は何だろうと思った。 川上先生は、僕の学校で英語を教えている教師だが、学生時代の経験を生かして吹奏楽部の顧問をやっている。去年までは女子校に勤めていたそうで、今年の4月、僕らの学校へ転勤してきたばかりだ。 僕は吹奏楽部に所属していたから、顧問である川上先生とは何度か話したこともあった。だが吹奏楽部は人数が多いから、一対一で話すような機会はあまりなかったし、もちろん呼び出されるような要件にも心当たりがなかった。 先生から呼び出し、となると大抵は、秋帆が言うように悪い知らせのことが多いから最初は悪い予感がしたのだが、それでもみんなのアイドルである川上先生と話せるのは悪い気はしない。だから、何事かと思いつつも若干鼻の下を伸ばして、ワクワクするような気持ちを抱いて、二人きりで音楽室に入っていったのが先週の出来事だ。 とは言っても、みんなのアイドルである川上先生と、もっと仲良くなってやろう、程度の可愛い動機だ。だから、秋帆にも川上先生に呼び出されたと正直に言ったし、彼女に冷やかされながらも先に帰ってもらったのだ。 ――だってまさか、会ってすぐに川上先生に「私の彼氏になって」と言われ、呆気にとられて答える間もないままキスされるなんて、夢にも思わなかったから。 ましてや、舌を差し込まれディープキスされながら、僕の心を溶かしてしまうかのように優しく、いやらしく、股間を撫でられるなんて。 ズボンの上から性器を撫でまわすそのテクニックのあまりの気持ちよさに僕は、何が何だかわからないまま、そのままズボンの中で射精させられてしまって――。 それは、まだ恋人ができて2か月ばかりの僕には刺激が強すぎる経験だった。 秋帆とは恋人関係になってから何度もデートにも行っていたし、手をつないだり軽くキスぐらいはしていたが、まだ体の関係まで進展するほど、ませてもいなかったから。 先週、先生に射精させられた後、「来週もまたここに来てくれたら、今度は直接触ってあげる」と耳元で囁かれたのが忘れられなくて。 断るべきなのはわかっていたけど、結局今日もまた、来てしまった。先生の綺麗な手に、僕の男の弱点を、触られてみたいという好奇心に勝てなかった。 この一週間、先生に言われた言葉が忘れられなくて、毎晩自慰してしまった。そして逆に昨日はその自慰を必死に我慢した。今日まで我慢すれば……もっと先生に気持ちよくしてもらえると思ったから。 「ふふ、すごいおっきくなってる……何日も我慢したのかな? それじゃ約束通り、今日は中まで触ってあげる……♡」 川上先生の白い手が、するりと僕のズボンの中に。さらに下着の中にまで入ってくる。 ――ああ、今日こそ、先生に直接触ってもらえる。触られてしまう。 あと、これだけ。これだけ体験したら、終わりにしよう。今日、川上先生の手で射精させてもらうんだ。大人の階段を上って、それで満足しよう。 その代わり、一度射精して冷静になったところで、先生と付き合うという誘いはハッキリ断るつもりだ。美味しいところだけ味わって、その後はまた秋帆と正常な恋人関係に戻ってやるんだ。 だから、今だけ、あと一回だけ、ごめん、秋帆―― だが、そんな自分にとって都合のいい考えが甘かった事を……先生の柔らかな手が僕の股間に侵入し、その感触が伝わってきた瞬間、嫌というほど思い知った。 だって、僕のペニスの上を、滑らかにするりと滑っていく大人の女性らしい細指の感触は、もう訳がわからなくなるくらい気持ちよくて、僕の理性をぐずぐずに溶かしてしまったから。 それまで考えていた秋帆の顔もあっという間に吹き飛んでしまい、先生の誘惑を断るという決意が一瞬で揺らいでしまったから。 川上先生は最初にペニスを少し弄び、僕の理性をドロドロに蕩けさせてしまったあとは、あえて性器に直接触れず、僕の腿の付け根部分や、お尻の割れ目の部分といった敏感なところを、スッ、スッ、とソフトタッチで優しく、どこまでも優しくさすってくる。 僕のペニスは触れられてもいないのに、魔法にかけられたように一層激しく、硬く反りあがっていく。 「あ……♡ あ……♡」 「あはは、佐藤くん、気持ちよさそう……♡ ……ねえ、私と付き合って欲しいって話、考えてくれたかな?」 「はいっ、それはっ……いやっ……僕には、彼女が、秋帆がいるからあっ…… ひいっ!♡」 今誘われたら、思わず頷いてしまいそうだった。 それでも僕が何とか断ろうとしたタイミングで、股間を這い回っていた手がペニスに絡みついてくる。 先生のひんやりとした指先の感触に思考を奪われて、まともに答えられない。 「知ってるよ、だから、秋帆ちゃんと別れて、私と付き合って♡」 「そんなことっ……できっ……できな……♡」 「本当にそう思ってる? そんなに大事な彼女さんがいるなら、またここに来ちゃダメだよね? ふふ、こんな事されるって分かってたのに、ひどい彼氏さん……♡」 「だって……こんなの我慢できな……っ……♡ どうして、どうしてこんなっ……」 「どうして? そんなの、君みたいなコが好きだから……それ以外に理由なんている? 私、君みたいなタイプの男の子が好きなの。だから奪ってでも手に入れたいんだ♡ ほら、私のテクニックをちゃんと味わって、もう一度考えてみて……♡」 先生は俄かに信じがたいような卑猥なセリフを、あっけらかんと言ってくる。 細長い腕が、蛇のように僕の背中に巻き付いてきて、抱きしめられる。大人の豊満な胸が僕の体に押し付けられる。 瑞々しい唇が、再び僕の唇に押し付けられる。舌が、唇を割って、ぬるりと侵入してくる。 ――ああ、もうダメだ。先生の与えてくる快楽にどっぷりと浸かってしまうのが、心地よすぎて―― 思考力がどんどん奪われていく。このままではまずい、そう思って今更ながら身体を引き離そうと試みるが、舌で舌をなぞられ、とろとろと甘い唾液を流し込まれた瞬間、力が入らなくなる。 僕はもはや、大人のキスのテクニックに、されるがままになってしまっていた。 「あはは♡ もう、ガチガチだね……♡」 すべすべとした細い指がにゅるにゅると男根に絡みついて、先端の皮を器用に剥いてくる。 四本の指が竿を支え、親指が露出した先端を捉え、亀頭にカウパー液を塗りたくるようにぐりぐりと撫でまわしてくる。 キスと手で、上半身と下半身を同時に気持ち良くされ、僕は抵抗するのも忘れて先生の体にしがみつき悶える。 「あっそれ…… それ、いいっ♡」 「……先っぽから、いっぱい何か出てるよ♡」 ぬちゅ♡ ぬちゅ ぬちゅ♡ 僕のペニスからは我慢汁が次から次へと溢れ、先生の手淫に粘着質な水音が混ざり始める。 もともと端正な顔立ちの川上先生の顔がいやらしく歪み、僕の股間を気持ちよくしてくれているという光景が、僕を興奮させる。 ――だめだ、先生の事がどんどん好きになっちゃう……いや、ひょっとして初めから僕は、川上先生の事が―― 「あっあっ……♡ 先生っ……出ちゃっ……出ちゃうよ……!」 「出ちゃうの? 出しちゃったら、私とお付き合いしますって事でいいかな?」 「……っ! そんな、ずるいよ……!」 この状況で射精を我慢できる男子がいるだろうか。僕は息も絶え絶えになりながら抗議するが、 「そう、じゃあやめて欲しい? それならいつでも、やめてあげるから」 「……!」 先生の手が僕のペニスを扱く動きが一瞬止まる。 手が、僕の下着の中から引き抜かれそうになる。 このまま射精できないのでは、という不安が頭をかすめる。ここまで昂らされて途中で止められたら、どうにかなってしまいそうだ。 ――嫌だ。やめないで。出したい。射精したい―― 「や、やめないで……」 「ふふ、続けてほしいんだね♡ じゃあ、合意の上、ってことで♡」 先生の手がぬるりとペニスに絡みつき、また動き始める。 先ほどよりスピードアップし、僕をイかせるため、搾り取るような動きに変わる。 ぐちゅ♡ ぐちゅっ♡ ぐちゅ♡ ぐちゅっ♡ 「あっ♡ あっ♡ 先生っ……♡」 「ほらいいよ、私の手に、どぷどぷって一杯出して♡ ここ、音楽室だから、声出しても、聞こえないから……♡」 先生の掌の上で、翻弄される。 普段は優しく清楚で、まるでエッチな事なんて何も知らなそうな川上先生。 それがまるで豹変してしまったかのようにいやらしい言葉を口にしながら僕の性器を責めまくり、僕を射精に導こうとする様子は例えようもなく淫らで、そのギャップに僕は興奮が抑えられず、先生に弄ばれるのが癖になってしまいそうだった。 普段から、憧れの存在ではあったけど、それはテレビでアイドルを遠くから見るみたいなもので……まさかその川上先生が、僕と、こんなことを……! 「佐藤君、腰がガクガクしてきた♡ 壊れちゃいそうだね……♡ ウフフ、壊してあげる……♡」 ぐちゅっ! ぐちゅぐちゅっ! 「あ……いぐっ! ……いっ……!!♡♡」 どくっっ! どくどくどくどくっ! どく、どく…… 最後は声にならない声を出しながら、パンツの中に入り込んだ先生の柔らかい掌の中に、僕は精液を吐き出す。 先生の指が、僕のペニスから青臭いエキスを搾り取るかのようにぐにぐにと蠢く。 僕は膝をガクガクと震わせて、立つのもやっとだった。先生の手と指が僕のペニスと擦れる感触を少しでも味わおうとするかのように勝手に腰が動く。 先生の手が受け止めきれなかった精液が下着を汚し、さらにその外のズボンにまで溢れてくる。 「あーあ、ちゃんとお返事もできないまま、今日も私のお手々だけで出しちゃったね……♡」 「あ……♡ っあぁ……」 「私と付き合うかどうかについては、もう少し時間をあげる。来週は新しいレッスンに進もうね。次はこことか……どうかな?」 自分の唇を指さしながら妖艶に笑う川上先生の笑顔を、僕はまともに返答もできず、射精直後の朦朧とした意識のまま眺めるしかなかった。 ◆ 一度だけ手でしてもらったら、終わりにしよう。そんな都合の良い僕の考えは、蜜のような甘い快感を味わったその日からどこかに吹き飛んでしまった。 直接川上先生の手に扱いてもらった快感を僕は到底忘れることができず、翌週もふらふらと、先生の待つ音楽室へ足を運んでしまった。 翌週は、約束通り先生の口と舌を使っての特別レッスンを受けた。 始めはいつもどおりキスから。口の中に先生の舌をねじ込まれ、これまで何度も味わったそのいやらしい動きを復習させられ。 次に舌は口から下へどんどん降りていき、首筋をじっとりと舐められた。首筋だけでも感じてしまうという事を、この時に初めて学んだ。 次は乳首を、舌でねっとりと舐められた。口の中に乳首を含まれ、舌先で飴玉を転がすようにレロレロと舐められると僕は甲高い喘ぎ声を止められなくなった。乳首をしゃぶられながら、股間を揉みしだかれると、少しも我慢できず漏れるように軽く射精してしまった。 さらに射精後も衰えずギンギンになった股間の立派な一物を、口にくわえられ、嫌というほどしゃぶられ、舐められ……アイスキャンディーを味わうかのようなねっとりとした舌使いでフェラチオされる快感を教え込まれ、その生暖かい口内にたっぷりと射精した。 乳首攻め、フェラチオでの射精という基本をマスターした僕は、次から応用問題を学ぶことになった。 キス手コキ、乳首攻め手コキ、耳舐め手コキ。 特に僕はディープキスされながらの手コキにハマってしまった。されればされるほど、回数を重ねるほど僕は先生の手コキが好きになって、先生とのキスが気持ちよくなって、先生のことが好きになって……。 最後は足腰が立たなくなって、先生にしがみつき、抱きしめられながら射精するのか気持ちよくてたまらなかった。 結局僕はそうやって毎週のように先生に誘惑され、射精し続けた。毎週、吹奏楽部の練習がない水曜日に僕は音楽室の準備室に入って行き、そこで目眩くような先生の課外授業を受けた。 僕はようやく気が付いた。普段の清楚な先生の方が、演技だったのだ。川上先生の性的なテクニックは、一朝一夕で身につくようなものではなく、きっとこれまでにも沢山の男を……ひょっとしたら、僕と同じ様な男子生徒を手玉に取ってきたであろう事を想像させるだけの圧倒的な快楽を僕に与えてきた。僕に考える時間を与えると言って、少しずつ僕をその身体の虜にしてしまうのも、先生の計算通りだったのだろう。 一見清楚で純真に見えていた川上先生の用意した巧妙な罠。その罠に気づいた時にはすでに遅く、僕は先生の身体にずっぽりとハマり抜け出せなくなっていた。 家で行う自慰の際に川上先生が登場する回数はますます頻度を増していった。 以前の様に恋人の秋帆の顔を想像しながら致そうとしても、興奮が高まるにつれていつの間にか先生の顔に置き換わってしまう。 僕は猿のように毎日オナニーに励んだが、だんだんその自慰すら不満を感じるようになった。お願いすればすぐに先生に直接触ってもらえるのに、自分の手で射精するなんて味気なくて、勿体ないと思った。 だから、ますます先生の元に通っては、溜まった性欲を抜いてもらうようになった。 そんな状態だったから、週に一度の水曜日にしか使えない音楽室での淫行はやがて、別の場所で……例えば、先生の車の中で行われるようにもなった。 僕は約束の時間になると、授業中にも関わらず体調が悪いと嘘をつき、保健室に行くように見せかけて、駐車場に向かう。 先生が通勤に使っている車は、格好の隠れ場所だった。先生の車は覗き見防止のブラインドが設置されていたし、遮光シートも貼られており外からほとんど見えない。さらに日中、地下駐車場に出入りする人も少ない。 まだ授業中、恋人の秋帆は真面目に授業を受けている間……僕は、川上先生の車の中で大人のキスをされ、全身を愛撫され、ペニスを口いっぱいに頬張られ、どくどくと射精していた。 こういった事を繰り返しているうち、僕は川上先生の担当する英語の授業中や、吹奏楽部の練習中など、先生のすらりと伸びた手や足を見ただけで勃起してしまうようになった。 そんな状態の僕に気づいた先生は、僕のそばを通るたび、誰にも分からないように、僕の手にすっと触れたり、さわさわと太腿を擽ってきたりした。それだけで僕は体がビクンと反応してしまい、周りの友達にばれないかヒヤヒヤしていた。 そしてそんな日は、僕はもう我慢できなくなり、自分から先生に連絡を取って……授業中に勃起してしまっていたことを耳元でからかわれながら、性器を弄られた。 そうやって先生に責められるといつも以上に僕はマゾヒスティックな快感を感じ、ビクビクと悶えてしまい、思う存分射精するのだった。 何度もやめようと思った。断るべきだとわかっていた。 恋人の秋帆ともしたことのないような性的な行為を、付き合ってもいない川上先生とすることへの罪悪感は常に頭に付きまとっていたが、断れなかった。断り切れなかった。川上先生の淫らなレッスンを定期的に受けているうちに、女性に一方的に責められる快楽が麻薬のように僕の脳を蝕み、病みつきになって、やめられなくなってしまったのだ。 それに……先生はとても美人で、そしてエッチだったから。その誘惑を断ち切るのはあまりに難しかった。遠くから見ているだけでも綺麗な、皆のアイドルである川上先生が、僕の前でだけその整った顔をいやらしく歪めて、僕だけに性の知識を教えてくれる先生になってくれるのは凄く興奮した。秋帆と付き合っているだけでは決して味わえない大人の体を、嫌というほど味わわせてくれた。 秋帆は、僕が川上先生とこんな仲になっているなんて夢にも思っていなかっただろうし、少しも疑うこともなく僕のことを想っていてくれたから、裏切るわけにはいかなかったのに……何も悪くない秋帆に対して別れを切り出すこともできず、僕はずるずると先生と深い関係になっていき、秋帆のことを裏切り続けた。 ■ 「……そっか、今日も部活、なんだ……。土曜日だから遊べると思ったけど、忙しいんだね」 「秋帆、ごめん……来週こそ……っ ……んっ!」 「……どうしたの? さっきから様子が……」 「いやっ…… っ……♡ なんでもっ……なんでもないから……」 「……? わかった、じゃあ。また電話するね。」 秋帆との通話が切れる。 ――ああ、僕はまた嘘を……秋帆ごめん、ごめん……っ―― 「……ふふ、よく我慢したね♡ このまんま、秋帆ちゃんに君のかわいいイキ声を聞かせてあげてもよかったんだけど」 僕は、とあるマンションの一室にいた。 綺麗に整えられたベッドの上で……全裸で、川上先生に上に乗られて。 ここは、川上先生が一人で暮らしている家。そう、僕はついに、先生の家に一人でやってきたのだ。 誰の邪魔も入らない状況で今日、先生が教えてくれるコト。その期待に胸を膨らませ、股間をガチガチに硬くしながら、初めて入った川上先生の部屋。そこは20代の女性らしい、可愛らしい部屋。先生のいつものいい匂いがいっぱいの部屋。 そこで僕はいつもどおり先生にキスをされた。服を脱がされ、乳首を責められ、ペニスを手と口でたっぷりと可愛がられ。 そして、ベッドの上に仰向けに押し倒されると、前戯でガチガチに直立した肉棒を先生の下腹部に導かれ、濡れた秘部に先端をあてがわれ……ぬぷ、ぬぷ、という粘着質な音と共に少しずつ先生の中に飲み込まれて……。 僕はとうとう、童貞を失った。 夢にまで見た、先生との初セックス。みんなの憧れである川上先生の女体に僕の分身が挿し込まれ、下半身と下半身で繋がっているという信じがたい光景。 僕は我を忘れて、先生との性交に夢中になった。カクカクと獣のように腰を動かした。 そうやって柔らかい大人の身体に溺れているまさにその最中、突然かかってきたのが先ほどの秋帆からの電話だ。 快感で意識が朦朧としていた僕は、電話を取るべきかどうか判断がつかなくて……先生に促されるまま、電話を取ってしまった。川上先生と繋がったまま秋帆と通話したのだ。 その状態で先生がじっと待っているはずもなく……先生は僕がイきそうでイかない絶妙なタイミングで、何度もいやらしく腰をくねらせてきた。僕が嬌声を必死に我慢しながら、通話を終えるまで。 先生はきっと、恋人の前で葛藤する僕を見てサディスティックな愉悦を感じていたのだろう。だが僕もまた、そんな状況に興奮していたのかもしれない。 僕はもう、大事な恋人であったはずの秋帆のことよりも、川上先生との刹那的な快楽に溺れる、最低な人間にまで堕落していた。 僕のペニスを受け入れたまま静止していた川上先生の腰が、またゆっくりと上下に動き始める。 ずっちゅ、ずっちゅずっちゅ、ずっちゅずっちゅ……♡ 「ああ……っ♡ もう、もう出ちゃうよ……先生……!」 「いいよ、このまま1回出しちゃお♡ まだお昼だから、このあと2回でも、3回でも、抜いてあげる……♡」 そう言うと、先生は貪るように僕の唇を啄み、舌を奥深くまで差し入れてくる。 情熱的なキスに、ここまで散々焦らされていた僕は、もう我慢ができなくなる。 僕はいよいよ先生のことが愛しくてたまらなくなり、自ら腕を伸ばし、先生の細い体を力いっぱい抱きしめる。先生も僕のことを抱きしめ返してくれる。 それはまさに、愛し合う恋人以外の何物でもなかった。 「ああ、いくっ! 川上先生っ! 好きいっ……♡」 「私も、好きだよ♡ ……きて……♡」 どくっっ! どくどくどくっ! どくどくどくどく! 僕の若い情熱が、川上先生の中で爆ぜた。 我慢に我慢を重ね、精嚢の内部でマグマの様にふつふつ沸き立っていた精液が、出口を求め次から次へと吐き出される。 「ん……熱い……♡」 先生は搾り取るように腰をくねらせると、より一層僕を強く抱きしめ、さらに僕の射精を促すかのように、乳首をペロペロと舐めてさらなる快感を送り込んでくる。 「ああっ! あ……♡」 どくっ! どくどくっ! どくどく…… 名残惜しそうにペニスが何度も脈打つ。 射精は何度も繰り返され、気怠い心地よさがいつまでも続いていた。 ◆ 2回や3回どころでは終わらなかった。 僕と先生は、昼にそのまま2回戦、3回戦。 少し休憩した後お風呂で1回、手や口で抜いてもらい、夕飯を食べて1回、深夜にまた2回。 この日は土曜日だったから、翌日も学校はない。僕は家に帰してもらえなかった。母親には、友達の家に泊まると嘘をついて、先生の家に泊まって行った。 翌朝起きてすぐにまた1回。交われば交わるほど、身体を重ねれば重ねるほど、僕は先生のことが好きになっていった。 川上先生は4月にこの学校へ転勤してきたばかりだが、吹奏楽部に所属する僕を一目見て気に入り、特に彼女がいることが分かってからずっと、狙っていたそうだ。 どんなに真面目そうな男子でも、先生に目を付けられ、色々なコトを教えられると、その美貌とテクニックに溺れて、大事な恋人との狭間で葛藤しながらも最後には恋人を裏切り先生に心を奪われてしまう。 無理やりに犯すのではなく、男子が自分から川上先生を選ぶように誘惑する、それが愉しくてたまらないらしい。 明るくて優しくて男なんて知らなそうな表の顔と、好みの男子を狙う根っからのS女性という裏の顔を併せ持った川上先生の毒牙に僕はまんまとかけられてしまったのだ。この学校に転勤してきたのも、前の女子校には先生の大好きな男子がいないからなのだろう。 川上先生の思惑通り、すっかり調教されきってしまった僕は今、四つん這いになり、背後に覆いかぶさってくる川上先生に乳首をクリクリと弄られながら、牛の乳を絞る様にペニスを扱かれていた。 しこしことペニスを扱きあげる指の動きに加えて、さらにお尻の穴にも、ローションでぬるぬるになった先生の細い指が入り込んでくる。 前立腺を刺激されながらの手コキ。もちろん人生初めての経験だ。 今日だけでもう何度も先生に射精させられたにも関わらず、僕のペニスはその未知の快楽に硬さを取り戻し、さらに僕をおかしくしてしまうには十分だった。 「あっ♡ 先生っ♡ それっ♡ すごいっ♡」 「あはは、佐藤くん、あんなに出したのにまた出ちゃいそう♡」 「アッ♡ ……先生♡ 先生……♡」 「ふふ、気持ちいい? ……佐藤君、そろそろ私と付き合ってくれる気になったかな?」 「あ……♡ 僕、先生とっ♡ ……つき……付き合っ……」 言えない。どうしても最後の一言が言えなかった。 もう、ここまでシてしまって、後戻りなんてできないところまで来ていたのに。 ただ、秋帆への罪悪感が喉につかえて、自分のしている行為があまりに最低すぎて、自分の口からどうしても言い出せなかった。 僕はこのところ、全く秋帆と連絡を取らなくなっていた。 川上先生に定期的に会うようになった最初の頃は、秋帆との約束だけは守ったり、できるだけ一緒に帰るようにしたり、涙ぐましい努力で何とか元の関係に戻ろうとしていた僕だったが、最近では彼女とのデートの約束もすべてキャンセルし、先生に会うことを優先するようになっていた。 会ってもお喋りしたり手をつないだりするだけの秋帆よりも、会うたびに下半身を気持ちよくしてくれる川上先生に会いたいと思うようになってしまった。 あんなに好きだったはずの秋帆との純粋な思い出はすっかり色褪せてしまって、直接的な快楽を与えてくれる川上先生のほうに僕の心は奪われていった。 「アハハ、どうしても言えないみたいだね。 ……それじゃあ私が、秋帆ちゃんにサヨナラ、させてあげるね……♡」 先生が、美しく冷たい微笑を浮かべる。 ベッドサイドに置かれた僕のスマホを取り上げ、電源を入れる。彼女の、秋帆と一緒に写った待ち受け画面が現れる。初めて彼女が出来て、嬉しくて嬉しくてたまらなかった頃に撮った写真。 そして、初めてのデートで一緒に買った、秋帆とお揃いのスマホケース。 その思い出のスマホを、先生は僕のペニスの真下に置いた。四つん這いにされた僕のペニスの先端が、ちょうどスマホの方に照準が合うように。 「もう君の中で結論が出てるって証拠、今ここで見せてあげる。佐藤君は私の事が好きすぎて、今まで付き合ってた彼女の事なんて、どうでもいいっていう証拠……♡」 先生が何をさせようとしているのか、僕は今から何をしようとしているのかが分かった。 ああ、ダメだ、僕は。僕は。 全身を襲う快楽に朦朧となった頭でうっすら理解しながら、でも、もう、我慢の限界だった。 ぐちゅ♡ ぐちゅ♡ ぐちゅ♡ ぐちゅ♡ 肉棒が扱き尽くされる淫靡な水音が響く。脳内が桃色に染め上げられる。目の前が真っ白になっていく。 僕のペニスはもう、先生の魔性の指先にぐちょぐちょにされて、濡れた舌が僕のお尻の穴をかき混ぜて、何が何だかわからなくなって。 ああ、ごめん、ごめん秋帆……僕は……! 「出るっっ……!!」 どびゅっっっっ! どぴゅるるるるっ! どぷっ……どぷ…… 僕は川上先生の手に導かれ、スマホの待ち受けにしていた彼女の写真に向けて、大量に射精した。 飛び散った精液がスマホにかかり、秋帆の、元恋人の顔を汚していく。 ――ああ、ごめん。秋帆……ぼく、ぼく…… 川上先生の誘惑に負けて……僕はもう、秋帆より先生の事が……好きになっちゃって…… 秋帆に何も言わないで、川上先生と付き合うことに―― イっている最中も、先生の手が、ぐっちゅぐっちゅと僕の魂を搾り取るように動き続ける。 その度に、僕は無様に射精し続ける。白濁液が次から次へとスマホにかかり、汚れていく。 精液が画面にかかるたびに、まるで、秋帆と築き上げてきたかけがえのない絆が穢され、壊れていくのが目に見えるかのようだった。 汚れは拭けば元に戻るかもしれない。だが、秋帆の顔と、思い出のスマホケースに、秋帆以外の女性の手に導かれて精液をぶちまけた事実と記憶は決して消すことができない。 僕はすでに体を先生に奪われていたが、とうとう心までも秋帆を裏切り、名実ともに川上先生のものになってしまったのだ。それを、今まさに自分で証明してしまったのだ。 「……改めて聞くわ、佐藤君、私の彼氏になってくれる?」 「……はい、なるっ……♡ なります……♡」 「うふふ、良かった。じゃあ、私と付き合うことになった思い出に、午後は一緒に新しいスマホケースを買いに行こうね。今日からもっともっとイイことしてあげる。学校でも、家でも……♡」 川上先生が嬉しそうに僕をベッドに押し倒す。 再び僕の上に馬乗りになると、啄むようにキスの雨を降らせ、僕をしっかりと抱きしめる。 今日もきっと、先生が飽きるまで、離してもらえないだろう。 ――ああ、このあとも、スマホケースを買いには行けそうもないな。 川上先生の体温と重さを身体で感じながら、欲に染まり切った頭の中で僕は、そんなことをぼんやりと考えていた。 夹书签 往前1 / 1 页继续 赞! 匿名さんのリクエストで作られた作品 先生と僕の放課後特別レッスン 僕の同級生の彼女、秋帆。まだ付き合って二ヶ月だが、普段から一緒に帰ったり仲良くやっている。 今日は、所属する吹奏楽部の顧問で、学校でも一番の美人と評判の川上先生に音楽室へ呼び出された。要件はきっと先週と同じだ。そう、先週も同じように呼び出された僕は、二人きりの音楽室の中で川上先生にあることをされて……。だから、今週も行かなければ……。 逆寝取られ。 HO-HO! 突然だけど、皆さんはサンタクロースってこの世にいると思う? え?いるはずないって? 夢がないことをおっしゃいますな~。 実は、サンタクロースは実在するんだ。 それが、国際サンタクロース協会公認サンタクロース。 グリーンランドにあるこの協会の承認を得た人は世界中で公認サンタクロースとして活動することができるんだよ。 夢のある話だよねー。 とはいえ、サンタクロースだらけになっても大問題になるという訳で、厳しい選考をパスした人だけが公認サンタクロースを名乗ることが許されるようになっているんだ。 まず、サンタクロースになるためには4つの資格を満たさなければならないよ。 1.結婚している事 2.子供がいる事 3.これまで、サンタクロースとしての活動経験がある事 4.サンタクロースに相応しい体型である事(衣装やその他の装備込みで、体重120Kg以上) もうこれだけでかなり厳しい条件だと言わざるを得ないよね。 サンタクロースとしての活動経験って、どういう経験を指すのだろうね。 でもまだまだ、サンタクロースへの厳しい道は始まったばかり。 上記の条件を満たし、書類選考を通過したサンタクロース候補者たちは、デンマークの首都コペンハーゲンにある世界最古の遊園地・バッケン遊園地に出向かなければならないんだ。 オンラインで試験を受けられるほど、サンタの世界は甘くはないんだね。 しかも、この試験、自宅を出る時から始まっていて、試験会場までサンタクロースの格好をしていかなければならないんだ。 どこで審査官が目を光らせているかわからないから、一瞬たりとも気を抜いちゃだめだ。 電車も、出国審査も、飛行機も、注目されること間違いなし。 気を抜いているところを写真にでも撮られてSNSに投稿されたらと思うと、気が気じゃないよね。 その上、試験が行われるのは真夏だと言うから苦行以外の何物でもないわけだ。 でも、こんなことでへばっていたらサンタクロースにはなれない。 厳しい選考は、ここからが本番なのさ。 試験会場に着いたサンタクロース候補者たちを待っているのは、体力測定。 これがなかなかにえぐい代物なんだ。 まず、50mを全力で走る。 そして、梯子で煙突(高さ280cm、内幅120cm×120cm)に登り、煙突の中に入り、その下の暖炉から這い出て、樅の木の下にプレゼントを置き、暖炉の上に置かれたクッキー6枚と牛乳568mlを完食。 再び暖炉から入って煙突から出たら国旗を振り、梯子で煙突から降りて再び50m疾走してゴール。 笑っちゃうほどハード! しかも、合格基準は2分以内。 アスリートかよっ!! サンタクロース候補者たちは装備込みで120Kg以上あると言うのに、凄まじいまでの俊敏性を発揮しなければならないわけだね。 あんまりサンタクロースにきびきび動けるイメージはないけれども、実はすごいムキムキだったりするのかも。 もうへとへとだろうけど、サンタクロースへの道はまだまだ続くよ。 体力測定の後は長老サンタクロースによる面接で、英語かデンマーク語で自己紹介を行うんだ。 そして、身だしなみ、装備品の審査。 ちなみに、各サンタクロースの衣装は候補生の出身地の伝統や風習に合った衣装を自作しなければならないんだ。 サンタクロースには裁縫技術も必須という訳だね。 そして、最後に宣誓文の朗読。 試験会場に集まったすべての公認サンタクロースを前にして、宣誓文をすべて「HO HO HO」のみで朗読します。 え、マジで?って思うよね。 そう、真剣と書いてマジと読みます。 笑っちゃいけないよ。笑うと敦姉がメガネ外して怒るからね。 敦姉って誰って?脱線するので説明は省くけど、気になるなら「マジすか学園」をググろう。 話を元に戻して、宣誓文の朗読だけれども、この朗読はすべてのサンタクロースが納得するまで何度も繰り返し続けなければなりません。 もはや軽い苛めレベル。 こんなレンジャー部隊かよっという感じの試験をパスした公認サンタクロースは現在世界に約120人。 アジアでは日本にたった1人いるだけなんだ。 ―――えっ?話の流れ的に、俺がその一人なのかって? いやいや、俺は単に町内会長の爺さんに押し付けられて、町内の子どもがいる家庭を回っているだけのしがないサンタさ。 体重120Kgもないし、嫁も娘もいない身では、公認サンタクロースになる事は難しいだろうね。 ぶつぶつと独り言で蘊蓄を垂れ流しているのは、単に寒いから。ご容赦ください。 ―――閑話休題。 「―――さて、次は、滝沢さんちの蛍ちゃんか」 町内に配る30個ばかりの様々なプレゼントが入った麻袋を担ぎなおす。 「重っ、そして寒いっ」 ぼやきつつ、滝沢家の庭に入り込む。 うっすらと積もった雪がさくっ、と音を立てる。 ホワイトクリスマスだなんてロマンチックだと宣うのは、頭にお花畑が広がってるような連中だけで、大抵の人にとっては迷惑でしかない。 俺にとっても例外ではない。 寒いし。音出るし。足跡残るし。ぶっちゃけ、サンタからしたらクリスマスに風情とかロマンは要らないのだ。こちとら、これが仕事なんだから。 門扉には、某警備会社のロゴシールが貼ってあるが、家主が事情を説明して今日は稼働していない。 まぁ、サンタクロースには“ネマワシ”という魔法が必須だね。 昔と違って、煙突とかないし。セキュリティ万全だし。 庭から家の様子を窺うに、寝静まっているようだ。 リストに目を落とす。 「えーと、庭の右隅に梯子……っと、あったあった」 事前に家主から聞き取りしていた情報通り、梯子を発見する。 何事にも用意周到なのが、町内会長のモットーなのだそうだ。 「なまら冷たいっ」 冷えた鉄程冷たいものは、この世の中で熟年妻の視線ぐらいなものだろう。 熟年妻なんて俺にはいないけどね。あはは。 あと、「なまら」と発言したが、別に北海道民という訳でもない。 「え~と、蛍ちゃんの部屋は右から3番目の窓、と」 馬鹿な事を脳内で呟きながらも、着々と作業を進める俺。 格好いい。誰も褒めてくれないから、もう自分で褒めちゃうよ。 音を立てないよう慎重に梯子をかける。 安定している事を確認し、一段目に足を乗せる。 予め、家主にはちゃんと梯子の錆などを落としてもらっているので、不用意にギシギシ音などはしない。 準備万端、抜かりなし。素晴らしい。ブラボー。 慎重に梯子を上り、カーテンの隙間から部屋の様子を窺う。 窓のすぐそばにベッド。 少女が眠っている。 近所でも美少女と名高い、滝沢蛍ちゃん。 なんでも小学校の入学式の時には、彼女が歩いた傍から桜が開花していったとかなんとか。 桜の開花と入学式の時期って、違うよね?とかいうツッコミはなしだ。 伝説と言うものは、得てしてそういうものなのだから。 そもそも、サンタクロースの元となった聖ニコラオスの祝日は12月6日であって、子どもたちが枕元に靴下を飾ってお菓子を貰うのはこの日なのだ。 12月25日は聖体礼儀に行く日であって、本来プレゼントを貰う日ではないのである。 西洋でクリスマスプレゼントの交換を12月25日にするようになったのはマルティン・ルターが1535年に提唱してから。まだ500年しか経ってない訳だ。 ちなみに、プレゼントの金額の多寡で男性を計る女性がいるらしいけど、わかっている限りのトップはアメリカの実業家ジェンキンス・グリフィスさんだと言われているよ。 彼は1896年、ロサンゼルス市民のために公園の用地をプレゼントしてる。 広さは12㎢、東京ドーム261個分というアメリカンスケール。びっくりだね。 この公園には今、有名なグリフィス天文台があるよ。 余談はこれぐらいにして、慎重に蛍ちゃんの様子を窺う。 カーテンの隙間から差し込む月光に照らされて、濡れたような黒髪と白磁のような肌が輝いているように見える。 布団の胸元が規則正しく上下しているのを確認して、ゆっくりと窓に手をかける。 ―――サンタさんが来てくれるかもしれないから鍵を開けておきましょうね。 今日、蛍ちゃんはお母さんにそう言われ、普段はしっかりと閉めるはずの鍵を開けて就寝しているのだ。 ゆっくり、ゆっくりと窓を開けて、隙間に身体をねじ込むようにして床に着地する。 息を止め、蛍ちゃんの様子に変化がないことを確認する。 異常なし。 寒い外気で起きてしまわないように、窓を閉める。 それからゆっくりと息を吐き出し、肩から麻袋を下ろして、中から蛍ちゃん希望のプレゼントを取り出す。 かわいらしいクマのぬいぐるみ。 ―――手紙に欲しいものを書いてサンタさんに送って、良い子にしていると持ってきてくれるかもしれないよ。 そんな風に説明され、目を輝かせながら無邪気に、町内会長宛とは知らずに認めた手紙に書かれていた、蛍ちゃんの欲しいプレゼントである。 ゲームだのスマホだのとプレゼントに対する要望も高額化してきた昨今、微笑ましくて、謙虚で、懐にも優しい、まるで天使のような最高の要望だと町内会長は涙ぐんでさえいたのだ。 そのクマのぬいぐるみをそっと、蛍ちゃんの枕元に置く。 間近に見る蛍ちゃんは、ハッとするほど綺麗な顔立ちをしている。 勿論、邪な気持ちを抱いたりはしない。 そんな気持ちを抱く対象と見るにはまだ若すぎる。 (寝顔が天使すぎるな。10年後とか、凄い美人になってそう………) そんな感想を抱きつつ、部屋の中を見回して、テーブルの上に置かれたものに気づく。 お皿とコップ。 (クッキーと牛乳か………) 日本ではあまり普及していない気がするが、西洋ではサンタさんに対してクッキーと牛乳でおもてなしをするのが一般的なのだ。 (せっかくだからな……いただきます) 蛍ちゃんを起こさないよう、慎重にテーブルの傍に移動して、掛けられていたサランラップを慎重に取り外す。 クッキーを一枚手に取り、頬張る。 噛むと音が立ちそうなので、唾液でゆっくりと溶かして、飲み込む。 (甘くておいしいけど、水分持っていかれるな) そんな感想を思い浮かべつつ、牛乳を飲む。 仄かな甘みが体中に染み渡っていくようだ。 (やっぱクッキーには牛乳が合うな、うん) 用意されていた6枚のクッキーと牛乳を胃に流し込む。 寒空の下、重いプレゼントを担ぎ、誰かに見られやしないか、子どもを起こしてしまわないだろうかという極度のプレッシャーの中で任務遂行に当たるサンタにとって、クッキーと牛乳の甘さと、これを用意してくれた子どもの思いやりが実に心に沁みる。 心だけでなく、心なしか、身体も温かくなってきた気さえする。 もうちょっと頑張ってみよう、そんな気分になる。 たぶん、世界中のサンタクロースが同じような想いを抱いている事だろう。 屈強な公認サンタクロースたちも、たぶん。 (―――ごちそうさま。さて、まだまだ周らないといけないし、そろそろ行くか) 長居は無用、とばかりに踵を返そうとして。 「―――ん」 びくん、と硬直する。 蛍ちゃんが寝返りを打ったのだ。 どくん、どくんと心臓が早鐘を打つのを懸命に抑えながら、中腰の姿勢で息も瞬きも止め、蛍ちゃんの様子を窺う。 寝返りを打って顔が窓側に向いてしまったので、こちらからだと寝ているかどうか顔で確認することはできない。 もし蛍ちゃんが起きてしまえば、任務は失敗。 幼気な少女の夢を壊してしまうことになるのだ。 生きた心地もしない数秒が、気が遠くなるほどゆっくりと過ぎていく。 ―――大丈夫。 蛍ちゃんの寝息は規則正しいものに戻っている。 起きた様子はない。 ほっ、と一息つこうとして―――再び硬直する。 寝返りを打って、布団を抱えるような格好になった蛍ちゃん。 その右足が、露わになっている事に気づいたのだ。 寝巻がホットパンツであるために、太ももから足先までが露出している。 カーテンの隙間から覗く月光を受けて、瑞々しく輝くほっそりとした足。 どくん、どくん、と鼓動が早鐘を打つ。 はぁ、はぁ、と呼吸が荒くなっていく。 下半身に血が集まっていく。 (なんで………) 自分はロリコンではない。 こんな年端もいかぬ少女に、欲情などするはずがないのだ。 だと言うのに、蛍ちゃんの足から目を逸らす事が出来ない。 細いのに、柔らかそうな太もも。 かわいらしい膝小僧。 きゅっとしまった足首。 きれいな足の甲。 白魚のような足指。 桜色の爪。 いつの間にか、麻袋は床に落ちていた。 ずきずきとこめかみの辺りが疼く。 全身の血管が拡張し、普段とはまるで異なる猛スピードで血液が全身を巡っているような感覚。 全身が、燃えるように熱い。 赤いズボンの股間部分には、グランピングが出来そうなほど立派なテントが張ってしまっている。 吸い寄せられるように、蛍ちゃんの足元に跪く。 おずおずと手を伸ばし、輝くような肌に、震える指先を触れさせる。 ひんやりとして、滑らかで、すべすべの肌。 その感触に触れただけで、勃起した肉棒の先端から我慢汁が滲みだし、口の中に大量の唾液が分泌される。 (う……な、なんで……だめだ、こんな事……) 頭ではわかっている。 こんな事、絶対に許される事ではない。 すぐに手を引き、他の子どもたちに渡すはずのプレゼントを持って、この家を立ち去らなければならない。 なのに―――。 指先だけに留まらず、掌全体で蛍ちゃんの肌を撫でまわしてしまっている。 (あぁッ、触ってるだけなのに……) ずくん、ずくん、とズボンの中で肉棒が疼く。 次から次に我慢汁が溢れ出し、パンツはおろか、サンタ衣装の赤いズボンにさえ黒いシミが広がっていく。 蛍ちゃんの足を撫でながら、そっと寝顔を確認する。 (あぁっ、かわいいっ………) まるでお人形か天使のように整った顔立ち。 その寝顔を見るだけで、鼓動がどんどん高鳴っていく。 (なんで、なんで………) 疑問は尽きない。 だが、どんどん視野が狭まっていき、もはや蛍ちゃんしか見えない。 頭の中に桃色の靄が掛かったように、思考が鈍くなっていく。 その代わり、どんどん劣情が膨れ上がっていく。 (も、もう、我慢が………ちょ、ちょっとだけ……) 左手で蛍ちゃんの足を撫でながら、右手でズボンの中から怒張した肉棒を引っ張り出し、扱き始める。 「あぅっ、ぅぁっ………」 普段のオナニーとは比べ物にならないほどの快楽に、口の端から涎が零れ落ちる。 あっという間に射精感が込み上げてくる。 (だ、出す、訳にはっ……!) 理性が警鐘を鳴らすが、蛍ちゃんの足を撫でる左手も、肉棒を扱く右手も、動きを止めるどころかむしろ加速していく。 歯を食い縛って耐えようとするが、滑らかな蛍ちゃんの肌の感触に力が抜けていく。 快楽が膨れ上がって、膨れ上がって―――呆気なく弾けた。 どびゅどびゅっと大量の白濁液が噴き出す。 噴き出た白濁液は床を、ベッドを、布団を、そして―――蛍ちゃんの足を汚していく。 今までに味わったどんな射精をも上回る快楽。 (やってしまった……俺は、なんてことを……っ!!) その放出感と多幸感に呆然としていた俺は、電撃を浴びたかのように目を見開き、硬直した。 蛍ちゃんと、目が合ったから。 「あ……あ……」 動揺しすぎて、言葉が出てこない。どころか息を吸う事さえできない。 馬鹿みたいに顔を真っ青にして、震えている俺を見て、蛍ちゃんの口元に微笑が浮かぶ。 くすっ、と笑う声が聞こえて、俺は漸く息を吸う事が出来た。 だが、この日初めて口を開いた蛍ちゃんが発した言葉に、俺の体は再び硬直する事となった。 「―――気持ちよかったですか、サンタさん?」 可愛い顔に微笑を浮かべて、これまた天上の鈴のような可愛い声で、蛍ちゃんはそう言ったのだ。 サンタが、醜い肉棒を握って自分の右足を撫でながらオナニーをして射精をしていると言う、俄かには信じがたい光景を目の当たりにしているにもかかわらず。 普通なら、トラウマになってもおかしくないほどのおぞましい光景であるはずだ。 だと言うのに、蛍ちゃんはまるで、こうなる事が予めわかっていたかのような落ち着いた様子で。 俺はあまりの事態に完全に思考能力を失って、ただ茫然と立ち尽くす事しかできなかった。 布団を払って、ベッドの上に座りなおす蛍ちゃん。 彫刻のような端麗な顔立ち。 シミ一つない純白の肌。 上はキャミソール、下はホットパンツ。 覗く肌の多さに、相手が普段はまるで意識などするはずもない年齢の少女である事さえも忘れて魅入られる。 その肌を、自分の精液が汚していると言う事実に、言い知れぬ興奮が募る。 「あ……あの……俺は……」 「わかってますよ、サンタさん。大丈夫。サンタさんは今、お薬の影響でエッチな気分になっているだけです」 「………。は?」 目の前の美しい少女が発した言葉に、馬鹿みたいな、言葉とも言えぬ音を漏らす俺。 「そう、お薬。知り合いに貰った媚薬です。クッキーにも牛乳にもたっぷりと入れてあったんです。だから―――」 蛍ちゃんの眼差しが、俺の股間に向けられる。 美少女に見られている。 そう考えるだけで、射精して尚、全く硬さを失わない肉棒が震え、先端から透明な雫が溢れだす。 それを見て、蛍ちゃんが小さく笑い声を漏らす。 「び、媚薬?そ、そんなもの、どうやって……」 「それは秘密です♪」 愉しそうに、蛍ちゃんが囁く。 「な、なんで、こんなことを………」 「プレゼントが欲しいんです」 俺の言葉に、蛍ちゃんが答え、麻袋を見る。 「そこに、他の子たちにあげるはずのプレゼントが入っているんですよね?」 確認するように言って、首を傾げたまま、俺を見て微笑む蛍ちゃん。 つまり、他の子にあげるはずのプレゼントを寄越せと言う事。 ―――微笑ましくて、謙虚で、懐にも優しい、まるで天使のような最高の要望 脳裏に、町内会長の涙ぐんでいた姿が思い浮かんでくる。 冗談じゃない。 天使どころか、まるで悪魔じゃないか。 「ふざけるな。そんな事できるはずないだろう」 怒りを感じるままに、少し声を荒らげてしまった。 だが、蛍ちゃんは怯える様子など一つもなく、自身の形のいい唇の前に、美しい指を一本立てる。 「しーっ。大きな声を出すと両親が起きてしまいます。そうなったら―――」 その視線が、自身の足に向かう。 その目線の先を追って、いや追うまでもなく、背筋が寒くなる。 白い肌を汚す、点々とこびりついた精液。 口元に浮かんでいた笑みが、諧謔的な色を帯びる。 それに反比例するかのように、俺の顔は青白くなっていっている事だろう。 「困るのはサンタさんの方なんじゃないですか?」 笑みを含んだ声音には、圧倒的な勝利を確信した優越感が含まれていた。 それを感じ取って、俺が感じていたのは雁字搦めの敗北感。 急速に怒りは萎み、幼気なように見える少女に対する恐怖感が膨れ上がる。 「っく……。だからって……」 否応なく立場を思い知らされて、懸命に言葉を探すものの、反抗の糸口さえ見いだせない。 「勿論、私もわかっていますよ。“プレゼントを貰えるのは良い子だけ”って」 意味深な声音で囁きながら、そっと右足を伸ばす蛍ちゃん。 その爪先が、俺の太ももに触れ、くるくると円を描く。 たったそれだけ。ズボンの上からの僅かな接触だけで、どくん、どくん、と股間にさらに血が集まっていき、肉棒がより固く隆起していく。 こんな状況であるにも関わらず、浅ましくも欲望を主張する肉棒が、快楽の予感にわななく。 「あ……ぁ……」 指先が、徐々に股間に近づいていく。 一歩下がれば、逃れられる。 それがわかっていながら、俺はその場から動くことができなかった。 恐怖心が、劣情に飲み込まれていく。 逃げない俺を見て、蛍ちゃんはますます勝利を確信した事だろう。 ゆっくりと近づいてきた足が、俺の肉棒に触れる。 根元から、触れるか触れないかの絶妙な距離を保ったまま、裏筋をつぅっと撫でられる。 「ぅっ、はぁ……❤」 たったそれだけの事で、膝ががくがくと笑ってしまう。 親指の腹で、亀頭をタップする。 「んっ、はうっ……❤❤」 爪先でカリ首をくすぐられ、血管をなぞるように根元へ。 「はぁぁんっ……❤❤❤」 足の甲に玉袋を載せて、たぷたぷと弄ばれる。 「う、そ、そこは……❤❤❤❤」 一つ一つの動作で他愛もなく喘がされる僕。 脚一本で翻弄される、そんな僕を、蛍ちゃんはうっすらと笑みを浮かべたまま見守っている。 玉袋の中で、急速に精液が生産され、射精の瞬間を待ち焦がれて煮え滾る。 「ね、サンタさん?……蛍は“良い子”?」 僕の限界が近いと悟った蛍ちゃんは足の裏で肉棒を扱きながら、小首を傾げて上目遣いに訊いてくる。 年齢に似つかわしくない、さながら男を手玉に取る娼婦のような巧みな技巧で、射精寸前ぎりぎりの快楽を俺に与え、篭絡し、甘い屈服へと誘おうとする。 その顔は正直言ってとても可愛い。 なのに、恐ろしい。 恐ろしいのに、ときめきが抑えられない。 翻弄され、弄ばれ、支配される事に、堪らない興奮を覚えて、思わず頷いてしまいたくなる。 頷いてしまえば。 きっと、このまま射精させてもらえるだろう。 自分でオナニーするのとはきっと比べられないほどの快楽を得られるに違いない。 だけど、彼女に屈服すると言う事は、プレゼントを心待ちにしている子供たちを裏切ると言う事に他ならない。 そんな事を―――仮にも、サンタの衣装に身を包んでいる自分がする訳には………。 「プレゼントくれたら、両足でしこしこ~ってしてあげる♪」 ベッドに両肘をつき、僅かに上体を反らしながら左足を虚空に伸ばす蛍ちゃん。 「ぁ………」 カーテンの隙間から差し込む月光を浴びて、輝く左足。 右足一本だけでも、射精寸前に追い込まれているのだ。 びくびくと震える肉棒が射精を求める。 さながらラッシュのような射精欲求の前に、理性が土俵際に追い込まれていく。 そんな俺に止めを刺すかのような、目の前にぶら下げられた人参。 (1個、1個ぐらいなら………) 欲望に目を血走らせ、息を荒らげ、涎を垂れ流しながら、手探りで麻袋を探って、中から無造作にプレゼントを一個取り出し、ベッドへ置く。 「ふふ、ありがと、サンタさん❤」 蛍ちゃんが笑う。 無邪気な、毒婦の笑み。 「“良い子にはプレゼント”……あげなくちゃね♪」 囁かれた言葉が、脳裏に深く刻まれる。 ゆっくりと下ろされた左足と、右足が、限界まで勃起して望陀の涙を流し続ける肉棒を挟み込む。 ひんやりとした右足と、まだ布団のぬくもりが残った左足。 温度差のある両足に挟まれて、扱かれる。 齎される快楽に、頭の中がぐずぐずと溶けだしていく。 人生観や倫理観と言った価値観さえも塗り替えられていくような悦楽によって、瞬く間に腰の奥底から射精感が込み上げてきて、俺は耐えることもできずに射精していた。 どびゅどびゅと、一度目に比べ、はるかに大量の白濁液が噴き出し、蛍ちゃんに降り注いだ。 蛍ちゃんに促されるまま、ベッドに背を向けて床に座る。 後ろから、ベッドの縁に座った蛍ちゃんに抱きしめられる。 自分よりも遥かに小さな女の子に、まるで包み込まれているような安心感。 耳をしゃぶられて。時には口づけを交わして。 乳首をくすぐられて。時にはわき腹をくすぐられて。 足で肉棒を扱かれて。足の裏だけでなく、指の間でも。 俺が射精しそうになる度、蛍ちゃんが訊いてくる。 「ね、サンタさん……蛍は、“良い子”?」 そう尋ねられる度、俺は涎を垂れ流しながら何度も何度も頷き、麻袋からプレゼントを取り出しては蛍ちゃんに渡す。 その度に、蛍ちゃんが鈴のような綺麗な声で、囁いてくれる。 「ありがと、サンタさん♪……“良い子にはプレゼント”、あげるね❤」 そして―――俺は射精をさせてもらう。 蛍ちゃんは“良い子だからプレゼントを貰う” 俺も、“良い子だからプレゼントを貰う” ただそれだけの事。 何もおかしなことはない。 プレゼントが全部なくなるまで、俺たちのプレゼント交換は続いた。 「―――そのプレゼント、どうするんだ?」 結局、持っていたプレゼントすべてを蛍ちゃんに貢いだ後、漸く薬の効果が切れた俺が尋ねると、蛍ちゃんは沢山のプレゼントに囲まれながら、笑顔を浮かべる。 「フリマアプリで売るよ♪」 (―――誰だ、天使とか言った奴は。ごりごりの現代っ子じゃねぇか……) その返答に呆れる俺に向けて、蛍ちゃんは可愛らしく小首を傾げて、 「ね、サンタさん。来年もよろしくね♪」 などと宣う。 ふざけるな、と言いたいところだったが、俺の白濁液に塗れて笑う蛍ちゃんに対してそんな言葉を口にすることはできず、ただ頷く事しかできなかった。 結局、他の子どもたちのプレゼントは自腹で購入した。 最近は24時間営業のおもちゃ屋なんかもあって、便利になったものである。 来年もきっと、俺はこの町でサンタをやっている事だろう。 メリークリスマス。 HO-HO-HO! 天使见习生 「皆、よくお聞きなさい」 荘厳な雰囲気に満たされた白い空間に、凛とした声が響く。 居並ぶ数百人もの少年少女たちが、壇上へと視線を向ける。 そこには一人の女性が立っていた。 豪奢なまでの黄金の髪、どんな芸術家でも作り出しえぬであろう美貌、その豊満な肢体を白い薄絹に包み、そこにいるだけで他者をひれ伏させずにはおかない威厳に満ち満ちている。 天使長ミカエル。 大天使とも呼ばれる彼女は、魔界との戦争において、天界の軍を率いる総大将であり、神の側近中の側近ともされている。 ミカエルは居並ぶ者たちをゆっくりと見回す。 「あなた方はこの度、天使養成課程を無事に終えました。これより後、地上界にて一週間の間、善行を積み重ね、立派な天使とならねばなりません。魔界との戦争は日々激化しています。あなた方の一日でも早い成長と共に戦える日を心待ちにしています」 『はいっ』 数百もの天使見習いたちが気負った表情で一斉に頷く。 ミカエルはようやく少しだけ表情を和らげ、 「地上に降りたら、まず教会を頼りなさい。あなたたちの道しるべを指し示してくれることでしょう」 そう言って壇上から降りていくミカエル。 天使見習いたちはホッと息を漏らしたのち、苦楽を共にしあってきた仲間同士、互いに健闘を誓いあいながら三々五々、地上へと旅立つべく歩みを進め始めるのであった。 *** 天使見習いたちを送り出し、執務室に戻ったミカエルは席に着くなり、自分の戻りを待っていた副官に厳しい視線を向ける。 「様子はどうだ、ライラ」 「よくはありません」 銀髪の天使ライラは厳しい声音で答え、 「この一週間で三つの城が落とされました。兵の損耗も多いです。やはり件の英雄を魔界に奪われたのが大きいです。彼の指揮のもと、魔界軍はより高度な戦術を用いるようになっています」 「見習いたちの早期成長に期待せざるを得ないとはな……」 「態勢を整え反撃に出るためにも、今は一人でも多くの戦力が必要です。引き続き、死者の勧誘にも勤めます」 「よろしく頼む」 壁際に飾られた天界の地図。 その4分の1ほどが、すでに黒く塗りつぶされていた―――。 *** 「―――わぁ、ここが地上かぁ……!!」 天使見習いの一人ジョシュアは、初めて見る地上の風景に目を奪われ、歓声を上げる。 天使らしい輝かんばかりの金髪に彫像の如き白い肌を持つ、可愛らしい少年だ。 きらきらと青い瞳を輝かせながら、きょろきょろと周りを見渡す。 きらきらとした街並み、活気にあふれる人々、どこからともなく漂ってくるおいしそうな匂い……。 ついつい、いろいろなものに目移りしてしまう。 「っと、ダメだダメだ。まずは教会を探さないと!」 誘惑に流されてしまいそうなところで、ハッと我に返る。 今や天界と魔界の勢力バランスは大きく魔界優位に傾き、多くの同胞たちが血を流しているのだ。 自分も早く一人前の天使となり、戦列に加わり、天界に勝利をもたらす一助となるべく努めなければならない。 こんなところで油を売っている暇はない。 ジョシュアはやる気に満ち溢れた眼差しで、教会へと歩を進めるのだった。 *** 何度か迷いかけながら、やっと辿り着いた教会は、路地裏にひっそりと佇んでいた。 少し大きめの家ぐらいの大きさで、周囲を3~4階建てぐらいの建物に囲まれ、埋もれてしまいそうだ。 緊張の面持ちで、木造りの扉を拳で叩く。 2度、3度と叩いていると、 「は~い、今開けます!」 中から若い女性の声とぱたぱたと駆け寄ってくる足音が近づいてきた。 がちゃっと鍵を外す音がし、ぎぎぃっと耳障りな音を立てながらゆっくりと扉が開かれる。 「はい、お待たせしましたぁ」 少し間延びした声と共に空いた扉の隙間から姿を現したのは、まだ若いシスターだった。 「あら?」 その、自身のものよりも少し薄い水色の瞳が、緊張の面持ちで佇む彼を捉え、わずかに小首をかしげる。 「は、はじめまして……ぼ、僕の名前はジョシュアと言います。きょ、今日からしばらくの間お世話になります!」 失礼にならないようにと何度も練習してきた挨拶のセリフを、何度かつっかえながらもなんとか口にし、一礼する。 「ってことは、君が天使見習い様?」 「は、はいっ」 「普通に来るんですねぇ」 「え?」 きょとんとした表情をしているシスターに、首をかしげる。 するとシスターはあはは、と笑いつつ、扉を大きく開けてくれる。 「いえ、実は天使見習い様をお迎えするのは初めてでして。てっきり礼拝堂とかにぷわぁ~って降臨されるのかと」 「あ~、なるほど。できなくはないんですが、修行のお手伝いをしていただくのになんというか、少し偉そうになってしまうので」 「あ。できるんですね~」 導かれるまま教会の中へ歩を進める。 そこは、10個ほどの長椅子が並べられた、小さな礼拝堂だった。 正面には、鎧甲冑に身を包んだミカエル様の像。 「改めまして自己紹介させていただきますね。私は当教会でシスターを務めておりますアンナと申します。少しの間ですが、ジョシュア様の修行のお手伝いをさせていただきます」 姿勢を正して一礼するアンナに、僕も居住まいを正す。 「こ、こちらこそよろしくお願いします、アンナさん。そ、それとできれば様付けはやめていただけませんでしょうか。まだ見習いの身、それにお世話になるのは僕の方ですので」 「わかりましたぁ、ではジョシュア君で」 「はい」 気さくな微笑みを向けられて、僕も笑顔を浮かべる。 綺麗で、とても優しそうなシスターで内心安堵感を覚える。 「それじゃまず、教会の中の案内をしてから、お食事にしましょう」 「わかりました」 アンナの案内で教会内をぐるりと回る。 とはいえ、それほど大きな教会ではないため、すぐに終わってしまう。 割り当てられた自分の居室には、先に天界から送ってもらっていた自分の身の回りの品々が、すでに荷解きもされて綺麗に片づけられていた。 早速テーブルに向かい、日誌を書き始める。 まずは無事に修行先の教会にたどり着けたことを神に感謝するとともに、優しそうなアンナさんに出会えたことも感謝する。 「修行、頑張るぞ………」 決意の言葉を記したところで、扉がノックされる。 「お待たせ、ジョシュア君。お食事の用意ができましたよぉ」 「あ、はい、すぐ行きます!」 返事をし、部屋を出る。 「あの、荷解きまでしていただいてありがとうございました」 「なんのなんの」 二人で食堂まで移動すると、食卓にはパンとスープが並べられていた。 質素ながら、とてもおいしそうな匂いがする。 食卓に向かい合って座り、まずは日々の糧を与えてくださったことを感謝する祈りを神に捧げてから、 「いただきます♪」 「どうぞ召し上がれ」 早速、パンをスープに浸して口に頬張る。 「お、美味しいっ…!」 簡単な料理だが、だからこそ、そこに込められた心の温かさを感じられるような、じんわりと体全体が温まっていくような、そんな味だった。 「口に合ってよかったぁ」 「これならいくらでも食べられそうです」 「お代わりもあるからたくさん食べてね」 「はい!」 瞬く間に料理を平らげる僕を、にこにこと笑顔を浮かべつつ見守るアンナさん。 空になったスープをよそってくれ、パンを新しく盛ってくれながら、自身も食事を進めていく。 他愛もない話をしばらくしながら食事を終え、食後の紅茶を楽しむ。 「ごちそうさまでした。こんなに楽しい食事は久々でした」 「そうなの?」 「はい、天使養成学校は結構厳しくて」 「そうなんだぁ、天使様も大変なんだねぇ」 「でも、とても素晴らしい役目だと思っています。僕も、立派な天使になりたいです」 「そのための修行だもんねぇ。頑張らないと」 「はい!」 「私もできるだけの協力をさせてもらいます」 「はい、よろしくお願いします」 「うん。……で、修行って具体的には何するの?」 紅茶を啜りながらのアンナの質問に、思わず困惑する。 「えと…ミカエル様からは教会を頼れと。そこで道しるべが示されるだろう…としか言われてません。天使となるべく、善行を積めと」 「ふぅん…やり方は各教会に一任されてるって感じなのかなぁ。ごめんね、ジョシュア君も不安だよね、私も初めての事だからよくわからなくって」 「い、いえ、あの、僕、アンナさんにやれと言われたことなら何でもしますので」 「何でも…ねぇ」 この時、アンナの瞳に過った一瞬の光に、僕は気づけなかった。 「ま、とにかく【イイコト】を一杯しなさいって事よね」 その言葉に含まれた言外の意味にも。 紅茶を啜る彼女の口元に浮かんだ、意味深な笑みにも。 *** 【修行1日目】 食事の後、風呂に入り、自室で聖書に少し目を通したのち、布団に入る。 明日からの修行の事や同胞たちは今頃どうしているだろうかなどととりとめもなく考えながら、やがて眠りの中に落ちていく。 違和感に気づいたのは、それからどれぐらいしてからだろうか。 布団とは明らかに異なる感触に包まれている。 不快ではない。 むしろ、温かくて、柔らかくて、とても安らいだ気持ちになる。 まるで幼い頃、母に抱かれて眠っていた頃のような。 「ん…」 ゆっくりと微睡の中から意識を引っ張り上げ、うっすらと目を開けると、 「あ、ごめん起こしちゃった?」 自分を包むようにして抱きしめているアンナの顔が間近にあった。 「アンナ…さん?…え、どうして?」 状況をゆっくりと認識するにつれて、思考が混乱していく。 ここは自分に割り当てられた部屋のはず。 自分は一人で布団に入っていたはず。 なのに、今、アンナに抱きしめられている。 「ふふ、一人で眠るの寂しくないかなぁって思って」 慈愛の籠った眼差しで、アンナが答える。 「え、えと、だ、大丈夫です。一人で寝れますから…」 状況を認識したところで、改めて大人の女性と同衾しているという事実に動揺してしまう。 否応なく、アンナの柔らかな肢体を感じてしまう。 「はじめて見た時から思ってたけど、ジョシュア君、凄くかわいいよねぇ」 「そ、そんなこと…んぁっ…ちょ、耳舐めないで」 僕を右側から横抱きに抱きしめつつ、アンナが僕の耳に舌を這わせる。 ぬめっとした感触に、ぞくりと背筋が震える。 「お肌もすべすべで~」 「んっ、ぁぁっ…ちょっ…」 右手が、夜着の隙間から胸元に差し込まれ、まだ薄い胸板を撫でまわす。 「きめ細やかで、それにすごくいい匂い♪……羨ましい…ふぅっ❤」 「ひぁんっ」 耳元に息を吹きかけられ、びくんっと体が跳ねてしまう。 何とかこの状況を打破しようと試みるが、しっかりと抱きしめられていて身動きできない。 「な、なんでこんなことぉ……」 思わず涙目になりながら訴えかけると、 「これも修行よ」 「しゅ、修行!?」 アンナの口から思いもよらぬ言葉が飛び出してきた。 「そう❤…あなたはこの一週間で、【イイコト】を一杯しなくちゃいけない。だから、私と一緒に、【キモチイイコト】を一杯しましょう❤❤」 「そ、そんなの、絶対間違ってる!ひあぁっ」 拒絶の言葉を口にするものの、首筋を舐められて甲高い声に変えられてしまう。 「間違ってないと思うなぁ」 「ま、間違ってます!こ、こんな淫らなこと……!!」 「だって、子供を作るためには必要なことなんだよぉ?」 「で、でも……」 「子供を作るために、キモチイイコトしなさいって、神様は私たちをそんな風に御造りになられたのよ?」 「だ、だめぇ…あひぁっ❤」 首筋や耳元など敏感な場所を舐められ、生暖かい吐息を吹きかけられ、全身に柔らかな肢体を押し付けられ、どことなく甘い香りに満たされた布団の中で身もだえするしかない僕。 必死に抵抗の言葉を口にしようとするのだが、それ以前に彼も男性であることを示すかのように体の一点が変化を始めてしまう。 「ふふ、そんなこと言いながら、おちんちんは固くなってきてるよ?」 その変化を敏感に察したアンナが、僕の股間に太ももを押し付ける。 「あぁっ……❤」 柔らかくて、弾力のある太ももを押し当てられて、さらに硬度を増していく。 厳しい修行生活の中で、思春期を迎えるにつれて同胞たちの中でも話題に上る機会が徐々に出始めていた男女の差。 修行の妨げになるからと意識しないように努めてきたとはいえ、気にならないわけもなく。 修行のふとした瞬間に垣間見える同胞たちの異性としての部分に、どぎまぎしたことがないかといえばウソになる。 体を動かすたび、かすかにふるえる胸元やちらちらと視線に入る太もも、髪をかき上げた際などに除くうなじ。 だが、これほど成熟した女性の肢体を、これほど間近に、まさしくゼロ距離で感じることなどこれまでなかったことだ。 体の反応を抑えようとして、抑えられるはずもなく、弾力ある太ももを押しのけかねないほど固く雄々しく天を衝く。 「熱い……それに、凄く固いよ」 熱にうなされたような、アンナの囁き。熱い吐息。 胸元を這いまわる掌。 股間に押し当てられる太ももの感触。 だんだんと頭がぼーっとなってくる。 「ね、ジョシュア君、こっち向いて?」 囁く声に、思わずアンナの方を向いてしまう。 「ぁ………」 昼間見たときは確かに、水色だった彼女の瞳が、赤く輝いている。 その瞳を見た瞬間、どくんっと心臓が大きく跳ねる。 赤い瞳に映った自分の姿。 欲情にのぼせ上がった、自分の姿。 体が熱くなる。 「アンナ…さん……」 「ふふ、どうしたい?」 「そ、それは………」 アンナさんの艶やかな唇。 かすかに覗く白い歯とピンク色の舌先。 甘く薫る吐息。 理性が、麻痺していく。 「これも修行よ❤」 「アンナ……さん……」 どちらからともなく顔を寄せ合い、唇を重ねる。 柔らかな唇の感触に、何も考えられなくなる。 唇を割って、彼女の舌が差し込まれてくる。 おずおずと僕も舌を伸ばすと、嬉しそうに舌を絡みつかせて来る。 くちゅっ、んちゅっ…… 厭らしい水音が響く。 アンナさんの左腕が、僕の頭と枕の間に差し込まれ、後頭部を抑え、より深く密着する。 アンナさんの口から、とろとろと涎が流し込まれる。 美味しい。 僕は、夢中になって、アンナさんの唾液を飲み込んでいく。 どんどん体が熱くなっていく。 股間が、びくびくと脈動する。 胸元を這いまわっていた右手が、僕の乳首をつまみ、くりくりといじくりまわす。 ぴくぴくっと体が震える。 今までに感じたことのない快感に、頭の中が白く濁っていく。 腰の奥から何かが競りあがってくる。 股間が―――おちんちんから、何かが飛び出してきそうな未知の感覚。 だが、恐怖心も動揺も、アンナさんの舌に溶かされてしまう。 気づけば僕は、自分からアンナさんの足に腰を押し付けていた。 「っぷは。気持ちいいでしょ?」 キスの合間に尋ねられて、僕は顔を真っ赤にしながらこくりと頷く。 「んちゅっ、こんなこと天界の学校で教えてくれた?」 今度は首を横に振る。 「天界で知ることのできなかったことを学ぶ、それがわざわざ地上界で学ぶ意義だと思うの」 そう言われると、そんな気がしてくる。 小さく頷くと、アンナさんはより強く太ももを押し付けてきた。 「こ、こんなの知らないっ、怖いよぉっ……」 「怖がる必要なんかないよ。これは【イイコト】なんだから❤…気持ちよく、精通しちゃお?」 僕を安心させようとするかのように、ちゅっと優しいキスをされる。 何かの堰が決壊したかのように、腰の奥底から、一気に何かが溢れ出してくる。 「だから―――イっちゃえ❤」 その言葉と同時に、おちんちんの先端から何かが噴出した。 どくどくっと溢れ出したそれが下着を、ズボンを、アンナさんの右足を、汚していく。 生まれて初めての射精。快楽。 僕は何も考えられず、自分のものでないかのように脈動を繰り返すおちんちんが、何かを吐き出し続ける感触に身を任せる。 「ふふっ、私の足、気持ちよかった?」 笑顔で尋ねられ、僕は荒い呼吸を繰り返し、赤面しつつも、頷いた。 「じゃ、綺麗にしてあげるね」 そう言い残し、アンナさんは布団の中を、僕の足元に移動していく。 「わぁ、凄くたくさん出したね。ズボンが凄いことになってる」 「う、ご、ごめんなさい……」 「謝らなくていいよ。それより脱がすから、少し腰上げてくれる?」 「は、はい……」 言われるまま腰を浮かすと、ズボンだけでなく下着まで一緒に脱がされてしまう。 「あっ、アンナさん、下着まで……」 「だって、こっちも汚れちゃったでしょ?」 「そ、そうだけど…恥ずかしいよ」 「恥ずかしがらなくていいよ。じゃあ、綺麗にするね」 「えっ、ちょ、アンナさん、何やって―――うあぁっ」 何ら躊躇う素振りもなく、アンナさんが僕のおちんちんを口に含む。 「だ、だめだよ、そんな所!汚いから―――あぁ、舐めないでぇ」 先端を舐められて、びくんっと腰が浮いてしまう。 排泄器官を口に含むなど、とても背徳的なことをしているように感じてしまう。 だが、そんなことはお構いなしにアンナは先端に吸い付き、竿の中に残っている精液までも吸い出してしまう。 さらに、辺りに散らばった精液も丁寧に舐めとっていく。 「―――ふふ、ジョシュア君の精液、凄くおいしいっ」 「ま、まさか、飲んだの……?」 「ご馳走様♪」 そう言って朗らかに笑うアンナの瞳は、昼間見た時と同じ、綺麗な水色だった。 先ほど、赤く見えたのは気のせいだったのだろうか。 「今、新しい着替え持ってくるからちょっと待っててね」 「う、うん………」 持ってきてもらった着替えを身に着けると、アンナは手早く精液に汚れた服を片づけて、 「じゃあ、今日の修行はこれで終了!お疲れ様でした♪」 「今日のって…明日もやるの?」 「もちろん、毎日やるわよ。【イイコト】をたくさんするのが、修行なんだから。じゃ、おやすみなさい♪」 笑顔で手を振りながら部屋を出ていくアンナ 僕は再びベッドに横になる。 だが、眠ることができなかった。 布団の中にはアンナの残り香とぬくもりがまだ残っていたから。 そして、火照った体の中で、快楽の残滓がまだ熾火のように残っていたから。 *** 【修行2日目】 昼間は教会の手伝いに忙殺された。 天使見習いが修行に来ているということを聞きつけ、近所の信者たちが集まってきたので、挨拶をし、アンナがミサを執り行うのを手伝ったりもした。 アンナを見る度、複雑な感情に襲われる。 昨日あんなことがあったからか、アンナの事がものすごく美しく見える。 そして、ゆったりとした僧衣に包まれていながらも、その中に隠された肢体の柔らかさを思い出してしまう。 その度、煩悩に押し流される自身の精神の惰弱さを呪い、視線を逸らすのだが、気づけばまたアンナを見つめてしまっている自分に気づくのだ。 このままではまずい。 根拠はうまく言えないが、ものすごくまずいことのような気がする。 だが、だからと言って何をどうすればいいのか思いつかぬまま、悶々と時を過ごすしかないのであった。 そしてあっという間に夜。 二人で食事を済まし、交代で風呂に入ったのち、日誌をまとめる。 とはいえ、昨日の出来事や自身の心情などとても書けたものではない。 当たり障りのない内容を書き連ね、そろそろ休もうかと思い始めた頃。 扉がノックされた。 どくん、と心臓が跳ねる。 忘れていたわけではない。 だが、昼間も、食事の際も、別れる際も。 アンナは昨日のことなど忘れたかのように普通に振る舞っていた。 だから、あれはもしかしたら夢だったのではないかなどと思いもしていたのだ。 だとしても、そのような夢を見る自分の愚かしさには腹が立つけれども。 いや、まだわからない。 本当にあれは夢で、今ノックされたのは本当に何か用があるだけなのかも。 そんな淡い期待を抱きつつ、 「はい」 答えると、ノブが回され、僧衣姿のアンナが入ってくる。 そして、笑顔で告げる。 「さ、今日も修行するわよ♪」 なんとも朗らかに、いとも容易く、淡い期待を打ち砕く言葉を。 椅子に座ったまま硬直している僕に近づいてくる。 「なに、その顔。傷つくなぁ。ジョシュア君たら、今日の昼間はあんなに熱い目で私を見ててくれたのに♪」 「なっ……」 見ていたことを気付かれていた。 その事に思わず赤面する。 「女はそういう視線に敏感なの。気をつけなさい?」 「は、はい、ごめんなさい……」 「で、気づいたんだけどぉ、ジョシュア君の目線、私のある所にかなり集中してた気がするんだけど、気のせいかな?」 至近距離まで近づいてきて、やや前かがみになりながら僕の顔を覗き込んでくる。 その拍子に―――。 「ほら、やっぱり。今も見た」 確信を得たという笑顔を浮かべるアンナ。 「え?」 だが、自覚のない僕には何のことかわからない。 アンナは秘密を打ち明けるみたいに人差し指を唇の前に1本立てて、 「好きなんだね、おっぱい❤」 「っ………」 アンナの口から唐突に飛び出してきた単語に、硬直する。 確かに、僧衣越しでありながらはっきりと形を主張する大きな胸が気になっていなかったとは言えない。 ふとした拍子にとても柔らかそうに、しかしながら重量感たっぷりに揺れ動く様には遂釘付けになってしまっていたのも事実だ。 「すっごく熱い視線で見られてたから、私今日一日凄くドキドキしてたのよ。ね、ジョシュア君もドキドキしてた?」 「は、はい……」 「ふふ、じゃあ今日はおっぱいで沢山【イイコト】してあげるね❤」 アンナの両手が、僕の後頭部に回され、そのままぐいっと引き寄せられる。 もにゅんっ❤❤ そのまま、僕の顔は柔らかなアンナの胸に抱き寄せられる。 僧衣越しとはいえ、とてつもなく柔らかな感触に包まれ、脱力する。 昼間から思ってはいたが、直接触れてみるとその想像以上にアンナのおっぱいはとても大きかった。 その深い谷間に捉えられてしまう。 しかも、谷間の奥から、とても甘い香りがしてくる。 思わず深く吸い込むと、全身からますます力が抜けていく。 「ふふっ、いい匂い?」 尋ねられ、こくこくと頷く。 「深呼吸して。一杯吸い込んで」 言われるまでもなく、貪欲に深呼吸を繰り返す。 体中の酸素を、すべてこの香りに置き換えてしまいたいぐらいだ。 「もっと、私のおっぱい感じて❤」 両脇を寄せて、おっぱいを中央に寄せる。 乳圧が高まり、僕の頭がさらに埋もれていく。 「締め付けたり~、緩めたり~、また締め付けたり~。これ、ぱふぱふって言うんだよ?気持ちいい?ぱふぱふ」 「ふぁい……❤❤」 脱力しすぎて、口にも力が入らない。 口の端から涎があふれ、僧衣を汚していく。 「じゃあ、次は直接やってあげるね」 一旦谷間から僕を開放したアンナが、僧衣の上着部分をずり下げる。 反動でぶるんっと大きく揺れながら飛び出してきた白い二つの乳房。 その先端で、桜色の唇がぷっくりと膨らんで自己主張している。 「綺麗だよ、アンナさん……すごく」 「ふふっ、ありがとう。さ、おいで❤」 それぞれの乳房を片手で持ち、広げて見せる。 僕は吸い寄せられるように、その谷間に顔を寄せる。 そんな僕を包み込むように、おっぱいを寄せて圧力をかけていく。 「あぁぁ……気持ちいい……❤❤」 本当は、こここそが天界なのではないかと思わせるほどの極上の感触。 柔らかな絹のような滑らかな感触。 ミルクのような優しい香りに包まれて、全身が安堵感に覆われ、どこにも力が入らない。 いや、正確には一点だけ、激しく力強く自己主張している部分があったが。 痛いほどに勃起したおちんちんは、我慢汁を垂れ流しながら、ひくひくと快楽を求めてわななく。 「アンナさん……舐めたい……」 「いいわよ」 許しを得て、柔肌に舌を這わせる。 まるで、舐めているこちらが溶けてしまいそうな極上な舌触り。 ぺろぺろ、ちゅうちゅうと舐め、吸い付く。 「ふふ、ジョシュア君、赤ん坊みたい♪……ね、こっちも舐めて?」 大きな乳房を持ち上げ、僕の口元にその先端を差し出す。 可愛らしい果実のような乳首。 迷うことなく、僕はその果実にむしゃぶりつく。 ちゅうちゅうと音を立てて吸いたてながら、ぺろぺろと舌を這わせる。 「ほんと、赤ちゃんみたい。でも、こっちはすごく立派………」 ズボンの合わせ目に手を入れ、固く勃起したおちんちんを引っ張り出す。 血管の浮き立ったそれを、白い手で握り、しゅこしゅこと上下にしごいていく。 「んんんっ……!!」 下半身から齎される強烈で、直接的な快楽に声を上げるが、口いっぱいにおっぱいを頬張っているせいで声にならない。 かといって、この幸福感を自らの意志で手放すことなどできようはずもなく、くぐもった声を上げながら、乳房の肉ごと乳首に吸い付き、口内で転がし、味わう。 「おいしい、アンナさんのおっぱいおいしいよぉ……」 「ふふ、いっぱい召し上がれ❤」 我慢汁が次々と溢れ出すおちんちんをしごく手も止まらない。 くちゅっくちゅっと厭らしい音を立てながら、ジョシュアの身に快楽を響かせ続ける。 女の手はおろか、自身の手で自慰をしたことすらない身には過ぎた快楽である。 瞬く間に射精感がこみ上げてくる。 「あぁっ、また、また出ちゃうよぉっ」 「一杯出して❤びゅるびゅるって、白いザーメン、いっぱい出して❤私のおっぱいちゅうちゅう吸いながらどびゅどびゅって出して❤❤」 喘ぐ口元に乳首を差し出され、縋りつくように吸い付く。 一気に高みへと導こうとするかのように、アンナの手の動きがどんどん早くなっていく。 頭の中にぴかぴかと光が明滅する。 腰の奥から、どろどろに煮えたぎったマグマがおちんちんの中を駆け上り、そして先端から一気に噴き出す。 どびゅっ、びゅるるるっ、どびゅぅっ……! 昨日は下着の中であったから直接見てはいない自身の射精。 自分の体から放出されているとは俄かに信じがたいほどの量と勢い。 天井近くまで吹き上がったそれが、放物線を描きながら、二人に降り注ぐ。 べちゃべちゃと降り注ぐそれに、思わず目を閉じる僕。 それに対し、アンナは陶酔の面持ちでそれを浴び続ける。 その間も手の動きは止まらず、徐々に脈動が弱まり、完全に止まるまで続いた。 快楽の余韻に、言葉もない僕。 荒い呼吸を繰り返しながら、何とか今日の修行も乗り越えられたと思う。 「―――凄く、一杯出たね」 「は、はい…その、ごめんなさい……また、汚しちゃって……」 「いいよ。私の手、気持ちよかった?」 「う……はい、とても…」 「ふふ、ありがと。じゃ、今日の修行はこれで終了❤」 「その……ありがとうございました」 「お粗末様でした♪それじゃ、もう一回お風呂入ってきて?その間にお部屋、掃除しとくから」 「は、はい………」 朗らかな笑顔で促さるまま、部屋を出て、お風呂場へ向かう。 汚れてしまった服を脱ぎ、ふと姿見に映った自身の姿が見える。 金の髪にも白い肌にも、ところどころ精液が付着しており、自身のものながらやや嫌悪感を覚える。 そして―――背中に生える小さな天使の翼。 まだ小さな純白の翼の中に1枚だけ、黒く染まってしまった羽があることに、残念ながら死角であったが故、気づくことができなかった。 *** 【修行3日目】 昼間、教会の仕事を手伝っている間、しょっちゅうアンナを目で追いかけてしまっていた。 そんな視線に気づく度、アンナは信者などにばれないようその場で軽くジャンプをしてみたり、伸びをしてみたりとからかってくる。 弾む胸や強調される胸に、僕は顔を真っ赤にして視線を逸らす。 だが、頭の中はアンナの事ばかりで、仕事が手につかない。 そのおっぱいの感触を思い出すだけで、ズボンの下でおちんちんが固く勃起してしまう。 修行中の身でありながらなんたる体たらくと自分を叱ってみるが、すると今度は今晩の修行についつい思いを馳せてしまう。 結局、この日僕はほとんど1日中前かがみで過ごすことを余儀なくされたのだった。 そして、夜。 僕は日誌の記入を終え、鼓動を高鳴らせながらその時を待っていた。 そして、足音が近づいてきて、扉がノックされる。 「ど、どうぞ」 ほとんど被せ気味に答えると、入ってきたアンナがほほ笑む。 その笑顔を見ただけで、心が高鳴ってしまう。 「準備はできてるって感じね」 「はい。その……きょ、今日もよろしくお願いします。しゅ、修行」 「了解♪……で、今日はどうしたい?そろそろジョシュア君の意見も取り入れようかと思って」 「ぼ、僕が決めていいんですか?」 「ええ、勿論。だってこれはジョシュア君の修行なんですもの」 「じ、じゃあ………」 ごくりと生唾を飲み込んで、僕は今日1日心の奥底に秘めていた願いを口にしていた。 「お、おっぱいで……おちんちんを、は、挟んでもらえませんか?」 「ふふっ、ジョシュア君はほんとにおっぱいが好きなんだね」 「う、は、はい……」 「じゃあ、服を脱いでベッドに仰向けで寝て」 「は、はい」 指示の通り、服を脱いでベッドに横になる。 その足元にアンナが座り、昨夜同様、上半身の僧衣をずらす。 大きくて柔らかそうな双乳がまろび出る。 「ジョシュア君のおちんちん、早速カチコチだね。期待してくれてるのかな?」 「は、はい……」 正確には今日一日中勃起しっぱなしだったのだが、さすがに恥ずかしくてそんなことは言えない。 「でも、今日一日中勃起してたよね」 「っ………!!??」 「あれ、ばれてないと思ってたの?あんなに前かがみになってちゃ誰でも気づくと思うけど」 「う、ご、ごめんなさい……」 まさかばれていたとは。 羞恥のあまり、このまま死んでしまいたいぐらいだ。 「じゃ、ご期待に応えて」 僕の両足の間ににじり寄ってきたアンナが、おっぱいを両手で支えながら、僕の股間に覆いかぶさる。 おちんちんが、柔らかな感触に包まれる。 「感想は?」 「き、気持ちぃぃっ………」 一気に全身が弛緩し、口元から涎があふれでる。 「まだ挟んだだけなのに、ジョシュア君のおちんちん、凄くびくびくしてるよ❤」 「こ、これ、ダメ、すぐ出ちゃいそう………!」 「まだまだこれからなんだから♪」 楽しそうに笑みを浮かべつつ、ぎゅぅっと両側からおっぱいを押し付け、乳圧を高めていく。 さらに、谷間からはみ出し、ひくひくと我慢汁を溢れ出させながら震えている亀頭にちろちろと舌を躍らせる。 「あっ❤くぅっ、んあぁっ……」 股間全体を包み込む柔らかであたたかな感触と先端を容赦なく擽ってくる感触。 その相乗効果によって、どんどん絶頂へと押し上げられていく。 「我慢してるジョシュア君、かわいいなぁ。でも、もっと気持ちよさそうに喘ぐ顔も見たい♪だから、ちょっと虐めちゃうね❤」 赤い瞳を爛々と輝かせながら、アンナがうっとりと舌なめずりをする。 「えっ、うあっ、そんな、動かさないでぇっ……」 それまで挟むだけだった乳房を、左右互い違いに動かし、おちんちんを扱きあげるアンナ。 さらに、舌を這わせるだけだった先端は、亀頭そのものをぱくっと口中に収め、カリ首の敏感な場所に舌を這わせる。 これまでよりも数段上のレベルの快楽に、シーツをぎゅっとつかんでなんとか耐えようとする。 だが、胸の動きはどんどん激しく、舌の動きはどんどんねちっこく、そして先端部分を思い切り吸い上げられて。 「んああぁぁあっっ………❤❤❤」 遂に耐え切れず、アンナの口内、その最奥に向けて精を放つ。 どくっ、びゅくっ、どびゅるるるるっ……!! 「んぐっ、こくっこくっこく………」 喉奥を打ち付ける激しい射精に、眉根に皺を寄せながら、吐き出される大量の精液を飲み込んでいく。 それでも飲みきれなかった精液が口の端から溢れ、その顔や乳房を汚していく。 竿に残った最後の精液を吐き出すまで、アンナはゆっくりと胸を動かし、あふれ出た精液も丁寧に舐めとっていく。 「どう?私のおっぱい、気持ちよかった?」 「は、はひ………」 この上ない幸福感に包まれながら、僕は頷くのだった。 *** 【修行4日目】 「修行も兼ねて懺悔の手伝いをしてもらうわ。懺悔に来た信者の方には私から協力をお願いしてあるから。一杯、【イイコト】をするのよ」 「は、はい」 懺悔室は相手の顔が見えないよう、仕切りで区切られた部屋に、互いに異なる入り口から入って罪の告白を聞き、助言や救済を与えるもの。 声は届くよう、目の細かい格子が入っているのが通常なのだが、この教会の懺悔室の仕切りには、ちょうど腰ぐらいの高さに直径10センチぐらいの穴が開いている。 「じゃあ、準備を始めるわよ」 どうしていいやらわからず困惑して立ち尽くしていると、アンナがいそいそと僕のズボンに手をかける。 「ちょ、アンナさん!?」 慌てて手首を掴んで止める。 「どうしたの?」 「い、いや、どうしたもこうも、何してるの?」 「服を脱がせようとしてるのよ」 「だから、どうして!?」 「言ったでしょう。修行のためよ」 「しゅ、修行って………」 これまでこの数日間、アンナとしてきた修行を思い出し、懺悔室に空いた不可思議な穴とズボンを下ろそうとする彼女とを交互に見やって、ぴんと閃くものがあった。 「ま、まさか……この穴に?」 「そう。この穴におちんちんを入れるの。そして、懺悔に来た信者たちは罪を告白し、天使見習いである貴方を射精へと導く。するとあなたは修行になり、天使の慈悲を浴びた信者たちは罪が許される。そういうこと」 「そんなのあり!?」 「まぁ、いつもは逆だけど。ほら、今日は罪を告白したい信者が一杯詰めかけてるから急いで準備して頂戴。一応、穴からおちんちんが抜けないよう手足を留めておくから」 下半身全裸の姿勢で、穴におちんちんを入れさせられ、四肢を革ベルトで固定される。 「じゃ、昨日までよりも大変だと思うけど、頑張って修行してね」 いつも通りの朗らかな笑顔を最後に、扉が閉められる。 それから幾ばくもせず、もう一つの扉が開かれる音と壁の向かい側に人が入ってくる気配がして、 「あの、よろしくお願いいたします、天使見習い様」 おずおずとした、若い少女の声。 今、彼女に見えているのは壁の穴から突き出された僕のおちんちんだけだろう。 視線を感じ、赤面しながら、それでも己の役目を果たそうと平静を装って言葉を口にする。 「はい。よろしくお願いします。それでは告白したい罪をどうぞ」 僕自身も懺悔を聞くのは初めての経験。しかも、この異様な状況。 思わず声が上ずりそうになるのを必死に堪える。 「はい。私、どうにも手癖が悪くて。遂、人の物に手を出してしまうんです。遂先日もお友達の大切にしているアクセサリーを盗んでしまって。そんな自分が嫌で嫌で仕方がないんです。そうしたらシスター・アンナが教えてくださったんです。天使見習い様にお縋りし、その慈悲を賜れば手癖の悪さを治せるかもしれない、と」 「なるほど」 頷きつつ、さてこれは困ったと首をひねる。 盗みは下手をすれば死罪になるほどの重罪。 一体どうやってこの娘を助ければよいのか。 と、答えに困っていると、 「な、なので、その失礼いたします……」 「え、っっ………」 おちんちんの先端に、冷たい感触。 それはおちんちんの形を確かめるかのようにゆっくりとなぞっていく。 (こ、これ、指…!触ってる、女の子が僕のおちんちんを……) アンナ以外の女性に触られるのは初めてだ。 アンナとは異なり、逡巡しながらゆっくりと指がおちんちんの表面を這いまわる。 興奮しているのか、はぁはぁ、という少女の吐息も感じる。 このような異様な状況であるにもかかわらず、少女の手に触られていると認識したそこには急激に血が流れ込み、固さを増していく。 「あっ、大きく………」 驚いたような、少女のささやかな声。 拘束されていて身動きできない僕は、ぎゅっと目を閉じて羞恥に耐えるより他にない。 「に、握りますね」 「は、はい……」 許しを求めつつ、少女がやんわりとおちんちんを握ってくる。 その柔らかさ、温かさに、思わずびくんとおちんちんが跳ねる。 「あっ、痛かったですか?ごめんなさい……」 「い、いや違います。痛いわけではなく………」 「もしかして、気持ちいいんですか?」 「…。は、はい……」 「ふふっ、なんだか天使見習い様、とても可愛いです。精一杯頑張りますので、一杯気持ちよくなって、慈悲をください❤」 元は快活な少女なのだろう。 徐々に緊張が解れるにつれて、口調も柔らかくなる。 おちんちんを握り、リズミカルにしごきあげていく。 「声は可愛らしいのに、おちんちんはすごく血管が浮き出ていて、男らしいんですね❤」 「そ、そんなこと言わないで……」 「亀さんからお汁も出てきてるし、そろそろ出そうですか?」 この異様な状況に、僕自身も興奮していた。 いつの間にか、穴にぴったりと腰を押し付け、少しでも少女の手を感じようとしてしまっている。 アンナに比べ稚拙な手こきだったが、まだまだ経験の浅い僕を絶頂に押し上げるには十分。 「あっ、も、もう出るよ」 「わかりました。一杯、出してください❤」 優しく促され、どぴゅどぴゅと射精する。 「凄い、これが天使見習い様のお慈悲………」 最後の一滴まで絞り出し、 「ありがとうございました。もう悪さはしません♪」 明るい声を残し、少女の気配が懺悔室から消える。 荒い息をつきながら、アンナがやってきて拘束を外してくれるのを待っていると、向かいの部屋に人が入ってくる気配がする。 「次はあたしね、天使様♪」 「え、ちょ、続けて……!?」 「何言ってるの。まだ私の他に5、6人は待ってたよ。休んでる暇なんてないよ」 入ってきたのは、おそらく20代後半ぐらいのお姉さんだろう。 少しきつめの香水の匂いがこちら側にまで広がってくる。 「5、6人……!」 まさか、その全員の相手をしろというのだろうか。 そこでようやく、去り際にアンナが言っていたことを思い出した。 ―――昨日までよりも大変だと思うけど、頑張って修行してね――― そんなこちらの様子などお構いなしに、女性がしゃべりだす。 「いやはや、口が災いの元ってのはほんとだね。この間も旦那と大喧嘩しちゃって。んで、困ってたら、なんでも天使見習いさんのザーメン飲めば治るんだってね。ふふ、こんなかわいいおちんぽしゃぶらせてもらって口も治るなんて、こんなうまい話はないよね。じゃあ、早速―――」 止める間も、手段もなく、先ほど射精したばかりでまだ小さいおちんちんが生暖かい口中に包まれる。 じゅるるるるっ―――!! 「ひぃっぃっ!?」 ものすごい吸引力で吸われ、あっという間におちんちんが固さを取り戻す。 「あはは。さすがに若いってすごいね―――じゃ、本気で行くよ♪」 じゅぼじゅぼじゅぼずちゅずちゅずちゅっ……!! 「あっあっぁっぁぁぁあっ……!!」 何がどうなって、何をされているのかまるでわからない。 今までに味わったことのない暴虐的なまでの快感が全身を貫き、荒れ狂う。 がくがくと全身を震えさせ、半ば白目を剥き、舌を虚空に突き出しながら、僕は嵐に舞う木の葉のように快楽に翻弄される。 時間にすればわずか数秒だろう。 だが、その数秒で、僕はあっという間に2度目の絶頂に押し上げられていた。 びゅるるるるっ―――!! じゅぞぞっ、じゅるるるっ、ごくごくっ、じゅるるるっ 「いぃぃっ、イッてる、イッてるからぁぁぁぁっ……や、やめてぇぇっ!!」 射精しているにもかかわらず女性は一向に動きを緩めることなく、がんがん首を振り舌を絡め頬粘膜で締め付け、喉奥まで銜え込んで絞り上げていく。 「あっ、あぁあっ、ま、また来るっ、また来ちゃうぅぅぅっ……!!」 頭の中で黄色いスパークが鳴り響き、壊れた蛇口のように精が噴き出す。 それをまたこくこくっと喉を鳴らして飲み干すと、ようやく女性は満足したのか、おちんちんを開放してくれた。 「ふぅっ。やっぱり若いっていいねぇ。濃くっておいしい♪ありがとね、天使見習い様、また来るよ」 そう言い残して、女性が出ていく。 はっきり言ってそこから先の記憶はほとんどない。 何人かの女性の悩みを聞いて、おっぱいや口や手で射精させられたのだろうが、よく覚えていない。 気づけば夜。 いつの間にか眠ってしまっていたらしい。 記憶は途切れ途切れだったが、体に残る疲労感が、あれは現実だったのだと物語っていた。 汗といろいろな体液にまみれた体が、正直気持ち悪かった。 さすがにこんな状態では夜の修行もないだろう。 そう思い、僕はお風呂に入るべく重い体を引きずるようにしてベッドを降りた。 脱衣所で服を脱ぎ、風呂に入ろうとしたところで―――。 「あれ……」 僕は違和感を感じ、その正体を確かめようと脱衣所の姿見に目を凝らした。 背中にある小さな羽。 その3分の1ほどが真っ黒に染まっていたのだ。 「な、なんだこれ………」 鏡に両手をつき、まじまじと翼を観察する。 だがやはり、翼が黒くなっている。 背中に手をやり、黒くなった羽をむしろうとしたところで―――。 「あら。ジョシュア君もお風呂?」 脱衣所にアンナが入ってきた。 「どうしたの?深刻な顔をして」 「アンナさん!僕の翼が………」 「あら、ちょっと黒くなってるわね。汚れちゃったのかしら。じゃあ、私が洗ってあげる♪」 「っつ………」 アンナが僧衣を脱ぎ捨てる。 初めて見る女性の裸体に、僕は羽の事も忘れて見入ってしまった。 大きな胸、キュッとしまった腰、ぷりんと艶めかしいお尻、すらりと伸びる肉感的な太もも。 まるで芸術作品のような美しさ。 ごくりと生唾を飲み込んでしまう。 昼間、あれほど射精したにもかかわらずむくむくとおちんちんが大きくなっていく。 そんな様子を見て、アンナがくすりと笑う。 「もう、ジョシュア君のエッチ。じゃ、今日の夜の修行はお風呂でしちゃお❤」 手を引かれ、そのまま浴室の中へ。 互いにシャワーを浴びたところで、アンナがボディーソープを掌にとり、泡立たせる。 そして、僕に見せつけるかのように全身に塗りたくっていく。 大きな胸は特に念入りに。 手の動きに合わせてぐにぐにと形を変える卑猥な肉の塊。 痛いほどに勃起したおちんちんがひくひくと震える。 「さ、準備OK。ふふ、ジョシュア君、おいで❤」 泡まみれのまま、両手を広げて微笑むアンナ。 僕は吸い寄せられるように、アンナに抱き着く。 身長差から、僕の頭はすっぽりとアンナの胸の谷間に埋もれてしまう。 「じゃあ、こっちも♪」 「んああああっ………気持ちいいっ、おちんちん気持ちいいっ……」 固く固く勃起したおちんちんが、むちむちとした太ももに挟まれる。 にゅるにゅるとした快感に声が止まらない。 「じゃ、翼も❤」 泡でぬるぬるになった両手に背中の羽をわしゃわしゃと洗われる。 「ん、んにゃっ❤❤」 得も言われぬ快楽に、思わず胸の谷間から顔を出し喘いでしまう。 すると、その口を、アンナのそれにふさがれる。 「んんっ……!?」 貪るような口づけ、流し込まれる甘い唾液、柔らかなおっぱい、にゅるにゅるの太もも、かき回される羽、さらに片手が背骨に沿って下降し、お尻の穴のあたりをくすぐってくる。 「んんっ!?」 驚き、抵抗しようとするが、 「んちゅっ~❤」 強く唇を吸われ、体が半分溶けてしまうのではないかと思うほど抱き寄せられて、脱力してしまう。 泡にまみれた指先が、ゆっくりとほぐすように皺をかき分け、体の中に入ってくる。 体中で何かが弾けていく。 弾ける度、甘くどろっとした何かが流れ出し、体を作り替えていくような。 全身の感度がどんどん高められていく。 天にも昇るような、あるいはどこまでも奈落の底へ向かって堕ちていくような。 快楽に包み込まれ、射精する。 (キス気持ちいい……おっぱい気持ちいいい……翼気持ちいい……お尻の穴もぉ、おちんちんもぉ……もぉ、何が何だか………) 全身が蕩けて、流れ出してしまいそう。 「気持ちいいの、好き?」 「好きぃぃ………」 「私の事、好き?」 「アンナさん……大好きぃ……」 アンナの柔らかな肢体がうごめく。 挟まれた太ももの間から間欠泉のように何度も精が噴出していく。 「天使になれなくても?」 「っ……」 その問いに、一瞬だけ我に返る。 そして見つめたアンナの瞳。 深紅に染まった瞳。 背中を撫で上げられる。 快楽に思わず仰け反る。 浴室内の姿見が視線に入る。 背中の羽は、もう4分の3ほどが黒く染まっていた。 ようやく理解した。 快楽だ。 快楽を得る度、羽が黒くなっていく。 天使じゃなくなっていく。 アンナが僕を開放する。 ふらふらとしている僕をよそに、アンナが浴室の床に寝そべる。 「ね、ジョシュア君。気持ちいいことは悪いことじゃないよ。だから……ね?」 アンナが己の秘所を指で開く。 サーモンピンクの厭らしい襞が、誘うように蠢いている。 「一緒に、気持ちいいことしよう?ここに、君のおちんちん、入れて?」 「嫌だ」 僕は首を横に振った。 「天使なんかになったって、いいことないよ。だから…ね?」 「嫌だ嫌だ。僕は……」 僕は横になったアンナに馬乗りになると、仰向けになってなお、その形を崩さないおっぱいを鷲掴みにする。 「僕は……おっぱいがいい❤❤❤」 バカみたいな笑みを浮かべて、僕は馬乗りになったまま、おっぱいの谷間におちんちんを挿入した。 即、射精する。 白濁液を浴びながら、きょとんとしていたアンナは、やがてこみ上げてくるものを抑えられないとばかりに笑い出す。 「あはは、ジョシュア君ってば、ほんとにおっぱいが好きなのね♪いいわ、今日もたっぷりおっぱいで絞り出してあげる❤❤」 アンナが乳房を寄せ、飛び出してくる亀頭を口にくわえる。 僕は天井を仰ぎ、涎をこぼしながら、へこへこと腰を振り、何度も何度も、アンナの口の中に精を迸らせた。 *** 【修行5・6日目】 長机を取っ払った礼拝堂の真ん中で、僕は四肢を投げ出し、横たわっていた。 その視界には二人の少女。 必死に、僕が伸ばしている舌をついばんでいる。 さらに視線を動かせば、両耳は別の少女にしゃぶられている。 動かせる範囲であたりの様子を窺えば。 乳首は二人の女性にしゃぶられ、おちんちんには四人の女性が群がり、睾丸も誰かに転がされている。 横たわっていると言ったが、床の上に、ではない。 僕の下には何人もの女性や少女が横たわり、すっかり黒く染まった羽やお尻をしゃぶっている。 もう時間の感覚もない。 今日が5日目なのか、6日目なのかも。 何十回も射精しているが、一向に性欲が衰えない。 アンナ曰く、毎日食べていた食事に細工がされていたらしいが、今となってはどうでもいい。 射精する。 その度に上がる女たちの嬌声。 いや、あるいは嬌声を聞いて、自身が射精したことに気づいたのかもしれない。 それすらも、どうでもよかった。 気持ちいい。 キモチイイ。 これは修行。【イイコト】をたくさんしなければ。 気持ちいことを、もっと。もっと。 手で射精して。 口で射精して。 おっぱいで射精して。 もっと、もっと。 「もっと…僕を犯してぇぇぇっ……❤❤❤」 そんな僕の嘆願を、信者たちは快く受け入れてくれた。 *** 【修行7日目】 近隣で修行していた同胞たちがそれぞれのシスターたちと共に次々に集まってきた。 シスターたちはみな深紅に瞳を輝かせ、天使見習いたちは一人の例外もなく、その翼は黒く染め上げられ、快楽に蕩けた顔をしていた。 その中に僕は見知ったとある元天使見習いを見つけていた。 常に成績トップで、将来は天使長にもなれるのではないかと噂されていた逸材。 そんな彼は今や首輪を嵌められ、四つん這いでシスターの椅子と化していた。 「もっとしゃんとなさいっ」 「も、申し訳ありません、クローネ様っ❤」 「誰がしゃべっていいと言ったのです?あなたは豚です」 「ぶひっ、ぶひっ、ぶひぃぃぃっ❤❤」 豚の鳴き声を上げながら、鞭で叩かれ、射精する。 そんな様子を、僕はアンナに後ろから抱きかかえられ、その豊かなおっぱいに後頭部を埋もれさせながら、眺めていた。 隆起した僕のおちんちんには、信者代表の少女と女性が舌を這わせている。 どんぐりの背比べかもしれないが、今ここに集まった数十人の中で、自分が一番幸せなのではないかと、僕はぼんやりと、そんなことを考えていた。 「さあ、皆さん。そろそろ魔界へ参りましょう。リリー様やノエル様指揮の元、かの英雄と共に天界の軍と戦うのです。戦いに勝てば、もっともぉっと【イイコト】をしながら過ごすことができるのですから❤」 アンナの言葉を聞きながら、その場にいるすべての堕天使が精を放った。 *** 「―――なんだと?」 執務室に、怒気を孕んだミカエルの言葉が響く。 銀髪の天使ライラは苦渋の表情で、同じ報告の言葉を繰り返す。 「地上界にて実習中であった天使見習い全343名のうち、帰還者は0です。全員が、堕天した模様です」 「馬鹿な……」 「研修を受け入れたすべての教会に、魔界の手が伸びていたようです。驚くより他にない手並み。間違いなく、かの英雄の差し金でしょう」 「っっっ………」 やり場のない怒りに拳を机に叩きつけるミカエル。 彼女の怒りに触発されて、城自体が震えているようだった。 「このままでは済まさんぞ………決して!」 かくして、天界と魔界の勢力は、さらに魔界側優位へと傾くのであった。
女王小说
SM小说
调教小说
成人色情小说
Femdom Novel
Femdom Book
Femdom Story
精彩调教视频